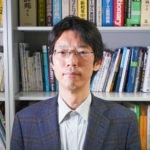次世代シークエンサーの発展により、医科学・生物学の分野では膨大な量のデータが産出されるようになりりつつある。これらのビッグデータに対して、新たな情報処理アルゴリズムの基板研究開発によってこれまで不可能だった解析を可能とし、医科学を新しい次元へ進展させることをめざす研究を行なっているのが、東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター・シークエンスデータ情報処理分野の渋谷 … [もっと読む...] about バイオインフォマティクス分野で、高度なビッグデータ解析を実現する〜渋谷 哲朗・東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター 准教授
AI/ICT/Robotics
「飲む体温計」の開発で、新時代の健康デバイスを開発する〜吉田 慎哉・東北大学大学院工学研究科 特任准教授
ヘルスケアの市場が拡大するなか、次なるデバイスとして無限の可能性を秘めているのが、飲む体温計だ。実用化することができれば、我々の生活を大きく変える可能性がある。こういった飲込み型デバイスの開発に取り組んでいるのが、東北大学大学院工学研究科・工学部 ロボティクス専攻の吉田 … [もっと読む...] about 「飲む体温計」の開発で、新時代の健康デバイスを開発する〜吉田 慎哉・東北大学大学院工学研究科 特任准教授
5G時代の実現に向け、ミリ波の通信技術を開発する〜岡田 健一・東京工業大学工学院 電気電子系 教授
5G時代の到来にむけ、無線機器の開発が求められている。5Gは従来使用されてこなかった帯域で、ミリ波の導入が最大の特徴となっている。こうした5G時代を見据え、新世代の無線機器開発に取り組んでいるのが、東京工業大学工学院 電気電子系の岡田 健一教授だ。今回は岡田教授に、時代に求められる開発の状況について話を伺った。 電波資源を有効利用する「ミリ波」帯域 Q:まずは研究の概要について教えてください。 現在の無線通信に使われているのが、マイクロ波です。マイクロ波は周波数としては、0.3~30ギガヘルツのもので、その中でも主に携帯電話の通信で使っているのが6ギガヘルツ以下のものになります。3G, … [もっと読む...] about 5G時代の実現に向け、ミリ波の通信技術を開発する〜岡田 健一・東京工業大学工学院 電気電子系 教授
新しいメモリ技術で、次時代のコンピューティングを実現する〜小林正治・東京大学工学系研究科附属d.lab、東京大学生産技術研究所 准教授
世の中で年々増大しつづけるビッグデータはデータセンターでの処理とネットワークトラフィックをひっ迫しつつあり、端末であるエッジデバイスの役割が増々重要となってきている。エッジデバイスはエネルギー制約のもとで低電力かつ高性能な処理が求められてくる。こうした中、エネルギー効率が良い集積回路・システムの実現に向けて、既存のデジタルメモリとは異なる新たな不揮発性メモリ技術の開発と応用に取り組んでいるのが、東京大学工学系附属d.labおよび東京大学生産技術研究所の小林正治准教授。今回は小林准教授に、新時代のメモリ技術の展望について伺った。 人工知能に必要なメモリデバイス技術を開発 Q:まずは、研究の社会的なニーズについて教えてください。 現在のスマートフォン、パソコン、ロボット、自動車まで、すべてのエレクトロニクスの心臓部となっているのが半導体集積回路です。この … [もっと読む...] about 新しいメモリ技術で、次時代のコンピューティングを実現する〜小林正治・東京大学工学系研究科附属d.lab、東京大学生産技術研究所 准教授
触覚センサーの開発で、ロボットの社会応用を実現する〜室山真徳・東北大学マイクロシステム融合研究開発センター 准教授
ものづくりや介護、農業などさまざまな場面で、ロボットの活用が望まれている。そこで必要になるのが、高性能で省電力な触覚センサーの開発だ。こうしたなか、次世代ロボット用触覚センサネットワークシステム実現のため、LSI、MEMS、ソフトウェア、システム全体を統括する研究開発を行なっているのが、東北大学マイクロシステム融合研究開発センターの室山真徳准教授だ。今回は室山准教授に、触覚センサーの開発がもたらす社会的インパクトについて話を伺った。 現場のニーズをもとにロボットの触覚を開発 Q:まずは、研究の概要について教えてください。 私たちが行なっているのは、ロボットに皮膚感覚をつけるための研究です。五感をベースにして考えると、カメラなどの「視覚」をはじめ、Google HomeやAmazon … [もっと読む...] about 触覚センサーの開発で、ロボットの社会応用を実現する〜室山真徳・東北大学マイクロシステム融合研究開発センター 准教授
AIと音楽を組み合わせ、音楽制作をデータベース化する〜浜中雅俊・理化学研究所 革新知能統合研究センター チームリーダー
近年めざましい発達を遂げるAI(人工知能)は、クリエイティブの分野でも活用が期待されている。長年にわたって音楽の専門家がおこなう操作の事例をデータベースに蓄積し、再利用するシステムを構築していたのが、理化学研究所 革新知能統合研究センター(AIP)の音楽情報知能チームの浜中雅俊チームリーダーだ。一般の利用を踏まえた音楽研究について、その最新状況をうかがった。 音楽家の直感を「構造」であらわす Q:まずは、研究の概要について教えてください。 音楽を作ったり曲を編曲したりすることは、足し算・引き算のように記号で表現をして計算することができるものです。例えばある式ができて、別の曲にそれを足したり掛けたりすることで、また新しい曲ができたりするわけです。これは言い換えれば、「音楽のメロディーに対する操作をデータベースに蓄積していくと、音楽を再利用することができ … [もっと読む...] about AIと音楽を組み合わせ、音楽制作をデータベース化する〜浜中雅俊・理化学研究所 革新知能統合研究センター チームリーダー
ブレイン・マシン・インターフェースで脳の力を引き出す〜牛場潤一・慶應義塾大学理工学部准教授
脳血管疾患では、罹患後に生じる運動や高次機能障害の予後不良性、そしてその結果として増す介護負担など、長期にわたるさまざまな課題が問題視されている。こうしたなか、脳に残された回路を呼び覚まし、病気やけがで失った神経機能を回復させる研究が注目を集めている。BMI(ブレイン・マシン・インターフェース)と呼ばれるこの装置の開発研究に取り組んでいるのが、慶應義塾大学理工学部 … [もっと読む...] about ブレイン・マシン・インターフェースで脳の力を引き出す〜牛場潤一・慶應義塾大学理工学部准教授
CRISPR-Cas9の立体構造をもとに、ゲノム編集をさらなる高みへと導く〜西増弘志・東京大学大学院 理学系研究科 准教授
生命の設計図であるゲノム情報を書き換える「ゲノム編集」という言葉がにわかに注目されている。2013年に報告されたCRISPR-Cas9を用いたゲノム編集技術はさまざまな分野に技術革新をもたらした。DNAを切断するハサミ役であるCas9タンパク質、ガイドRNA、ターゲットDNAからなる複合体の結晶構造を世界にさきがけて解明し注目を集めているのが、東京大学 大学院理学系研究科 西増弘志 … [もっと読む...] about CRISPR-Cas9の立体構造をもとに、ゲノム編集をさらなる高みへと導く〜西増弘志・東京大学大学院 理学系研究科 准教授
地球規模で河川の流れを予測し、災害を防ぐ〜山崎 大・東京大学生産技術研究所准教授
大規模河川の洪水や氾濫による大災害を防ぐには、事前の流況予測が必要である。しかしながら、これら大陸スケールの河川における「水の動き」を正確に把握することは、複雑な要因が関連するため、非常に難しいとされている。そうしたなか、最新の高解像度衛星観測データを活用して、複雑な氾濫原浸水プロセスを効率よくモデル化しているのが、東京大学 生産技術研究所の山崎 … [もっと読む...] about 地球規模で河川の流れを予測し、災害を防ぐ〜山崎 大・東京大学生産技術研究所准教授
航空宇宙工学の観点から、空気力学の可能性を追求する〜北村 圭一・横浜国立大学 大学院准教授
ロケットやドローンなど、空気力学をもとにした設計・シミュレーションの研究ニーズが年々高まっている。こうした中、航空宇宙工学を軸として、空気力学を中心とする様々な流体現象を研究しているのが、横浜国立大学 大学院工学研究院 システムの創生部門(理工学府 機械・材料・海洋工学系専攻 航空宇宙工学教育分野,機械工学教育分野 併任)(理工学部 機械・材料・海洋系学科 機械工学教育プログラム 併任)の北村 … [もっと読む...] about 航空宇宙工学の観点から、空気力学の可能性を追求する〜北村 圭一・横浜国立大学 大学院准教授