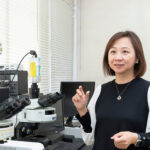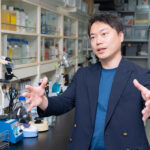新しい薬の開発は、これまで「効くか、効かないか」で判断されることが多かった。しかし、現代医療では「なぜ効くのか」「どのように効くのか」を正確に説明することが求められている。東京大学大学院 … [もっと読む...] about 物理と化学で創薬に挑む──工学の貢献〜津本浩平・東京大学大学院 工学系研究科バイオエンジニアリング専攻 教授
Bio/Life Science
血液中の希少ながん細胞を捕獲し、個別化医療を切り拓く技術を開発〜吉野知子・東京農工大学 大学院工学研究院 教授
がん診断は、大きく2つの工程に分けられる。第一に行われるのが「画像診断」であり、これは体内におけるがんの存在や広がりを調べる検査である。次に、疑わしい病変が発見された場合に、その性質を明らかにするために、組織の一部を採取する「生検」が行われる。しかし、これら従来の診断方法にはいくつかの課題が指摘されている。前者では、腫瘍が1㎝程度の大きさにならないと検出が難しいため、早期発見が困難なこと。後者は患者に身体的負担が伴うため、頻繁な検査や継続的なモニタリングができないことがあげられる。 この2つの課題を解決するために、液体生検(リキッドバイオプシー)の診断における、希少ながん細胞(血中循環腫瘍細胞/CTC)を捉える細胞マイクロアレイ技術を開発したのが東京農工大学 大学院工学研究院 吉野 知子教授である。最近では、直径20 … [もっと読む...] about 血液中の希少ながん細胞を捕獲し、個別化医療を切り拓く技術を開発〜吉野知子・東京農工大学 大学院工学研究院 教授
構成要素の分子から細胞を創り出すメカニズムを解明する〜松浦 友亮・東京科学大学 地球生命研究所 教授
近年、細胞を構成する生体分子を用いて、細胞の性質の一部を持つ人工細胞などの分子システムを構成する研究が盛んに行われている。そんななか、生命システムの動作原理の理解を目指す理学的研究と、医療応用などを目指す工学的研究の両面から、ボトムアップに人工細胞や分子システムを創る研究に取り組んでいるのが東京科学大学 地球生命研究所 松浦 … [もっと読む...] about 構成要素の分子から細胞を創り出すメカニズムを解明する〜松浦 友亮・東京科学大学 地球生命研究所 教授
エイジングのメカニズムを解明し、社会実装につなげる~早野 元詞・慶應義塾大学 医学部整形外科学教室 特任講師
人生100年時代といわれて久しいが、そこからさらに30~40年と健康寿命を伸ばすアンチエイジングの研究が世界的に注目を集めている。DNAの損傷によって誘導されるエピゲノムの変動が、後天的に老化の速さやタイミングを制御している。その仕組みを明らかにしたのが慶應義塾大学 医学部整形外科学教室の早野 … [もっと読む...] about エイジングのメカニズムを解明し、社会実装につなげる~早野 元詞・慶應義塾大学 医学部整形外科学教室 特任講師
嗅覚回路で発見した、新たな神経可塑性メカニズムを解明する~竹内春樹・東京大学大学院 理学系研究科 教授
神経回路の形成メカニズムの基礎となっている、ドナルド・ヘッブが発見した「ヘッブ」という脳内のニューロン結合の法則がある。2019年に嗅覚領域において、これとは異なる第二の法則を発見したのが東京大学 大学院理学系研究科の竹内 … [もっと読む...] about 嗅覚回路で発見した、新たな神経可塑性メカニズムを解明する~竹内春樹・東京大学大学院 理学系研究科 教授
発熱がウイルス性肺炎の重症化を抑制するメカニズムを解き明かす〜一戸 猛志・東京大学 医科学研究所 准教授
これまで外気温や体温がウイルスに感染した場合の重症度に与える影響についてはほとんど解明されていなかった。さまざまな温度条件で飼育したマウスのうち、36℃のグループでは体温が高まり、インフルエンザウイルスなどの感染に対して高い抵抗力を獲得することがわかった。さらにマウスの体内では、腸内細菌叢が活性化し、二次胆汁酸が増加することも明らかになった。世界で初めて、ウイルス性肺炎の重症化抑制を分子レベルで解明したのが東京大学 医科学研究所 … [もっと読む...] about 発熱がウイルス性肺炎の重症化を抑制するメカニズムを解き明かす〜一戸 猛志・東京大学 医科学研究所 准教授
タンパク質の基本原則を解き明かし、人工タンパク質の合理的な設計法を確立する~坪山 幸太郎・東京大学 生産技術研究所 講師
従来の生物では活用できていないタンパク質のポテンシャルを創出するために、多くの研究者が人工タンパク質の研究に取り組んでいる。しかし有用な人工タンパク質の設計は、成功率が極めて低く、運任せになってしまっている。その理由は、タンパク質の基本的な法則が解明されていないところにある。特に、タンパク質の機能や性質に関する良質なデータは限られており、深層学習モデルの構築のボトルネックとなっていた。そこで、機能性を示すタンパク質分子の割合を規定する重要な性質である「構造安定性」を効率よく、大規模に測定できる方法を開発したのが、東京大学 生産技術研究所 坪山 幸太郎講師である。今回は、坪山氏が目指す人工タンパク質の合理的設計の研究概要と現状の課題について、詳しく伺った。 タンパク質の構造安定性を、効率的かつ大規模に解析できるデータ手法を開発 Q … [もっと読む...] about タンパク質の基本原則を解き明かし、人工タンパク質の合理的な設計法を確立する~坪山 幸太郎・東京大学 生産技術研究所 講師
効率的な新薬開発に向け、マルチモダリティ志向の情報基盤を実現する~大上雅史・東京工業大学 情報理工学院 情報工学系 准教授
新薬の開発は、年々難易度を増している。1つの医薬品を開発するのに、10年以上の開発期間、そして数千億円もの研究開発費が必要だと言われている。また、低分子薬だけでなく、中分子薬や抗体薬などモダリティ(治療手段)も多様化しており、標的タンパク質もさまざまだ。従来は、こうしたタンパク質ターゲットを1つ1つ調べ上げて創薬を進めていた。多様化するモダリティや標的に影響されることなく、より効率的にさまざまな医薬品開発を行うことを目指して、マルチモダリティ志向の情報基盤を研究しているのが、東京工業大学 情報理工学院 情報工学系 … [もっと読む...] about 効率的な新薬開発に向け、マルチモダリティ志向の情報基盤を実現する~大上雅史・東京工業大学 情報理工学院 情報工学系 准教授
1分子計測技術により、感染症の迅速検査を可能にする~渡邉 力也・理化学研究所 主任研究員
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大によって、感染診断の検査として活用されるようになったPCR検査法は、感度に優れ、確定診断に適しているが、時間と費用がかかることが課題となっていた。そこで2021年に、新型コロナウイルス由来の遺伝子を「1分子」レベルで識別して、5分以内に検出できる革新的な検査法を開発したのが理化学研究所の渡邉 力也主任研究員である。2022年には、感度・精度をさらに向上させ、新型コロナウイルスだけでなく、インフルエンザなどの複数のウイルスを検体から検出できる全自動検査装置を開発した。どのようにして全自動検査装置が生まれたのか。渡邉主任研究員にその背景と今後取り組んでいきたいテーマについて話を伺った。 新たなアプローチで、世界最速の、汎用的な全自動感染症検査装置を開発 Q: 研究概要につ … [もっと読む...] about 1分子計測技術により、感染症の迅速検査を可能にする~渡邉 力也・理化学研究所 主任研究員
エンハンサーの働きをライブイメージングを駆使して、分子レベルで解明する~深谷 雄志・東京大学 定量生命科学研究所 准教授
遺伝子の発現を調節するエンハンサー。エンハンサーのDNA配列に変異が起こると、遺伝子自体が無傷でも、発現制御に異常が生じ、その結果、ガンなどの疾患を起こす原因になると、近年数多く報告されている。それだけ非常に重要な機能を持つエンハンサーだが、これまでその基本的なメカニズムは解明されていなかった。そこで、独自のライブイメージング技術を用いて、エンハンサーのメカニズムを解き明かしたのが、東京大学 定量生命科学研究所 深谷 雄志 … [もっと読む...] about エンハンサーの働きをライブイメージングを駆使して、分子レベルで解明する~深谷 雄志・東京大学 定量生命科学研究所 准教授