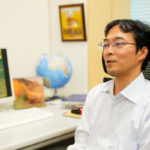IoTの普及により、あらゆるデバイスがネットワークにつながる今、プライバシー情報の漏洩や改ざんなどの事態が大いに懸念されている。それゆえ、2030年頃の実現が期待されている6Gに向けたセキュリティ対策も急務になってきた。そんな中、暗号技術の研究において第一人者のひとりである兵庫県立大学大学院 情報科学研究科の五十部 … [もっと読む...] about 6Gにおける暗号技術の実用化を実現する〜五十部 孝典・兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 教授
Society
薬剤耐性菌の挙動を明らかにして、ワンヘルスを推進する~春日 郁朗・ 東京大学 先端科学技術研究センター 准教授
パンデミックの恐れがあるとして、G7などのサミットで主要課題として挙げられている薬剤耐性(Antimicrobial Resistance :AMR)。一般に抗生物質と呼ばれる抗菌薬の濫用などによって、病原細菌に薬が効きにくくなるというもの。この薬剤耐性を制御するためには、ヒト(人)だけでなく、動物や環境を含めた総合的な健康リスク対策が必要で、それを「One Health(ワンヘルス)」と呼んでいる。しかし、この薬剤耐性のリスクが、世の中にどのくらい広まっているのかは、明らかになっていないのが現状である。この実態を把握するため、世界に先駆けて日本とベトナムの都市で薬剤耐性菌の調査を行っているのが、東京大学 先端科学技術研究センター … [もっと読む...] about 薬剤耐性菌の挙動を明らかにして、ワンヘルスを推進する~春日 郁朗・ 東京大学 先端科学技術研究センター 准教授
折紙の可能性を広げ、社会実装を実現する〜石田 祥子・明治大学 理工学部 専任准教授
宇宙開発から飲料缶まで──今や、さまざまな領域で活用されている「折紙」技術。JAXA(宇宙航空研究開発機構)では、宇宙ヨット「イカロス」のソーラーセイルで採用され、最近では火星探査ロボットにも使われている。この折紙の「折り畳み」のアイデアを工学に応用し、新たなハニカムコアによる、自動車の衝撃吸収材の研究を行っているのが、明治大学 理工学部の石田 … [もっと読む...] about 折紙の可能性を広げ、社会実装を実現する〜石田 祥子・明治大学 理工学部 専任准教授
半導体増感型熱利用発電で、エネルギー問題を解決する〜松下 祥子・東京工業大学 物質理工学院 准教授
安心・安全で、クリーンな熱エネルギーの有効利用が強く望まれている。通常、熱を使った発電では、地下水を水蒸気化しタービンを回転させ発電する「地熱発電」と温度差を利用した「ゼーベック型熱電発電」の2種類がメジャーだが、どちらもエネルギーの変換効率向上が課題になっていた。そこで、地熱や工場排熱などの熱源に置くだけ、埋めるだけで発電し、発電終了後もそのまま熱源に放置すれば、発電能力が復活する「半導体増感型熱利用発電」を開発したのが、東京工業大学 物質理工学院の松下祥子 … [もっと読む...] about 半導体増感型熱利用発電で、エネルギー問題を解決する〜松下 祥子・東京工業大学 物質理工学院 准教授
電動モビリティシステムの研究を通じて、高効率・高性能な電気エネルギーの利用技術を確立する〜近藤圭一郎・早稲田大学 理工学術院 先進理工学部 電気・情報生命工学科 教授
カーボンニュートラルの実現に向けて、エネルギーの変換効率が高く、CO2の排出を抑えられる自動車や飛行機など「動くモノ」の電動化のニーズが高まっている。ここには、電力の供給、電気エネルギーの貯蔵、電力交換、電気・機械エネルギーの変換などを、小型化・軽量化した機器で高精度、高速に実現する技術が不可欠である。そして、世の中で電気エネルギーを利用する上でも、これらの技術が必須となる。自動車,鉄道車両などの電動モビリティシステムの研究を通じて、社会における高効率・高性能・高機能な電気エネルギーの利用技術の確立に取り組んでいるのが、早稲田大学 理工学術院 … [もっと読む...] about 電動モビリティシステムの研究を通じて、高効率・高性能な電気エネルギーの利用技術を確立する〜近藤圭一郎・早稲田大学 理工学術院 先進理工学部 電気・情報生命工学科 教授
土木工学の観点から、新たなCO2地中貯留の可能性を解き明かす〜岩井裕正・名古屋工業大学 社会工学科 環境都市分野 助教
日本は、国土の約12倍もの広大な領海や排他的経済水域を有しているにもかかわらず、海洋はまだまだ未知な領域である。カーボンニュートラルの実現に向け、温室効果ガスの削減が叫ばれるなか、大気に放出されるCO2を回収して、深海底に貯留する研究を進めているのが、名古屋工業大学 社会工学科 環境都市分野の岩井裕正助教だ。岩井助教が取り組んでいるのは、「CO2ハイドレート」と言われる、新たな地中貯留の方法である。今回は「CO2ハイドレート」の仕組みや可能性について話を伺った。 日本の海洋地盤に適した「CO2 … [もっと読む...] about 土木工学の観点から、新たなCO2地中貯留の可能性を解き明かす〜岩井裕正・名古屋工業大学 社会工学科 環境都市分野 助教
水供給システムの研究で、持続可能な社会像を描く〜小熊 久美子・東京大学大学院工学系研究科 准教授
世界には、水システムの整備が不十分で安全な水を十分に得られない地域が多くある。こうしたなか、水を安定的に持続可能な形で供給するためのシステムづくりと浄水技術についての研究に取り組んでいるのが、東京大学大学院工学系研究科 小熊 久美子 … [もっと読む...] about 水供給システムの研究で、持続可能な社会像を描く〜小熊 久美子・東京大学大学院工学系研究科 准教授
スマートグリッド研究で、電気の新たな時代を描く〜山口 順之・東京理科大学工学部 電気工学科 准教授
電力システムは社会を支えるインフラとして、地球温暖化、エネルギーセキュリティ、電源ベストミックスといった課題に直面している。その課題を解決すべく、「電力システム工学」という分野から再生可能エネルギーの大量導入やIoT・AIと融合したスマートグリッド・超スマート社会の構築を実現するための研究を行なっているのが、東京理科大学工学部 電気工学科 の山口 … [もっと読む...] about スマートグリッド研究で、電気の新たな時代を描く〜山口 順之・東京理科大学工学部 電気工学科 准教授
地球規模で河川の流れを予測し、災害を防ぐ〜山崎 大・東京大学生産技術研究所准教授
大規模河川の洪水や氾濫による大災害を防ぐには、事前の流況予測が必要である。しかしながら、これら大陸スケールの河川における「水の動き」を正確に把握することは、複雑な要因が関連するため、非常に難しいとされている。そうしたなか、最新の高解像度衛星観測データを活用して、複雑な氾濫原浸水プロセスを効率よくモデル化しているのが、東京大学 生産技術研究所の山崎 … [もっと読む...] about 地球規模で河川の流れを予測し、災害を防ぐ〜山崎 大・東京大学生産技術研究所准教授
最新の気象モデルで、都市気候を解き明かす〜日下 博幸・筑波大学計算科学研究センター教授
異常気象や温暖化が社会問題として叫ばれるなか、東京や名古屋など都市近辺の気候研究の必要性が高まっている。世界最大のユーザ数を誇る「WRF」モデルや筑波大学が中心となって開発した世界最新の「City-LES」を用いて、都市気候を中心とした気候や気象の研究に取り組んでいるのが、筑波大学計算科学研究センターの日下 … [もっと読む...] about 最新の気象モデルで、都市気候を解き明かす〜日下 博幸・筑波大学計算科学研究センター教授