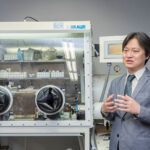レントゲン撮影や手術室で使われる防護板や防護メガネ──X線が発見された1895年から今日に至るおよそ130年間、防護材の主役は鉛ガラスが中心である。20世紀初頭に欧米で開発され、日本でも1950年代に国産化されて以来、医療・研究・工業の最前線で用いられ、「透明性」と「高い遮蔽性能」という二つの価値を兼ね備えた画期的素材として普及してきた。 しかしその一方で、重くて割れやすく、高価で、鉛由来の環境負荷が避けられないという弱点は、常に専門家を悩ませてきた。透明で、しかも鉛を用いずにX線を遮へいできる素材は「実現不可能」とされ、答えは鉛ガラスに委ねられてきたのである。 その130年にわたる前提を、若干27歳にして覆したのが山形大学大学院 有機材料システム研究科/日本学術振興会 … [もっと読む...] about 世界初の“無色透明“な“鉛フリー“X線遮へい材──X線発見以来130年間の常識を覆す挑戦~床次僚真・山形大学/日本学術振興会 特別研究員(PD)
Nano Technology/Materials
最先端分子科学の普及と、極微量の試料による分子構造解析の確立を目指す〜佐藤宗太・東京大学 社会連携講座「統合分子構造解析講座」特任教授
私たちの身の回りにある医薬品、食品、化学製品の多くは、特定の分子の構造によってその特性が決まってくる。しかし、これまで極微量の試料では分子構造を解析することが困難だった。こうした課題を解決するため、東京大学の「統合分子構造解析講座」では、企業とアカデミアが共同で最先端の分子構造解析技術の開発に取り組んでいる。現在、東京大学大学院 工学系研究科応用化学専攻の藤田誠教授が提唱した「結晶スポンジ法」を駆使し、ピコグラムレベルの試料から分子の形を特定することに挑戦している。この研究を主導しているのが、東京大学 社会連携講座「統合分子構造解析講座」 … [もっと読む...] about 最先端分子科学の普及と、極微量の試料による分子構造解析の確立を目指す〜佐藤宗太・東京大学 社会連携講座「統合分子構造解析講座」特任教授
柔軟な接合技術でフレキシブルエレクトロニクスの集積化の課題を解決〜高桑 聖仁・東京大学 大学院工学系研究科 総合研究機構 助教
在宅医療や遠隔医療のニーズの高まり、スマートフォンなどのウェアラブルデバイスの普及により、食品ラップフィルムより薄い次世代のフレキシブルエレクトロニクスの研究が盛んに行われて、さまざまな電子素子が開発されている。特に、極薄ディスプレイや極薄太陽電池などの柔軟な電子部品の開発は進んでいるものの、それらを接合したり集積化する技術の研究が遅れている。こうした中、世界で初めて、「水蒸気プラズマ処理」を用いてフレキシブルエレクトロニクス同士の無接着剤の直接結合を実現したのが、東京大学 大学院工学系研究科 総合研究機構 高桑 … [もっと読む...] about 柔軟な接合技術でフレキシブルエレクトロニクスの集積化の課題を解決〜高桑 聖仁・東京大学 大学院工学系研究科 総合研究機構 助教
次世代の電化による有機合成の実現を目指す~信田 尚毅・横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授
化学産業においては、大量のエネルギー消費とCO2排出量が大きな課題になっている。2050年のカーボンニュートラルは、従来の化学合成プロセスでは実現することが難しいとされており、企業にとってはそれに替わる製造プロセスの導入が急務になってきた。そこで、注目されているのが電化による「有機電解合成」である。この手法を活用すれば、「低エネルギー」「クリーン」さらには「低コスト」を実現することが可能になる。しかし、従来の有機電解合成においては「低生産性」「溶媒抵抗によるエネルギーロス」「支持電解質による廃棄物の発生」などの問題が山積している。それらの課題を一挙に解決できるのが固体高分子電解質(SPE)電解技術であり、その技術を世界に先駆けて研究開発しているのが横浜国立大学 大学院工学研究院の信田 … [もっと読む...] about 次世代の電化による有機合成の実現を目指す~信田 尚毅・横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授
コンクリートがれきや廃棄食材で、持続可能な建材を開発~酒井 雄也・東京大学 生産技術研究所 准教授
コンクリートの原料に使う、天然資源の「砂」が世界的にも足りなくなってきている。それにより、海外では違法な採掘も行われており、生態系の破壊などにつながっている。この課題を解決するために、世界で初めて100%リサイクルのコンクリートを開発したのが、東京大学 生産技術研究所の酒井 … [もっと読む...] about コンクリートがれきや廃棄食材で、持続可能な建材を開発~酒井 雄也・東京大学 生産技術研究所 准教授
認知バイアス などの無意識の状態を可視化し、応用する~津村 徳道・千葉大学 大学院工学研究科 准教授
肌の色にはヘモグロビン、メラニン、そして照明の色が現れている。肌解析を通じてヘモグロビンだけを限定して抽出できる技術を2003年に開発したのが、千葉大学 大学院工学研究科 津村 … [もっと読む...] about 認知バイアス などの無意識の状態を可視化し、応用する~津村 徳道・千葉大学 大学院工学研究科 准教授
高い送達効率・安全性などを持つDCBで再狭窄を抑制する~赤木 友紀・東京農工大学 工学研究院 先端物理工学部門 准教授
足の動脈が詰まり、血液の流れが悪くなることで発症する「末梢動脈疾患」。患者数は増加傾向にあり、現在だけでも350万人以上が報告されている。この治療には、「バルーン拡張術」が用いられるのが一般的だが、「再狭窄」の課題があり、それを解消するためにバルーンの表面に再狭窄を防止する薬剤が塗布されたドラッグコーティングバルーン(Drug Coated Balloon、以下DCB)が導入されている。しかし、患部に到達する前に大半の薬剤が流出するなど、従来のDCBは到達効率の低さが問題になっていた。そこで、安全で高い送達効率をもつ新型DCBを開発したのが、東京農工大学 工学研究院 先端物理工学部門の赤木 … [もっと読む...] about 高い送達効率・安全性などを持つDCBで再狭窄を抑制する~赤木 友紀・東京農工大学 工学研究院 先端物理工学部門 准教授
プリンテッド・エレクトロニクスの技術をフレキシブルセンサに活用して、社会課題を解決する〜時任 静士・山形大学 有機エレクトロニクス研究センター 卓越研究教授
近年、IoTが拡大する中、物流、セキュリティ、ヘルスケア、メタバースなどあらゆる領域において、センサを活用した、薄型化、軽量化したフレキシブルなデバイスのニーズが高まっている。そんな中「プリンテッド・エレクトロニクス」といわれる印刷法を活用して、ヘルスケア向けのフレキシブルな生体センサなどを開発してきたのが山形大学 有機エレクトロニクス研究センターの時任 静士 … [もっと読む...] about プリンテッド・エレクトロニクスの技術をフレキシブルセンサに活用して、社会課題を解決する〜時任 静士・山形大学 有機エレクトロニクス研究センター 卓越研究教授
貴金属に頼りすぎない、次世代の触媒開発を目指す~ 砂田 祐輔・東京大学 生産技術研究所 物質・環境系部門 教授
さまざまな用途で利用されている貴金属。中でも、自動車の排気ガス浄化や化成品・医薬品の製造の触媒においては、必要不可欠な素材になっている。しかし、高価な上に、特定の産出国に偏在しており、今後入手が困難になりうる課題を抱えている。こうした問題を解決するために、最少量のパラジウムなどの貴金属で駆動できる金属ナノシート分子触媒を創出したのが、東京大学 生産技術研究所 物質・環境系部門の砂田 … [もっと読む...] about 貴金属に頼りすぎない、次世代の触媒開発を目指す~ 砂田 祐輔・東京大学 生産技術研究所 物質・環境系部門 教授
情報を制御して自律的に動く人工細胞をつくり、物質と生命の違いを解明する~ 瀧ノ上 正浩・東京工業大学 情報理工学院 教授
「物質」と「生命」との境界はいったいどこにあるのか───この根源的な問いを物理学的な観点から解明するために、情報を制御して自律的に動く人工細胞の構築や、分子コンピュータや分子ロボットの構築など、新たなサイエンスの開拓を行っているのが東京工業大学 情報理工学院 情報工学系 瀧ノ上 … [もっと読む...] about 情報を制御して自律的に動く人工細胞をつくり、物質と生命の違いを解明する~ 瀧ノ上 正浩・東京工業大学 情報理工学院 教授