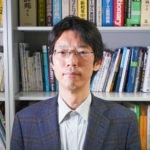従来のロボットのあり方を180度変えるソフトロボティクス(柔らかい材料を用いたロボット工学)が、世界で注目を集めている。ソフトロボットは人工筋肉と呼ばれる柔らかいアクチュエータなどの新しい材料で開発されており、環境に適合しやすく、安全性が高いため、人との協働や共生がしやすいと言われている。可食(食べられる)ロボットや泳ぐ魚ロボット、植物ロボットなど、さまざまな機能を持つソフトロボットを開発しているのが、電気通信大学 大学院情報理工学研究科 新竹 純 准教授である。今回は、社会的ニーズのある、さまざまなソフトロボティクスの特性などについて話を伺った。 多彩な機能を付与できるソフトロボットを開発 Q: … [もっと読む...] about さまざまな機能を付与してロボットと共生できる未来を創る~新竹純・電気通信大学 大学院情報理工学研究科 准教授
AI/ICT/Robotics
「動物にもやさしい情報通信社会」の実現のために、新たなツール開発を追究する~小林博樹・東京大学情報基盤センターデータ科学研究部門 教授
森林地帯などでの野生動物群の生態調査では、従来は人間社会で活用しているカメラやGPSセンサーを情報ツールとして使っていた。しかし、運用コストが高く、かつ電源・情報インフラの未整備な場所も多く、長期的に安定した調査を行うのが困難を極めていた。そこで、野生動物群の生態相互作用(習性)などに着目し、省電力のセンサ・ネットワーク機能で、野生動物の生態データを回収できるシステムを開発した。それが東京大学 情報基盤センター データ科学研究部門 小林 … [もっと読む...] about 「動物にもやさしい情報通信社会」の実現のために、新たなツール開発を追究する~小林博樹・東京大学情報基盤センターデータ科学研究部門 教授
時間変化する複雑な現象を読み解くための数学理論を構築する~湯川 正裕・慶應義塾大学 理工学部 電気情報工学科 教授
IoTの普及などにより、「M2M(Machine to Machine)」での通信が当たり前になりつつある今、Machineデバイスの爆発的な拡大が予想され、従来の線形モデルに基づく信号処理方式では限界があると言われている。それに変わる信号処理手法として、凸解析・不動点理論を利用した適応信号処理アルゴリズムで、線形カーネルと非線形カーネルを組み合わせた「マルチカーネル適応フィルタ」を発表したのが慶應義塾大学 理工学部 電気情報工学科の湯川 正裕教授である。2022年7月には米 NVIDIA社と独 Fraunhofer Heinrich Hertz研究所との共同研究によりGPU(Graphics Processing … [もっと読む...] about 時間変化する複雑な現象を読み解くための数学理論を構築する~湯川 正裕・慶應義塾大学 理工学部 電気情報工学科 教授
組み込みシステムの考え方に立ち返った、超小型・省力化CPUを開発し、次世代IoTのニーズに応える〜原 祐子・東京工業大学 工学院 准教授
あらゆるモノ(製品)がインターネットでつながるIoT時代。今後IoTが進展して、今まで以上にモノがつながり、データ量が膨大になってしまうと、従来の集中処理型のシステムだと、末端にある製品(エッジ端末)が処理結果を受け取るのに相当な時間を要してしまう。それによりリアルタイムで情報を受け取れない可能性が出てくる。そこで重要になるのが、エッジ端末の近くで情報処理を行う「エッジコンピューティング(自律分散型)」だ。このエッジコンピューティングに適した、超小型・省電力のCPUを開発したのが、東京工業大学 … [もっと読む...] about 組み込みシステムの考え方に立ち返った、超小型・省力化CPUを開発し、次世代IoTのニーズに応える〜原 祐子・東京工業大学 工学院 准教授
「民主化」が駆動する情報通信の革新と地域創生の推進~中尾 彰宏・東京大学大学院 工学系研究科 教授
2020年に商用化された5G、そして、2030年頃のサービス提供が想定されている6G(Beyond5G)。情報通信を進化させる研究開発と、その実証実験はもう既に始まっている。中でも、注目されているのが『ローカル5G』である。『ローカル5G』とは、地域の企業や自治体などが、5Gの通信を自由にカスタマイズして構築できる、いわば、「情報通信の民主化」を実現する政策である。ローカル5Gにより、地域の社会課題を解決しようと、全国で様々な実証実験を行っているのが東京大学大学院工学系研究科の中尾彰宏教授だ。今回は、日本の5G研究の第一人者である中尾教授に『ローカル5G』をどのように利活用していくのかーー具体的な取り組みや課題点、そして将来実現される「Beyond5G」の可能性について話を伺った。 通信の「性能」を維持しながら「柔軟性」を高めてきた Q … [もっと読む...] about 「民主化」が駆動する情報通信の革新と地域創生の推進~中尾 彰宏・東京大学大学院 工学系研究科 教授
シミュレーションと機械学習の融合で、社会問題を解決する〜 平田晃正・名古屋工業大学 大学院工学研究科 電気・機械工学専攻 教授
「医工連携」領域の研究においては、倫理的に検証の難しい医療分野の問題を予測・解決する手法として、計算によるシミュレーションが有効である。こうした視点から、電磁界や熱などの物理的負荷によってヒトの体内で生じる物理量と、それによって誘発される生理応答を統合し、計算機上でモデル化する手法で注目されているのが、名古屋工業大学大学院工学研究科/電気・機械工学専攻の平田晃正教授だ。 携帯電話が出す電波の人体に与える影響を調べる技術から始まり、現在は分野横断的な研究に取り組んでいる平田教授に話を伺った。 医工連携・異分野融合するための技術開発 Q:研究の概要を教えてください。 「生体」におけるシミュレーションを、複数のテーマで研究しています。 シミュレーションによる予測技術が本当の意味で進化すると、AIではなくシミュレーションですべてが可能になると予想されています … [もっと読む...] about シミュレーションと機械学習の融合で、社会問題を解決する〜 平田晃正・名古屋工業大学 大学院工学研究科 電気・機械工学専攻 教授
高分解能データの推定技術で、超高精細な結晶構造解析を実現する〜星野 学・理化学研究所 創発物性科学研究センター 物質評価支援チーム 研究員
物質を構成している原子や分子がどのように集合しているのかを観察するための方法として、X線結晶構造解析がある。X線結晶構造解析は、結晶中の原子配置を精度良く評価して、被験物質の性質を解明する研究手法としてすぐれているが、試料の放射線損傷やX線光子数の少なさが原因で高分解能データが得られないと、解析精度が低下するという弱点がある。こうしたなか、計測できない高分解能データを推定・発生する技術により、超高精細とも言えるX線結晶構造解析を実現させるべく研究を進めているのが、理化学研究所 創発物性科学研究センター 物質評価支援チーム … [もっと読む...] about 高分解能データの推定技術で、超高精細な結晶構造解析を実現する〜星野 学・理化学研究所 創発物性科学研究センター 物質評価支援チーム 研究員
高次元データ解析で、コンピュータに「視覚」を持たせる〜石川 博・早稲田大学 理工学術院 教授
機械が画像中の物体や状況などを認識することは、ロボットの能力向上に不可欠であるものの、既存の情報技術ではいまだ実現が困難とされている。こうした中、コンピュータに視覚を持たせる「コンピュータービジョン」とパターン解析を中心とした研究に取り組んでいるのが、早稲田大学理工学術院の石川 … [もっと読む...] about 高次元データ解析で、コンピュータに「視覚」を持たせる〜石川 博・早稲田大学 理工学術院 教授
パッシブロボティクスの研究で、バリアフリー社会を実現する〜平田 泰久・東北大学大学院教授
ロボットを用いた高齢者の運動アシストが徐々に実現されつつあるなか、人間ーロボット間のより安全な相互作用の実現をめざし、受動的アクチュエータをロボットに用いた研究を進めているのが、東北大学大学院工学研究科ロボティクス専攻の平田 … [もっと読む...] about パッシブロボティクスの研究で、バリアフリー社会を実現する〜平田 泰久・東北大学大学院教授
バイオインフォマティクス分野で、高度なビッグデータ解析を実現する〜渋谷 哲朗・東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター 准教授
次世代シークエンサーの発展により、医科学・生物学の分野では膨大な量のデータが産出されるようになりりつつある。これらのビッグデータに対して、新たな情報処理アルゴリズムの基板研究開発によってこれまで不可能だった解析を可能とし、医科学を新しい次元へ進展させることをめざす研究を行なっているのが、東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター・シークエンスデータ情報処理分野の渋谷 … [もっと読む...] about バイオインフォマティクス分野で、高度なビッグデータ解析を実現する〜渋谷 哲朗・東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター 准教授