パンデミックの恐れがあるとして、G7などのサミットで主要課題として挙げられている薬剤耐性(Antimicrobial Resistance :AMR)。一般に抗生物質と呼ばれる抗菌薬の濫用などによって、病原細菌に薬が効きにくくなるというもの。この薬剤耐性を制御するためには、ヒト(人)だけでなく、動物や環境を含めた総合的な健康リスク対策が必要で、それを「One Health(ワンヘルス)」と呼んでいる。しかし、この薬剤耐性のリスクが、世の中にどのくらい広まっているのかは、明らかになっていないのが現状である。この実態を把握するため、世界に先駆けて日本とベトナムの都市で薬剤耐性菌の調査を行っているのが、東京大学 先端科学技術研究センター 春日郁朗准教授である。今回は、ベトナムでの薬剤耐性菌の実態や取り組み、そして今後の展望についてお話を伺った。

メタゲノム解析を用いて、環境での薬剤耐性菌を可視化
Q:研究の概要についてお聞かせください。
まずは「薬剤耐性菌」についてお話しします。何らかの感染症にかかると、病院で抗生物質(以下、抗菌薬)を処方されると思います。抗菌薬は、人間の細胞には無害のまま、病原細菌だけを殺すことができる細菌感染症の特効薬です。かつての戦争では、戦闘で直接亡くなる人よりも、怪我や負傷をして細菌感染症で亡くなる人のほうが多かったと言われています。しかし、1929年以降次々と発見された抗菌薬のおかげで、諦めるしかなかった細菌感染症が治るようになったことは、人類にとって革命的なことだったと言えます。
しかし、あまりに重宝する薬だったこともあり、濫用による問題が発生してきました。抗菌薬は使いすぎると、細菌の薬に対する抵抗力が高くなり、薬が効かなくなってきてしまいます。この菌のことを「薬剤耐性菌」と呼びます。
抗菌薬を発見・開発しても、すぐに新たな薬剤耐性菌が出現してしまう「いたちごっこ」が続いており、強力な薬剤耐性菌に対する「最後の切り札」といわれる抗菌薬はあと2〜3種類しかないと言われています。今ではそれらに対しても耐性をもつ菌も現れ始めています。ちょっとしたケガでも、そこから化膿して命取りになりかねない、という時代に逆戻りするリスクに直面しているのです。
現在、世界で最も多い死因はがんで、年間死亡者数は約800万人となっています。エイズやマラリアは、それぞれ年間70万人です。一方、薬剤耐性菌が直接の要因で亡くなっているのは年間約100万人程度と言われています。もし、このまま薬剤耐性菌に対して何の対策も行わない場合、2050年には薬剤耐性菌による死亡者数は年間1000万人にも達し、現在のがんによる死亡者数を超えると予測されています。国連総会、WHO、G7サミットなどでも、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の前から、この薬剤耐性菌への対策が主要議題として取り上げられています。日本でも、2016年にアクションプランが策定され、対策が進められているところです。
薬剤耐性菌がまん延する要因は、いくつかあります。1つは先ほども紹介したように「抗菌薬の不適切な使用」です。抗菌薬は風邪を引き起こすウイルスには全く効きませんが、インフルエンザなどにも抗菌薬が効くと考えている一般の方はかなりいることがわかっています。正しい知識がないと、抗菌薬の使用が中途半端になったり、過剰になったりして、薬剤耐性菌が選択されやすくなることが懸念されています。
もう1つの大きな要因としては、抗菌薬がヒトだけではなく、家畜などの動物にも大量に使われていることが挙げられます。これは、動物の感染症予防に加え、成長促進の目的もあります。現在、畜産における抗菌薬利用の見直しが進められていますが、大量の抗菌薬を使う動物も、薬剤耐性菌のホットスポットなのです。家畜の排泄物に含まれる薬剤耐性菌が適切に処理されないと、放流先の水環境が耐性菌で汚染され、薬剤耐性菌が拡散されることになります。
ヒトや動物から排出される薬剤耐性菌は、最後は環境に集約されていき、再びヒトや動物に循環する可能性があります。このように薬剤耐性菌を制御するためには、ヒトだけでなく動物や環境を含めた総合的なリスク管理が必要です。それを「One Health(ワンヘルス)」といい、薬剤耐性菌対策の重要なコンセプトになっています。
現在、日本では「ヒト」(病院)と「動物」(畜産)に関する薬剤耐性菌の体系的なサーベイランスは行われています。しかし、「環境」のモニタリングは手つかずの状態です。この状況は、日本だけでなく世界的にも当てはまります。環境には多種多様な薬剤耐性菌が存在しているので、モニタリング指標をどうすればよいのか、コンセンサスがなかなか得られていないのです。また、薬剤耐性遺伝子はある細菌から別の細菌に移行することができるため、例えば病原性のない細菌から病原細菌への薬剤耐性の移行も問題になりえます。その場合、病原細菌だけではなく、薬剤耐性遺伝子を保有しているキャリアの細菌も幅広く監視する必要があり、検査はますます難しくなってしまいます。こうしたことにより、環境での薬剤耐性のサーベイランスが進んでいないのです。
Q:研究の独自性はどこにありますか?
私たちのラボでは、調査が手つかずになっている「環境」や「下水」における薬剤耐性菌の存在状況や水平伝播の実態の把握を進めています。下水というのは、都市住民の腸内の平均的な情報が得られるサンプルです。ヒトについては薬剤耐性菌のサーベイランスが行われていると言いましたが、これはあくまで病院での検査の結果です。実際には健康な人も薬剤耐性菌を保菌しているので、都市住民全体の薬剤耐性菌の情報は実はよくわかっていません。また、下水はヒトと環境をつなぐ重要なルートにもなっており、下水処理における薬剤耐性菌の挙動は、環境への放出を考える上でも、とても大切です。
「環境」や「下水」のような複雑な試料中の薬剤耐性菌の組成や量を可視化し、そのリスクを軽減することが、私たちの研究の一番の目的です。現在の状況で、一体どれだけ薬剤耐性菌の健康リスクがあるのかを定量化して示さないと、薬剤耐性菌対策の合意形成も難しいと思います。
私たちは、下水中の薬剤耐性菌も含むすべてのDNAを解析する「メタゲノム解析」と言う方法に注目しています。この場合、事前にターゲットを決める必要がないので、薬剤耐性遺伝子の組成を網羅的に把握することができます。また、すべてのデータを取得してデータベース化できるので、例えば、将来、新興の薬剤耐性遺伝子や薬剤耐性菌のアウトブレークが起きるような場合でも、データを過去に遡って検索すれば、いつ、どのようにこの遺伝子や細菌が都市に侵入して、拡散していったかという情報を推測することも可能になると期待しています。
Q:具体的な研究事例を教えていただけますか?
ベトナムで行った薬剤耐性菌の調査事例をご紹介いたします。私は、2018年から2021年まで、JICAの専門家としてベトナムの日越大学 環境工学修士課程プログラムに赴任していました。その間、ベトナムの下水や環境中の薬剤耐性菌の研究を行いました。ベトナムは世界的に見ても、薬剤耐性菌による健康リスクが顕在化しています。病院内での薬剤耐性菌の検出率も、日本をはるかに上回る状況になっていますし、健康保菌者の割合も極めて高いことが知られています。
ベトナムで薬剤耐性菌の問題が深刻になっている要因としては、抗菌薬の濫用があります。日本では医師の処方があって初めて入手できるような抗菌薬が、ベトナムでは薬局に行って処方箋なしで購入できてしまいます。結果的に、一般市民の自己判断で抗菌薬が使用されてしまい、薬剤耐性菌の選択が起こりやすい状況にあると言われています。
もう1つ私が着目しているのは「下水の処理」の問題です。日本における汚水処理の人口普及率は9割以上に達していますが、ベトナムでは1割にも満たない状況です。残りの9割は未処理のまま環境に放出されていることになります。つまり、未処理下水と共に、薬剤耐性菌も環境に拡散しているということです。こうした未処理下水で汚染された河川水の多くが、農業などに再利用されている実態があります。ベトナムでは、日本同様、生野菜を食べる食文化があるので、野菜の洗浄が不十分であると、食を介して薬剤耐性菌を体内に再び取り込んでしまうリスクはかなり高いのではないかと予想しています。体内で増えた薬剤耐性菌が下水として放出され、水環境や食品を汚染するわけですので、薬剤耐性菌が都市、水、食と循環しているという構図が推測できます。これまで、下水処理というのは、単に水質を浄化するという点のみが重視されてきましたが、ベトナムのような国では、社会における薬剤耐性菌の循環を抑止するという効果も大きいのではないかと考えています。
ベトナムでは、サーベイランスにかけられるコストも限られています。そこで、我々はWHOが推奨している「三輪車プロジェクト(Tricycle Project)」というサーベイランスを、国立感染症研究所の先生方と共同して、2020年から試行しています。三輪車というのは、ワンヘルスの「ヒト」、「動物」、「環境」を指しています。このプロジェクトの目的は、セフォタキシムというヒトの治療に重要な抗菌薬に耐性のある大腸菌を共通の指標として、ヒト、動物、環境における薬剤耐性の状況を把握することです。同時期に日本でも調査を行うことで、ベトナムと日本の状況を比較しているところです。
一例として、都市下水の状況をお話したいと思います。調査はちょうど新型コロナウイルス感染症が蔓延し、ベトナム国内や日本国内への外国人の入国が厳しく制約された時期に行われました。外国人観光客が非常に少なかったため、それぞれの国におけるベースラインのデータを得ることができたとも言えます。我々の調査によると、日本の下水に比べて、ベトナムの下水中のセフォタキシム耐性大腸菌の割合は約4倍も高いことが明らかになりました。都市下水には病気の人だけではなく、無症状の保菌者の情報も含まれています。この数字は、ベトナムの都市住民の間に薬剤耐性菌が広く蔓延していることを明確に示していると言えます。
ワンヘルスの考え方を反映した、監視方法を導入していきたい
Q:研究において課題として感じている点はありますか?
環境における薬剤耐性菌のリスクをどのように評価するのか、それを基にどのような基準を設定すべきか、という点は大きな課題だと思っています。多種多様な薬剤耐性菌をどう扱うか、ある細菌から別の細菌への薬剤耐性遺伝子の移行のリスクをどう見積もるか、など難しい問題は多くあります。現在、環境中の薬剤耐性菌の基準を設定している国は日本を含めてありません。どの程度のリスクが環境にはあるのかがわからなければ、リスク制御にかけるコストを見積もることもできません。不確定要素が多い問題だからこそ、データに基づいた議論を行うことがとても重要だと思っています。
Q:今後企業とはどういった関わり方を求めていらっしゃいますか?
薬剤耐性はSDGsには明示的には取り上げられていないのですが、健康、医療、水、食品、消費、生産、教育など、SDGsがかかげる様々な目標と密接にかかわっています。SDGsを具体化した問題とも言えると思います。国際的にも、国内的にも薬剤耐性やワンヘルスはますます重要な課題になっていくと思います。下水だけではなく、食や医療、健康などの異なるセクターの企業の方々とも連携をとって、薬剤耐性の制御を社会実装化していく研究を行ってみたいと考えています。
Q:この分野を目指す学生に対してメッセージはありますか?
日本では、かつて深刻な公害や衛生問題が起き、それらを解決するために多大な努力が払われてきました。その結果、著しい汚染は無くなり、私たちは快適な生活環境を手にすることができています。しかし、その快適さの裏側にはまだまだ課題があるということはなかなか知られていません。少しでも手をゆるめると、これまで築き上げてきたことが崩れかねないのです。例えば、水道や下水道などの水インフラにしても、施設の老朽化や人手不足が顕在化しており、持続可能な運用が各地で問題になっています。薬剤耐性菌だけではなく、脱炭素などの新たな制約条件も増えています。快適な生活環境や公衆衛生を今後も維持していくためには、まだまだ研究していかなければならないことは山ほどあります。興味があれば、是非研究室をのぞきに来てもらえればと思います。
Q:今後の目標を教えてください。
日本とベトナムという異なる背景のフィールドで、下水や環境の薬剤耐性菌の研究を地道に行っていきたいと考えています。そこで得られた薬剤耐性菌のデータをもとに、ワンヘルスの考え方を反映した薬剤耐性菌の監視方法を両国で社会実装できるように働きかけていきたいと思います。ワンヘルスがヒト、動物、環境という異なる分野の連携であるように、研究を通して様々な分野の産官学の方々と連携していきたいと思います。そうすれば、1つの健康(ワンヘルス)を実現する道が拓けてくるはずです。(了)
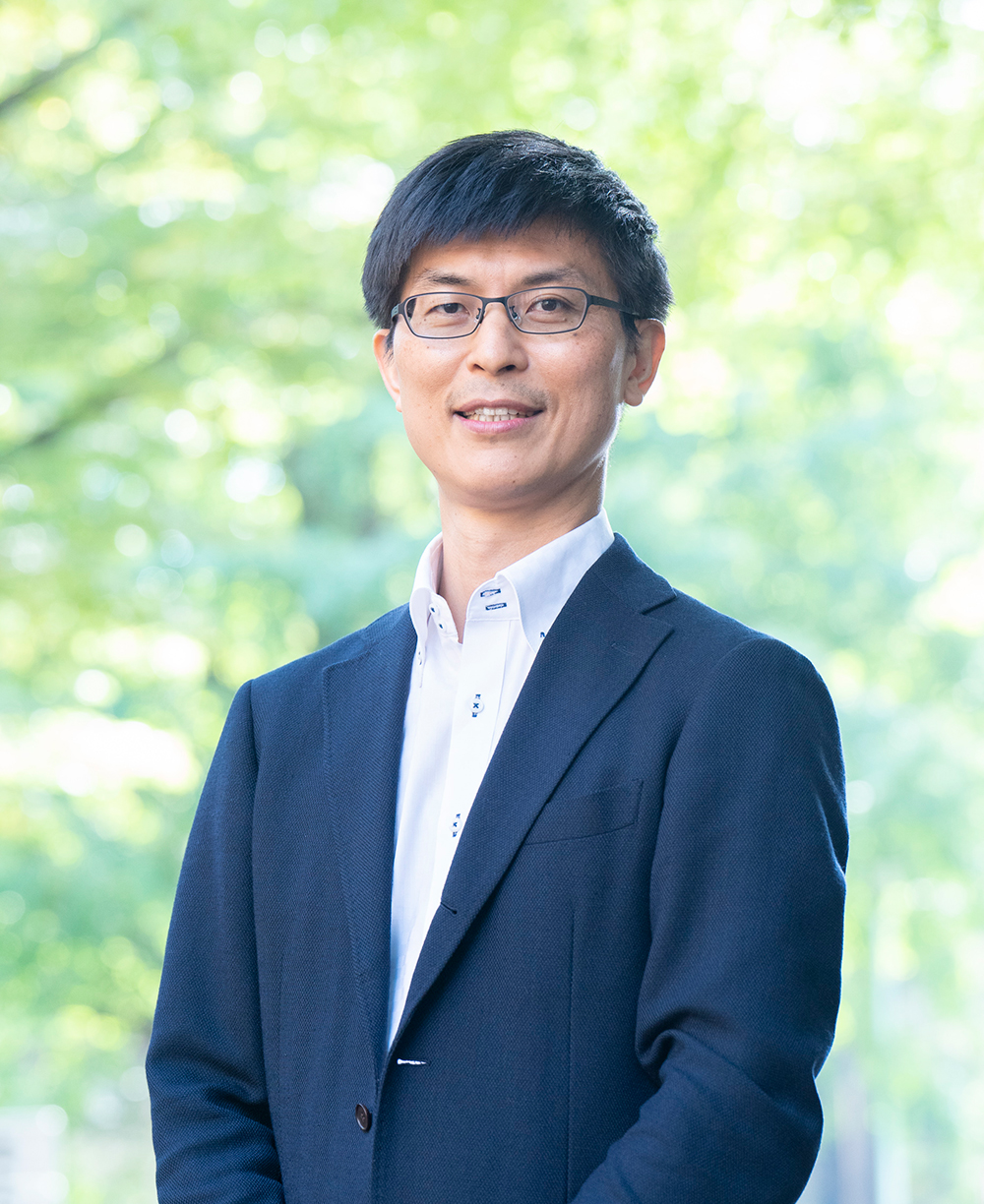
春日 郁朗
(かすが・いくろう)
東京大学 先端科学技術研究センター 准教授
2005年 東京大学工学系研究科 博士課程修了。博士(工学)。2006年6月より東京大学工学系研究科 助手、助教、講師を務めたのち2016年に准教授として就任。2022年より現職。
