新しい薬の開発は、これまで「効くか、効かないか」で判断されることが多かった。しかし、現代医療では「なぜ効くのか」「どのように効くのか」を正確に説明することが求められている。東京大学大学院 工学系研究科バイオエンジニアリング専攻の津本浩平教授は、物理と化学の視点から創薬を支える「創薬物理化学」という分野に取り組んでいる。薬が体内でどう働くのかを分子レベルで解析し、より効果的で安全な治療法の確立に挑んでいるのだ。特に、微生物由来のタンパク質や酵素を応用した創薬に注目し、それらが標的分子とどのように結びつき、病態にどう作用するのかを解き明かそうとしている。今回は、津本先生に「微生物を活用した次世代の薬づくり」や「創薬における物理と化学の役割」について伺った。
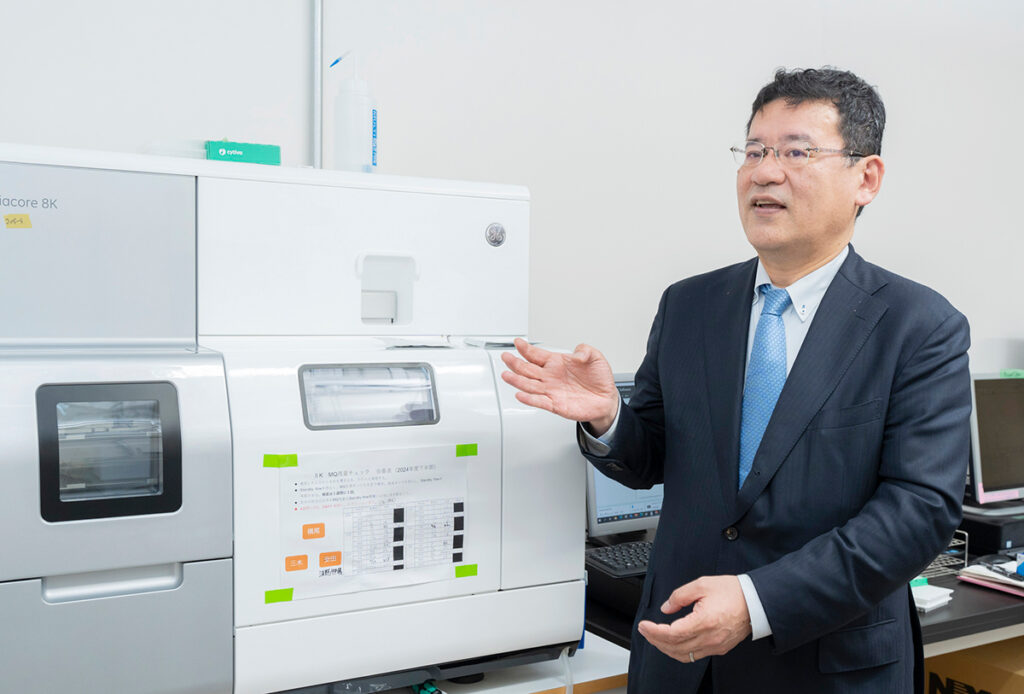
医薬品の設計を支える“工学の力”
Q:研究概要を教えてください。
現在、私が取り組んでいるのは、薬が生体内でどのように機能し、標的となる分子とどのように相互作用するのかを分子レベルで解明する研究です。従来、薬は「効く・効かない」という観点だけで評価されてきましたが、現代医療では「どうしてこの薬が効くのか」「なぜ副作用が少ないのか」といった仕組みを、科学的な根拠に基づいて説明することが求められるようになってきました。
また、患者一人ひとりの病状や体質に合わせて薬の性質を“設計する”アプローチにも取り組んでいます。必要な作用をどのように発揮させるか、副作用をいかに抑えるかといった目的に応じて、分子構造を精緻に最適化していく。こうした創薬のアプローチを物理と化学の視点から支えているのが、私たちの専門領域です。
このように、物理と化学の両面から、薬が体内でどのように働くのかを分子構造や結合のメカニズム、分子間相互作用などを通じて理解する学問があります。それを「創薬物理化学」と言います。薬がどのように作用するのか、あるいはなぜ期待通りに働かないのかといった問いに対し、分子レベルの論理とデータで答えることを目指しています。
低分子医薬品は、構造が比較的単純です。しかし近年、がんや自己免疫疾患など、従来の低分子では治療が難しかった病態に対し、抗体医薬などの高分子医薬品が登場しています。これらは、タンパク質そのものを薬効成分とするため、より高度な分子設計と解析が求められます。
高分子化合物が取り扱いにくい最大の理由は、高分子は「単分子パーティクル(粒子)」として、構造体としての分子的性質と粒子としての集合的性質という二重の特性を有している点にあります。すなわち、単一分子でありながら、物理的には粒子としての挙動も示すため、全体を把握するためには、分子構造の解析と粒子レベルでの挙動解析という、異なるスケールの視点を組み合わせる必要があります。
こうした高分子に対する体系的な教育・研究は、主に工学部や農学部で行われてきました。一方、薬学部では、医薬品の薬理作用や製剤技術に重点が置かれているのが現状です。そのため、高分子医薬品の設計や作用機序の解明においては、工学的な視点に立った物理化学的知見が極めて有効に機能します。
Q:高分子医薬品の研究において工学的な知見が必要とされる背景について、もう少し詳しく教えていただけますか?
もともと工学部では、高分子材料や機能性物質の設計を通じて、物質の構造・特性・挙動の関係性を物理・化学的に捉えることが学術的に体系化されています。高分子薬物すなわち抗体医薬やペプチド製剤などは、粒子(パーティクル)としての性質を有する一方で、分子レベルでは極めて厳密かつ複雑な三次元構造を有しています。そのため「粒子としての集合体的性質」と「構造体としての分子的性質」の双方を同時に理解する必要があるのです。
このような二重性を踏まえた設計・評価は、工学や農学領域で長らく蓄積されてきた知見が大いに活かせるところです。対照的に、薬学部においては薬効・薬理・製剤に重点を置いた教育が中心であり、高分子の構造解析や設計に必要な理論体系については、現在体系化が進められているところです。創薬において物理化学的知識が求められているのは、こうした背景があります。
なお、高分子医薬品が注目を集めるようになったのは1990年代中頃からです。特に1997年に乳がん治療薬として登場した抗体医薬「ハーセプチン」が大きな契機となりました。従来であれば外科的切除が不可避とされていた症例において、薬理作用の機序が分子レベルで解明され、有効性と安全性が科学的に示されたことにより、高分子医薬の可能性が広く認識されるようになりました。
Q:現在、注力されている研究について、教えていただけますか。
大きく2つあります。1つは抗生物質が効かなくなった耐性菌(AMR: Antimicrobial Resistance)に対する新たな治療薬の開発です。特に欧米を中心に深刻化しているAMRの問題は、従来の抗菌薬の限界を浮き彫りにしており、がん治療薬のように、分子レベルで標的を捉えて作用する新しいタイプの医薬品が求められています。
私たちの研究では、特定のタンパク質に高い親和性で結合する分子を設計することで、難治性の病原菌に対して高精度に作用する薬剤の開発を目指しています。こうした取り組みは、感染症がグローバルな脅威となる中、既存薬が効かない劇症型細菌感染症にも対応できる可能性を秘めています。
現在は基礎研究段階にありますが、製薬企業との連携も視野に入れながら、相互にテーマを提案し合う形での共同研究へと発展させることを目指しています。さらに、これらの新薬候補が本当に人に効くかを見極めるためには、表現型スクリーニングだけでなく、標的分子への結合や作用機序を物理化学的に可視化する手法が極めて重要です。
従来の創薬開発では、実験動物での効果がそのままヒトにも適用されると見なされがちでした。しかし実際には、動物とヒトとではタンパク質構造や血流動態などが異なるため、実験では「効く」と判断された薬剤がヒトでは効果を示さないケースが少なくありません。こうした背景から、私たちは「本当に標的分子に結合しているのか」「その結果、どのような分子レベルの反応が引き起こされているのか」を明確に示す技術の構築にも取り組んでいます。
このようなアプローチは、医師が患者に対して薬の効果や副作用の根拠を説明する上でも大きな意味を持ちます。例えば「この薬はこの受容体に確実に結合し、炎症を引き起こす分子の働きを止めているため、効果が高く、副作用も抑えられます」といった説明が可能になることで、治療の納得感と精度が大きく高まるのです。
もう1つは、AI技術を活用した「ゼロからの抗体設計」です。これまでも抗体医薬の改良は進められてきましたが、真に新規分子を創出する、いわば「創薬の出発点」に立つ試みは、いまだ十分には実現されていません。私たちは、物理化学的データや独自の測定値をもとに、AIが有効に機能する設計環境を構築しようとしています。
従来のAI創薬では、遺伝子情報や既存の化合物データベースが主に活用されてきました。しかし、私たちの研究で扱うパラメータはより抽象的で、結合強度、立体構造の変化、分子間力の性質など、実験的な測定を伴う高度なデータです。こうした情報は一般的な創薬データベースには蓄積されておらず、自らが測定して初めて意味を持つものです。そのため、私たちは独自の視点と実験により、AIが扱えるデータセットを拡充し、「本質的な分子設計」を行うことを目指しています。
一時期は「そんなデータを集めても意味がない」と評価されなかったこれらの取り組みも、近年ではその重要性が再認識されつつあります。現在は、自らの切り口で、ゼロから新しい薬を設計できる環境を整え、まさに“創薬の主導権”を自らの手で握ろうとしています。
特に重要なのは、病気の変化に柔軟かつ迅速に対応できるスピードです。がん細胞などの標的分子は常に変異を繰り返し、進化しています。このような「イタチごっこ」とも言える状況を打開するには、AIと物理化学を組み合わせた分子設計が鍵となります。この手法により、薬の臨床導入までの期間を大幅に短縮できる可能性があります。
また、こうした研究は国内製薬企業の新たな競争力の源泉にもなり得ます。海外の巨大製薬企業が資本力で臨床試験を展開する一方、日本では、独自技術と研究開発の質で勝負する必要があります。その中で、AIを活用した分子設計の技術は、短期間で高精度な薬剤を設計できる戦略的手段となると考えています。
私たちの取り組みは、既存の技術や知識の延長線上にあるのではなく、新たな創薬の地平を切り拓くためのものです。人類の福祉に貢献するという工学的理念のもと、未来の医療に貢献する創薬の基盤を築いていきたいと考えています。
Q:この研究における独自性はどんなところにありますか?
最大の独自性は、「薬がなぜ効くのか」という根本的な問いに対し、物理化学的なパラメータに基づいて、精緻に可視化する点にあります。従来の創薬物理化学では、分子構造の静的な解析に留まることがほとんどでした。
私たちはそこから「なぜその分子が特定のタンパク質と結合するのか」「結合した後にどのような変化が生じるのか」といった、構造と機能の因果関係について、動的・定量的に記述することができます。
このようなアプローチは、物理学や工学の分野で蓄積されてきた知見と技術を医薬品設計に応用するものであり、創薬の枠組みに新たな視点をもたらすものです。私たちは、単なる計測にとどまらず、取得したデータを基に薬剤設計の最適化や疾患機構の理解に資する解釈体系を構築してきました。
さらに、医療現場との接続を意識した研究スタンスも大きな特徴です。単に専門家に向けた理論構築にとどまらず、医師や患者に対しても「この薬はこう作用するから効果が期待でき、副作用が起こりにくい」といった説明を支援する科学的根拠の提供を行っています。この「理解に資する可視化」は、治療選択の納得感やエビデンス・コミュニケーションの質を大きく向上させると考えています。
このような取り組みを積み重ねることで、次第に「津本に聞けばいい」と周囲から認知されるようになり、研究コミュニティの中で自然と“ハブ”としての立ち位置が形成されてきました。こうした評価は、特定の手法や成果だけでなく、周囲からの信頼や実績によって醸成されたものと受け止めています。
その結果、他大学からの客員教授としての招聘や集中講義の依頼も継続して増えています。物理学の研究手法を医薬品開発という応用領域へ展開したことで、「古典的な技術が異なる文脈で新しい価値を持つ」という学際的転換が評価されていると感じています。まさに異なる分野をつなぎ、創薬に新たな可能性をもたらす──それが私たちの研究のもう一つの独自性です。
創薬の次なる使命──「誰もが使える薬」を社会に届けるために
Q: 創薬研究を社会に実装する上で、直面する課題は何でしょうか?
現代の創薬においては、単に有効な薬剤を開発するだけでは不十分であり、それをいかに持続可能な形で社会に実装するかが、極めて重要な課題となっています。なかでも最大の障壁のひとつが「医療経済の制約」です。高い治療効果をもつ薬剤が開発されても、その価格が非常に高額である場合、限られた人しかアクセスできないという状況が生じます。
例えば、薬価が1回あたり4000万円もする治療薬があったとします。こうした薬剤は、たとえ有効性が明確であっても、保険制度や医療機関の負担能力を超える場合が多く、特に国民皆保険制度を採用する日本では制度そのものの持続性にも関わります。私たちの研究では、こうした高コスト薬を、数十分の一に抑える技術的可能性を提示しており、医療アクセスの観点からも注目されています。
このような背景のもと、創薬研究に求められる役割も変容しつつあります。「効く薬をつくる」ことにとどまらず、「誰もが使えるかたちで社会に届ける」ことが、創薬の重要な使命となりつつあるのです。つまり、薬の社会実装とは、単なる技術革新だけでなく、医療経済や倫理、制度設計といった多面的な課題に対応する総合的な取り組みとして捉え直す必要があります。
さらに、アカデミアと産業界の連携にも課題が残ります。特にスタートアップ企業との共同研究では、契約の柔軟性や資金面の不均衡が障壁となることが多く、研究成果の社会還元を加速するためには、制度面の整備が不可欠です。こうした状況を踏まえ、私自身もスタートアップの立ち上げを構想しています。これは単に研究成果を実用化する手段ではなく、医療イノベーションを迅速に社会へ届ける新たなエコシステムの構築でもあります。
創薬は今、効果や安全性だけでなく、価格、供給体制、実装スピードまでもが評価の対象となる時代に突入しています。私たちも、科学的な知見と社会的視点の両面から、より持続可能で包摂的な医療の実現に貢献していきたいと考えています。
Q:この研究を志す学生にメッセージはありますか?
最近の学生を見ていると、これまで以上に「正解」を早く求める傾向が強くなっているように感じます。正解が見えていないと動けなかったり、未知の領域に踏み出すことを躊躇したりする姿も珍しくありません。「誰も手をつけていないからこそ挑戦してみよう」という柔軟で主体的な姿勢を持つ学生は、以前に比べて少なくなった印象があります。
もちろん、明確な課題を提示すれば、素早く的確に対応する学生も多く、非常に頼もしく感じます。しかし、まだ答えの見えないテーマに一緒に向き合おうとする場面では、躊躇や戸惑いが見られることもあります。その背景には、「失敗することへの恐れ」があるのでしょう。
ただ研究とは本質的に未知と向き合う行為です。失敗は避けるべきものではなく、むしろ新たな発見の入り口です。正解が見えないからこそ、自分で問いを立て、手探りで進む。その姿勢こそが、研究の醍醐味であり、今後ますます重要になっていくと思います。
さらに、これからの時代は、キャリアのあり方そのものが大きく変わっていきます。例えば、一度企業に就職してから大学に戻って研究を再開する人や、医師・エンジニアなどの専門職から異分野に転身する人も増えています。ひとつの道に縛られず、自分らしい選択を重ねながら生きていくことが、より当たり前の時代になりつつあります。
ですから、「これが正解」という一本道のキャリアを目指すのではなく、自分の興味や偶然の出会いを大切にして、時には遠回りをしながらでも、自分のペースで歩んでほしいと思います。むしろ、その寄り道が結果として、最短距離になっていることも多いのです。
文系・理系といった枠組みも次第に意味を失いつつある今、分野を越えて考え、つなげていく視点と柔軟な発想こそが、新しい時代の研究を切り拓く力になると、私は信じています。
Q:企業に伝えたいことはありますか?
今は企業だけ、大学だけといった“単独プレイヤー”では、もはや複雑な課題に十分対応できません。特に創薬のように専門性が高度で、長期的な視点が求められる領域では、競争すべき部分と協調すべき部分を明確に切り分けたうえで、知恵やリソースを持ち寄る「共創の場」が不可欠です。
なかでも、意思決定権をもつプレイヤー同士が集まり、建設的な議論を交わせるようなコンソーシアムの形成は、今後ますます重要になっていくと考えています。単なる情報交換ではなく、具体的なアクションへとつながる関係性が求められています。
加えて、産・学・官がそれぞれの立場を越えて信頼関係を築き、国全体として創薬力を底上げしていく視点も欠かせません。私自身、創薬が持つ高い公共性を常に意識しており、研究者としての立場から政策への助言や、実務現場への橋渡しといったかたちで貢献できればと考えています。
立場の異なる者同士が互いの価値観や役割を理解し、力を合わせて課題解決にあたる。そうした連携の積み重ねが、これからの医療を支える確かな基盤になっていくでしょう。
Q:今後の展望を教えてください。
私たちがこれまで蓄積してきた物理化学的な視点や方法論を、より多くの研究者や医療関係者と共有しながら、「本当に有効な薬」を自らの手で生み出すための基盤を整えていきたいと考えています。単に知識を伝えるのではなく、それを現場でどう活かすか、実践的な“方法”として定着させていくことが、大きな目標です。
また、創薬分野において価値ある成果を継続的に生み出すためには、優れた人材が国内で育ち、活躍し続けられる環境の維持・発展が欠かせません。特に若手研究者に対しては一つの評価基準にとらわれることなく、多様な視点で課題に取り組む姿勢を養ってほしいと願っています。
これまで私たちの研究アプローチは、ときに「コストがかかる」「リスクが高い」として敬遠されることもありました。しかし実際には、時間や費用を抑える工夫を重ねており、そうした取り組みこそが次世代のスタンダードになっていくはずです。
今後も、先入観や誤解にとらわれることなく、研究の意義や価値を丁寧に伝えながら、幅広い理解と共感を得ていけるよう努めていきたいと思います。(了)

津本 浩平
(つもと・こうへい)
東京大学 大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻
教授
1991年 東京大学 工学部 工業化学科卒業。1993年 東京大大学院 工学系研究科工業化学専攻 修士課程修了。1997年 博士(工学)取得(東京大学)。1995年 東北大学助手(大学院工学研究科生物工学専攻)、2001年 東北大学講師(大学院工学研究科生物工学専攻) 、2002年 東北大学助教授(大学院工学研究科生物工学専攻)を経て2005年 東京大学助教授・准教授(大学院新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻)に就任。2010年 東京大学教授(医科学研究所 疾患プロテオミクスラボラトリー)。2013年より現職。
