脳血管疾患では、罹患後に生じる運動や高次機能障害の予後不良性、そしてその結果として増す介護負担など、長期にわたるさまざまな課題が問題視されている。こうしたなか、脳に残された回路を呼び覚まし、病気やけがで失った神経機能を回復させる研究が注目を集めている。BMI(ブレイン・マシン・インターフェース)と呼ばれるこの装置の開発研究に取り組んでいるのが、慶應義塾大学理工学部 生命情報学科の牛場潤一准教授だ。自身の研究領域を「リハビリテーション神経科学」と定義し、医学部との連携を行ないながら実証研究に取り組む牛場准教授に話を伺った。

脳に残る力を引き出すテクノロジー
Q:まずは、研究の社会的なニーズについて教えてください。
脳卒中を中心とした、脳のケガや病気についての研究をしています。
脳卒中は脳の血管に障害が起こり、その先の神経細胞に栄養がいかなくなってしまい、脳の一部の組織が死滅してしまう病気です。
さらに、脳卒中になった方の約半数近くの人が、運動の障害を患ってしまうこともわかっています。私は、そういった障害を治療するようなリハビリテーションの研究にずっと携わってきました。
脳卒中自体の患者数は、日本国内でおよそ130万人と言われています。死因でいうとがんなどに続いて第4位ぐらいで、数だけを見れば少し下がってきているといえます。しかし、それは脳卒中で直接的にお亡くなりになる方の数についての話で、脳卒中になった後、運動の障害を持ったまま生きていかなくてはいけない方は依然として多くいらっしゃいます。
現在、日本だと国からの介護保険がありますが、介護が必要になる理由の1位は脳卒中です。脳卒中になって介護が必要になり、健康寿命が終わってから生物学的な寿命を迎えるまでに男女とも10年ぐらいありますが、その間ずっと介護の問題が続くわけです。
ご本人も離職をしなければならないばかりか、周りの人もケアをするために介護離職をする方もかなり多くいます。国も介護費を支払い続けるわけですから、ご本人や家族だけでなく税負担者にも、大きく長年にわたって負担がかかってしまうわけです。
日本は高齢化も進んでおり、少ない働き手の人たちで大勢の患者を支えなければいけない状態です。そういった問題を少しでも解決していくために、私たちは脳機能の治療方法を開発したり、治療できないまでも再び充実した生活を送るために便利な福祉機器を開発したりしています。患者さんひとりひとりが社会復帰していくことを、テクノロジーの力でアシストしたいと考えて研究をしています。
Q:こうした課題に対し、どういった解決アプローチがありますか。
大きく2つの流れがあります。
まずひとつめは、残された身体をうまく利用することです。例えば右手が麻痺してしまったら、左手だけでも服を着たり、ごはんを食べられるように工夫する、家を改造し麻痺した身体でも生活できるようにするなどの、代替的なアプローチです。古典的なリハビリテーションでは、このアプローチが広く取られます。
もうひとつの流れは、麻痺した身体にアプローチをして運動機能を直していくというアプローチです。麻痺した手足そのものに、セラピストが徒手的に介入して、関節を動かす訓練をしたり、ものを持たせる訓練をしたりするなどの方法があります。ただ、実際のところ残念ながらそういったアプローチは、特に重い麻痺に対しては効き目が限定的であることが知られています。
そこで私たちは、人間の脳がまだ潜在的にもっている「治る力」を引き出してあげるようなテクノロジーを開発して、これまでの治療ではなかなか回復しないといわれていた重度の麻痺の患者の運動機能を、脳卒中によって壊れてしまったところ以外の別の脳の場所に肩代わりさせて、機能の回復を誘導する技術の開発をしています。
高齢になると脳の機能は変わりにくくなりますし、脳卒中によって脳組織に傷が付いていて、麻痺も非常に重くて、1年以上も経っている慢性期となると、コンディションとしてはとても不利です。患者さんがこういう状態にある場合、標準治療では運動機能障害はもうこれ以上治らないとされています。
しかし私は、もう少し脳の仕組みそのものに立ち返って考えてみることにしました。特定の条件さえ満たせば、高齢な脳であっても、脳の一部に傷があっても、脳に残っている「治る力」や「柔らかに機能を書き換える力」を引き出してあげることができるのではないか、と考えたのです。
脳が本来持っている力を引き出すテクノロジーをつくることができれば、これまでは難しいだろうといわれていたことも可能になる。こうした考えで、研究を続けてきました。
Q:脳の力を引き出すためには、具体的にどんな方法がありますか。
研究のひとつに「ブレイン・マシン・インターフェイス」(以下、BMI)というものがあります。髪の毛をかき分けた皮膚の表面に直径約1センチの電極を貼り付け、そこから電位信号を計測します。この電位には、脳のなかにある神経細胞の電気的な活動が反映されています。
ここにいくつかの信号処理を施すことで、治療の標的となる、身体の運動を司る脳の領域のシグナルだけを、感度よく取り出します。
ここで注意していただきたいのは、BMIは、脳卒中によってできてしまった傷そのものではなく、その傷のすぐ近くにある生き残っている神経細胞の活動を見ている、という点です。
脳から筋肉に向かって運動指令を送る、いわば「ケーブル」のような神経が脳卒中によって途中で切れてしまっていると、運動指令は途中で止まってしまう、これが麻痺です。しかし脳の中では、様々な神経細胞がお互いに手足を伸ばしてくっつき合っていて、信号を相互にやりとりしています。そのため、神経の一部分が切れていても、ほかの神経を迂回して筋肉に運動指令を送り届けることができるように、「代償経路」と呼ばれるバイパス部分が存在しています。
代償経路は、健康なときには使っていなかった部分でもあるので、ある神経経路が脳卒中によって予期せず切れたあと、次からこの経路を使いなさいと急に言われても、すぐに使うことができません。でも頑張ってここを鍛えれば、壊れた神経経路自体が再生しなくても運動命令を脳から筋肉に向かって送ることができるわけです。
つまり、BMIの治療のターゲットはこうした代償経路なのです。
BMIを使って最初にシグナルを測ろうとしたときに、全然反応がなくても、シグナルすらなくてもいい。まずは、治療のターゲットになる代償経路の活動を感度良く読み出すセンサーを使って、バイパス部分がどういう活動状態になっているかを画面上に表示し、本人に伝えます。
次に、麻痺している手にロボティクスを取り付けて、手を開こうと思った時に脳のなかの代償経路が活性化したら、ロボットのスイッチを自動的に入れます。手の動きがアシストされて、動いたという情報が、身体の中の感覚神経を通して脳にフィードバックされる仕組みです。
最初は、代償経路の活動を思いどおりにコントロールできていなくてもいいわけです。「とにかく試行錯誤して、手を動かそうと努力してください」とお願いします。麻痺した手を動かそうとしたときに、脳に不適当な反応が出たり、あるいは本人は頑張っているつもりでも代償経路からの信号が全く出ない場合、ロボットは動きません。その場合は、もう一回やり直します。再びトライしたときに代償経路が活動して、偶然でも信号が出たとします。するとBMIがそれを検出してロボットのスイッチが入り、手の動きがアシストされます。患者にとっては、こうしたBMIの動作を通じて「こんなふうに運動をイメージすれば、脳の中の代償経路が活動してくれるのだ」という実感が湧くわけです。
こういった練習を繰り返し行なっていけば、だんだんと自分の意図に基づいて脳内の代償経路を活動させることができるようになります。
以上が私たちの開発した、BMIの訓練方法です。1日40分ほど試行錯誤をして、それを10日間ほど続けます。
毎日訓練を続けていくことで、脳の中に残存している神経回路が徐々に活性化するため、最後は治療装置を外した生身の状態でも、代償経路を自分の力で駆動させて、手を動かすことができるようになるというわけです。
これまでに、標準治療がなく、脳卒中発症後半年以上も経ってしまった慢性期の患者を対象に、40例以上にBMI訓練を実践してきました。そのうち、約7割の患者で、一定程度の運動機能の回復を誘導できることがわかってきました。
Q:現在の研究に行き着くまでには、どんなきっかけがありましたか。
私自身、理工学部に所属していましたが、もともと医学の研究とか患者の役に立つものをつくることに興味がありました。実は大学に進学するタイミングで、私の祖父が脳卒中になり、私が知っている祖父が様変わりしてしまったのです。言葉を喋れなくなり、車いすの生活になってしまったことで生活も一変、本人もすごくつらそうでした。
こうした経験から、人の助けになるようなことがしたいと考えました。自分が小学生の頃からもともと好きでやってきた人工知能やプログラミングの勉強など、テクノロジーを活かした形で、祖父のような患者の助けになりたい、と感じたのです。
学生のとき、日中は理工学部で技術の勉強をし、夕方お医者さんの診察時間が終わったタイミングで医学部のキャンパスに移動して、毎日のように医師や療法士の先生方と神経生理学の研究に取り組んでいました。
当時、アメリカの教育スタイルにあこがれていて、理工学を専攻しながら医学も専攻する「ダブルメジャー」とか「メジャーマイナー」などと呼ばれる仕組みが自分には必要だと思っていました。当時、大学には正式にそういった制度はなかったので、ひとりで勝手に「ダブルメジャー」をしていたわけです。
私のバックグラウンドはプログラミングやものづくりですから、そういうものを使わなければできない医療をつくりたいと考えていました。患者さんと触れ合う機会はお医者さんのほうが多いし、資格を持っていて医療行為そのものに携わることができますよね。普通に考えたら、医療従事者が研究をするほうが圧倒的に有利なわけです。
だから、彼らが持っていなくて、そう簡単には真似できなくて、でも自分にはできる技術やノウハウを活かして医療をつくっていかなければ、自分が医学研究をする意味はないのではないか。そんなふうに、学生のときから独自性とはなにかを考えていました。
既存の治療方法との連携をデザインする
Q:今後の研究課題として、どんなものがありますか。
技術的な課題については、脳活動の検出感度を上げるということがあります。脳波計測は簡便ゆえにノイズが入りやすく、人によってはなかなか良い信号がとれないという部分がありますね。
もうひとつは、治療のターゲットとなる脳領域をきちんと同定するような技術を開発し、そこからの信号だけを選択的に読み出す、精度の高い信号分析技術の開発が必要です。治療のターゲットになる脳の領域は、患者さんによって場所が少し違っている可能性があります。脳卒中による脳の傷つきかたがまちまちなだけでなく、もともとの脳の配線構造が人によって微妙に異なっているからです。
脳という臓器は、ある一定の環境条件を満たせば、柔らかに機能を書き換えていくことが知られています。私たちが思ってもみないぐらいの変化をすることもあります。ただ、そういった現象の背後にある基本原理が何なのかということについては、まだ正確に分かっていない部分が多くあります。
何かの条件が成立すると脳の機能はものすごく書き換わるのですが、少しでも条件が満たされないと、脳の状態は全く変わらないことがあります。そういった、脳のまだわかっていない部分についてのサイエンスにも、しっかり向き合いたいですね。
そうすることで、BMIでは治せなかった残り3割の人を治す方法も見つかるかもしれません。脳卒中だけではなく、脊髄損傷やパーキンソン病といった様々な神経由来の運動障害の治し方をもっと自由に、もっと力強く、発明できるかもしれません。
続いて産業的な課題面でいうと、標準的な医療ではない革新的な治療方法であればあるほど、臨床の現場であるクリニックや病院で行われている治療との間に大きな乖離があります。
そこに対して、「飛び地」としてつくった革新的な技術をハーモナイゼーションすることと、人々がそれをひとつのツールとして使いこなせるようになっていくためのスキルセットの提供が重要です。また、他の治療方法との連携・連動の仕方をデザインすることも大事です。このBMIはこういう患者に使えますよ、10日間の訓練でここまでできますよ、ここまできたらあなたの病院で普段行なっているこの治療をやってくださいね、といった「流れ」のことです。
臨床の現場は、現行のやり方で大勢の患者さんに対処しながら毎日が忙しく過ぎていて、新しいものを取り入れていくインセンティブがない状態です。使い方やスキルセットも含め、トータルのパッケージでプロデュースしていかなければなりません。
Q:研究室にはどんな学生がいますか。
学生は、18人です。4年生から配属が始まり、大学院、社会人博士もいます。テーマによっては医師や療法士とペアを組んで、臨床研究に参加させてもらうこともあります。
進学動機は様々ですが、医療や看護にもともと興味のある人が来ることが多いです。あとは、プログラミングやロボットが好きで、何か人の役に立つようなことにそうした技術を応用してみたいと考えている人もいますね。
大学での研究では、既存のものの考え方を変え、いままでにない新しい価値を生み出していくことに挑戦していきます。世の中の当たり前を疑い、新しい視点を提案し、それを自分たちで証明していきながら形にしていきますよね。
自分一人で研究をやって終わり、ではなくて、研究会などで少しずつ議論を深めていきながら、自分の考えを磨いていったり、賛同者を増やしていったりしていくわけです。ですから、自分の考えを人に伝える力を養っていくことも大切だと思います。
この分野に限らずですが、何か新しいことをやろうというときに一番必要なのは、パッションだと思います。何か言われたり笑われたりしても、「自分が信じる道はこれだ」という気持ちで続けられる力があるかどうかが重要です。
学生を見ていて時々心配になるのは、「自分は〇〇が得意だから、将来はこの仕事を選んだ方がいいと思う」といった自己分析をしていることです。自分はこれに向いてるとか、これが得意だとか、そういう技能的な分析なんか二の次なんじゃないの?と、声をかけるようにしています。
苦手でもいいから、「寝ても覚めてもこれをやりたい、その先を見たい」と思ってしまうような、熱中できる対象をまず見つけるようにして、将来はそういう道に進むべきだという話をしています。
Q:企業とはどんな関わり方が必要でしょうか。
私たちは、リハビリ医療をテクノロジーの面から革新していきたいと考えています。社会的意義が大きいという話をしましたが、マーケットという意味では、一般的な市場性からすると大きいとは言えません。
産業構造上の問題で、リハビリの医療機器をやっている国内メーカーの規模は小さいです。大きな投資ができないし、革新的なものを生みだす体力が十分にないというのが現状ではないでしょうか。VRやAR、ウエアラブル・ロボティクス、ライフログ・センサといった、革新的な一般市場製品を開発・普及をしている人たちの力を借りながら、リハビリ医療のテクノロジーを大きく育てていきたいと思っています。
いまの世の中には、たくさんの魅力的なセンサやディスプレイ、それにロボットなどがあります。潜在的な市場性も大きく、投資する意欲も大きいと感じます。ただ、彼らには、それを医療に応用したときの効果や安全性を検証するノウハウがありません。何かプロダクトをつくった時に、人がそれを身につけて生活した場合に体に対してどのような作用性があるのかを検証し、生活がどのように変容していくのかを理解していく必要がある。あるいは、行動変容を充分に起こさせるような機械設計する。こうした研究開発のやり方については、まだ効果的な方法が確立していないと思います。
私たちは、そうした部分のノウハウを提供できます。皆さんが持っている技術資産をプラットフォームとして一緒に医療応用製品を開発しましょう、その代わり、リハビリの分野では私たちにその成果物を利用させてください。たとえばそのようなやり方で、一緒に研究開発に関わっていけたらいいなと思っています。
Q:最後に、今後の目標について教えてください。
まずはBMIを実用化して、患者の手の届くところまで持っていきたいですね。
もうひとつは、脳を治すテクノロジーや、人間拡張テクノロジーを生み出すために必要な、脳の基本的な動作原理を理解していきたいです。そこは大学のサイエンスとして突き詰めなければいけないポイントだと考えています。多少粗くてもいいので、脳がどのような仕組みで動いているのかがわかれば、それをもとにしてデバイスを自由に設計することができるようになります。そのために必要な「ものの考え方」そのものを自分の手で生み出していきたいですね。(了)
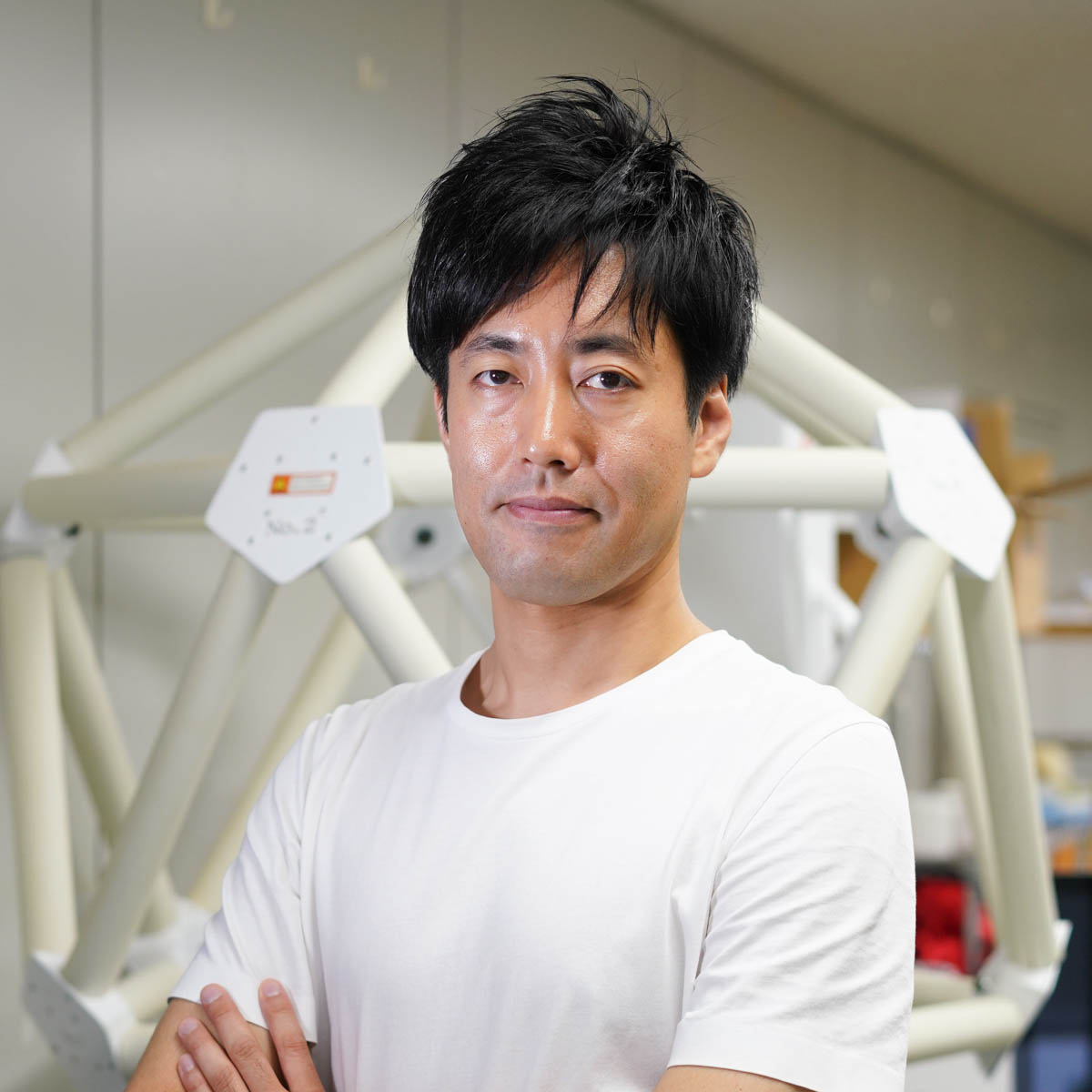
牛場 潤一
うしば・じゅんいち
慶應義塾大学理工学部生命情報学科 准教授。
2001年、慶應義塾大学理工学部物理情報工学科 卒業。2004年に博士(工学)取得。
同年、慶應義塾大学理工学部生命情報学科に助手として着任。2007年より同専任講師となる。
2012年より現職。2014-2018年、慶應義塾大学基礎科学・基盤工学インスティテュート(KiPAS)主任研究員。
2019年より研究成果活用企業Connect株式会社 代表取締役社長を兼務。
共著書に『バイオサイバネティクス 生理学から制御工学へ』(コロナ社)がある。
