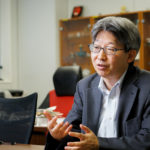日本国内でも年々認知が高まりつつある再生医療であるが、細胞は個別単位にばらばらの状態で移植しても治療効果が不十分であり、組織工学と呼ばれる、細胞から組織単位のものを培養作製し移植する技術が求められている。日本国内における組織工学の黎明期から20年以上研究を続けているのが、東京女子医科大学先端生命医科学研究所の清水所長。臨床医でありながら、この分野のエンジニアとして基礎研究も行なう清水所長は、細胞シートの研究開発、および臨床応用を推進し、現在ではiPS細胞から人の心筋細胞シートをつくることができるまでになるなど、めざましい成果をあげている。基礎研究と臨床応用の両面で期待を集めている清水所長に、現時点での組織工学の成果について伺った。 ティッシュエンジニアリングで組織を丸ごと移植する Q:組織工学研究の概要についてお聞かせください。 再生医療の研究自体は … [もっと読む...] about 組織工学の研究で、生体移植を実用化する〜清水達也・先端生命医科学研究所 所長
Bio/Life Science
バイオメカニクスの観点から、ヒトの歩行の仕組みを解明する〜荻原直道・慶應義塾大学理工学部教授
人が歩くメカニズムは、単純そうにみえて非常に奥が深い。歩くメカニズムを解明することで、臨床医学やロボット工学への応用が可能になるとされ、新たなアプローチでの歩行研究に期待が寄せられている。こうしたなか、「歩く」の起源にせまるべく、ヒトおよび霊長類の運動機能と身体構造の進化メカニズムを機械工学的視点から研究しているのが、慶應義塾大学理工学部機械工学科の荻原直道教授だ。人間の歩行の仕組みを理解することで、からだの動きに関わる様々な分野のベースになると考える荻原教授に、ニホンザルの二足歩行研究を中心とした現在の研究手法について伺った。 機械工学をベースに、二足歩行のメカニズムと進化を探る Q:まずは、歩行研究の社会的なニーズについて教えてください。 もともと機械工学科の出身で、航空宇宙工学の勉強をしたいと思って大学に入りました。しかし大学で学ぶうち … [もっと読む...] about バイオメカニクスの観点から、ヒトの歩行の仕組みを解明する〜荻原直道・慶應義塾大学理工学部教授
線虫の行動ルールの解明から、脳の仕組みを解き明かす〜飯野雄一・東京大学大学院理学系研究科教授
人間の脳を知るためには、脳を構成している細胞を研究することが必要である。しかしながら、脳全体の細胞の数は膨大なものになり、全体を一度に研究することは現実的に難しい。そこで必要になるのが、人間よりも細胞の数がすくない実験動物の観察である。今回取材に伺った東京大学理学系研究科 … [もっと読む...] about 線虫の行動ルールの解明から、脳の仕組みを解き明かす〜飯野雄一・東京大学大学院理学系研究科教授
化学の視点から、ヒトと動物の嗅覚研究に切り込む 〜東原和成・東京大学大学院教授
「嗅覚」は人間にとっても動物にとっても必要不可欠なものであるが、嗅覚を理解するためには、匂いやフェロモンがどのように感知され、それがどのように脳に伝わり、最終的なアウトプットである行動や生理的な変化、情動の変化が起こるかといった一連の流れをすべて解明する必要がある。従来の研究では、神経生理学や分子生物学など、特定の分野に限った研究が主流であったため全貌の解明が難しいといわれていた。こうしたなか、匂いやフェロモンを情報物質=化学シグナルととらえ、有機化学の視点から新たなアプローチを実現しているのが、東京大学大学院 農学生命科学研究科の東原教授だ。今回は嗅覚研究のアプローチ手法と、人間社会と香りとの向き合い方について伺った。 化学シグナルの受容という観点から、嗅覚を研究 Q:研究の概要からお聞かせください。 五感のひとつ、嗅覚を研究しています。嗅覚はもと … [もっと読む...] about 化学の視点から、ヒトと動物の嗅覚研究に切り込む 〜東原和成・東京大学大学院教授
トランスポーターを標的とした創薬研究で、小児難病を克服する〜林久允・東京大学大学院助教
生後間もない小児の肝臓疾患のなかには、治療に肝移植が必要となる難病がある。しかしながら肝移植には、提供元の肝臓数が足りないという問題がつきまとう。そこで一つの解決策となるのが、薬によって小児肝臓疾患を治療することだ。そんななか、トランスポーターの機能が低下することで病気が起こるというメカニズムから、トランスポーターの機能を改善するべく新規薬物療法の開発を指向した創薬研究をすすめているのが、東京大学大学院薬学系研究科 … [もっと読む...] about トランスポーターを標的とした創薬研究で、小児難病を克服する〜林久允・東京大学大学院助教
ショウジョウバエの神経研究で、聴覚の仕組みを解き明かす〜上川内あづさ名古屋大学 大学院理学研究科 教授
生物の「聴覚」はさまざまな音から適切な情報を取り出し瞬時に判断する高度なシステムであるが、その聴覚の仕組みを解き明かすためにはどんな研究が有効であろうか。その一つの研究アプローチとして、ショウジョウバエの聴覚系が哺乳類の聴覚系と類似することに着目し、人間の聴覚システムの理解につなげる試みを進めているのが、大学院理学研究科の上川内あづさ教授だ。研究の対象としてショウジョウバエを選んだ経緯とその理由、研究の先にある人間の聴覚システムの理解へのゴールマップについて、上川内教授に話を伺った。 音を使ったコミュニケーションの基本を研究する Q:まずは、研究の概要についてお話しください。 まず、私たちは必ずしも人間を理解したいと思って研究をしているわけではなく、自然界の仕組みを理解したいという観点から研究をしています。 ですからショウジョウバエを理解したいわ … [もっと読む...] about ショウジョウバエの神経研究で、聴覚の仕組みを解き明かす〜上川内あづさ名古屋大学 大学院理学研究科 教授
マウスの透明化技術で、生命システムの時間の解明に取り組む〜上田 泰己・ 東京大学教授
生物の体の組織は細胞で構成されているが、その細胞ひとつひとつを観察することができれば、治療や研究に大きな成果をもたらすことができる。組織を構成する細胞の観察のために有効なのが、透明化だ。これまで組織の透明化の技術はさまざまな研究者が挑戦してきたが、2014年にCUBICという方法でマウスの全身透明化を実現させたのが、東京大学 医学系研究科 機能生物学専攻システム 薬理学教室の上田 … [もっと読む...] about マウスの透明化技術で、生命システムの時間の解明に取り組む〜上田 泰己・ 東京大学教授
現場ニーズに即し、生体イメージング技術を自らの手で生み出す~西村 智・自治医科大学教授
生活習慣病の発症に重要な炎症は、血管と組織の境界部分にしばしば認められる。一方で、従来の観察手法ではアプローチが困難という課題があった。そのような中で、光を用いた独自の生体イメージング手法を開発し可視化を行ない、実態の解明及び新規治療法の開発を目指しているのが、自治医科大学分子病態治療研究センター分子病態研究部の西村智教授だ。現場に即した生体イメージング技術を重視し、自らも機器を開発する西村教授に、医学部としては珍しい研究手法について伺った。 現場での撮影課題を解決する Q: … [もっと読む...] about 現場ニーズに即し、生体イメージング技術を自らの手で生み出す~西村 智・自治医科大学教授
微小管の研究で、細胞分裂の特性を明らかにする~佐藤 政充・早稲田大学先進理工学部教授
不妊や流産、がんの原因を解明する研究において、細胞分裂時の異常が原因の一つに挙げられる。細胞分裂時、遺伝情報を伝えるために染色体を正確に2個の細胞に分配する役割を持っているものを「微小管」と呼ぶが、この微小管の異常が不妊や流産、がんに関係しているとされている。こうしたなか、微小管研究に正面から取り組み、医療への応用も視野に入れているのが、早稲田大学 先進理工学部 生命医科学科の佐藤政充教授だ。今回は佐藤教授に、微小管研究の基本と応用について伺った。 細胞内で重要な役割をはたす微小管 Q: … [もっと読む...] about 微小管の研究で、細胞分裂の特性を明らかにする~佐藤 政充・早稲田大学先進理工学部教授
自然免疫の研究で、アレルギーを引き起こすメカニズムを解明する~茂呂 和世・理化学研究所チームリーダー
昨今、さまざまなアレルギーが報告されており、社会問題となっている。アレルギーは先進国特有の症状であることがわかっており、また明確なアレルゲンがわからないままアレルギー症状を発症させるケースも散見される。なぜアレルギーが起こるのかを考えるにおいて重要なキーとなるのが、人間が生来もっている自然免疫だ。免疫系は体内に侵入した異物の排除に重要な役割を持つ一方、アレルギーの発症にも関与するためだ。この自然免疫を解明することで、アレルギーの原因を追求することができる。こうしたなか、「ILC2」とよばれる自然リンパ球の発見によって、アレルゲンがない状態で起こるアレルギーのメカニズムを説明したのが、理化学研究所生命医科学研究センター自然免疫システム研究チームの茂呂和世チームリーダーだ。今回は茂呂チームリーダーに、これまでに説明がつかなかったアレルギー症状を解明する大き … [もっと読む...] about 自然免疫の研究で、アレルギーを引き起こすメカニズムを解明する~茂呂 和世・理化学研究所チームリーダー