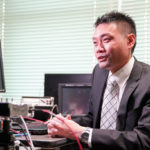全世界で省エネが注目される昨今、ニーズが高まっているのが、電気を扱う新たな半導体素子の開発である。従来、大きな電力を扱う半導体はシリコンで作られていたが、その代替として注目されているのが、ワイドギャップ半導体だ。このワイドギャップ半導体を用いた新しいエネルギー創出技術に取り組んでいるのが、名古屋工業大学大学院工学研究科電気・機械工学専攻 … [もっと読む...] about 省エネ・創エネの観点からワイドギャップ半導体を開発する〜加藤正史・名古屋工業大学 大学院工学研究科 電気・機械工学専攻 電気電子分野 准教授
シミュレーションと機械学習の融合で、社会問題を解決する〜 平田晃正・名古屋工業大学 大学院工学研究科 電気・機械工学専攻 教授
「医工連携」領域の研究においては、倫理的に検証の難しい医療分野の問題を予測・解決する手法として、計算によるシミュレーションが有効である。こうした視点から、電磁界や熱などの物理的負荷によってヒトの体内で生じる物理量と、それによって誘発される生理応答を統合し、計算機上でモデル化する手法で注目されているのが、名古屋工業大学大学院工学研究科/電気・機械工学専攻の平田晃正教授だ。 携帯電話が出す電波の人体に与える影響を調べる技術から始まり、現在は分野横断的な研究に取り組んでいる平田教授に話を伺った。 医工連携・異分野融合するための技術開発 Q:研究の概要を教えてください。 「生体」におけるシミュレーションを、複数のテーマで研究しています。 シミュレーションによる予測技術が本当の意味で進化すると、AIではなくシミュレーションですべてが可能になると予想されています … [もっと読む...] about シミュレーションと機械学習の融合で、社会問題を解決する〜 平田晃正・名古屋工業大学 大学院工学研究科 電気・機械工学専攻 教授
運動器疾患の発症メカニズム解明から創薬を考える 〜稲田 全規・東京農工大学大学院 生命工学専攻 准教授
運動器である骨・歯・筋はからだの運動を司り、動くこと、歩くこと、食べることを支えることから、これらが病(疾患)に陥いることにより、著しく生活の質( QOL:Quality of Life)が制限される。運動器の疾患は、社会の高齢化や生活習慣と密接に関連し、予防するには個々の病の発症要因を正確に突き止める必要がある。運動器疾患を生命科学からアプローチし、これらの疾病の発症メカニズムの解明と創薬への開発を目指した研究を行なっているのが、東京農工大学大学院 生命工学専攻の稲田 全規 … [もっと読む...] about 運動器疾患の発症メカニズム解明から創薬を考える 〜稲田 全規・東京農工大学大学院 生命工学専攻 准教授
水供給システムの研究で、持続可能な社会像を描く〜小熊 久美子・東京大学大学院工学系研究科 准教授
世界には、水システムの整備が不十分で安全な水を十分に得られない地域が多くある。こうしたなか、水を安定的に持続可能な形で供給するためのシステムづくりと浄水技術についての研究に取り組んでいるのが、東京大学大学院工学系研究科 小熊 久美子 … [もっと読む...] about 水供給システムの研究で、持続可能な社会像を描く〜小熊 久美子・東京大学大学院工学系研究科 准教授
生殖細胞学の観点から、不妊のメカニズムを解明する〜林克彦・九州大学医学研究院教授
不妊症は社会問題のひとつであり、その治療と原因究明が望まれている。生殖細胞の発生過程を体外培養系で再構築するべく、哺乳類の生殖細胞の発生・分化について、分子生物学や細胞生物学的な手法を用いて研究に取り組んでいるのが、九州大学医学研究院の林 克彦 … [もっと読む...] about 生殖細胞学の観点から、不妊のメカニズムを解明する〜林克彦・九州大学医学研究院教授
高分解能データの推定技術で、超高精細な結晶構造解析を実現する〜星野 学・理化学研究所 創発物性科学研究センター 物質評価支援チーム 研究員
物質を構成している原子や分子がどのように集合しているのかを観察するための方法として、X線結晶構造解析がある。X線結晶構造解析は、結晶中の原子配置を精度良く評価して、被験物質の性質を解明する研究手法としてすぐれているが、試料の放射線損傷やX線光子数の少なさが原因で高分解能データが得られないと、解析精度が低下するという弱点がある。こうしたなか、計測できない高分解能データを推定・発生する技術により、超高精細とも言えるX線結晶構造解析を実現させるべく研究を進めているのが、理化学研究所 創発物性科学研究センター 物質評価支援チーム … [もっと読む...] about 高分解能データの推定技術で、超高精細な結晶構造解析を実現する〜星野 学・理化学研究所 創発物性科学研究センター 物質評価支援チーム 研究員
新世代3Dプリンターの開発で、地産地消をつくる〜梅津 信二郎・早稲田大学 創造理工学部 総合機械工学科 教授
3Dプリンターの登場後、「個人がつくりたいときに物をつくることができる」社会への期待が高まっている。こうしたなか、単なる趣味を超えた「社会にとっての最適な地産地消」を理想系とし、3Dプリンタが日常に溶け込んだアーキテクチャを構想しているのが、早稲田大学 創造理工学部 総合機械工学科 の梅津 … [もっと読む...] about 新世代3Dプリンターの開発で、地産地消をつくる〜梅津 信二郎・早稲田大学 創造理工学部 総合機械工学科 教授
遺伝子研究から、嗅覚の謎を解き明かす〜廣田 順二・東京工業大学生命理工学院 生命理工学系 准教授
嗅覚は五感のなかでも研究がすすんでおらず、手付かずの未解明の問題がまだまだ残されている。嗅神経系の成り立ちと機能の理解を目指し、遺伝子レベルから個体レベルまでの化学感覚研究を広く行なっているのが、東京工業大学生命理工学院の廣田 順二 准教授。長大なゲノムDNAを安定に操作するための技術開発とその応用研究というゲノム工学技術領域にも携わる廣田 … [もっと読む...] about 遺伝子研究から、嗅覚の謎を解き明かす〜廣田 順二・東京工業大学生命理工学院 生命理工学系 准教授
放線菌の研究で、新物質を見つける、生み出す〜大西 康夫 ・東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
天然の抗生物質の3分の2程度を生産するのが、複雑な形態分化と二次代謝産物の多様性に特徴づけられる細菌「放線菌」である。「発酵学」すなわち「応用微生物学」の分野で、この放線菌に関わる研究に力を入れているのが、東京大学大学院農学生命科学研究科の大西 … [もっと読む...] about 放線菌の研究で、新物質を見つける、生み出す〜大西 康夫 ・東京大学大学院農学生命科学研究科 教授
生態発生学の観点から、多様な動物の進化を解明する〜三浦 徹・東京大学大学院理学系研究科 附属臨海実験所 教授
動物の革新的な進化は、いかにして起こるのか。これら発生過程を解明するべく、さまざまな種類の動物の生活史や発生機構について研究を行なう学問が、生態発生学と呼ばれる学問である。この生態発生学の第一人者として知られるのが、東京大学 大学院理学系研究科 附属臨海実験所の三浦 … [もっと読む...] about 生態発生学の観点から、多様な動物の進化を解明する〜三浦 徹・東京大学大学院理学系研究科 附属臨海実験所 教授