地球上の環境・資源問題を解決するためのヒントとして、宇宙に滞在するための技術開発によって生まれたエコ技術、再生技術を応用するというアプローチがある。こうしたなか、光エネルギーを化学反応エネルギーへと変換する光機能性材料を開発・応用して環境汚染物質や有害微生物の除去、ありふれた資源から化学品や薬剤などの有用物質を作り出す研究に取り組んでいるのが、東京農工大学大学院・農学研究院・生物システム科学部門の 中田 一弥 准教授。今回は中田准教授に、宇宙での技術開発がもたらす環境資源技術の進歩の可能性について伺った。
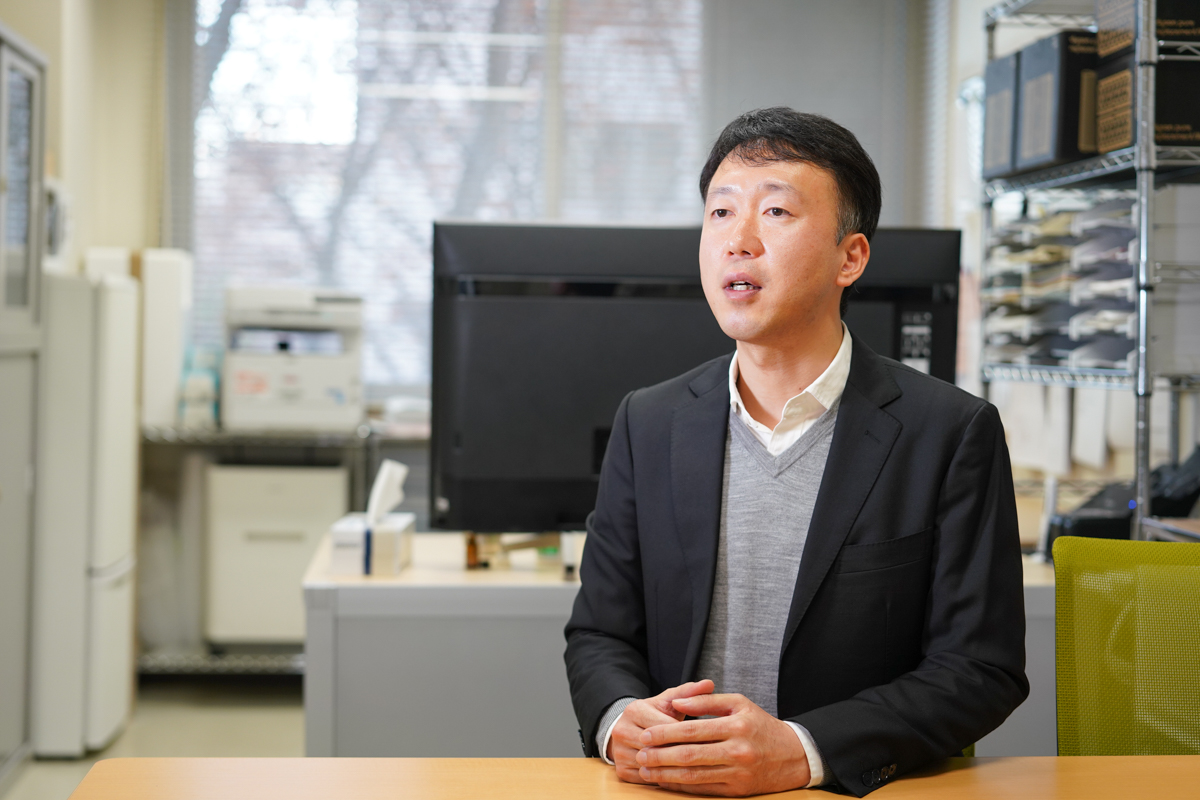
光触媒の技術であらたな有用物を生み出す
Q:研究の概要について教えてください。
環境資源技術は「環境技術」と「資源技術」の2つに分けることができます。
環境技術は、環境を綺麗にしましょうとか維持しましょうといった環境に関すること、資源技術はエコやリサイクルというような資源に関することを指します。それらを合わせて環境資源技術と呼んでいます。
私は東京農工大学の環境資源科学科というところに所属しています。私の研究とまさに合致した学科だと思いますが、そもそも日本で「環境」という名前を付けた初めての学科がこの環境資源科学科だそうです。
私が東京農工大学に来たのは2019年の4月でして、前職は東京理科大学にいました。東京理科大学には宇宙飛行士の向井千秋さんが特任副学長としていらっしゃって、宇宙に関するプロジェクトをやっています。私もそのメンバーというか、当時4つのチームがあった中で、環境に関するチームのリーダーをしていました。
そこではスペースコロニーというプロジェクトがありましたが、それは例えば宇宙の月面みたいなところで長期間にわたり暮らすための技術に関する研究に取り組むプロジェクトです。宇宙というと星座や天文学、あるいはロケットや衛星といったイメージを持つ方が多いかもしれません。一般の方もなんとなく興味を持ってくれるのですが、いざ宇宙を研究対象にするとなると、ちょっと現実味がないというか距離感があると思います。
スペースコロニーのプロジェクトは、宇宙で暮らすための技術を開発するものです。それはつまり衣・食・住で、私たちの生活や仕事の多くが衣・食・住に関わりがあると思うんです。そうすると、ぐっと距離が近くなるというか身近なものに感じられますし、実際に研究対象としても捉えやすくなるはずです。
宇宙の場合、特に環境分野に関していうと、国際宇宙ステーションが地球の周りを回っていますが、その中に長期間滞在するためには環境を維持しなくてはなりません。
例えば、人間は酸素を吸い込んで二酸化炭素を吐き出していますが、それを宇宙にある密閉空間の中でやってしまうと二酸化炭素ばかりが増えてしまいます。そこで、二酸化炭素をリサイクルして酸素に戻さなければなりません。あとは、水もそうですね。水を飲んで尿として排出するわけですが、その尿をリサイクルして水に戻すことも必要でしょう。
このようにあらゆるリサイクル技術が必要になってきますし、そもそも宇宙はものが少ない空間ですよね。国際宇宙ステーションもそうですが、外はほとんど真空ですし、本当にどんなものでも貴重なんです。それこそ、排泄する便ですら私は貴重な資源だと思います。それらをいかにリサイクルしていくか、少ない物資をいかに有効なものに変えてあげられるかは、宇宙だけでなく日本という国にもいえることだと思います。
日本も資源が少ないし、環境にも関心が高い。日本が将来目指すべきことと宇宙でやろうとしていることは、目指すべきベクトルが同じなんです。世界的に見てももちろん大事ですが、まさに日本向けというか、日本にとって非常に大事なことだと思います。
Q:その中で、具体的な研究の柱はどれになりますか。
衣・食・住で言うと多分「住」にあたると思うのですが、いかに宇宙空間の中に長期間、より快適に住むか。今でも半年くらいの短い期間であれば、宇宙飛行士は国際宇宙ステーションに滞在することができます。
ただ、例えば数年とか数十年というスパンで宇宙に暮らしてみようとなると、今よりも様々な技術が必要になってくるので、そこを研究していこうと考えています。
私たちがやっていることは宇宙での環境を維持することで、リサイクルしていくことが基本になってきます。先ほどお話ししたように空気や水などは汚れてしまうので、リサイクルして元に戻す必要があります。
現状でも国際宇宙ステーションにはそういったリサイクルシステムがあるので、短期間であれば暮らせないわけではありません。ただ、より長期間、より快適に暮らすとなるとさらに技術が必要になってくるのです。
また、空気や水を普通にリサイクルして元の状態に戻すのではなく、新しいリサイクルの形も考えています。汚れた水とか汚れた空気でさえも、本当に貴重な資源です。それをなんらかの方法で変換してあげて、一度、有用物に変えてあげる。そうするとゴミだったものから有用物ができて、その有用物を宇宙で暮らすために必要なものとして使い倒していく。使い倒したあとのゴミは、元の状態に戻しましょうという感じです。
つまりリサイクルではあるものの、単に汚れたものを元に戻すのではなく、一度有用なものに変えてからもう一度使っていく。そこで本当に使い終わったら元の状態に戻すというような、新しいリサイクルができないかと今トライしているところです。
私たちが主に使っている技術は「光触媒」というもので、日本発、そして日本が一番進んでいると言われている技術のひとつです。光触媒は光を当てることによって化学反応を起こすような物質で、様々なところに使われていて実用化もされています。
例えば建物の外壁や窓ガラスに光触媒を塗ってあげると、通常、長年使っているとついてしまう車の排気ガスなどの汚れがなくなるというか、きれいな状態をキープしてくれる「セルフクリーニング」という作用があるんです。これは建物の壁や窓だけではなくて、今では鉄道のホームの上にテント素材の屋根のようなものがあったりします。通常だとテント素材って汚れて黒くなってくるのですが、ああいうところを光触媒でコーティングすると汚れにくくなるわけです。
現在、私は光触媒についての研究をしていますが、これは先ほどの宇宙のリサイクルの話にも繋がってきます。光触媒を使って、宇宙空間でリサイクルできないかというところが結論になります。太陽から降ってくる光という意味では地球上にもたくさんありますが、宇宙空間にも太陽光はたくさんありますので、光触媒をどんどん使っていこうと考えています。
宇宙の話に戻りますが、国際宇宙ステーションには空気の再生システムがあります。しかし、空気をきれいにする装置が大きくて重かったりするので、できるだけ軽くコンパクトにして、なおかつ高性能なものがほしい。それを実現するために、光触媒を搭載することで小型化できないかとか、そういった研究をしています。
水に関しては中に菌が含まれていることがあって、光触媒は殺菌ができるので、例えば光触媒を搭載した浄化装置などができないかということも研究対象になっています。
この他にも、暮らすことには食べ物も関係してきます。まだ将来の話なのですが、宇宙で食べ物をつくるとなると、植物工場みたいなところで葉っぱを育ててあげてというようなイメージがあると思うんです。もちろん、それはそれで食料の主要な取得元だと思います。
ただ、植物工場って実は結構ゴミが出るんです。皆さんも普段、野菜の葉っぱの部分は食べるけれど根っこの部分は食べないことって結構あると思います。私も様々な植物工場を見させてもらったのですが、根っこのゴミがポリバケツにたくさん捨ててあって。これどうしてるのって聞いたら、ゴミとして捨てていると。もしこれが宇宙だったら困るよなと思いまして、食事はできるかもしれないけれどゴミも大量に発生してしまうので、じゃあそのゴミをリサイクルしようと考えました。
根っこのゴミから何かしらの有用物をつくろうとする時、例えば植物は糖が結合したセルロースという物質からできていますが、それを分解すると糖になるわけです。私たちは光触媒の技術を使って、ある糖を別の糖に変換するという技術を開発しました。
セルロースを分解するとグルコース(ブドウ糖)になるのですが、そのグルコースに光触媒を作用させてあげると、希少糖というものができます。希少糖は最近注目されている糖で、健康食品や機能性食品、添加物、それから薬にもなるものです。
例えば希少糖のひとつであるアロースは、ガン細胞の増殖を抑制する効果があることもわかっています。あとは、私たちが普段ガムなどで目にするキシリトールも希少糖のひとつです。自然界に少ない糖のことを希少糖と呼んでいるのですが、キシリトールもこれにあたります。
キシリトールは人間が化学的に合成する方法をつくり出したので、今はすぐ手に入るものになっています。つくっているからたくさんあるだけで、自然界には少ないものです。そういった希少糖も、光触媒を使うことで簡単につくれるということを私たちが発見したわけです。
このようにゴミを原料にして、役に立つ有用物ができることがわかってきています。ゴミも資源になるということで、これらはすべて光触媒がキーワードになっています。光触媒って材料にはいろんな種類があるので、その材料を変えてあげると別の物ができます。
実用化に向け、研究開発を進める
Q:今後乗り越えていくべき研究の課題としてどんなことがありますか。
宇宙で使うことを想定しているので、実際に宇宙で長期間の実験をしたいですね。
机上では光触媒をこう使えばこういうことがうまくいくでしょうと考えることはできますが、実際には多分問題がたくさんあると思います。特に私たちがやろうとしているような、より長期間より快適に宇宙で暮らしましょうという時には、想定していないような問題が出てくると思うんです。だからこそ、実際に宇宙で長期間の実験をして、未だ見出していない課題を見極めたいという思いはありますね。
技術的な問題を挙げるなら、光触媒には反応効率が少し遅いという欠点があります。例えばそのビルの外壁などに光触媒を塗って、汚れがつかないようにします。汚れって少しずつ付いていくので、同じように少しずつ分解していけば基本的にはきれいな状態を保つことができます。このようにちょっとした反応をずっと続けていくことが、光触媒の得意分野なのです。
一方、短時間に大量の反応をやりましょうということは苦手です。ですから、そこに他の技術を組み合わせて補ってあげるとか、あるいは光触媒自体を改良してもっと効率を上げるとか、そういったところは今後の課題かなと思います。
例えば新しい光触媒をつくってあげるという話であれば、これは私たちの研究室だけじゃなくて、世界中の光触媒の研究者たちがこぞって競争していることです。
光触媒を水の中に入れて光を当てると、水が分解されて酸素と水素になります。特に水素はエネルギーになるので、水から水素をつくりたくてみんなこの研究をしているわけです。光触媒の欠点は効率が悪いところなので、なるべく効率を上げてあげましょうという部分で競争しています。
光触媒の材料で一番有名なのは酸化チタンというチタンと酸素からできているものです。そこでチタンを使わずにタングステンのような違う元素のものを使ってあげたり、あるいは1種類の光触媒だけではなく2種類3種類と組み合わせた光触媒を使って、新しく効率のいい光触媒をつくる方法もあるでしょう。あと、光触媒は基本的に表面で反応が起こるので、表面積が大きければ大きいほど反応効率が高くなります。なので、光触媒の形や表面積を含めたデザインを変えることで効率をあげる、そういった方法もアプローチのひとつかなと思います。
Q:研究室にはどんな学生がいますか。
農学部、環境資源科学科の学生さんが研究室に入ってきています。農学部はバイオ系のイメージがありますが、環境資源科学科については化学も結構強いです。環境や資源って、物質なども関わってくるので。
宇宙って様々な分野の複合なので、何かひとつの分野に強いのもいいと思いますが、それだけじゃなくてやっぱり様々な分野の人と関わり合いながら頭の中で考えを練り上げて、アウトプットしていくことが必要になってきます。その意味で柔軟さというか、人とコミュニケーションを取りながら物事を進めていける力は大事かなと思います。
Q:企業とはどんな関わり方をしていきたいですか。
企業さんとは(光触媒の研究をしていた)昔からお付き合いをさせていただいて、宇宙に関してもお付き合いのある企業さんに入っていただいて、例えば新しい光触媒の空気清浄機に向けた材料開発とか、そういうことを一緒にやっています。宇宙のメーカーというわけではなく、化学メーカーが興味を持ってくださっています。
先ほどお話しした希少糖についても、今ベンチャーの企業さんと取り組んでいるところです。企業さんの方から問い合わせが来ることもありますね。光触媒についての問い合わせはもちろん、新しい事業を見つけたいからというケースもあります。
やはり宇宙については参入しにくいですし、私たちは衣・食・住の考え方で進めていくので、たとえ普段やっていることの延長線上だといっても、じゃあ実際にどう行動したらいいのかと。
以前私が勤めていた東京理科大学のスペースコロニー研究センターには、そういう企業さんとか外部の方が入ってくれるコンソーシアムみたいなものをつくってあるんです。その中で一緒に情報を共有して、必要に応じて共同研究をやりましょうというシステムをつくってあるので、そういうところに入っていただくこともあるかと思います。
Q:今後の目標を教えてください。
やはり私たちの技術が宇宙で使われるようになってくれたらいいですね。
例えば国際宇宙ステーションでは二酸化炭素をリサイクルする時にメタンガスがゴミとして出ます。私たちは光触媒を使ってメタンガスを殺菌剤に変換することに成功しています。これを国際宇宙ステーションで、地球からの補給ではなく、ゴミのメタンガスから本当に殺菌剤を作って、それが国際宇宙ステーションの環境維持に大いに役立つとか。理屈としてできるものではありますが、実際に使ってもらっているというステップに上がりたいなと思っています。(了)

中田 一弥
なかた・かずや
東京農工大学大学院 農学研究院 生物システム科学部門 准教授。
2005年、東京都立大学大学院 博士(理学)取得。2005年、東北大学大学院 日本学術振興会特別研究員(PD)
2006年よりマサチューセッツ工科大学 日本学術振興会特別研究員(PD)となったのち、2007年 神奈川科学技術アカデミー 常勤研究員を務め、2013年より東京理科大学 准教授。
2019年より現職。
