電気自動車の普及など、100年に一度の変革期とされる自動車業界にとって、あらたな蓄電池の開発は必要不可欠である。こうしたなか、既存のリチウム電池の高機能化や、リチウムに代わるナトリウム電池の開発など、新時代のバッテリー開発に取り組んでいるのが、横浜国立大学大学院工学研究院 機能の創生部門の藪内 直明教授だ。人と車の新たな関係が生まれる未来の社会像に向けて、その根幹となるバッテリー技術にはどんなことが求められるのか、藪内教授に未来予想図を伺った。

電気自動車の時代に必要な蓄電池とは
Q:研究の概要について教えてください。
電気自動車の市場は、年々伸びています。ガソリンに依存しない社会をつくるため、あるいは大気汚染が問題になっている国もあるため、そういったことを背景にして電気自動車は普及してきたと言えるでしょう。2018年には、世界中の電気自動車の販売台数が200万台を突破しました。かなり多いように感じるかもしれませんが、自動車全体の販売台数は年間で約1億台と言われていますので、全体の2パーセントほどが電気自動車ということになります。
さて、従来の車ではエンジンが主役だった動力源も、電気自動車ではリチウムイオン電池とモーターに置き換わりつつあります。自動車業界は、100年に一度の変革期と言われるような時代を迎えているのです。
10年ほど前は、太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーは、火力発電や原子力発電などに比べて非常にコストが高いものでした。そういう状況で自然エネルギーに立脚した社会をつくることもできたのですが、そうなると電気代が異常に高くなり、経済的に苦しくなってしまいます。
それが現在では太陽光発電の値段がものすごく下がっており、例えば中東では今1 kwh 2.5円というコストでつくれるようになっています。日本だと同じ1 kwhで火力発電が約10円、原子力発電も同じぐらいです。中東の国は、石油を自分の国で掘って、それを火力発電に使って電気をつくるよりも、ずっと太陽が照っているので、太陽光パネルで発電したほうがむしろ儲かるのです。それによってどんどんコストが下がって、現在の値段になっているというわけです。
日本は天候がまちまちですのでそういうわけにはいきませんが、島国ですから風力発電はもっと活かせると思いますし、温泉も活発ですので地熱発電なども使えるはずです。本当に使えるようにするには様々なしがらみがあると思いますが、日本も自然エネルギーの資源には恵まれた国であるといえます。
以上の状況を踏まえて最後にどうしても必要になってくるのが、自然エネルギーからつくったエネルギーを一時的に蓄えるための方法です。
まず、現状で一番効率が良い方法は、蓄電池だと思います。コストはまだ少し高いのですが、利点を生かしつつコストを下げるような研究を少しやっています。太陽光発電も、過去10年で性能がすごく進化したわけではなく、生産技術がどんどん進化したことで安くなったといえます。そしてようやく蓄電池の存在にみなさんが気付きはじめたことで、社会的にも注目されるようになりました。実際にアメリカなどでは、自然エネルギーと蓄電池を組み合わせた充電がターゲットになってくるのではないかという話が出ています。
私自身も、少なくとも将来的には太陽光発電などの自然エネルギーと蓄電池の組み合わせのほうが、コスト的に安くなる時代がやってくると考えています。
そうなると、二酸化炭素をはじめとする様々な問題も解決できると思いますし、日本も外国に依存することもなくなるはずです。非常に取り組む価値のある研究だといえますね。
電気自動車で言われているのは、「エネルギー密度」の問題です。ガソリンに比べるとエネルギー密度が低いので、どうしてもかさばってしまい、走行距離が短くなってしまいます。
そこで研究室としては、エネルギー密度をどんどん上げていくための研究開発もしています。同時に、エネルギー密度はそこまで上がらなくても、コストを下げることができる電池もターゲットにしています。前者の電池は、電気自動車用。後者は自然エネルギーとの組み合わせを主に考えています。
研究においては、周期表にある元素をうまく組み合わせていきます。そのなかでもやはり、リチウム蓄電池はエネルギー密度が高いです。高い理由は、リチウムという元素を使っているためです。
ただリチウムは、日本の場合ほぼすべてを南米から輸入していて、基本的に日本では取れない資源でもあります。地球の裏側からわざわざ運んできたものを電池に入れているので、コストは下がりにくい傾向にあります。
電気自動車が普及したことで、リチウムがなくなるという話がよく出ています。また、リチウムに加え、ニッケルとコバルトという3つの元素が、このままいくと足りなくなるだろうと言われているのです。
ヨーロッパなどは特に厳しく、例えばノルウェーなどはすでに市販の自動車販売のうち50%が電気自動車になっています。多くの国が、2030年頃にガソリンの自動車は販売禁止することを宣言しています。こうした背景から、リチウムだけではなくニッケルやコバルトなど、リチウム電池に必須の元素がなくなりつつあるのです。
こうした状況から、ニッケルやコバルトを使わないリチウム系の材料の開発や、リチウムすらも使わない電池の研究に取り組んでいます。
周期律表で見ると、リチウムの下にあるのがナトリウムです。ナトリウムを使った材料開発、電池の構築の研究を続けています。元々は低地用など、エネルギー密度が低くてもいいようなところをターゲットにしていました。
さて、このナトリウムには、イオンとしてはリチウムよりも動きやすい特長があります。それをうまく活かしてあげることで、リチウムではつくれないような電池ができるのです。
例えば、3分で充電が可能な超急速充電ができる電池などがそうですね。最近流行している全固体電池についても、リチウムの全個体電池の場合だとリチウムが動きにくいのですが、ナトリウムであれば動きやすいため、全個体にもしやすいわけです。
急速充電において、リチウムイオン電池であれば30分かかるところが、ナトリウム電池であれば数分でできてしまう。そういった電池をつくれれば、ガソリンスタンドで給油する時間と大して変わらない状態にまでもっていけます。
また、最近は電池とは違ったところで、無線給電も結構使われるようになってきています。
すでに携帯電話などでは使われていますが、同じシステムを少し大きくするだけで、電気自動車に使うこともできるはずです。無線給電がもう少し電気自動車に普及すれば、ケーブルを繋がなくていいことになりますから、駐車場に停めてちょっとコーヒーでも買っている間に電池が満タンになっているとか、そういう時代が来るかもしれません。
これまではエネルギー密度が重要でしたが、さっきの自然エネルギーの発達とともに、様々なところであらゆる研究が進んでいます。無線給電の技術と急速充電の電池ができてくると、本当に社会がガラッと変わるような時代がやってくるのではないかなと考えています。
Q:こうしたなか、中心となる研究テーマはどういったことになりますか。
企業側の需要は、高密度・高エネルギー密度リチウム蓄電池ですから、当研究室ではこれらの研究をベースにしています。
ナトリウムもずっと研究のターゲットにはしていますが、本流からは少し外れてしまいます。個人的にはリチウムが一通り普及した頃に、リチウムの性能の過剰さに気づき、ナトリウムに置き換わっていくのではないかと予想しています。
現在、電気自動車は、ガソリンの代替として考えられています。しかしそれはエネルギー密度を考えると、ベストな手法とは言えません。電気自動車には電気自動車に適した電池とシステムがあるはずなのです。電気自動車に適した電池とシステムができれば、時代が変わっていくのではないか。たとえば無線充電と組み合わせれば、電池や走行距離というものを意識せずに、気がつくと充電されているというような社会ができあがっていくでしょう。
今後、電気が社会においてますます重要なものになっていくはずです。その時に、たくさんの場所に蓄電池があるとどこからでも供給できるので、分散型の電源システムができれば停電などで発電所からの送電が途絶えても、太陽光発電などをもとにして補うことができます。社会インフラの安全性といった面でも、非常にメリットがあるのではないかなと思います。
Q:研究室の体制はどうなっていますか。
我々は電池そのものというよりも、電池の中に入っている材料の開発をしています。材料なので、様々な元素を組み合わせて、調整して、これまでの世の中には存在しなかったような新しい材料を設計して、つくって、それを評価しています。
電池1本よりもさらにスケールの小さい、性能を実証するためのセルをつくっているというとイメージしやすいかもしれません。いまのベストがあっても、実験によってさらにいいものになることもあります。元素を変えるだけで全く新しい現象が出てくることもありますね。
研究室で学生が学ぶのは、そういった材料の合成の手法であったり、材料を評価して電気をどれくらい蓄えられるのかということを実際に仕上げたり、さらに電気を蓄える特性があるなら、なぜそうなのかというメカニズムについて調べたりもします。
基本はそれができたときにどういうビジョンがあって、どういう社会的な変革があるのかということを考えながら研究をしています。
また、国プロや大企業との共同研究にも取り組んでおり、需要に合わせて研究設定をすることもあります。私の興味本位で別のテーマに取り組んだりもしますね。
将来像を共有し、実現する
Q:今後の課題としてどんなことがあるでしょうか。
技術的な課題というよりは、あとは本当に電池をつくる気があるかどうかというところです。お金を集めてきて、人を雇って、本気でつくれば、問題なくできるものです。ただ、そこが一番敷居の高い部分でもあると言えます。企業が実際にやるかどうか、姿勢の問題だということですね。先ほどお話ししたような将来性の話を、どこまで信じてもらえるかですね。
課題をあげるとすれば、やはり今の電気自動車をどのようにしてより良くしていくかになると思います。
ナトリウム電池については、先ほどお話しした夢をどこまで一緒になって見てくれる人がいるか。それは投資家も含めてですし、僕の代わりにベンチャー企業の社長をやってくれるような人も必要です。
海外だと社長をやってくれるような学生が多くいるのですが、日本人はまだまだ、大企業に入ることが幸せという超安定志向の学生が多く、「一発当ててやる!」という人がなかなかいないのが現状です。学生には夢が足りていない感じがしますね。最近の学生は言われたことは要領良くできますが、逆に言えば言われたことしかやらない人が多い。もう少しチャレンジ精神がほしいかなと思う部分はありますね。
Q:企業とはどういった関わり方が必要でしょうか。
企業とは日頃から話をすることも多いです。自動車メーカー、電池メーカー、材料メーカーなどあらゆる企業とお付き合いしています。電池ってこれからの時代、いまよりももっと身近なものになってくると思います。
それこそ街づくりをしているようなデベロッパーさんなどと一緒に取り組むことがあれば、電池の新しい使い方なども提案できるようになるのではないかと考えています。
例えば、セグウェイのように未来的な歩行器をつくったら、無線給電を活かすという使い方もできます。ガソリンの自動車が中心の現代とはまったく違う、新しい街づくりにつながっていくでしょう。ガソリンの延長ではなく、EVならではのメリットをうまく生活の中に組み込んでいく。その上で、大学としてできることは積極的に取り組んでいけたらと思います。
Q:最後に、今後の目標を教えてください。
私もあと20年は、現役の研究者として研究を続けなければなりません。石油エネルギーに依存しない社会をつくることが、研究者としての20年後の大きな目標です。(了)
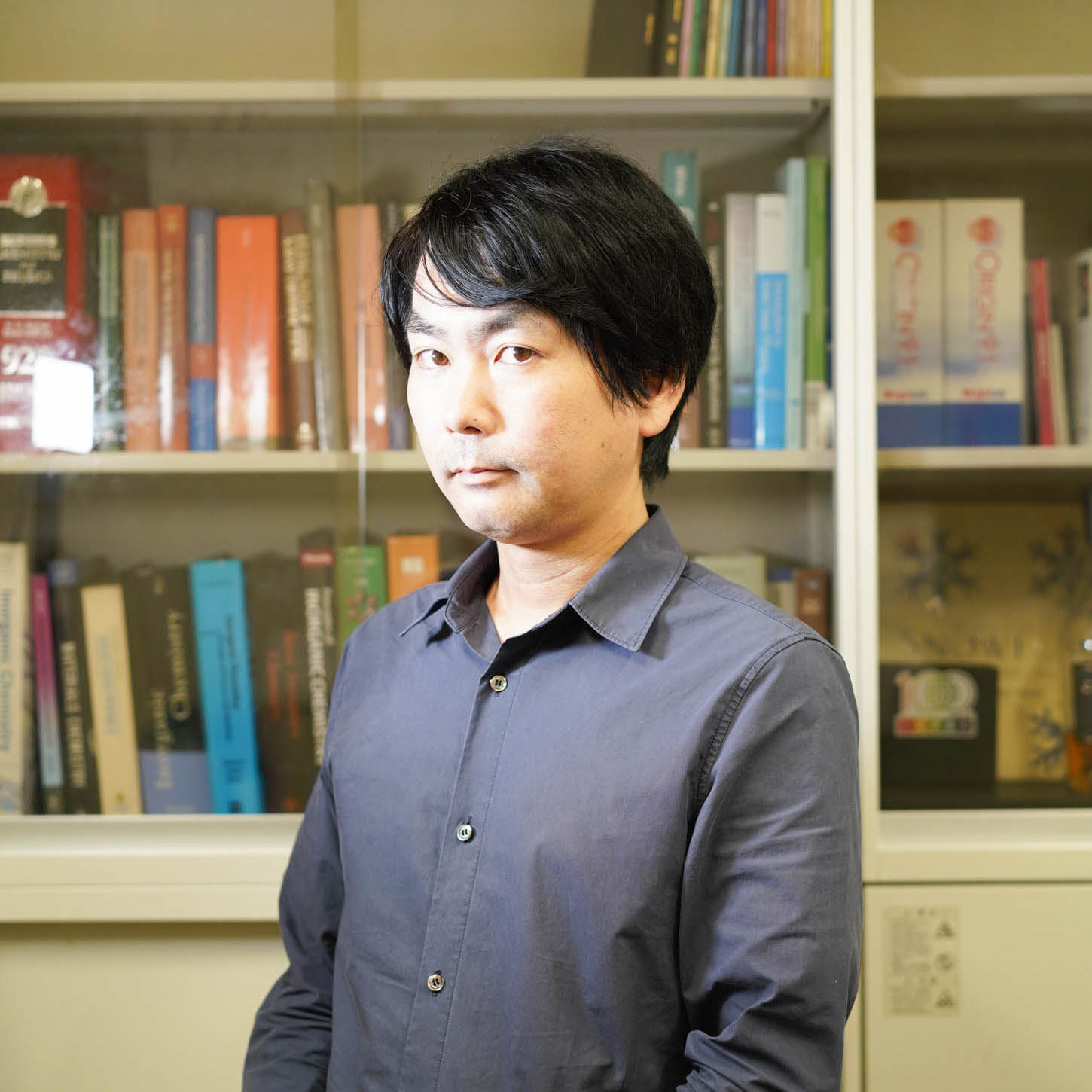
藪内 直明
やぶうち・なおあき
横浜国立大学 大学院工学研究院 機能の創生部門 教授。
2006年、大阪市立大学大学院工学研究科 応用化学専攻 後期博士課程 修了。博士(工学)。2006から、米国マサチューセッツ工科大学 機械工学科 博士研究員。
2010年より、東京理科大学 総合研究機構 助教、2012より同講師を務めたのち、2014年に東京電機大学 工学部 環境化学科 准教授に就任。
2018年4月より現職。
2014年より京都大学 触媒・電池の元素戦略ユニット拠点准教授、2018年より同拠点教授 (兼任)。
