国内の大型プロジェクトをはじめ、国内外で多数の報告があり、多くの研究者が取り組んでいる「アクリルガラスの脆性改善」。しかし、特殊な合成や材料が求められるなど実用化には困難を極めている。そんな中、材料調製やコスト面の導入が容易にできる、「紫外線照射によるアクリルガラスの機械強度の制御」で研究成果を上げたのが、名古屋工業大学 工学専攻 生命・応用化学系プログラムの信川 省吾准教授である。アクリルガラスの機械強度の改善にはアゾベンゼンの光異性化を利用しており、本研究ではそのメカニズムの解明にも取り組んでいる。今回は、信川准教授に本研究の特長や現時点での課題についてお話を伺った。
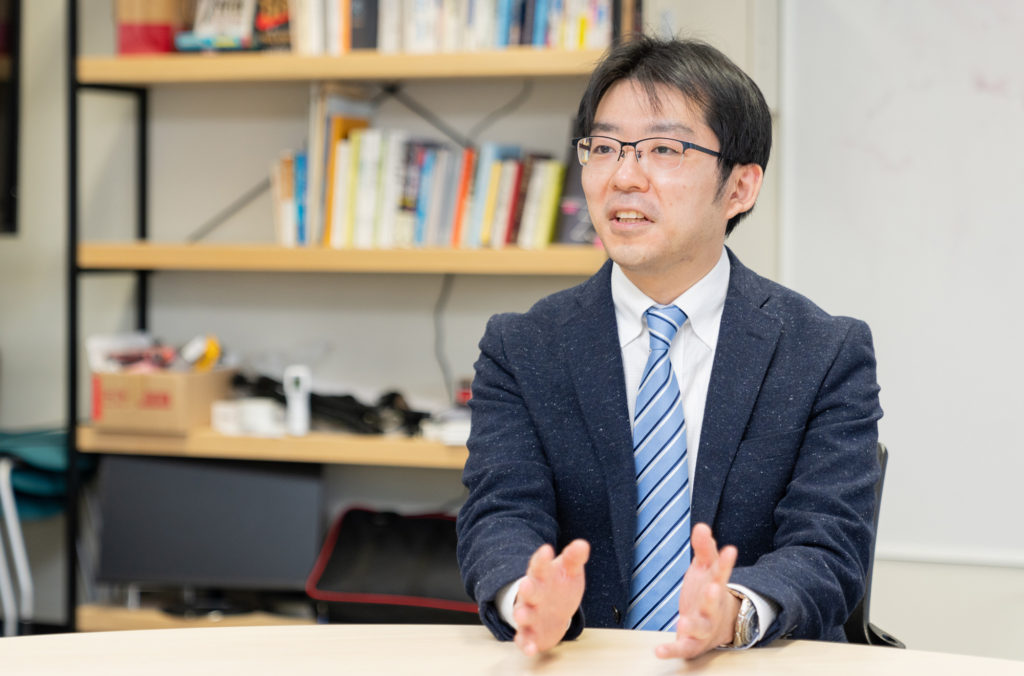
材料調製が容易で、既存の溶融成形技術にも適用できる
Q:研究概要について教えてください。
紫外線の照射による、アクリルガラスの機械強度の制御を研究しています。高分子ガラスであるアクリルは、従来のガラスと比べると軽量で耐久性に優れ、加工しやすいのが特長ですが、ポリカーボンネイトと比較すると、軽さや加工しやすさは変わらないですが「脆さ」があります。
アクリルガラスはスマートフォンの液晶ディスプレイなどに使われており「薄さ」「軽さ」「透明性」が必要なため、それらの優れた物性を維持しながらも、唯一の欠点である「脆性」を改善するために、日々研究に取り組んでいます。
具体的には、光異性化分子の「アゾベンゼン」を用います。「アゾベンゼン」には棒状構造と球状構造の2つの異性体が存在し、紫外線を照射することで棒状が球状に変化する働きがあります。この「アゾベンゼン」をアクリルに混ぜて、紫外線を当てると、アクリルガラスは内部から力を受け、ガラスに亀裂が入りにくくなります。ちなみに、この亀裂はナノ~マイクロメートルという小さなサイズです。この目に見えないようなレベルの亀裂をいかに抑えるかが「強靭化」の大きなポイントになります。
これまでアクリルなどの樹脂ガラス材料の機械強度の制御については、他大学はもちろん、国内の大型プロジェクトでも10年ほど前から取り組まれており、成功例も数多くありました。しかし、特殊な合成や材料を使用してコストがかかるため、実用化が容易ではありませんでした。その点、我々の研究で使用しているアゾベンゼンは染料の基になる物質で、比較的安価に販売されていて、手に入りやすく、使用量もそれほど多くありません 。それに製造プロセスも変わらず、既存の溶融混錬機などをそのまま使えるため、コスト面もあまりかからず、社会実装する際のハードルも低いと思います。
Q:アクリルにアゾベンゼンを活用するようになった経緯を教えてください。
博士課程を修了する年に、アゾベンゼンを使って、アクリルガラスに紫外線を照射する研究を始めました。ただその際は機械強度の制御ではなく、低融点のアクリルガラスの研究でした。アクリル板の成形は、アクリル樹脂を200〜250℃に溶かして金型に入れて固めます。その際のガラス転移温度を下げるために、添加剤としてアゾベンゼンを用いました。しかし、学生時代は研究を発展させていくようなアイデアがなく、思うような成果が得られませんでした。
それから、2015年に名古屋工業大学に着任して2〜3年後に、当時の研究を思い出し、新しく始めたテーマが今回の「アクリルガラスの機械強度の制御」でした。実際に、アクリルとアゾベンゼンを混ぜたフィルムに紫外光を当てながら引っ張ってみると、予想以上に機械強度が改善し、実験が成功した時は驚きました。
Q:研究にはどんな独自性がありますか?
1つは、誰にでもすぐに手に入る材料にこだわった点です。先ほど説明したようにアゾベンゼンは市販の材料で安価ですし、粉末をアクリルに入れるだけなので、従来のアクリルガラスの製造工程と全く変わりません。そのため、特殊な装置も一切必要ありません。
もう1つは、ある程度の透明性を維持できることです。透明性があることで、通常のガラスやスマートフォンのディスプレイなどにも活用できます。ただし、実用化にはいくつかの課題も残されています。
光異性化のメカニズムを解明する
Q:研究課題としてどんな点がありますか?
大きく2点あります。1つは「着色の問題」です。先ほど透明性を維持できるとお話ししましたが、実は無色透明というわけではありません。アゾベンゼンは色素や染料にも使われるので、若干の色がついてしまいます。無色透明なガラスを実現する方法としては、アゾベンゼンと似たような構造で、色がつかない代替素材を探すことです。今はまだ検討段階ですが、その研究も行っています。
2つ目は「アゾベンゼンの耐久性」です。アゾベンゼンは紫外線の照射によって「形が変わる」と言いましたが、形が変わるということは、分子にとって非常にストレスになり、一定の確率で壊れてしまいます。そうならないようにするためには、アゾベンゼンの耐久性を高める必要があります。もう1つは、アゾベンゼンが形を変えアクリルガラスが割れにくくなるーーこの光異性化のメカニズムを解明することです。それができればアゾベンゼンを使わずに、別の素材の活用も可能になるので、その研究にも併せて取り組んでいます。
Q:学生に期待することは何ですか?
まずは、自分の研究にどのような社会的な意義があるのか、考えながら取り組んでもらうことです。社会的な意義というと、実用性や産業界への貢献性を考えがちですが、学術的な発展に貢献するということも十分な意義です。個人的には、単純に自分の知的好奇心を満たす目的でもよいと思っています。
また、昨今高分子材料はマイクロプラスチックの問題で、苦境に立たされています。プラスチック材料は軽量で、かつ成形性に優れていることから、今後もなくならず、金属や木材、セラミックスとともに重要な材料として残っていくはずです。アクリルガラスはガラス代替材料ですが、だからといってガラスがなくなることはありません。「どの材料が一番か」ではなく、素材の相互に良い部分を活かして材料設計を行うことで、地球に優しく持続的な社会を実現できればと思います。いろんな視点でSDGs につながるような研究を学生には考えてほしいと思います。
Q:企業に期待することは何かありますか?
ユーザーの顔がイメージしやすい最終製品を作っている企業とはあまり接点がないので、共同研究とまでは言いませんが、研究や技術に対するご意見やお話をしてみたいですね。例えば、現在高温のガラス転移温度を大幅に低下させる技術を開発しています。しかし研究室では、溶解温度を下げることはできても、製造プロセスに導入しようとした時に、どのくらいのコストカットが実現できるかまでは分かりません。社会実装に向けての技術やノウハウをぜひご教示いただきたいと思っています。
また、粘着効果を高める研究なども行っています。光を照射した箇所だけが粘着する「接着シート」のような材料を開発中です。こういった技術に興味もある方は、ぜひご連絡いただければと思います。
Q:今後の目標はありますか?
今回はアゾベンゼンの研究についてお話ししましたが、主に既存のプラスチック材料やゴム材料の機械的強度や力学的強度の制御を研究しています。これらの材料に何らかの素材を追加して、強靭化をはかったり、逆に柔軟性を高めたりしています。将来的には、企業のニーズに合わせて強度を自由に調整できるマニュアルをつくり、どんな強度にも対応できるようにしたいと考えています。最近はAIもあるので、ビッグデータを活用して強度制御の自動化などができるようになれば、この分野の発展にさらに貢献できると思います。(了)

信川 省吾
(のぶかわ・しょうご)
名古屋工業大学 工学専攻 生命・応用化学系プログラム 准教授
2006年 大阪大学 理学部 化学科卒業。2011年 大阪大学 理学研究科 高分子科学専攻博士課程 修了。2011年4月 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 助教、2012年 ウィスコンシン大学マディソン校 客員研究員を経て、2015年名古屋工業大学 生命・応用化学専攻 助教に就任。2020年4月より現職。
