生物の持つ五感のうち、最も原始的な感覚が嗅覚である。未解明な部分も多い嗅覚メカニズムを解明することで、生物のさまざまな行動の作動原理が理解されることが期待されている。こうしたなか、マウスやゼブラフィッシュをモデル生物として用い、匂い入力から行動出力へと至る嗅覚神経回路メカニズムの統合的研究を手掛けているのが、理化学研究所脳神経科学研究センター システム分子行動学研究チームの吉原良浩チームリーダーだ。吉原良浩チームリーダーに、嗅覚の研究から生まれる発見や、そこから派生して生まれた脳内の「意識」の研究の概要について話を伺った。
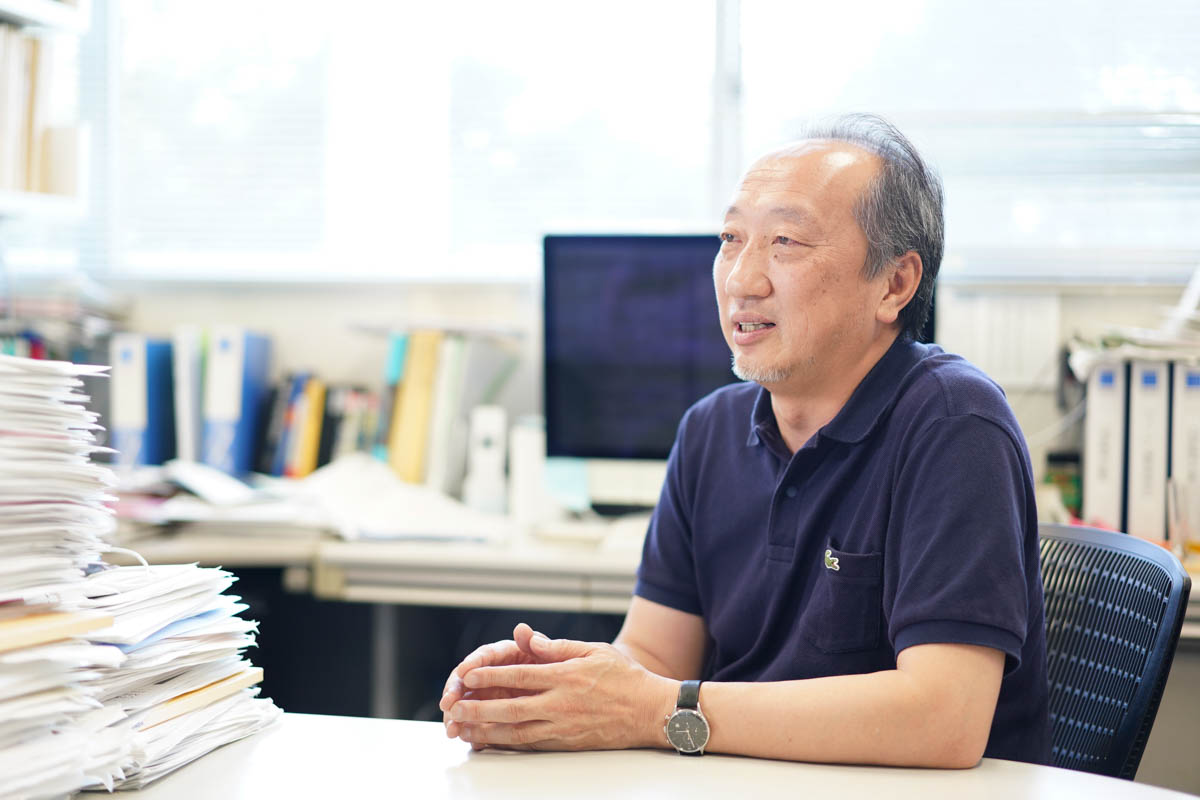
ゼブラフィッシュの「嗅覚」を研究
Q:まずは、研究の概要について教えてください。
私たちには5つの感覚がありますが、その中で一番原始的な感覚が「嗅覚」です。
生き物の進化を遡っていった時、その始まりは単細胞生物です。単細胞生物は水の中で生きていますが、生き物ですから何かを食べなければならない。食物を探すためには、何か手がかりがなくてはいけません。
その手がかりが、食物から発せられる化学物質です。その後、単細胞から多細胞になって、だんだんと複雑な生物になっていきます。
身体の中の細胞同士の距離が長くなると、その間をつなぐ神経ができ、脳が形成されます。そして、さらなる進化の結果、私たち人間ができ、感覚の入力情報を脳で処理し、多様な行動を発現したり、自律神経や内分泌系の活動を変化させたりするなど、様々な反応が起こるわけです。
「食べ物を探す」、「交尾相手を見つける」、「危険な状況から逃げる」という3つの行動が、生物が生存するため、種を保存するために最も根源的な行動です。これらの行動を発現するために単細胞生物から多細胞生物まで多くの生物が嗅覚を使っているので、五感の中で最も原始的な感覚といえるでしょう。
まず最初の、「食べ物を探すこと」。普段、私たちが街を歩いていて、お店からいい匂いが漂い、それに惹きつけられることがありますよね。これは「食べ物を探す」という嗅覚行動です。これをしなければ生物は生存できませんから、人間だけでなく単細胞生物に至るまであらゆる生物にとって必須な行動だといえます。もちろん人間は、そこに視覚や聴覚など様々な感覚を取り入れています。一方でマウスや魚などは、匂いだけをたよりにして食べ物をうまく探すことができます。
また、魚などの水棲生物は、水の中に溶けている化学物質を匂いとして感じることができます。私たち人間のように空気中に漂う化学物質を感じ取るのではなく、水の中に溶けている化学物質を匂いとして感じ取るわけです。進化の過程で生物が陸に上がった時、つまり魚類から両生類になった時に嗅覚系は大きく転換しました。
2つ目の根源的な行動は「交尾相手を見つけること」です。これもほとんどの生物が、嗅覚を使って行なっています。すなわち、子孫を残すためにも嗅覚が非常に重要な役割を担っているといえます。
例えば、分裂酵母にはオスとメスがいますが、もちろん彼らに目や耳はなく、化学感覚(性フェロモン)を使って異性を刺激して交配へと導きます。このことからも嗅覚は非常に原始的な感覚であることがわかりますね。
3つ目の行動は「危険から逃げること」です。例えば、私たちもガスの匂いがしたら、危険を感じます。都市ガスは本来は無臭なのですが、あえて匂いをつけてあります。その匂いによって人間は危険を察知することができるのです。マウスも魚も昆虫も同様に、危険を回避するために嗅覚を使っています。
このような嗅覚行動は、1)どんな物質(匂い分子、フェロモン分子)によって誘起されるのか、2)それを検知するのはどのような嗅覚受容体なのか、3)受容された情報がどのような神経回路で脳へと伝わるのか、4)脳はその情報をどのように処理して、行動発現を引き起こすのか、このような疑問に対して解答を得るために私たちは研究をしています。
1990年頃、私が嗅覚の研究を始めたころは、主にマウスを使っていました。2000年頃から「ゼブラフィッシュ」に注目したのは、この魚には多くの利点があるからです。
ひとつは、体外での受精・発生です。魚は卵を産みますから、発生の様子を顕微鏡下で簡単に観察することができます。さらにゼブラフィッシュの稚魚の身体は透明なので、例えば、蛍光タンパク質を特定の細胞に発現させておくと、その細胞がどのように分化して神経細胞となり、どのように移動し、どのように神経突起を伸ばして神経回路を形成するのか、などの発生・発達過程を外から見て解析できるのです。
また、ゼブラフィッシュの脳はマウスの脳よりもずっと小さいですが、脳の基本的な構成要素はマウスや人間とほとんど同じです。哺乳類の脳のミニチュア版といってもよいくらいです。彼らは目で見て、鼻で匂いを感知し、音を聞き、口で味を感じ、触られたら逃げることができます。人間と同じように、視覚・嗅覚・聴覚・味覚・体性感覚という5つの感覚すべてを使って行動しているのです。さらに、魚は非常に嗅覚が発達しており、エサの匂いをすぐに感知して寄っていきます。
ATP(アデノシン三リン酸)という物質があります。これはすべての生物が産生し、細胞のエネルギー源として使われています。筋肉の収縮、酵素の反応、脳の活動など、すべての生命活動にATPは必要です。またATPは、DNAやRNAという核酸の構成分子でもあり、遺伝情報のコード、発現にも重要です。このATPが、魚では強い誘引物質としての役割も果たします。
ゼブラフィッシュは、プランクトンや小さなエビを食物として摂取します。水中のこのような生物は自分が生存するために使っているATPを水中にも放出しています。すると、それを嗅ぎつけて魚が寄っていくのです。
また、メスの魚が排卵時に用いるホルモン(プロスタグランジンF2a)も水中に放出され、オスの魚は鼻でこれを感知して、求愛行動(性行動)を起こします。これも嗅覚によって起こる行動です。
さらに、天敵に襲われて怪我をした魚がその皮膚から「警報フェロモン」を水中に発します。周囲にいる同種の魚は、怪我をした仲間から発せられたこの警報フェロモンを感知し、危険を察知し、逃避行動を起こします。すなわち、危険な状況からの回避行動です。
魚以外の生き物も同様です。これら3つの行動以外にも嗅覚は重要で、例えばある匂いがした時にエサをもらえるとか、逆に何か罰を与えられるなどというような、「嗅覚の記憶」をつくることもできます。嗅覚は本能的な行動はもちろん、記憶という後天的な行動にも重要な役割を果たします。このような嗅覚記憶のメカニズムについても私たちは研究を進めています。
1990年代初頭にRichard AxelとLinda Buckによって嗅覚受容体が発見(2004年ノーベル生理学・医学賞受賞)されてからは、異分野の研究者たちが嗅覚研究にどんどん参入してきました。嗅覚受容体を発見したRichard Axelも、もともとは分子生物学者・免疫学者でしたが、彼も嗅覚研究、さらには脳科学の研究に入ってきました。日本でも嗅覚分野にたくさんの研究者が参入し、嗅覚研究は広がりを見せています。
Q:現在、研究の体制はどうなっていますか。
私のラボには小さな魚小屋があり、約200個の水槽でゼブラフィッシュの飼育をしています。また理化学研究所内の別の建物には、世界トップレベルの大規模ゼブラフィッシュ飼育施設があり、そこには約9000個の水槽が備わっています。この施設はNational BioResource Project “Zebrafish”として国からの支援を受け、様々な変異体や遺伝子改変ゼブラフィッシュ系統の収集・保存・提供に貢献しています。
産業面では魚の嗅覚を使った技術応用を考えており、実際に水産養殖の専門家とも共同研究を始めています。先ほどお話ししたようにATPおよびアデノシンには魚を強くひきつける作用があります。私の研究室の実験では淡水魚しか調べることができませんが、共同研究では海水魚で同様の作用があるかどうかを確かめる実験をしているところです。
水産養殖業の分野では、養殖魚が人工飼料のエサ(無魚粉飼料)には食いつきにくいことが問題になっています。そこで、無魚粉飼料に何か食いつきをよくするサプリメントのようなものを入れてはどうかという意見が出てきました。アデノシンを無魚粉飼料に加えることで、効率的な給餌方法が確立され、養殖魚の生育を促進できる可能性があります。
思わぬ発見から、前障の研究をスタート
Q:研究課題として、どんなことがありますか。
嗅覚受容体遺伝子ファミリーの発見以来、嗅覚神経系の鼻における匂いやフェロモンの受容機構が解明されてきました。すなわち、どんな匂い分子あるいはフェロモン分子が、嗅細胞に発現するどの嗅覚受容体に結合して、脳の一次嗅覚中枢である嗅球へと情報を伝達するか、という一次嗅覚神経回路についてはかなりの部分が分かってきました。
しかしながら、脳の内部については未解決の問題がたくさん残されています。嗅覚受容体が特定の匂い分子やフェロモン分子を受容した後に、シナプスを介して嗅球のニューロンさらには高次嗅覚中枢へとその情報が運ばれ、最終的にそれがどのように認知・情動・意志決定・記憶、さらには行動に結びつくのか。そのあたりはまだまだ明らかになっていないわけです。
私たちはモデル生物としてゼブラフィッシュとともに、マウスも使って研究をしています。最近の約10年間で、マウスを用いた脳科学実験において大きな技術的なブレイクスルーがありました。
例えば脳内に小さな顕微鏡レンズを埋め込んで、たくさんの神経細胞の活動をリアルタイムで観察する方法が開発されました。また、光を使って特定の神経細胞を興奮させたり、抑制させたりする光遺伝学技術が開発されました。 さらにウイルスベクター技術が脳科学に広く応用され、特定の神経回路の可視化や神経細胞の活動制御が容易にできるようになりました。
最近、私たちの研究チームは、嗅覚の研究から発展させて、意識の研究に着手し始めました。嗅覚研究の過程で、非常に興味深いトランスジェニックマウスを偶然、作製することができました。哺乳類の大脳皮質の下には「前障」という薄いシート状の神経核があります。この前障にDNA組換え酵素「Cre」を発現するトランスジェニックマウス系統の樹立に偶然成功したのです。
もともとは嗅覚系の神経細胞にCre組換え酵素を発現させようとしてトランスジェニックマウスを作製したのですが、そのCreが前障に異所的に発現してしまったのです。まさにSerendipity(偶然、面白い重要なものを発見すること)でした。
Creという酵素はDNAの特定の配列を認識して、DNAの組換え現象を起こすことができます。この作用を利用してCreを発現する神経細胞に、オワンクラゲの緑色蛍光蛋白質(GFP)を発現させてその詳細な構造を蛍光可視化したり、細菌由来の光作働性イオンチャネルを発現させてその神経細胞を光刺激によって人為的に興奮・抑制させたりすることができます。
すなわち前障にCreを発現する私たちのマウスを使えば、ウイルスベクター技術を駆使して前障の神経細胞を選択的に可視化したり、光遺伝学を使って興奮させたり抑制させたりすることが可能になったわけです。
また、前障についての解剖学的知見はたくさんあるものの、その機能は全くわかっていませんでした。ただ、大脳皮質のほとんど全ての領域と双方向的な神経結合を持っているので、大脳皮質全体の活動に関わる何かをコントロールしているだろうと考えられていたのです。
DNAの二重らせん構造を解明したイギリスのフランシス・クリック博士は、1970年代頃から脳科学の分野に参入し、脳の機能についての様々な仮説を提唱しました。彼は2004年に亡くなった翌年にも共同研究者のクリストフ・コッホ、「前障は、意識を調節する中枢かもしれない」という論文を発表しました。私たちが作製した前障にCre組換え酵素を発現するトランスジェニックマウスを使うことで、今ようやく前障の機能についてのクリックの仮説を実験的に確かめることができるようになりました。
最近、私たちの実験で、前障の神経細胞を光で興奮させると、大脳皮質の多くの神経細胞の活動が同時に消失してしまうことがわかってきました。クリックの仮説では、前障は意識レベルを上げるのではないかということでしたが、それとは逆に前障の活性化は意識レベルを下げる可能性が見つかったわけです。このように前障は何か重要な高次脳機能を司っていることが分かりつつあります。
Q:この分野を志す学生にはどんなことが必要でしょうか。
若い学生さんたちにとっては、自由な研究、チャレンジングなテーマをもらえる研究室がいいと思います。
私の研究室では、当たればすごく大きな仕事につながるような革新的・挑戦的なテーマを各自に1つずつ与えています。しかしながらそれが頓挫してしまってはダメなので、リスキーなテーマに加えて、手堅く確実に論文になるような研究テーマも与えて、これらを上手く組み合わせて研究をしていくのが生き残るためには必要かなと思います。チャレンジもするけれど、そこにはきちんと保険をかけておくといったところでしょうか。
また、先ほどお話しした前障のマウスのように研究をしていると思いがけない結果にも出会うので、それを見逃さない注意深さ、見識の広さも大切ですね。
実験をしていて自分の予想とは違った結果が出た時に、「これは目的の結果とは違うから捨ててしまおう」という人が多いです。しかしもしかすると、そこにはもっと面白い真実が隠されている、あるいはそれは誰も見つけたことがない新発見かもしれない可能性があります。それを知るためには、嗅覚だけではなくて他の感覚のこと、脳のこと、あるいは生物全体のことを勉強しておかなければなりません。
長い研究人生を送っていると、セレンディピティは誰にでも訪れるものだと思います。それをものにできるかどうかは、日頃からどれだけ勉強しているか、アンテナを張り巡らせているかにかかってくると思います。
たとえ最初の目的と違ったことでも、それが本当に面白いと思うなら、テーマを大きく変えてもいいのです。私の研究室もずっと嗅覚の研究をやってきましたが、今はメンバーの半分が意識の研究を行なっています。
研究者人生は限られていますから、ずっとステディな実験を進めていくよりも、大きなチャレンジができるポジションや環境で思い切ってやることも大事だと思います。
Q:今後の目標について教えてください。
意識の研究について。これまで『意識』という概念が漠然としすぎていて、きちんとした研究ができていない領域でしたので、それを分子・細胞・神経回路さらにはシステムレベルで明らかにしていけたら、すごく面白くなっていくだろうと思っています。(了)
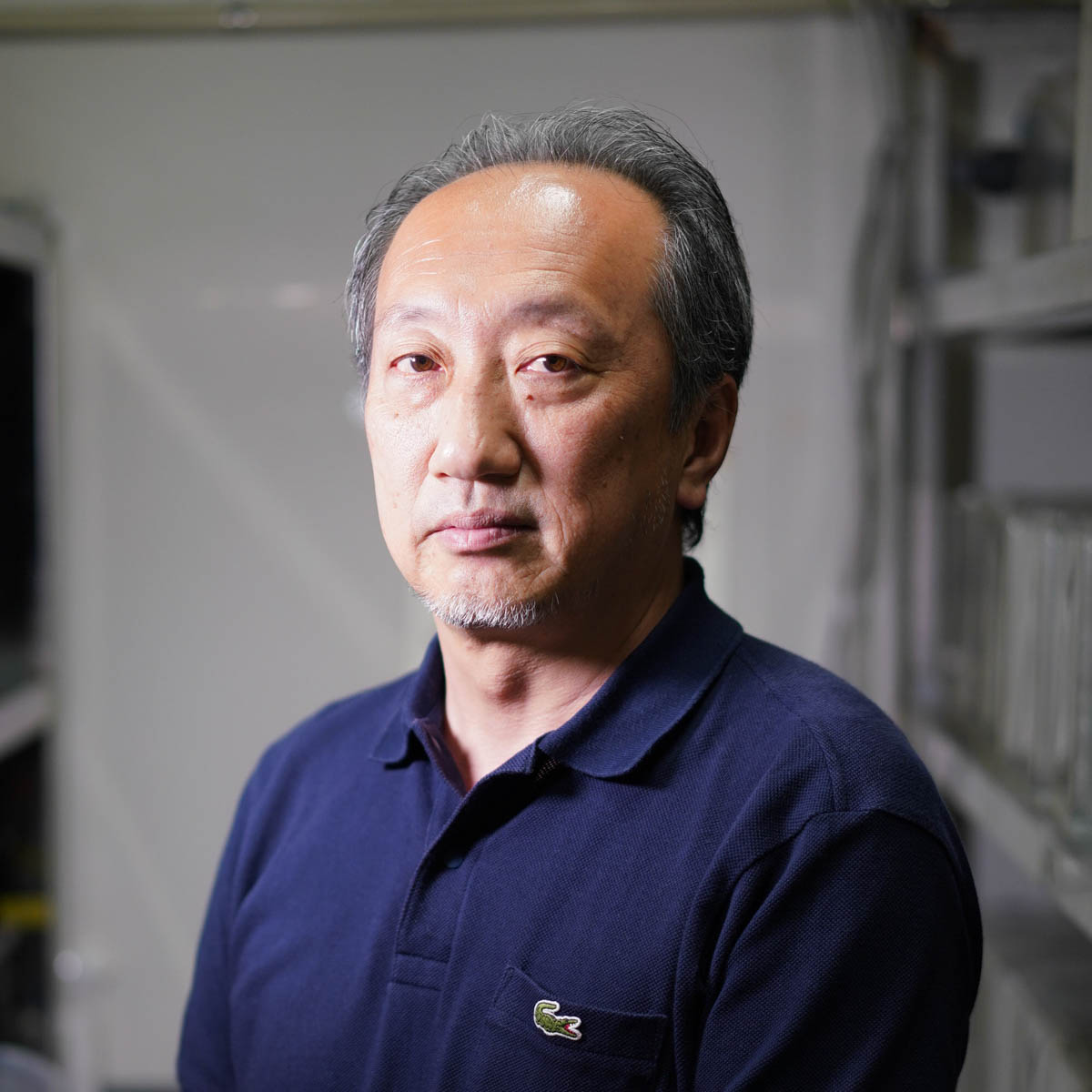
吉原 良浩
よしはら・よしひろ
理化学研究所 脳神経科学研究センター システム分子行動学研究チーム チームリーダー
1984年、京都大学薬学部卒業。1989年、京都大学大学院薬学研究科修了(薬学博士)。
1989年より、大阪バイオサイエンス研究所 神経科学部門 研究員。
1992年より、大阪医科大学 医化学・医学部 助手を務めたのち、1993年から大阪医科大学 医学部 講師に着任。
1995年、大阪医科大学 医学部 助教授となったのち、1998年から20年間にわたり、理化学研究所 脳科学総合研究センター シナプス分子機構研究チーム チームリーダーを務める。
2018年より現職。
