植物の香り(匂い)は、植物同士や昆虫との空間コミュニケーションにおいて、欠かせない機能である。例えば、害虫に食べられた植物の葉から大気中に放出された香りは、近くにいる被害のない植物の防御力を高めることで知られている。このように香りに反応した近隣の植物からは防御物質が作り出され、害虫などからの攻撃に対処することができる。このメカニズムを分子レベルで初めて紐解いたのが東京理科大学 先進工学部生命システム工学科の有村源一郎教授である。今回は有村教授に、植物の香りにおける複雑な機能や、生物間のコミュニケーションの可能性について話を伺った。

分子レベルで「生態の謎」を解き明かす
Q:まずは、研究の概要について教えてください。
今から20年ほど前、研究員(ポスドク)として最初に働いたのが、京都大学の化学生態学の研究室でした。そこで植物の香りによる他の生物種とのコミュニケーションについて興味を持ち、こうした現象が、いかに生態系の維持や、生物同士の共進化や多様化につながっているのかを、分子レベルで紐解く研究を行っていました。最近は、社会貢献につながる研究を意識して取り組んでおり、中でも注力しているのは減農薬への利活用です。
我々が思っている以上に、農薬の環境汚染は深刻化しています。日本では戦後あたりから、ほとんどの作物に今なお使われている農薬。この大量使用は、土壌汚染だけでなく水汚染にも影響を及ぼしていると言われています。
そこで、我々は植物の免疫力に注目し、免疫力を向上させる「防御物質」を植物の体内に作らせる仕組みや機能について研究しています。例えば、アブラナ科の植物であるわさびやカラシの、鼻に「ツーン」とくる独特の刺激性の香味。その他には、タバコのニコチンに含まれている「アルカロイド」や、お茶の「カテキン」も防御物質となります。このように防御物質は、薬と毒の表裏一体になっているので、使い方次第だと思います。
こうした物質をたくさん作り出すことができれば、農薬の使用回数を減らしても、植物を病気や害虫から防除することができます。ただし、昆虫の中には、モンシロチョウのようにわさびの匂いが好きなものもいるので、防御物質を利用するといっても、そう簡単なことではありません。
また我々は、植物の防御応答を誘導させるための因子も発見しました。ハダニやヨトウといった害虫の唾液中にある誘導因子「エリシター」。近年は、植物がいかにそのエリシターを認識するのかといったメカニズムも解明されつつあります。この研究も環境に優しい、新たな害虫防除開発につながる可能性を秘めています。
「生物間のコミュニケーション」という観点では、害虫に食べられた植物の葉から大気中に放出される香りで、害虫の天敵を誘引することができたり、被食植物から放出される香りが、害虫に未被害の近隣植物の防御力を高めることを発見しました。
後者の研究では、ミントの香りには非常に強い防御力を活性化できる機能があることを解明。ミントの近くにダイズや、アブラナ科の植物を置くだけで、被害率を半分ぐらいまで抑えられることが分かりました。
害虫に食べられた植物には、香りというSOSシグナルを大気中に放出する機能があります。これまでは「本来同一個体を守るためのSOSシグナルだ」という考えが一般的でした。つまり植物には「近い品種」と「遠い品種」があり、近い品種ほどコミュニケーション能力が高く、遠い品種(他品種)になればなるほど、コミュニケーション能力が低いと言われていたのです。
しかし、我々が行ったミントの研究結果は全く異なりました。これまでミントの香りを嗅いだことのない小松菜やダイズが、SOSシグナルに反応したのです。この結果から、起点は同一個体を守るためだったのが、次第に強烈な匂いを放つ植物であれば異種間でも「植物間コミュニケーション」が引き起こせるのではないかというのが、私の考察です。それが証明されれば、これもまた一歩、減農薬栽培の応用に近づけます。
Q:有村先生の研究のアプローチには、どのような独自性があるのでしょうか?
私がポスドクとして働き始めた頃は、分野間の交流が今ほど活発ではありませんでした。そんな中、私は学生時代、植物の分子生理学が専門だったので、分子生理学と生態学を融合させた研究ができるのが独自性の1つだと思います。しかし、現在では同じようなスタイルで研究を行う研究者は増えてきています。
もう1つは、生態系の現象を基礎研究と応用研究の両面で行える点です。世界的にも見ても、まだまだ少ないと思います。こうした基礎と応用の研究を行うには、技量(技術)と同様にマンパワーも必要になります。例えば、研究者としての業績評価につながるような基礎研究に取り組みながら、社会貢献につながる応用研究にもチャレンジする。このように社会貢献度と業績評価を両立させるためにも若いマンパワーがあるのは、非常に有利です。
Q:現在の研究に至るまでの経緯について教えてください。
被食植物が放出する香りに近くにある植物が反応するというのは、20年ぐらい前から現象としては発表されていました。近年我々の研究室では、それを分子レベルで解明することに成功したのです。それによって、「やはり、あの現象は嘘ではなかったんだ」ということが初めて実証できたこともあって、実はその年あたりから、「植物間コミュニケーション」の分野が再加熱しました。
失敗しても「やる気」を継続できる力が大切
Q:研究課題としては、どんなことがありますか?
やはり一番大きいのは遺伝子組換え植物の栽培の多くが容認されない点です。これが容認されるようになれば、農作物は大きく改造できます。これまで世界中の研究者が発表してきた遺伝子組換え技術は相当数ありますが、実用化されているのは数%にも満たないと思います(国によりますが)。もちろん、遺伝子組換えによる、人体や環境への影響などを考慮すれば、我々専門家の間でさえ大きく意見が分かれるところです。
世界で起きている食糧問題の解決策としてのアプローチと、人体や環境への影響を考慮した倫理観とのバランスをどうとっていくのか。これは、今後終わりのない社会課題だと思います。
Q:この分野を志している学生に必要なことは何ですか?
一言でいえば、「やる気」を持続できる力だと思います。東京理科大学では、大学4年生になると、いずれかの研究室へ配属になります。最初はやる気に満ち溢れているんですが、研究に取り組み始めると8割ぐらいはうまくいかないため、次第に意気消沈してしまいます。それでも、途中で投げ出さずに、強い意志をもって継続できることが大切になってきます。それと、期待を込めてもう1つあげると「自分で考えられる力」ですね。まだまだ若いので、そこはちょっとよくばり過ぎかもしれませんが…この能力があれば、技術が備わってくると、この分野に限らずとも、どこに行っても通用すると思います。
現在、我々の研究室には学部生と修士・博士を合わせて20名ほどが在籍しています。
学生たちは、みんな高いポテンシャルを持っています。ただ、学部3年生になるまでは座学で教えられたことを学んできただけなので、そのポテンシャルを発揮できていません。我々の研究室で経験を積むことで、研究者としての基盤がつくれるのはもちろん、企業への就職を考えている人にとっても、実践で必要となるプランニング力や論理的思考力、プレゼンテーション能力を養えます。そのためには、やはりどんな壁にぶつかっても、途中で諦めずに、挑戦し続けられる「折れない心」が必要です。そういう素養を持った人にぜひ来てほしいですよね。
Q:企業に期待することは何ですか?
企業から「こういうテーマでやってほしい」という依頼があれば、何かしら貢献できることはあると思います。我々の研究室では、多岐にわたるテーマを取り扱っているので、今まで取り組んだことのないテーマについてもぜひお声をかけていただけたらと思います。
これまでの共同研究では、化学メーカーなどの企業が多いですね。最近では、食品とは直接関連のないような大手メーカーとも取り組んでいた実績があります。我々が研究している「香り(匂い)」を使って、何か新しい製品を開発できないかといったプロジェクトでした。我々とは異なる工学的アプローチは、大いに刺激になり、研究者としてのモチベーションも高まりました。
今一番一緒に取り組んでみたいのは、植物工場などを所有している大手企業、あるいは植物などの生産業者です。我々の研究室では製品の開発も行っていますので、共に実例を作っていきたいと考えています。また、抗炎症効果や、ダイエットに効く脂肪細胞の分化抑制効果のある健康機能の製品開発にも取り組んでおり、そういった分野に興味のある企業も大歓迎です。
Q:最後に今後の目標を教えてください。
大きく2つあります。1つは、誰もが驚くような発見を実現すること。もう1つは年々社会的ニーズが増えていますので、社会課題の解決につながるプロダクトを開発していきたい。まだプロダクトとして世に送り出した経験がないので、ぜひ研究者のうちにそれを実現したいと思っております。(了)
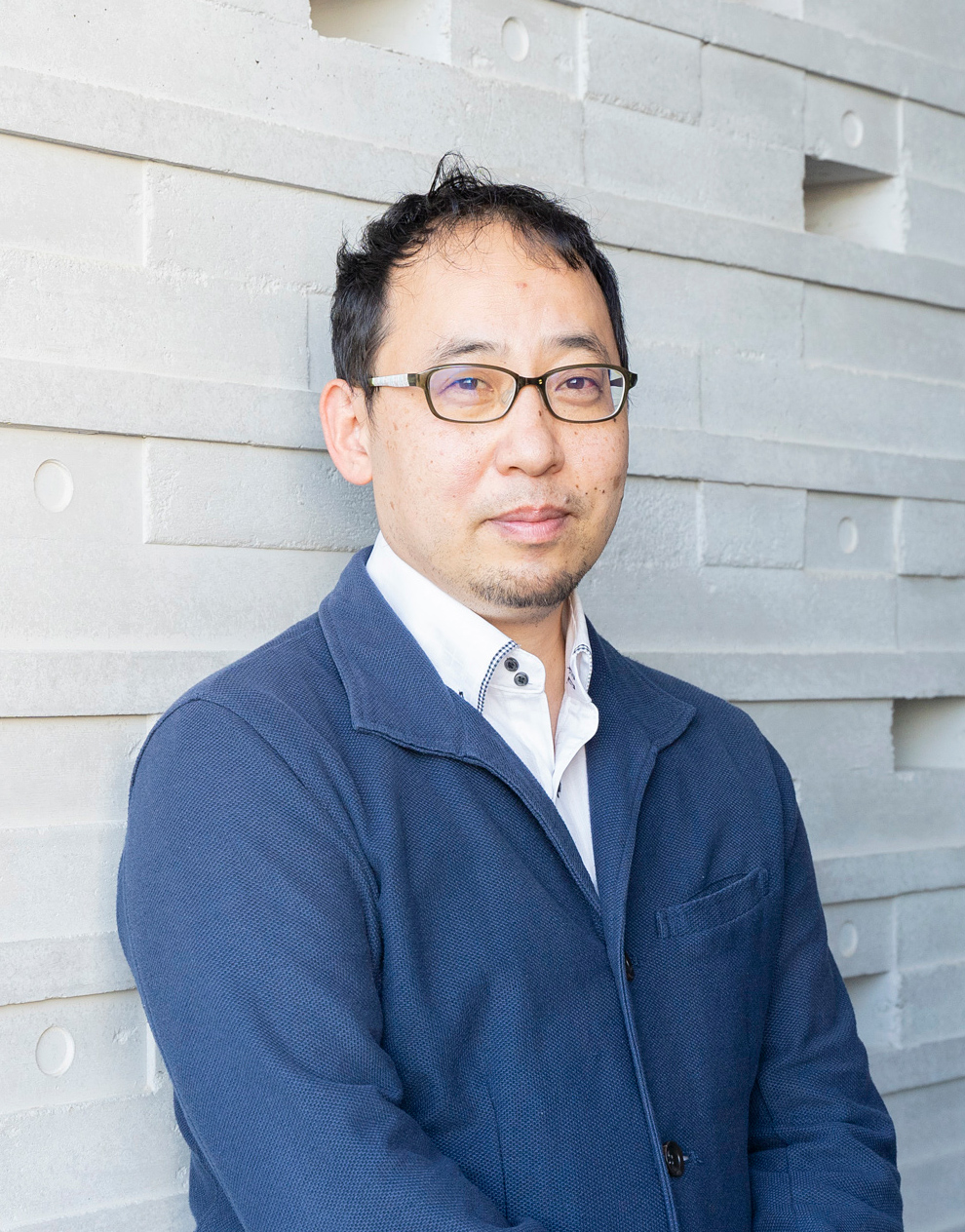
有村 源一郎
(ありむら・げんいちろう)
東京理科大学 先進工学部生命システム工学科 教授
1995年 広島大学 理学部 生物学科卒業、1998年同大学 理学研究科 遺伝子科学専攻 博士課程修了。京都大学研究員、ブリティッシュコロンビア大学(カナダ)研究員、マックスプランク研究所(ドイツ)研究員、京都大学准教授を経て、2013年より東京理科大学准教授に就任。2019年より現職。
