脳のなかには約千数百億もの神経細胞があり、それが複雑につながり合って、さまざまな機能を果たしている。しかし、脳にはまだまだ解明されていない謎が多い。そこで身体の外で脳のような神経組織をヒトのiPS細胞から育て、回路の様につなぎ、観察することで、脳の働きや発生の仕組みの解明に取り組んでいるのが、東京大学 生産技術研究所 物質・環境系部門の池内与志穂准教授だ。今回は脳疾患の治療薬の開発や、次世代コンピューターの応用にも期待できる研究について、話を伺った。
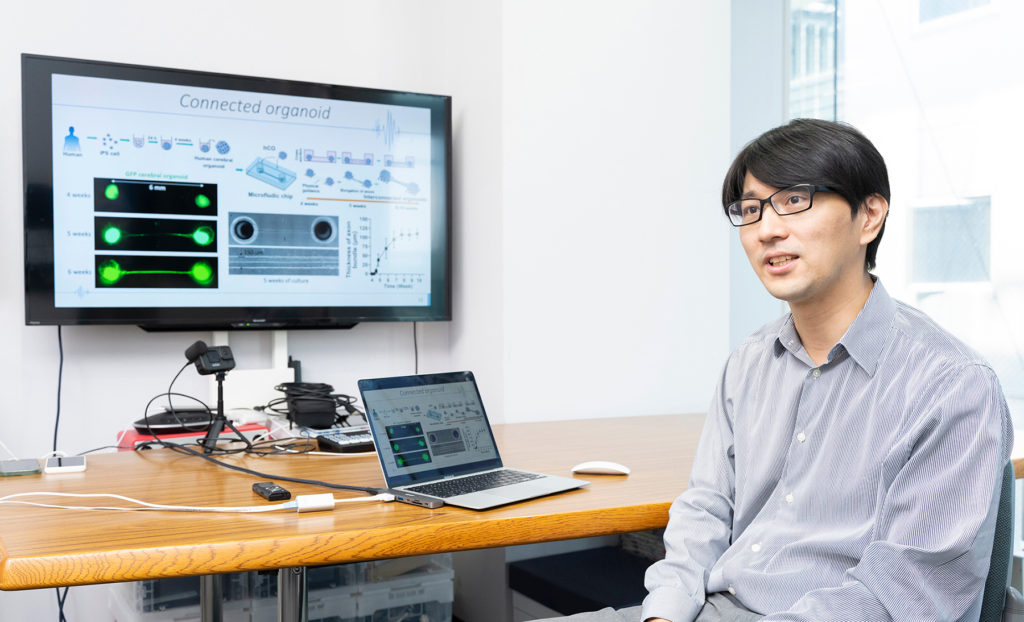
人工的な脳を身体の外につくり、脳の仕組みを理解する
Q:まずは、研究の概要について教えてください。
我々は、身体の外で脳の神経細胞を人工的につくり、観察することで、脳の発生の仕組みを明らかにする研究を行っています。
この研究で目指しているのは、主に3つです。
1つ目は、脳の働きを理解すること。神経細胞の働きや脳内回路がつくられる仕組みを解析しようとすると、身体内では脳の構造が複雑な上に、神経以外の細胞も無数にあり捉えることが難しい。そこで、独自の技術を活用して身体外に複雑な脳を模した組織をつくって、脳の細胞がどのようにつながるのか、電気や光の刺激を与えるとどのような活動を行うのかを観察し、研究しています。
2つ目は、脳疾患の治療薬の開発です。例えば、神経細胞は発生の過程でタンパク質の合成を制御しますが、この制御に異常が発生すると、自閉症やてんかんなどさまざまな脳の疾患を引き起こします。我々の研究では、タンパク質合成機構の制御が神経細胞の形成にどのような役割を果たしているのかを生化学的手法を用いて明らかにすることで、脳疾患の理解はもちろん、治療薬の開発にも寄与することを目指しています。
3つ目は、次世代コンピューターへの応用です。将棋や囲碁の人工知能や自動車の自動運転などに活用されているディープラーニングは、脳の一部の機能(働き)を模してつくられたと言われており、脳の神経細胞からはまだまだ学べることはあります。脳の仕組みをエッセンスとして抽出できれば、新しいタイプのコンピュータを開発するヒントになるのではないかと考えています。
Q:研究の独自性はどんなところにありますか?
神経科学の領域では、マウスやサルを用いて生態を観察する脳研究がさかんに行われてきました。一方、我々が行っている身体の外側に人工的に脳組織を作製して、脳の仕組みを解明するような研究は、これまで技術的に難しいものでした。
それが実現できるようになったのは、「ヒトiPS細胞」や「3次元培養」などの技術要素を組み合わせられるようになったことが大きな要因だと思います。さらに、3次元培養に極力人の手を加えず、細胞の自発性に任せる研究が主流のなか、我々はマイクロデバイスという培養容器をつくって、神経細胞にあえて一部空間的な情報を与えて、より生体に似た構造を持った神経組織を培養したのです。
具体的には、約1万個のヒトのiPS細胞からなる球状組織を分化させ、マイクロデバイスの両側に1つずつ配置しました。その結果、それぞれの球状組織から多数の軸索が伸び、25日後には、軸索束によって2つの球状(人工脳組織)がつながった組織を作製することに成功しました。
なぜ、空間的情報を与えたのかというと、脳は特殊な特徴を持つ臓器だからです。通常、脳以外の他の臓器は、機能的なユニットが繰り返されてできています。例えば腎臓の一部を取り出すと、その臓器全体と同様の機能を果たすことができます。しかし、脳は違います。部位によって機能が異なり、それぞれが複雑に繋がることではじめて、脳としての働きを生み出しているので、一部を取り出しても臓器全体と同じ機能は果たせません。脳の複雑な働きは、通常の自発的な三次元培養をしているだけでは実現しません。ですから、意図的に一部指示を与え、それが研究の独自性になったと思います。
Q:この研究が生まれた経緯を教えてください。
身体の外で脳をつくるというコンセプトは、多くの先生が考えていることだと思います。ただし、実際の研究としては、まだまだ少ないかもしれません。
この研究が生まれたのは、この東京大学 生産技術研究所に来たことが大きいと思います。学生時代は、タンパク質合成の制御という全く違う研究を行っていました。そこから、このタンパク質合成の制御が、実は神経細胞にとっても重要な働きを担っていることを知り、その研究を本格的に取り組むために、2007年にハーバード大学へ留学。その後、2014年に東京大学 生産技術研究所へ着任しました。
この研究所はいろんなジャンルの先生・学生がいるので、異なる学問・研究領域の人たちとコラボレーションできる機会がたくさんあり、彼らのアイデアや意見を反映していくなかで、この研究ができあがっていきました。
最初にお話した3つの研究目的のなかで、「次世代コンピューターへの応用」というのは、この生産技術研究所に移ってから出てきたアイデアです。「神経細胞からコンピューターをつくるなんて無理」と考える人もいると思います。しかし、この研究所では、「いろんな可能性を考えたらいいじゃない」と、背中を押してくれる人たちが多いので、私自身も自由な発想で研究に取り組めるようになりました。
また、生産技術研究所は、2016年12月に英国ロンドンの芸術大学RCA(ロイヤル・カレッジ・オブ・アート)と協同でデザインラボ「RCA-IIS Tokyo Design Lab」を立ち上げました。ここでは、数十年後に実際の製品となる種(アイデア)を考えてプロトタイプを製作し、展示して、みんなでディスカッションを行っています。
このラボでは、他の研究室や海外の人たちと一緒に、我々の研究が将来どんなものに活かせるのかといったことを話し合ったりしています。こうした環境があるおかげで、新しい可能性を追求していけるようになったのもあると思います。
単純さと複雑さのバランスのとれた組織作製を目指す
Q:技術的、産業的な課題としてどんなことを感じていらっしゃいますか?
技術的な課題としては、単純さと複雑さのバランスです。複雑さがないと脳はつくれないですし、複雑にするために手を入れすぎると、神経細胞同士が自発的に組織をつくろうとする力を弱めてしまいます。この両者のバランスをうまく取りながら、成熟した組織を作製するのが技術的に非常に難しく、世界的に見ても、まだ誰も実現できていないと思います。研究者としてはそこにやりがいを感じていますし、ぜひ挑戦していきたいテーマです。
産業的な課題としては、現段階では毎回つくったものが同じような結果が得られない点です。治療薬の開発にあたっては、この安定性が非常に重要になってきます。その要因として考えられるのが、手作業による培養です。細胞の培養工程や観察工程での多検体の自動化に取り組み始めています。これが実現できれば、品質の安定性や効率化が圧倒的に向上できます。
Q:この分野を志す学生には、どんな力が必要でしょうか?
まずは、未知のことに強い興味・関心を抱ける豊かな好奇心や探究心が必要だと思います。
もう1つ挙げるとすれば「楽しんで取り組むこと」でしょうか。最近の学生は、私の学生の頃に比べて、英語も堪能で、プレゼンテーションも上手いといった優秀な人材が多いです。それに真面目です。新たな研究の発想やアイデアは、リラックスしている時のほうが生まれやすいと思います。真面目に物事を考える時も必要ですが、たとえすぐに結果が得られなくても、楽しんで続けるほうがリラックスしている分、新たな研究のアイデアが生まれてきたりします。ぜひ、そんな想いを持った学生に、チャレンジしてほしいですね。
Q:企業とはどういった関わり方をしていきたいですか?
オープンにディスカッションできる関わり方が理想です。一緒にアイデアを出しながら研究などを進めていけると、次世代の商品やサービスなどにつながる提案などもできると思います。業種・業界問わず、幅広い企業と共同研究を行っていきたいと考えています。各要素技術の企業はもちろん、営業側の企業も含めて、何かあればお声がけいただければと思います。
Q:最後に今後の目標を教えてください。
今取り組んでいる研究テーマをステップアップさせて、いろんな回路を作製して、脳内の神経回路がどのように構築されているのかを、さらに踏み込んで取り組んでいきたいと思っています。現段階では、大きく分けて2つのタイプが考えられます。外から情報を処理する場合と、寝て起きてなどの長いスパンで自発的な行動をする場合です。それぞれ、どのようにして研究を行っていくのか、これから考えてなければなりませんが、細胞や脳の働きは未知なところが多い分、少しでも解明できると面白くなってくると思います。(了)

池内 与志穂
(いけうち・よしほ)
東京大学 生産技術研究所 物質・環境系部門 准教授
2002年 東京大学工学部化学生命工学科卒業。2004年 東京大学大学院 新領域創成研究科 修士課程先端生命科学専攻修了。2007年 東京大学大学院 工学系研究科博士課程化学生命工学専攻修了博士。同年よりハーバード大学医学部 リサーチフェロー、ワシントン大学セントルイス医学部 スタッフサイエンティストを経て、2014年から東京大学生産技術研究所講師となる。2018年より現職。2020年にはBeyond AI研究推進機構を兼任。
