「人はどのようにして学習するのか?」という根本的な問いはこれまで、基本的な原理がなかなか解明されてこなかった。人間の学習の仕組みを解明すべく、数理モデルの解析を通して、脳の情報処理機構および神経回路が環境に対して適応・学習するメカニズムの研究を進めているのが、理化学研究所の豊泉太郎チームリーダーだ。今回は人間の学習の基本となる理論をもとにしながら、脳科学におけるコンピュータシミュレーションの有効性について伺った。
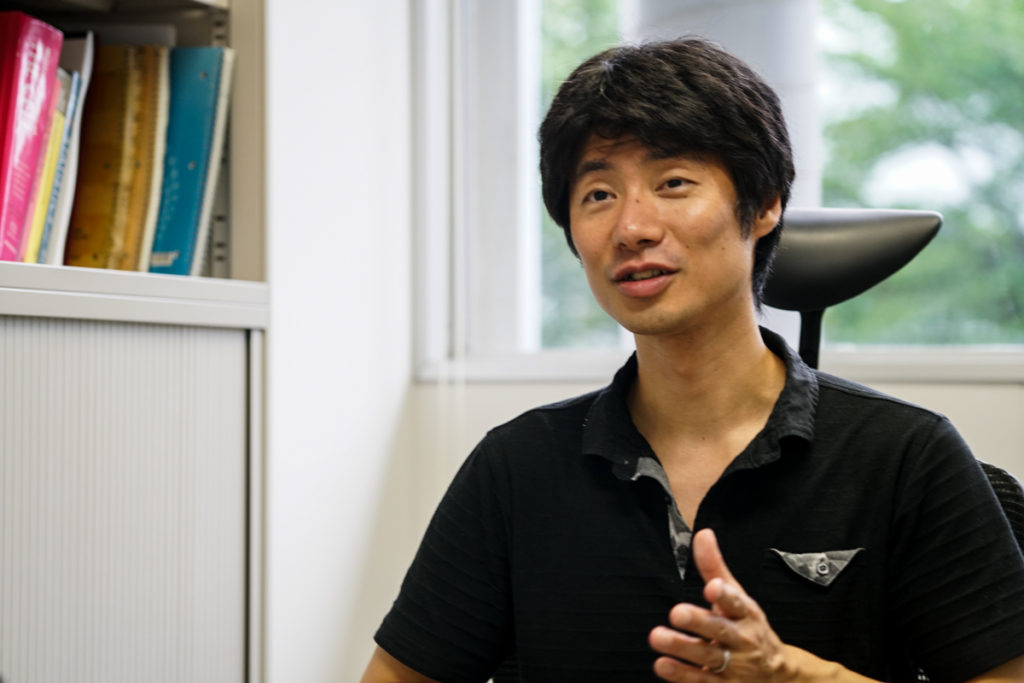
理論的手法により脳を研究
Q:まずは、研究についてお聞かせください。
脳科学を研究しています。脳科学といっても、普通のお医者さんや生物学的なものなどとは違って、基本的に数学や物理のような理論的な手法を使って脳の計算機構を理解する研究をしています。
そのため、アプローチの仕方が他と大きく違っています。実験設備を一切使わない点が特徴です。コラボレーションはしますが、基本的には脳がどのように機能しているかを考え、実験家の人たちとの共同研究によってデータを見ながら、それを説明する理論をつくるという方式を採っています。
紙と鉛筆で計算し、パソコンでシミュレーションを組む以外に、データの解析も行ないます。昔の脳科学は、脳の中にたくさんある細胞のうち一個を調べる研究も多かったのですが、最近は観測技術の発展でビックデータ解析的なアプローチも出てきています。
ようやく定量的に脳の機能を調べられるようになってきたという印象です。そのような膨大なデータを何に注目して解析すれば良いかを考え、性質の記述だけではなく脳がどう計算をしているのかという原理も解明していきたいと考えています。
Q:記述というのは、アウトプットのことですか?
脳の性質の記述といったのは、脳の観測によって直接的に得られる知見で「脳のこの部位とこの部位が結合している」とか、「神経細胞にはこんな種類の細胞がいる」とかいうデータです。このような記述は科学的に重要です。しかし、脳はとても複雑ですから、そのような記述だけから脳の機能を理解することは困難です。私がより興味を持っているのは、「脳をコンピュータに見立てた場合、それがどのような設計理念に基づいて機能を果たしているのか」という原理です。脳が様々な役割を果たすための根底にある法則を発見することを研究テーマにしています。
既存の研究は、特定の動物モデルに関する研究がほとんどです。多くの研究者はサル、ネズミ、ハエ、線虫のようなモデル動物を使います。もちろんヒトの研究もあります。私の研究する計算神経科学という分野では特定の実験環境に縛られないので、様々な実験的知見を統合して、それと計算機能を果たすための数学的条件とを照らし合わせて、脳の行う情報処理について考えます。
私の大学のときからの興味の一つは「学習」です。脳は、ある程度は遺伝子によって設計されますが、環境や実際の経験から柔軟に学ぶ器官です。私は脳が環境に適応するための原理を解明したいと考えています。
経験に応じて脳の素子(神経細胞の性質を決める蛋白や細胞間をつなぐシナプス)がどう変わるかという実験的結果と、人工知能の使う効率の良い学習アルゴリズムとの間には現時点ではかなりのギャップがあります。人間の脳がどのように学習しているのかについては分からないことだらけですが、それらの一端が分かると、新しい人工知能アルゴリズムも提案できるだろうと思います。私は、脳の性質の記述と計算機能の間のギャップを埋めるような「脳の学習理論」がつくれたら良いなと思っています。
Q:今までは経験という言葉で片づけられてきたような、「良い芸術作品を見極める」ことや「スムーズに泳ぐ」ための上手な体の動かし方を習得する過程が分かるようになるというようなことですね。
過程というよりは原理ですかね。私の研究は、「脳が学習するのを司る法則は何なのか」という問題から研究が始まった面があります。
元々私は物理の出身ですが、物理学だとニュートンの法則やマクスウェルの法則など個々の分野に基本法則があって、それを解けば多くのことが分かります。しかし、生物学や脳研究ではそうした基本法則がまだほとんどありません。
最も近いとすれば、ダーウィンの進化論でしょうか。ダーウィンの進化論では、数学的な定理ではないものの、体系立てて生物の分類の説明ができています。私の研究は、そういった基本法則が脳にもあるのかどうかという問題から始まりました。
学習とは個々の個体が環境に適応して上手くやっていけるようになるために脳が発達するプロセスですが、これには情報理論の概念が深く関わっていると考えました。情報処理をするために、神経細胞は情報を上手く他の細胞へ伝えていく必要があります。ある神経細胞が活動すると、その細胞と他の細胞をつなぐシナプスが働き、他の神経細胞に活動が伝播します。このような信号のリレーによって情報処理が行なわれます。そこで、「個々の細胞が、もっと効率的に情報を他の細胞に伝えられるように適応していったら、どうなるのか」を考えてみました。
Q:個々の細胞は、最初は情報伝達の効率が悪いけれども、慣れてくると上手く伝えられるということですか?
そういうことです。 どうやったら上手く情報を伝えられるようになるのか、考えてみると奥が深いです。
どのようにシナプスが適応したら神経ネットワークを流れる情報の効率が上がるのかについて考えてみて、最適なシナプス学習則を数学的に導くことに成功しました。そこで生理実験のデータに本格的に興味を持ち始めました。 様々な刺激を与えてシナプスがどう変わるかとか、その様式が異なる環境でどのように違うかという実験結果が、数学的に導いた適応の法則と一致したのです。脳の細胞もひょっとしたら情報伝達効率の最大化のような基本原理に従って学習しているのではないかと考えるようになりました。
Q:若い人はおぼえが早いですね。脳は年を取るほど細胞が減りますが、単純にダメになるわけではなく性質が変わるのでしょうか。成長に応じて脳はどのように変わるのでしょうか。
そうですね。脳の神経ネットワークは経験にともなってより環境に特化した構造を獲得していくと思いますが、成長とともに適応範囲は狭まるわけですよね。子供の時ならどんな言語も覚えられますが、大人になったらそうはいきません。
しかし一方で、限られた範囲の中ではちゃんと生きていける能力が身についているわけで、発達段階で学習がどう変わっていくのかは面白いですよね。基本原理は赤ちゃんでも老人でも共通する部分がありますが、違う部分もたくさんある。では、その違う部分は何なのでしょうか。
一つの大きな違いとして、「臨界期」というものがあります。
言語を例なら、おそらく小学校のはじめくらいまで、海外に行っているとバイリンガルになる臨界期があります。視覚の例では、弱視で右目だけが強くて左目であまり見ていない人がいるとしたら、早めに処置をしたほうが治りがよくなります。生まれつき白内障で片方の目の水晶体が曇っている子がいますが、早く手術すればちゃんと見えるようになります。手術をしないまま大人になるとずっと見えなくなってしまいます。これは脳が幼少期のある時点で、見えない方の目からの信号を放棄するように適応してしまうためです。
では、人間は臨界期にだけ学習して、それ以外は回路が固まってしまうかというと、そうではありません。臨界期の前段階でも、非常に大きな脳の作り替えが起こっています。逆に、大人になってからも、程度の差こそあれ神経細胞を刺激すればシナプスは変化します。
それでは、臨界期がどのように始まり、どのように特殊なのかを考えてみましょう。さきほどの視覚の例では、発達段階で抑制性の細胞が成熟すると臨界期が始まるという実験結果が報告されています。抑制性の細胞というのは、神経活動を抑える細胞です。しかし、何故抑制性の細胞が出てきたら臨界期が始まるのか分かっていませんでした。
そこで、1つの理論を提唱しました。神経ネットワークの適応とは、あることを経験した際に活動した細胞と細胞を結ぶシナプスが変化することで説明できると考えられていますが、「そのシナプス変化を引き起こす神経活動には2種類あり、それが臨界期の開始時に切り替わるのではないか」、ということを提案しました。
1つは、遺伝子によって設計されている活動です。例えば胎児の網膜の神経細胞は初めてものを見る以前から見るための準備をしています。視覚刺激がなくても隣り合う網膜の細胞が波のように活動し、脳はこの波によって網膜の細胞の位置関係を学習します。脳はものを見る前から視覚をトレーニングしているのです。
一方で目が開いてからは、どんな環境にいるのかが重要になります。例えば目が開いたときに左目が曇っている場合、「左目は使えないから、左目は使わずに右の目からの入力のみでやっていこう」となるわけですね。
これら2つのタイプの活動が切り替わることが、臨界期の始まるメカニズムではないかと考えました。
そうなると、抑制性というのは生まれながらにしてある初期形成のための自発的な活動を抑えて、経験による環境からの効果をより際立たせる役割を持つのではないかということになります。これによって、経験がメインの学習にシフトするということです。
私がアメリカにいるとき、この理論をハーバード大学の先生に話してみたところ、その理論を検証できそうな実験データがちょうどあると言われました。マウスを使った研究で、抑制を薬剤で強めた時に視覚野の神経活動がどう変化するかを調べたデータでした。そのデータでも、生まれつきの自発的な活動が計測されていて、何も見なくても視覚野の神経細胞は活動しています。抑制作用を強めることでその自発活動が下がり、何かを見たという刺激のほうが際立つようになっていくという結果が確認できました。このコラボレーションによって、臨界期の開始を説明する理論を実験的に検証できたのです。
脳は一度にすべてが大人になるわけではなく、センサー=感覚入力に近いほうから徐々に成長していきます。例えば前頭葉や連合野といわれる部分は、もっと思春期になってから成長します。思春期のときに精神病が発症しやすくなるのはこのためとも言われています。思春期に高次機能や高次の連合学習をする段階で、問題が起こって発症するということです。
これらの知見から、臨界期の「タイミング」は思った以上に重要だと考えられます。脳が形成されるタイミングを見計らって、適切な学習をする。この丁度良いタイミングをきちんと計測することでもっと学習効率が良くなるのではないかと思っています。
現在の学習は、基本的に集団全体の平均を元に行われていて、個別に最適ではありません。 fMRIやMEGなどの脳計測技術が更に発展することで、個々人の発達速度が分かると「あなたはいま、数学を集中的に学んだほうがいい」というような、上手いカリキュラムがデザインできるようになるだろうと思います。
Q:現在は理論家として研究をされていると思いますが、AI技術などの産業的な課題として感じられていることはありますか?
今研究者たちが力を入れているのは、「教師なし学習」です。現状の機械学習の多くは一つの課題に特化していて、汎用知識とか常識というものがありません。他の課題で学んだことを次の課題を解く為に生かす方法が不足しています。
特定の課題や期待される正解がない状況でも人間はいろいろなことを学習しています。このような学習を「教師なし学習」と呼びます。課題は指定されていないけれど、いろんな所に行って多様なものを見ることで、世の中の法則性や規則性を学習することができます。このような下地があると、特定の課題が与えられた時により効率よく学習ができるのです。例えばいろいろな生物を観察した下地があれば、後から先生が「これは鳥類です」、「これは哺乳類です」と教えてくれた時に、一から学習するより飲み込みが早いわけです。
例えば現在の人工知能だとビッグデータを元に学習しています。これは物量作戦です。人間の子供であれば、キリンもライオンも10個程度絵を見せればもう実物を認識できますが、今のAIは違います。AIは教師データが大量にある状況では既に上手く動くようになってきていますが、今後は教師がいなくても学習したり、特定の課題で得た知識を一般の課題に応用したりするメカニズムが重要になると思います。一を聞いて十を知るイメージです。
そして、この分野では、まだできることがいろいろあると思っています。
例えば私たちはパーティなどで複数の人が同時に話している状況でも一人の人の話を聞き分けることができますね。これをカクテルパーティー効果といいます。より一般的に、複数の信号の重ね合わせを観測して、それをもとの独立な信号に分解する数学的処理を独立成分分析と呼び、これは教師なし学習の一例になっています。
この独立成分分析は工学的に非常に有用な手法です。例えば潜水艦で受け取ったソナーの信号を、船舶の信号とそれ以外の雑音とに分解することができます。最近ではカメラで撮影した顔の動画から教師データ無しに心拍信号を抽出することもできるようになっています。独立成分分析は工学的な分析で使われていましたが、脳がどのようにこの問題を解いているかはまだ良く分かっていません。私たちは実際の神経細胞でも実装可能で効率的な独立成分分析の方法を発見しました。
この方法では、神経ネットワークの抑制性の細胞の振る舞いやシナプスの振る舞いにある程度近い形で独立成分を分離することができます。
この方法は脳の学習方式に関する仮説を与えるだけでなく工学的にも有用です。従来は一つの計算機プロセッサーでやっていた処理が、ニューロンのような素子で並列計算できるようになり、大規模な問題を高速に処理できるようになりました。
ニューロンタイプの計算チップは最近では携帯電話にも入っています。将来そのようなチップを使って素子を増やせばビッグデータを一気に扱えるようになり、消費電力も大幅に下げられるだろうと考えています。
この学習法則によって、教師データがなくとも、経験から感覚信号を独立なまとまりに分けられるわけです。その後、個別の課題について「これは視覚由来の情報を使う課題である」というような教師データが得られれば、少ないサンプル数でも高い学習効果が得られるはずです。
学問領域を横断しながら脳科学の道へ
Q:これまでのご経歴をお話しください。
東京工業大学の物理学科出身で、物理の技術を色々応用したいと考えて、東京大学新領域創成科学科の複雑理工学研究科に入りました。そこで脳の情報処理についての研究をやりたいと思ったんです。大学の卒業研究の時にニューラルネットワークを勉強したので、きっとその延長で脳のことも分かるだろうと思って。しかし、いざ始めて見ると、いろいろな細胞種やら伝達物質やら博物学的記述が多く、それに比して物理学のような基本法則がなく、挫折しました。脳は捉えどころがないと感じてしまったんです。結局、修士では卒業研究の延長で統計力学や情報理論などを研究しました。
ちょうど修士を出て東大の博士課程に進んだときに、もう一度脳の研究にチャレンジしようと思いました。当時評判の良かった計算神経科学の教科書を勉強して、その著者の教授のいるスイスの研究室に留学しました。この時にやった仕事が、情報伝達量の最大化から導かれる学習法則で脳の実験結果が説明できるという内容です。
その後日本に帰ってきて博士を取り、ポスドクとして理研に入りました。ただ、同じ対象を研究しているのに、私やっている理論と実験分野との興味の間に距離を感じていました。そこで、もっと実際の脳の知見に即した研究をしたいと思い、コロンビア大学の医学部の理論神経科学センターというところに留学して、より具体的な、発達段階での視覚系の学習を研究しました。環境が脳の構造に最も大きなインパクトを与える時期に何が起こっているかを実験的な知見も取り入れながら考えてみようと思ったのです。
そこで3年半ほど研究したのちにコロンビア大学から戻り、理研で1年特別研究員をして、ここのチームリーダーになりました。2011年からですから、6年前になります。
2007年くらいから2011年までがニューヨークのコロンビア大学で、それで2010、11年から理研ですね。今は、実験的な知見を知った上で、脳の計算原理の解明に回帰したいと考えています。独立成分分析の学習法則は最近の結果です。
Q:学生さんは指導されていらっしゃいますか?
現在は1人だけいます。理研は教育機関ではないので単独で学生さんを受け入れることができません。学生さんはどこかの大学で大学院課程に所属する必要があり、理研で研究するためには大学の指導教官の許可が必要になります。そのため、理研は基本的にポスドクが多いです。
しかし、研究を志すやる気のある学生さんはもっと積極的に実習生や研修生として理研に来てほしいと思っています。優秀な研究者に年齢は関係ありませんから。理研側からもサマースクールの募集や、給与つきでリサーチアソシエイトとしての受け入れ制度があります。興味がある人は是非チェックしてもらえればと思います。
理研は研究の専門機関ですから、研究を志す人にはもってこいだと思います。インターナショナルで海外の研究者が多く、公用語も英語ですので初めは取っ付きにくいかもしれません。しかし、どうせ研究者になるなら早いうちから慣れておいた方が世界がより広がります。
また、理研は大学の学部とは組織分割が違いますので、学際的な研究に興味がある人にも適しています。例えば脳科学センターでは、生物・医学の出身者だけでなく、私のような物理出身の理論家や、心理学分野の人も含めて脳の理解を目指す人たちが一緒に働いています。
Q:企業と共同研究などはされていますか?
2017年の6月に共同研究が始まったのですが、オムロンが連携センターを理研に設置するのにあわせ、私もその連携センターに所属しています。アカデミアと企業の連携を目指しています。企業も、基礎的な部分でアカデミアと協力することで、研究力アップが望め、将来的な展望が広がると考えているようです。
Q:数年以内の範囲で目下目標にされているところをお話しください。
神経の動的な自発活動が、脳の学習や信号処理にどのような役割を果たしているのかを解明したいと考えています。
脳の神経細胞を観測すると、とても不規則な活動をしています。そして、特に刺激がなくても常に活動しています。
そのような揺らぎが正常な脳の情報処理に必要だという仮説がある一方、そのような揺らぎは神経回路の至る所にノイズが乗っているからであるという解釈もされています。一昔前の脳の計測技術ではこれらの可能性は区別できませんでした。現在は観測技術が格段に良くなっており、それが本当にノイズかどうかを調べられるようになりつつあります。
先ほど胎児の脳は、網膜の自発活動をもとに学習しているという話をしました。私は脳の自発活動には積極的な意味があると考えています。例えば計算中のコンピュータの電気素子の電位を測ったらあたかもランダムな数値が観測されます。しかしこれは本当にランダムなのではなく、信号を処理したものの帰結として上がったり下がったりしているわけです。脳の細胞も、これと同様ではないかと考えています。
このような揺らぎがどういう機能を持っているかははっきりとわかりません。私はこのような自発活動の多くは無意識の「過去の経験の走馬灯のようなもの」ではないかと推測しています。脳がどのようにこのような揺らぎを生成しているのかを理解し、それがどのように学習や行動に寄与しているかを研究したいと思っています。(了)
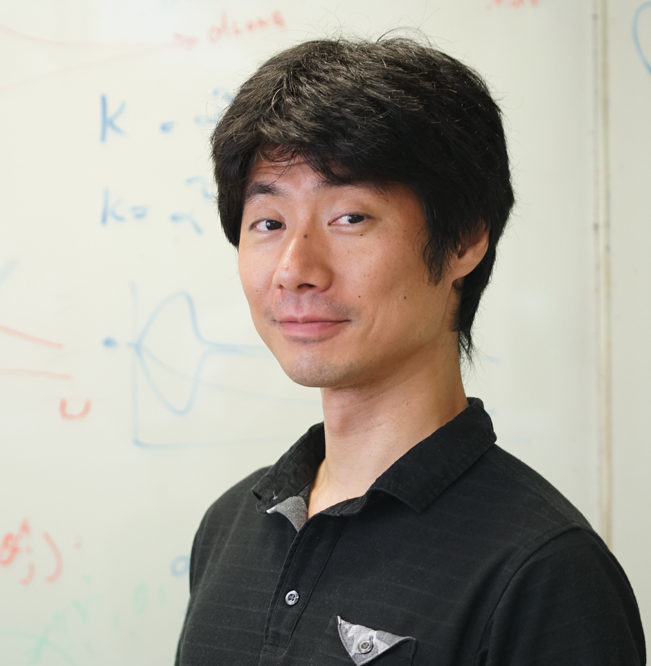
豊泉太郎
とよいずみ・たろう
理化学研究所 脳科学総合研究センター 神経適応理論研究チームチームリーダー
2001年、東京工業大学理学科を卒業後、東京大学大学院新領域創成科学研究科複雑理工学専攻(修士、博士)。2003年よりスイスのガードナー研究所に研究者として従事したのち、2005年よりアマリ研究室に従事。2010年よりコロンビア大学の理論神経科学センターを経て、理研の脳科学研究所へ。2011年より理研脳科学研究所チームリーダーに就任。
