近年の電子顕微鏡の発展はめざましく、原子サイズ以下の分解能を持つまでに進化している。こうしたなか、先端ナノ計測を可能にする電子顕微鏡の開発に取り組み、ナノテクノロジーにブレイクスルーを起こすと期待されているのが、東京大学大学院工学系研究科附属総合研究機構先端ナノ計測センターの柴田直哉教授だ。最近では、磁石や鉄鋼など磁性材料の原子が直接見える画期的な電子顕微鏡の開発を発表するなど、めざましい成果を挙げている柴田教授に、電子顕微鏡がもたらす無限の可能性について話を伺った。

電子の振る舞いを「直接」見るレベルまで開発を進める
Q:まずは研究のニーズについて教えてください。
現在の顕微鏡は性能がたいへん向上しておりますが、その顕微鏡の中でも分解能が一番高いものが電子顕微鏡です。
現在、最高性能のものでは「40.5ピコメートル」という分解能が出ています。これは1ナノメートル(=1000ピコメートル)よりも、さらに二桁下の領域です。
水素原子のボーア半径は、およそ53ピコメートルです。ですから、原子1個の大きさよりも小さな世界が見えるほどの性能の顕微鏡が出てきているのです。
さて、こうして日常的に原子を直接見ることができるようになってきている中では、むしろその先にどういうものが見えてくるのかに興味が生まれてきます。
私は電子顕微鏡の開発研究を2006年ぐらいから始め、14年ほどになります。研究のなかで、原子を見ることができるようになってきたことから、次は原子の内部がどうなっているかを見るためにはどうすればいいかを考えました。そこでたどり着いた答えが、原子の中にある「電場」や「磁場」を見る、ということでした。
原子の真ん中には原子核というものがあり、その周りをたくさんの電子が取り巻いています。原子核には陽子があるので、正に帯電しています。一方、電子はマイナスです。このようにプラスとマイナスの電荷があるので、その間には必ず「電場」があるはずです。この電場を見ることができれば、プラスとマイナスの電荷がどのように空間的に分布しているかがわかるだろう、と考えました。
さて、我々が使っている電子線はもともと電荷を帯びているものです。そこに電場があれば、この電場の中に電子線を入れていくと、力を受けて曲がります。この曲がりを精密に測れる検出器をつくれば、電場を見ることができるのではないか。こうした観点から、最初に原子の中の電場を見る方法を開発しました。
2012年に出した論文が最初のトライアルで、2017年の論文ではさらに精度の高い観察ができるようになったことを報告させていただきました。また2018年には、原子内部の電場分布がわかったことで「ここに原子核があって、ここに電子雲がある」という情報に変換できないかと考えました。変換を行なうことによって、原子核にプラスの電荷があるだけでなく、その周りをマイナスの電子雲が取り巻いている、というところまで観察できたことを報告させていただきました。
実際に見たいのは結合を担っている電子の分布ですが、それはまだ直接見るところまで至っていません。電子の分布を直接見るレベルを目指し、開発を進めています。
電子線は電場の中で力を受けて曲がるとお話ししましたが、磁場の中でも同じように力を受けて曲がります。そのため同じ原理を使えば、磁場も見ることができるわけです。
では原子の中の磁場は見えるのか、原子レベルの磁場は見えるのか。これについてはこの方法でできたらいいなと思っているのですが、ここで根本的な問題に出くわします。
電子顕微鏡で電子を絞るために使うレンズには、強い磁場を使います。つまり磁場で電子線を絞り込んで、試料の上に当てているのです。そのためには試料を電子ビームを絞るための強い磁場の中に常に入れて観察しなければなりません。
これは、電子顕微鏡の分野では常識のようになっており、研究者の間では「磁石を観察してはいけない」といわれてきました。原子分解能電子顕微鏡では、試料がレンズ磁場によって壊れてしまうなど様々な問題が生じるので、磁石や磁性体などの磁気を帯びた材料は観察してはいけないといわれていたのです。さらに、原子レベルの磁場を見ようとしても、そこには既にすごく強い磁場がありますから、何を観察しているのかわからなくなってしまいます。
ただ、そこをブレークスルーできれば、今までは見えなかった磁石の材料や、究極的には原子の内部にある非常に微弱な磁場も検出できるようになるのではないかと思っています。
これが、新しい顕微鏡の開発につながりました。試料に磁場を当てない新しいレンズをつくるべく、2014年の12月から JST のプロジェクト支援を受けて開発をスタートさせました。最近、その取り組みが順調に進んでいることについて報告させていただきました。
もともと低い倍率では磁場分布を観察することはできていましたが、高い分解能では見ることができなかったのです。通常はどのようにして磁場を観察しているかというと、試料に磁場が当たらないようレンズを切って観察しています。そのため、分解能は著しく落ちてしまいます。しかし、高い分解能にするには、試料に強い磁場をかけなければなりません。このようなトレードオフがあるというのが、一般的な電子顕微鏡です。
現状の電子顕微鏡では、ほぼすべてのものに磁界レンズが使われています。そのため、磁界を用いたレンズの性能をいかに上げるかというところがずっとポイントになっています。磁界レンズで性能のいい対物レンズを開発していくことは、電子顕微鏡開発の心臓だといわれてきました。
開発の歴史を振り返ると、20世紀の末に、日本の技術が世界トップレベルに踊り出る時期がありました。その頃には「超高圧電子顕微鏡」という、3階建てのビルが全部電子顕微鏡というような巨大な電子顕微鏡が開発され、1オングストローム(0.1ナノメートル)という分解能が初めて達成されます。
さらに20世紀末から21世紀初頭になるとレンズの収差(=レンズが不完全であるということに起因する問題)を補正する、新しいタイプのレンズがドイツを中心に開発されました。そこからは分解能は更に上がってきて、1オングストロームの壁を超えて、現在ではその半分以下の分解能が出るようになっています。
レンズ収差の補正技術は向上の一途をたどっていますが、電子顕微鏡の心臓部である対物レンズの設計はほとんど変わらずに来ました。逆の言い方をすれば、磁場を試料に強くかける対物レンズはそのままに、補正装置で収差の補正をするやり方が主流だったのです。
しかし、先ほどお話ししたように、通常の対物レンズには大きな問題があります。それが、試料に磁場をかけなければならないということなのです。
私たちは補正装置の恩恵を最も受けた世代といえますが、逆転の発想で、補正装置があるものだと思った時に、レンズ側にどれくらい自由度が出るかということを考えたわけです。すると、補正装置のフル活用を前提として新たに対物レンズを設計すれば、試料の部分のみ磁場をなくした状態でも、非常に良いレンズができるのではないかと考えました。
具体的には非常に簡単な発想で、2つのレンズを組み合わせて1つのレンズとして使うというアイデアです。上側のレンズと下側のレンズを、上下反対称にして励磁します。すると、両方のレンズから発生する磁場が完全に逆向きになり、打ち消しあうことで上下のレンズの間だけは磁場がなくなります。磁場のないところに試料を入れておけば、上と下のレンズをできるだけ近づけることができます。そうすると非常に強い磁場でビームを絞ることができ、なおかつ試料のところには磁場がないという状態をつくることができます。
この発想は、おそらく収差補正の前にはありえなかったことです。
結果として、1オングストロームを切る性能が出てきましたので、最近論文で発表させていただきました。こうして、従来苦手としていた磁石なども、何の問題もなく原子レベルで見えるようになってきました。
ただ、最初にお話ししたような原子レベルの磁場は見えるのかというと、実はまだ答えは出ていません。これからのトライアルですね。今はそのファーストステップとして、磁場のない状況下で原子レベルの性能が出る電子顕微鏡ができたという段階です。
「無磁場」状態での観察をめざして
Q:現在の課題としてどんなものがありますか。
我々の開発によって、電子顕微鏡は磁場のない環境においても原子分解能観察が可能になりました。今後は、磁場や電場を、無磁場環境の中で原子分解能観察していきたいと考えています。
そのためには、検出器の感度や装置全体のノイズ耐性などを、日進月歩で向上していかなければなりません。先ほど申し上げたような局所場の情報は、非常に弱い信号です。弱い信号をいかに検出するかということが、次の課題になると思っています。
また、例えば補正装置の更なる改良や進歩、安定化などもそうですが、電子を発生させる電子銃自体をもっと高度化していくなど、要素技術開発としてはまだまだこれからというところも多いです。
電子顕微鏡で重要なのは総合性能になりますので、一部分だけが特化していても、総合的な性能には繋がりません。心臓ともいえる対物レンズに新たなブレークスルーが生まれていますから、これからはレンズ以外のものを突き詰めていく必要があります。
最終的なゴールとしては、材料中の電子の振る舞いによって出てくる非常に弱い信号を観察できるようにしたいと考えています。
Q:この分野を志す学生には、どんなことが必要ですか。
私は東大のマテリアル工学科を兼務しておりますので、やはり材料系に興味がある学生さんが進学してくることが多いです。
もちろん、同じ学科には材料を開発したり、プロセスを開発したり、あるいは理論計算で理解していくなど、様々なアプローチの先生がいらっしゃいますし、学生さんの興味も多岐にわたります。ただ、私のところには、材料の中で何が起こっているかという基礎の部分を知りたいと考えてくる人が多いですね。
その中で私は彼らに、材料の本質を理解するためには、やはりそこで起こっている現象をきちっと観察し、捉えなければいけないと伝えています。
いま取り組んでいる電子顕微鏡開発は、そういうところにも繋がっていくと考えると、電子顕微鏡について取り組むことが面白くなりますし、誰も見たことがないものを見たいという思いも生まれます。こういったことにロマンを感じてもらえるといいですね。
その意味では「材料のことを知りたい、だからこそ電子顕微鏡をやる」と考えてもらいたいです。2つの分野はどちらが欠けてもダメです。それもあって私自身は、「電子顕微鏡材料学」と独自に名前をつけて自分の専門を紹介しています。2つの分野を、車の両輪のように進めていくことがコンセプトになっています。
学生にはやはり元気が大事ですね。基礎研究には、粘り強さみたいなタフネスが必要ですので、明るく楽しく前向きな学生さんが最後に一番力を発揮している気がしますね。
新しいことにチャレンジすることは楽しいもの。そこで我々がやるべきことといえば、チャレンジした先にはどんな面白いことがあるのかを、彼らに感じてもらえるようにすることだと思っています。電子顕微鏡の分野にはまだまだ伸びしろがあって、面白い世界が広がっていくことを研究室の学生さんはよくわかってくれていると思います。
実験では、私自身が開発した新しい電子顕微鏡を学生さんにどんどん使ってもらっています。学生さんも、ワクワクしながら楽しそうに実験に取り組んでくれているようです。
Q:企業とはどのような関わり方をしていますか。
産業界からは、非常に注目をいただいています。特に鉄鋼材料や磁性材料、あるいはスピントロニクスといった分野の方々との共同研究や問い合わせが多いです。将来的にはあらゆる研究分野で活躍するような電子顕微鏡にするべく、様々な部分を詰めていきたいと考えています。
電子顕微鏡ですので、そこで実際に何が起きているのかを直接見ることができるのが最大の強みだと思います。基礎科学の最前線で活躍するような装置であり、且つ産業応用にも強みを発揮するオールラウンドな装置になってほしいです。
この日本発の新技術をまずは国内で活かしていただいて、将来的には世界の研究の底上げにつながるようになればいいなと思います。
私自身、顕微鏡系の学会や材料系の学会で企業の方々と話をすることがあります。そこで興味を持ってくださった企業の方々が、自分たちの見たいものを持ってこられて、共同研究に発展することも日常的に起こっています。
ただ、まだ情報を届け切れていない分野もあると思っています。もっともっと様々な分野での応用可能性があると思っています。
私自身は非常にオープンマインドですので、「こういうものが観察できないか」とか「こういうことはできないか」というようなお話はなるべく受けて、議論させていただくようにしています。これは重要なことで、私たちが使えると思っていた分野だけでなく、他の分野にも役立つパターンが数多くあると思うんです。これからは、もっともっと視野を広げていきたいですね。
何かご提案をいただければ、前向きに議論していきたいですし、それが大学の使命だと思っています。せっかくJSTのプロジェクトとしてやっていますので、まずは日本の産業界に何か貢献していけたらと個人的には思っています。海外からのお話もあるので、今後はさらに大きく展開していくのではないでしょうか。
Q:最後に、今後の目標を教えてください。
無磁場の環境で原子サイズの電子ビームを漸く絞れるようになりました。いよいよ原子レベルの磁場を可視化できるかどうかに答えを出せる環境が整ってきました。これからは、「どこまで小さな世界の磁場を直接観察できるのか」という極限的な目標に挑んでいきたいと思います。これが実現すれば、磁性やスピンデバイス関連分野に、今までにない新しい計測技術を提供できると思います。(了)
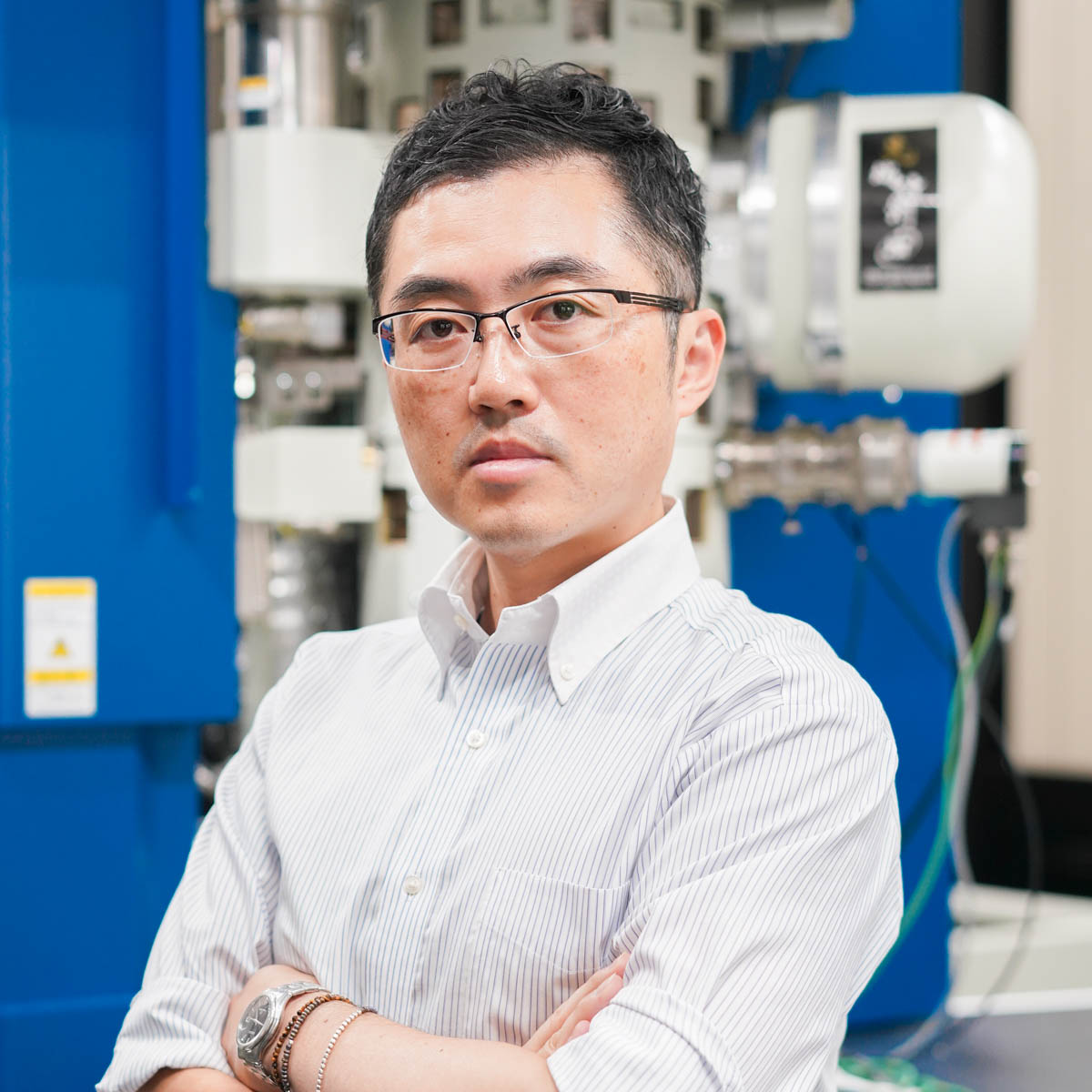
柴田 直哉
しばた・なおや
東京大学大学院工学系研究科附属総合研究機構 機構長・教授。
1997年、東京大学工学部材料学科卒業。2003年、東京大学大学院工学系研究科材料学専攻博士課程修了。博士(工学)。
日本学術振興会特別研究員(DC1)、日本学術振興会海外特別研究員⁄米国オークリッジ国立研究所客員研究員を経て、2004年より東京大学大学院工学系研究科附属総合研究機構 助手。2007年より同助教となる。
2011年より、東京大学大学院工学系研究科附属総合研究機構 准教授に着任後、2017年より教授、2019年より機構長。
