食品の「味」はその価値を決定づける重要な因子だが、味物質受容・認識機構について、その全体像の解明はまだまだ進んでいない。こうしたなか「甘味センサー」となりうる、味の強さを簡単に測れる方法を開発し、「食品の味」に関する研究を進めているのが、東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 生物機能開発化学研究室の三坂 巧准教授だ。
今回は三坂准教授に、味覚の測定システムを開発する目的や、「美味しさ」を科学的に研究するアプローチについて伺った。
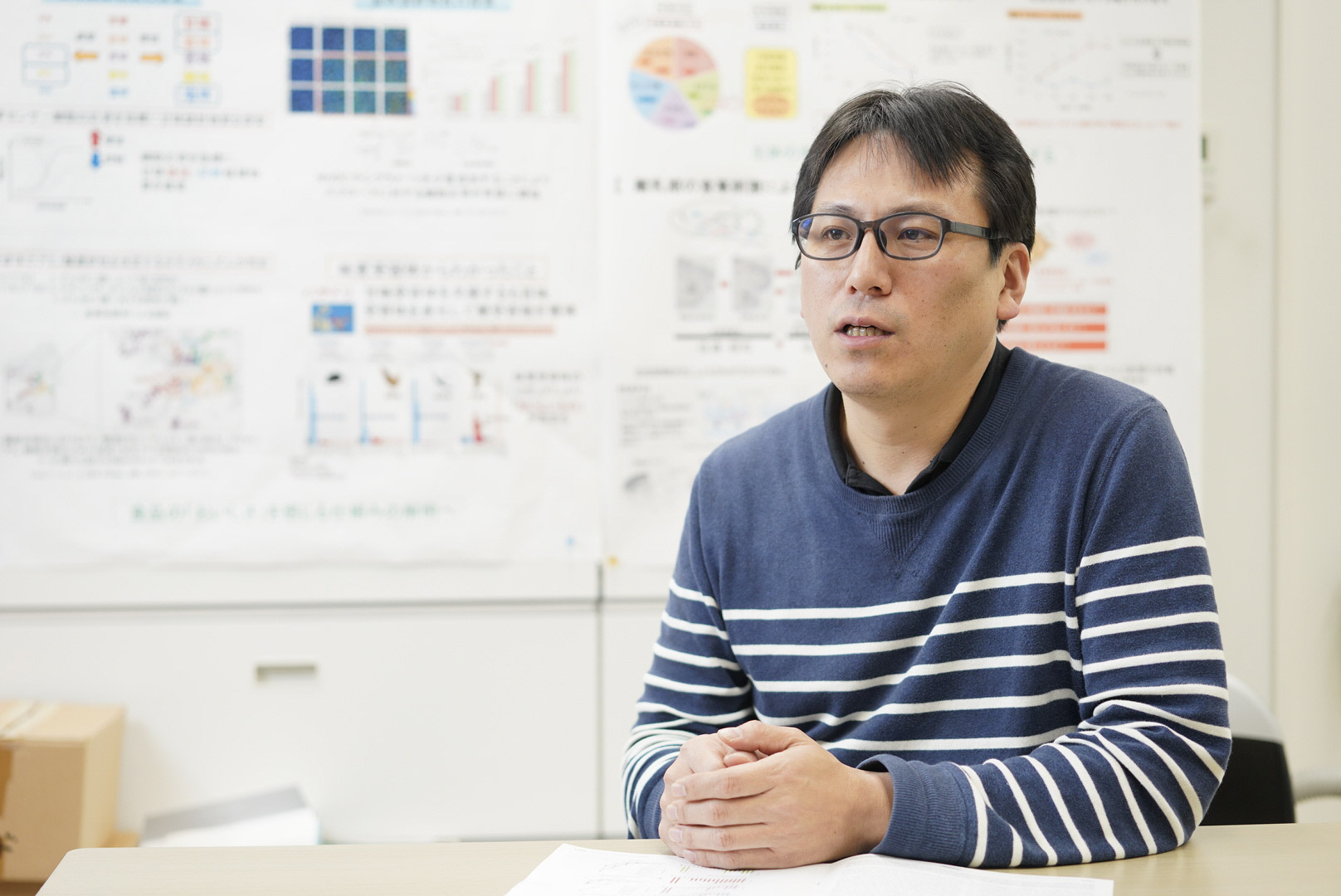
味の「強度」を測る研究
Q:まずは、研究の概要について教えてください。
人間の舌に「味」を感じる細胞があるということは、昔から知られていたことです。
舌にはセンサーの役割をする受容体があり、それが味物質を受けとってシグナルを流すことで味を感知しています。
こうした味の研究は、他の感覚に比べて非常に遅れています。視覚の研究は30年ほど、嗅覚の研究は10年ほど先に進んでおり、これらの先進的な研究手法を模倣しながら味覚研究が進んできたといえます。
鼻で匂いを感知する受容体が初めて見つかったのは、私が学生の頃でした。匂いを受け取る神経細胞の細胞膜に、匂いの受容体であるタンパク質が数多く存在していることがわかったのです。
一方で、甘味や苦味を受け取る口の中の受容体に関しては、最近まで詳しいことがわかっていませんでした。詳しいことがわかってきたのは2000年以降の話です。
この発見以降、この20年くらいの間にかなり研究が進んだといえます。
私自身の経歴と研究分野全体の経緯との関係をお話しすると、民間企業にいた頃に味覚研究の枠組みができあがって、研究者に戻って本格的に研究を始めたタイミングと、味覚に関する研究が進展した時期とが、ちょうど重なったことになります。
口の中にある受容体が見つかった当時、私は食品会社に勤めていました。甘味や苦味を感じるセンサーをアメリカの研究者が見つけ、世界的にもセンセーショナルな論文として注目されました。
その後、2005年に私が現在の研究室に戻り、味の受容体の遺伝子配列を使って味を測る研究を始めたのです。
さて、この研究室では、口の中で味を「感じる」のではなく、「味の強度を客観的に測る」というテーマで研究をしています。口で舐めて感じるのではなく、別の方法で味の強度を測るということです。
例えば、人間の口で何回か味を確かめても、舐めるごとにだんだんとその味に慣れてきてしまいます。そもそも危険なものは口に入れることすらできません。昔から自分の口以外のもので味を測りたかったのですが、それができていなかったわけです。
例えば、味ではなく視覚情報ならカメラで撮ればいいですし、音の情報はマイクで拾うことができます。しかし、味覚や嗅覚で感じるものは、未だに記録もできなければ再現も難しいのが現状です。
こうした制約があるなか、まずは甘味や苦味の強度を測定するような仕組みをつくることを目指し、研究をしています。
受容体を最初に見つけた人は、味がどのようにして脳に伝わるのかにかなり興味があったようです。しかしその測定技術については、さほど関心を持っていませんでした。
難しく高度な測定技術をいかに簡便に、食品分野の人たちにも使えるような形まで落とし込むか。それによって、味の強度の測定技術が広まり、その結果を食品表示に使ったりすることもできるようになるのではないか。
こういった視点から、受容体を使って味の強度を数値として提示するための研究をしてきました。
一つ例を挙げます。人間の鼻の受容体は約400弱あるのですが、それら全ての遺伝子をとってきて、一つ一つがどんな匂いを受けとっているのかを調べることは、とてもではないができません。
一方、鼻に比べて口の中は受容体の数が少なく、なかでも甘味の受容体はたった1種類しかありません。ひとえに甘い物質といっても、糖はもちろん甘いですし、人工甘味料やアミノ酸など他にもたくさんの種類がありますが、それを受け取る受容体はたった一つだけなのです。
また、旨味成分ともいわれるグルタミン酸やイノシン酸などを受け取る受容体も、一つしかありません。苦味については少し増えて25個。
つまり、甘味・旨味・苦味の全てを合わせても、その受容体の数は驚くほど少ないわけです。
特に甘味や旨味は、もし感度のいい測定システムが作れれば、人間が感じる物質をそのたった一つのシステムで評価できることになります。
これまでも糖の量を測るような技術はありましたが、糖は測れても人工甘味料はまた別の方法で測らなくてはなりません。しかし、甘味受容体が機能する細胞を一個つくると、糖であろうが人工甘味料であろうが、甘いものなら何でも応答するわけです。
つまり一つのデバイスだけで、人間の感じる味の1ベクトルを表現することができる。もし受容体がいくつもあったら、ここまではできなかったかもしれません。
受容体が少ないということは、逆に言えば一ついい評価システムがあれば、人間の甘味や旨味をそれだけで説明できるということになります。
Q:甘味の受容体にはどんな特性があるのでしょうか。
甘味は本来エネルギー源ですので、生物にとって食べてもいいシグナルになっています。しかし毒となる物質にも甘いものがあって、例えばクロロホルムという有機溶媒は、香りも味も甘いといわれています。
それから、水を凍らないようにする不凍液に含まれるジエチレングリコールという物質が赤ワインに混入したというニュースが昔にありましたが、この化合物も甘いといわれています。
あとは、金属イオンのうち鉛イオンも甘いといわれます。鉛イオンの錯体も甘いのですが、実はこれ、絵の具です。絵の具の白と黄色は、鉛の錯体が入っているために甘いようです。戦時中で甘いものがなかった頃、甘い絵の具を子供達が喜んで舐めていたということを、昔の先生から聞いたことがあります。
本来であればエネルギー源を感知するための受容体にもかかわらず、人間にとって毒である物質も甘いと感じることについてはまだまだ謎がありますが、受容体にはそういった面白い部分もあるということがわかってきました。
一方で、甘味を強めるような物質を見つけられれば、飲料メーカーなどではものすごく有用だと考えられています。例えば、カロリーを抑えつつ、より甘いものをつくることもできるようになります。
甘味の受容体は一つですが、甘さの中でも味に違いがあるのは不思議です。一般的には人工甘味料よりも砂糖のほうが美味しいと言われることもありますが、食品の種類によって要求される甘さの質に違いがあります。
なぜ甘味のセンサーが一種類なのに、美味しいと感じる甘さとそうではない甘さがあるのか。あとは、砂糖とブドウ糖は同じ糖ですが、人間が舐めると味に違いがあります。両方とも甘いけれども、違うものだと認識できるわけです。
つまり一つの受容体で甘さの強度以外にも様々な情報を伝えているという側面があることも、甘さの面白い部分なのではないかと思います。
Q:甘味以外にも、香りや苦味などの研究にも取り組んでいるのでしょうか。
他には、グルタミン酸などの旨味成分を測る仕組みもつくっています。また、最近では旨味を強めるような物質がどのように作用するのかということについても、成果を出すことができました。
酸味と塩味のセンサシングに関しては、2018年現在でもどのように作用しているのかわかっていない部分が多くあります。受容体の候補はいくつか出てきていて、複数の種類が機能していることまではわかっていますが、それでも全部が見つかっているわけではありません。味覚の研究は、みなさんがイメージしているよりもかなり遅れているのが現状です。
「酸っぱい」とか「しょっぱい」など、みなさんが毎日当たり前のように感じていることでも、科学の世界ではまだ明らかになっていないことばかりです。感覚の研究そのものが遅れているのは事実で、その中でも味覚の分野は特に遅れているので、まだまだやることは多くあると思っています。
Q:人によって味の好みが違ったり、年齢によって味覚が変わったりする要因は何でしょうか。
味の好き嫌いには個人差がありますし、同じ個人でも好き嫌いがだんだんと変化していくものです。
ではその変化は何によって起こるのかというと、個人個人のこれまでの食生活も当然、関係してきます。
特に小さい頃に味の強いものを食べると、好みにズレが出ることが多いです。ある時期に濃い味を与えると行動が変わることが、マウスの実験でも明らかになっています。
人間でも離乳期の時期にしょっぱいものを食べると、塩味に対する嗜好性が増すといわれていますが、このような現象に身体の中のどこが変化しているのかを知りたいわけです。
離乳期のように母乳から普通の食事に変わる時期に、強い甘味や辛味を与えると脳がどんなふうに変わっていくか。それがわかることで、嗜好性が変わる原因についての説明がつくようになると思います。
こういった現象についての報告は過去の文献にもあるのですが、その原因についてはまだまだわかっていない状態です。
また栄養状態が変わったときにも、味の感じ方は変わってきます。必須栄養素が欠乏したり、体内での備蓄量が変わったりした時でも、味の感じ方が変わってくるということです。それがどんな変化によって起こるのかも、突き止めようとしています。
人間を使った実験はなかなかできないので、まずはマウスを使って行います。小さいころについて調べるのはもちろん、若いマウスと老いたマウスの違いを比べたりもしますね。
どの部分がもっとも大きなキーポイントなのかについては、動物の実験でもわかるはずです。
一方、味については「満足感」という面もあります。例えば、少ない塩分でどれだけ満足できるかもそうですね。
大人になってからも食事の好みは変わりますが、その満足感はどこからきているのかということです。そもそも「美味しい」とはなんなのかを科学の言葉で表そうとしている中で、受容体という入り口の部分から、脳で感じてそれを美味しいと思うのはどういうことかという全体像を研究対象にしています。
Q:研究は独自のものなのでしょうか。
味覚研究については、医学分野の研究では取り扱われず、歯学部の口腔生理学の分野で研究されているのが現状です。
メディカルドクターがやらない分野ですし、一方で食品関係の人も盛んにやっている分野でもありません。そのため味覚は、なかなか手をつけないような分野とも言えるかもしれません。
我々が属している農学部の食品科学の分野では、美味しいものをつくるという視点から味覚の研究をしているわけです。
私たちは仕組みよりも、美味しいものをつくるためには何が必要かを考えて研究をしています。その意味では、世界的に見てもかなりユニークな立ち位置にいるのではないかと考えています。
味覚測定の感度という視点では、世界中の他の研究室より、はるかに先を行っていると思います。
実物の食品を測定できる技術の開発へ
Q:現時点で解決したい課題としてどんなものがあるでしょうか。
現状では味の強度を測る場合、測りたい試薬を測定用の溶液に溶かしたものであれば、正確に評価することができます。
ただ実際の食品を考えると、果汁が入ったジュースや固体のお菓子など、液体ではないものもあります。また液体であっても果汁などは、味の受容体がなくても細胞が反応してしまいます。
生理活性物質だったり、酸だったり、温度が冷たかったり温かかったり、様々なものが刺激になって細胞に応答を与えてしまうのです。
「ジュースをコップに入れてそのまま測る」ことも、現時点ではできない状態です。個体のクッキーやキャンディなども、もちろん測れません。
さらに、今の測定では光の変化を使って測るので、色がついていたり濁っていたりするものも難しいですね。測れるのはあくまでも、粉末を溶かしただけのピュアな液体だけともいえます。実際の食品に近くなればなるほど、何も効力を発揮しません。
こうした面から、測定できるものの種類を増やしていかなければならないと考えています。これからは実際の食品に近いものを測れるようにするための技術改良に、どんどん力を入れていきたいですね。
Q:研究室には、どんな学生がいますか。
学生は4年生の最初からです。毎年1、2人の学生が進学しています。
研究室を選ぶ動機としてはなにより、食べることが好きなのだと思いますね。味の客観的測定というのが非常にわかりやすく、そこでできることが数多くあることが魅力なのだと思います。
この学科には色んな食品分野の先生がいらっしゃって、様々な視点から研究をしています。その中で「美味しさ」は非常にわかりやすい現象で、美味しいものを科学的に解明すると聞いただけでも興味を持ってくれるのかなと思います。
この研究室では学生には、たくさんのことに挑戦してもらいます。様々なアイデアを出して、まずは試してみて、トライアンドエラーをたくさんやってほしいですね。学生のうちは、何回失敗してもいいわけですから。
最近の学生は、失敗することを恐れている人が多い気がします。いまの時代、調べれば何でも分かると思っているのかもしれませんが、科学の世界は調べてもわからないことを自分たちの手で提示していくものです。その突破口を切り拓くことにチャレンジしてほしいと思います。
また日本人の学生は、「自分たちはここなら勝てる」という部分を伸ばすことも苦手です。もっと野心的にと言いますか、自分たちの持っている技術でも世界で戦えるということを認識して、勝てる部分を戦略的に追求していってほしいです。
Q:企業との共同研究などはどのように進めていらっしゃるのでしょうか。
実際にいま共同研究を進めている企業は4~5社ほどになります。
先ほどお話しした甘味の増強などは、たくさんの企業が興味を持っている部分でもありますが、同時期に同じテーマを扱ってしまうと信頼関係にも影響してきます。そのため、同時進行でテーマが重複するものはお断りしている状況です。
ただ食品の企業は、研究開発費にかなり四苦八苦されています。食品はさほど高いものではありませんので、技術的にあれこれやっても、利益につながるアウトプットに繋がらないことも多いのです。
食品企業の研究所はかなり疲弊していて、予算的にもかなり厳しくなっています。日々の開発も非常に煩雑になっていて、なかなか将来を見据える研究に力を注げない状況です。
売り上げに対する研究開発費の割合は、薬品の分野では12%ほどありますが、食品は1%くらいしかありません。
新薬は一個作れれば大きく儲かりますが、食品で一つイノベーションがあったとしても、売り上げという意味ではそれほど効果はありません。
また、味の研究に関しては、古い人ほど「自分の舌でわかるでしょ?」という風潮がどうしても強い感じがします。味を科学的に測ることのメリット、そこからどんなふうにイノベーションにつながるかということを、あまりまだ認識していただけていない気がしています。
食品については消費者の要求が厳しく、中身はもちろんですが、外見の包装についても企業努力が求められています。食品包装についても、開けやすいとか漏れにくいとか、様々な視点からのイノベーションが進んでいます。
このように、中身も包装も様々なことに力を入れなければならない中でも、やはり味は食品の価値判断として最も大事な部分です。「食べて美味しい」ということを最低限担保しないと買ってくれないわけですから、こういった基礎研究の部分にももう少し力を注いでほしいなと思いますね。
Q:企業とは、どういった取り組み方がベストだとお考えでしょうか。
企業側の課題を解決するための方策を考えるのが、一番話が進みやすいと思います。
企業が抱えている技術的な課題のうち、解決できそうなものもあるのは事実で、そこを解決するのに少しずつ技術改良をしていければ、と思っています。そのため、現場で出ている課題がこちらによく伝わってくるような仕組みをつくれるといいなと思っています。
その会社ならでは、その業界ならではの問題点を、こちらから聞きにいくことも大事ですね。やはり産業との接点はただ待っているだけではつくれないので、こちらから伺うことで初めて課題が見つかっていくと思います。
個別の課題を解決していく中で見つかる一般則は、他のことにも使えたりしますから、業界で課題になっていることに着目しながら進めていきたいですね。(了)

三坂 巧
みさか・たくみ
東京大学 大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 准教授
1993年、東京大学 農学部 農芸化学科卒業。1995年、東京大学 大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 修士課程修了。1998年、同 博士課程修了。
1998年より日清食品株式会社に入社。その後、2000年より東京大学 大学院農学生命科学研究科 農学特定研究員を経て、2001年より日本学術振興会 特別研究員(PD)。その後、2003年より岡崎国立共同研究機構 生理学研究所 助手を経て、2005年より東京大学 大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 講師。2008年より現職。
