電気化学的酸化還元により色が変わる「エレクトロミック材料」が、最近、脚光を浴びている。日差しをさえぎる調光ガラス窓や、車の防眩ミラーの材料として、時代のニーズをつかみはじめているのがその背景だ。
こうしたなか、有機と金属のハイブリッドポリマーで独自のエレクトロクロミック材料を開発したのが、物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 電子機能高分子グループ の樋口昌芳グループリーダーだ。
今回は樋口グループリーダーに、研究の独自性と可能性について伺った。

電気で色が変わる「エレクトロクロミズム」を研究
Q:まずは、研究の概要について教えてください。
色が変わる物質には、様々なものがあります。
例えば紫陽花(アジサイ)の花が赤かったり、青かったりすることもそうです。紫陽花は地面の酸性度の違いによって、花の色が変わります。日本は酸性の土地で、青い紫陽花の花が咲きます。一方ヨーロッパあたりは中性なので、赤い花になりますね。色の変化を起こしているのは、紫陽花に含まれる「アントシアニン」という物質です。酸性度の違いで色が変わる現象は「ハロクロミズム」と呼ばれています。
他にも似たような性質で、触ると手の温かさで色が変わる温度計のような「サーモクロミズム」や、紫外線や可視光線を当てると変色する「フォトクロミズム」などがあります。
その中で私たちが研究をしているのは「エレクトロクロミズム」というものです。エレクトロクロミズムの実用化例としては、ボーイング787の飛行機に「ボタン押すと暗くなる窓」があります。
こうしたエレクトロクロミック材料は、実は30~40年以上前から研究されています。電気をかけると色が変わるような物質が報告されてきており、古くからあるものが最近実用化されてきているわけです。
例えば飛行機の窓に限らず、エレクトロクロミック材料をガラスで挟むと「調光窓ガラス」になります。街中で見かけるような、全面ガラス張りのビルなどにおいて調光窓ガラスが使われるようになると、窓自体が暗くなって遮光するので、ブラインドが不要になります。
将来的にはエレクトロクロミックの調光窓が世界中に広まっていくと考えられており、いままさに開発競争が進んでいる状態といえます。
Q:エレクトロクロミック材料の研究は、どのように発展してきたのでしょうか。
エレクトロクロミック材料は、いまから30年ほど前に一度研究が盛り上がった時期がありました。それまでのブラウン管に代わるテレビの画面に利用しようと盛んに研究された時期です。当時は液晶という競合相手があり、液晶とエレクトロクロミック材料という二つの選択肢がありました。結局は液晶が勝って、現在に至っています。
ただ、一般に、液晶にはない、エレクトロクロミック材料ならではの特徴があります。それは電源を切っても表示が続く「メモリー性」です。
液晶の場合は電源を切ると暗くなってしまいますが、エレクトロクロミック材料の場合は電源を切ってもその時の状態を保持させることが可能です。例えば、文字が表示されていたら電源を切ってもその文字は消えません。
このメモリー性のある表示物は最近徐々に注目が集まってきており、常時通電していなくてもいいものが注目されるようになってきました。
例えばウェアラブルの電子機器に簡易なディスプレイをつける時、常に通電しておかなければならないとなると、やはり表示にエネルギーをかなり使ってしまいます。すると消費電力が多くなり、バッテリーも大きなものが必要になってきます。その意味でメモリー性のある表示物なら、バッテリーを小さくできるため、ウェアラブルの電子機器に適しているわけです。
表示を変える時にだけ電力を使うので、動画向きではありませんが、表示する数字を変えるだけなどであれば常に通電しておく必要はありません。むしろ小さな電力で動くような表示物が適しているということになります。
最近のメモリー性を持つデバイスとしては、エレクトロクロミックとは少し違いますが「電子ペーパー」というものがあります。
電子ペーパーはマイクロカプセルの中に黒い粒子と白い粒子が入っていて、電気によって中の粒子が移動することで表示させるという仕組みになっています。Kindle などの電子書籍リーダーもそうですし、最近では SONYから電子ペーパーを搭載した腕時計が発売されました。
メモリー性があるという観点では、エレクトロクロミックデバイスと電子ペーパーは仲間であると言えます。
このように、省エネルギー性のある表示物が、最近非常に注目されてきているのです。
Q:こうしたなか、この研究室ではどのような研究が中心ですか。
私自身は元々、エレクトロクロミックの分野ではなく、「有機金属化学」や「錯体化学」と呼ばれる分野の研究を行なってきました。
錯体化学とは、金属イオンと有機物が結合してできた分子を研究する分野です。
一方で金属炭素結合を持っている化合物を有機金属と呼んでおり、有機金属化学は錯体化学に似ているのですが、日本は世界的にみても研究レベルが高いといえます。
例えば2000年には白川英樹先生が「電気が流れるプラスチック」でノーベル科学賞を受賞されていますが、有機金属はその時の触媒にも使われるなど、化学の分野では非常に活躍しているものです。
私はもともとこの分野の出身だったわけですが、慶應義塾大学の助手になった時から、専門が有機金属化学から高分子錯体化学に変わりました。
何が違うかというと、錯体化学や有機金属化学は、ある1個の分子について調べるのが一般的です。一方で、高分子錯体は、それが繋がって長くなった高分子(ポリマー)を調べる化学です。高分子になると、より材料に近づいてくるわけです。
Q:金属に色がでるメカニズムはどのようになっているのでしょうか。
錯体化学は、例えば血の色が濃い赤(ヘモグロビンの色)であるように、鉄と有機物がくっつくと、強く色がつくというケースが多いです。一方、金属錯体を高分子にした場合は、強く色のついたポリマーになるので、製膜などをすることで材料として扱えるような研究が進んできたということになります。
もう一つ重要なのは、膜ができることで、電気を流せるようになるということです。電極の上に材料を塗って電気をかけると、電極から電子をもらったり、出したりすることができるようになり、その材料自体に電気がかけられるようになるのですね。
ふつう、金属錯体や有機金属など、1個の分子の場合、通常は溶液に溶けているため電気をかけにくい状態になっています。それを固体にすると綺麗な結晶になるのですが、きれいな結晶も比較的電気をかけにくいものです。
このため、ポリマーにして膜になることがすごく重要で、それによって電気がかけやすくなります。これはつまり「金属が入っているポリマー」ということになります。
普通のポリマーはプラスチックやゴムなど、金属が入っていないものです。普通は有機分子があって、それを重合して繋げていくと長くなっていきます。普通のポリマーは電気が流れません。そのため、絶縁体としてコンセントのカバーなどに使われているわけです。
一方で鉄などの金属イオンは酸化されやすいものです。金属イオンの入っているポリマーは、電気的に酸化や還元ができるようになります。
ではなぜその金属錯体に強い色が出ているか。それを説明します。
有機物や金属にはたくさんの電子が含まれています。エネルギーが低いところから順番に電子が詰まっていて、金属によって電子の数が決まっています。実はその上にまだエネルギーの順位があり、そこには電子が入っていません。
それが光を浴びると、一番高いエネルギーのところにある電子は、電子が入っていない軌道の一番エネルギーが低いところに移動していきます。電子が移動するときに、移動に必要なエネルギーを吸収します。ある色のエネルギーを吸収したら、目に見えるのはそれ以外の色、つまり補色ということになります。白なら、光を全然吸収していないということですし、黒はすべての目に見える範囲の光の色を吸収しているということです。
例えばペットボトルは透明ですが、これは電子が入っている軌道と、その次の電子の入ってない空の軌道のエネルギー差がものすごく大きな状態と言えます。そのため、目に見える光、可視光線の光では全然上に行かない=移動が起こらないということです。
さて、金属イオンは金属の種類によって違いますが、金属イオンのみだと色がなかったり、黄色かったりするものもあります。黄色の補色は青紫なので、吸収するエネルギーは可視領域では最も大きく、いずれにしてもほぼ色がない。また、有機物も、いろいろな理由で着色しますが、基本的に色がないものが多いです。
では、金属錯体ではどうか。金属錯体は、「金属と有機物が両方ある状態」です。この場合、光の吸収の仕組みが、すこし違っているのです。
すると何が起こるかというと、金属の電子が有機物の電子の入っていない一番低い軌道のところに移動していきます。これを金属と有機物の間の「電荷移動」と呼んでいます。そのエネルギー差は、小さい場合が多いです。そのため、金属だけ、有機物だけでは色がないのですが、それがくっつくと、金属から有機物の電子の入ってない軌道へ電子が移動し、それが色となるのです。さらにその移動が頻繁に起きていると「色が濃い」という状態になるのです。
以上の理由から、金属錯体は色が濃いケースが非常に多いです。
もちろん金属だけでもエネルギー差を小さくして色を出すとか、有機物でもエネルギー差を小さくして色を出すことができます。例えばグラファイトなどの層状の炭素の化合物はエネルギー差が小さく、黒いです。一方で色味のないダイヤモンドなどは、かなりのエネルギー差があると言えます。
有機物の構造を変えていくだけでもエネルギー差は変えることができて、一般的にはエネルギー差が小さいと電気がよく流れるようになります。そのため、白川先生の電気が流れるプラスチックなどは、エネルギー差をなるべく小さくしていることで知られています。
普通の有機物はエネルギー差がすごく大きいので、色がありません。色がないということは、電子が動かない。つまり電気が流れないもの同士を近づけることで電気が流れるようになる、ということです。
さて、私自身はこうした研究をしているなかで、2004年にNIMSに来ました。
NIMSでは、慶應の時とは別のタイプの金属錯体ポリマーを博士研究員とともにつくって、それを膜にして、電気を流した時に、偶然にも色が消えることを発見しました。色がついていたところに電気をかけたら、色が消えたのです。
これは、従来の錯体化学の先生ではなかなか見つけられなかった発見でした。従来の研究ではある一個の金属錯体や分子を研究するアプローチだったため、溶媒に溶けてしまうため、電極で電気をかけることができませんでした。
ところが私がやったようにポリマーにすることで、電気が流せ、すると電子が取られる、すると色が消えるということがわかったのです。ポリマーにしたから膜にすることができて、膜にできたから電極に塗れて、電極に塗れたから電気を流すことができ、色が消えた。こうして、金属を酸化すると色が消えるということがわかったのです。
2005年にこの現象を発見し、それからずっとその研究を続けてきています。
新参者として、常識に縛られず新たな発見を追求する
Q:技術的・産業的な課題として、どんなことがありますか。
エレクトロクロミックの材料については30~40年前から研究されてきており、業界の「常識」のようなものができています。いっぽう、私は完全に新参者でした。もともとの分野が違うので、業界の常識的なことをあまり知らなかったんです。
最初にお話したとおり、エレクトロクロミック材料は何十年も研究されてきているのに、ほぼほぼ実用化されていません。業界を見ても、経験者であるほど、液晶と比較して「エレクトロクロミック材料はこんなもんだろう」「もう、この分野はやめておいたほうがいいな」という雰囲気が当時ありました。
そんな中、最近になってメモリー性が注目され、ウェアラブルなどのデバイスに求められるようになってきています。電池の性能ももちろん上がってきてはいますが、なるべく電力を無駄にしないようなものがいいと考えられるようになってきたのです。
しかし、ここで電子ペーパーにはある致命的な欠点が出てきます。それは、カラー化が難しいという点です。
電子ペーパーの中にあるマイクロカプセルには白い粒子と黒い粒子がありますが、その粒子が電圧で変わります。と言っても、カラーである液晶自身も実は色がないものです。普通に見たらカラーに見えますが、それはカラーフィルターをつけて後ろからバックライトで明るく照らしているから色があるように見えるのです。
そのため、電子ペーパーをカラー化しようとしたら、同じようにカラーフィルターを付けてバックライトで照らせばよいことになりますが、それだと省電力という売りを自ら消すことになります。
省電力を生かすと、白黒からは抜け出せないというジレンマが電子ペーパーにはあります。粒子を白黒ではなく赤黒とか青黒にはできるのですが、それならば白黒がいいですよね。
一方、我々の材料には、カラーバリエーションが豊富という特長があります。従来のエレクトロクロミック材料は、色がすごく限定されていて、例えば飛行機の窓の色のような感じで、デザイン性は出せないものです。電子ペーパーと同じような感じですが、いい部分を生かしていこうと検討しています。
Q:現在、外部企業との取り組みについてはどのようなものがありますか?
現在はベンチャーの立ち上げを含めて、実用化に向けて、様々な企業と連携してもらおうという取り組みを行なっています。
例えばエレクトロクロミック材料そのものをつくってくれる化学系の会社、それからガラス系。ガラスには透明電極を塗ってあるのですが、それを供給してくれる会社。ガラスは電気が流れないものですので、透明電極というものが必要です。それを作ってくれる会社ということですね。
企業とは別に、美術大学との共同研究も進めています。プロダクトデザインというか、カラーバリエーションをどうやって表現するかに関しては、ある程度「美術品」のような雰囲気もあるんです。いわば、新しい表現の仕方という感じですね。
2017年「グラデーション変化する調光ガラス」というものでプレスリリースを出しました。遮光状態になると、まったくと言ってもいいくらいに外が見えなくなります。そこで美術大学と共同研究をしているのは、「均一に変わらない、曖昧だったりぼかしが入るような感じ」です。あえてそういう変化をすることも、表現方法としては非常に重要だと考えているのです。
例えば液晶の画面はピクセルという小さな粒でできています。その中にRGBという3つの色があって、それが様々な色を表現しています。それは調光ガラスと同じように、全部がつくか全部が消えるかが、どんどん小さくなって表示されています。つまり、0か1か二択なのです。このディスプレイでものを考えると、人はどんどんデジタルな思考になっていて、美術作品などをこの画面の中で完結しようとすると、すべてがデジタル化されてしまいます。
ところが日本の美術には、侘び寂びやぼかしなど、0と1ではない表現方法が古くからあります。それが今まさにデジタルアートになっていくと、自由な表現をしているつもりでも、実はどんどんどんどんデジタルな画面の中での表現の仕方だけに入ってくるわけです。
その中で、グラデーション変化をするような不均一に色が変わるエレクトロクロミックデバイスは、表現に対する新しい可能性というか、電気製品ではありますが、新しいアートに繋がっていくのではないかなと考えています。
Q:最後に今後の目標について教えてください。
まずは私たちのエレクトロクロミック材料を、世の中に商品として出していくことが一つの目標です。
今、エレクトロクロミックは世界的にも盛り上がっており、中国や韓国、台湾など、各国で研究が盛り上がってきています。日本で見つかったものを日本発の技術として世界の中に出していく。それが非常に重要だと考えています。
また、いわゆる「ものづくり」にとらわれないようにしたいです。欧米などを見ると、デザインにおいては「ヒューマンセンタードデザイン」の意識が強くあります。そのため日本もものづくりが得意だとか言っているだけではなくて、人間を意識したデザインにも取り組んでいくべきだと考えています。
つくった材料を最短ルートで効果的に世の中に出し、世界的に広げていきたいですね。(了)
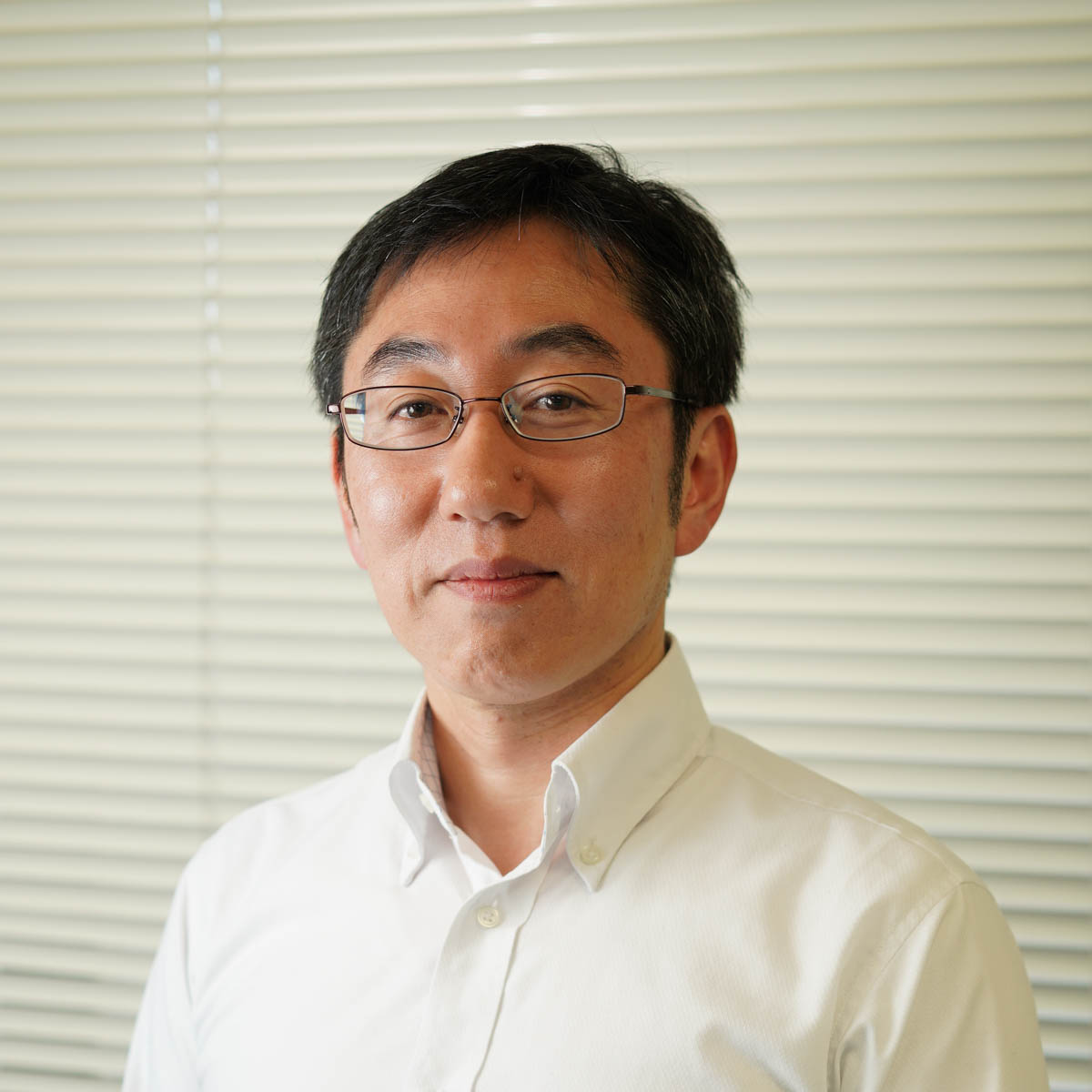
樋口 昌芳
ひぐち・まさよし
国立研究開発法人物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 電子機能高分子グループ グループリーダー。
1993年、大阪大学工学部 応用精密化学科卒業。1998年 大阪大学大学院工学研究科 物質化学専攻 博士後期課程 修了、博士(工学)取得。
1998年より、慶應義塾大学 理工学部 化学科 助手、のち専任講師を務めたのち、2004年に物質・材料研究機構 主任研究員として着任、のち主幹研究員などを経て、2009年より現職。
