急速に膨れ上がる我が国の医療費。その約1/3が生活習慣病に依るものであり、これを予防・軽減する機能を持つ食品の開発・販売が切望されている。2015年には「機能性表示食品」制度が施行され、生活習慣病予防のための食品開発が盛んに行われている。しかしながら、機能性表示の認可には医薬品同様にヒト介入試験をも含む科学的な機能性の証明が求められ、これが画期的・意欲的な機能性食品開発の障害となっている。こうしたなか、ヒト介入試験に先立って食品の機能性をプレ評価する「KUHIM」と名付けられたヒト腸管モデルを開発したのが、神戸大学 食の安全安心科学センターの大澤朗センター長だ。海外のモデルと比べて腸内環境の再現度の高いモデルの開発経緯と今後について、大澤センター長に話を伺った。

マウスの動物実験に代わる、ヒトの実験基盤を求めて
Q:まずは、腸管モデル研究の社会的ニーズについてお話しください。
私たちの「神戸大学ヒト腸管モデル(Kobe University Human Intestinal Model [KUHIM*])は、食品に含まれる成分の健康に資する機能性をヒト介入試験に先立ってプレ評価するツールとして開発されました。
開発の社会的ニーズからお話しすると、まず我が国の医療費の増大が背景にあります。
現在、日本の医療費は40兆円台ですが、2025年頃には60兆円台になるといわれています。こうした医療費のうち約1/3を占めているのが、生活習慣病と呼ばれるものです。高血圧や糖尿病、がんなどが日本人の死因の6割を占めているわけです。
ただ、これらの病気はその名からわかるように、生活の習慣を改善すれば予防・軽減できるものであります。例えば、薬に頼るのではなく食生活を変えてみる、などです。この意味で、生活習慣病を予防・軽減する機能を持つ食品が注目されるわけです。
これに付随する問題として日本の高齢化が挙げられます。日本は長寿国と言われていますが、介護がいらない「健康寿命」についてはそれほど長いとはいえません。男女差はあるものの、介護が必要な期間は10年にも及ぶといわれています。
特に最近テレビでも取り上げられているのは、認知症です。認知症になるとご本人も非常に大変だと思いますが、ご家族も大変です。またそういった人たちを看護する施設も大変で、人員も足りなくなってきているのが現状です。
一方で、認知症についても食事で進行を遅らせることができると、最近の研究でわかってきています。どの成分に進行を遅らせる機能があるのかを、できるだけ早く見つけ出していくべきと思っています。
日本政府は4年ほど前、安倍首相が掲げた経済対策として、「機能性表示食品」制度という取り組みを始めました。これは従来の「保健機能食品」と呼ばれるもの、これは所謂「特保」も含んでいますが、これらは厚生労働省が管轄をしているもので、薬を開発するのと同じぐらい、認可されるのが難しいものです。薬並みに様々なことを要求されるので、よほどの企業で覚悟がないとなかなか開発に踏み切れません。
そこで、私の勝手な推測なのですが、安倍首相は少し規制を緩めて、とにかく科学的に証明されれば、会社の責任で機能性を謳っても宜しいことにされたのだと思います。その経緯はともあれ、2015年から消費者庁管轄の「機能性表示食品」制度が始まりました。
機能性表示食品として、毎年300~400件ほどの申請があり、施行後3年間で難消化性食物繊維やポリフェノール、プロバイオティクス等を含む約1200件が認可されています。認可される要件としては、文献で人の健康に資するとわかっているようなもの、例えばビタミンなどがあれば、認可されます。認可のために、「これとこれが入っているから、機能します」というように、すでにわかっている事実を寄せ集めて謳うやり方は、「システマティックレビュー」と呼ばれています。
もう一つの認可方法は、ほとんど医薬品と同じですが、ヒト介入試験をしてそれなりの効果を証明していくものです。特に新規のものについてはヒト介入試験をしなければなりませんが、認可を受けた1200件のうち意欲的にヒト介入試験をしたものの割合は、5%程度。非常に寂しい結果になっています。
ヒト介入試験の実施に何故皆さん消極的なのか。これは、ヒト介入試験に至るまでのプロセスのハードルが高いことが大きな理由になっています。
特に新規のものなどは、いきなりヒトに食べさせるわけにはいきません。まず培養細胞にふりかけて良い結果を出し、次はネズミなどの実験動物で試験を行ないます。その段階で糖尿病に効く、中性脂肪を下げる効果があるなど、薬のような効果が認められた時に、「これならヒトに使えるかもしれない」ということでようやくヒト介入試験に至るのです。
しかしヒト介入試験は倫理的なハードルや金銭的なハードルが非常に高く、失敗覚悟で何度も行なうことはできません。それにもかかわらず、ネズミでは効いたのにヒトには効かないということがお薬開発の場合と同様に往往にしてあるわけで、みなさん消極的になってしまう。
ではなぜ、ネズミでは上手くいったのに、ヒトになると上手くいかないことがあるのでしょうか。これは1つには投与量の問題です。
ネズミを使って食品成分の機能性を測る際、ヒトに投与する濃度よりも多めに機能性成分を与えています。ネズミは体が小さいため、ヒトと比べると代謝能が桁違いに多いことが関係しているのですが、この投与量をヒトに換算するとものすごい量になってしまいます。
そのため、ネズミで得られた効果を求めて、ヒトに許せる範囲の投与量でやってみても、効果は出ないわけです。
次ぎに問題となるのは、ネズミは体が小さいので、食べたものが腸管を通過する時間がヒトに比べて非常に短いです。ネズミのお腹の中にいる微生物も、ヒトのお腹の中にいるものも同じ類のものですし、代謝能は同じなので、滞留時間の違い、つまり培養時間の違いは、入ってきた食品成分がどのように消化吸収されるかということに大きな影響を与えます。
それともう一つの問題点は、腸内細菌叢の構成です。ヒトやネズミの腸内には様々な細菌がおり、これを腸内細菌叢と呼びます。文献によれば、ネズミのおなかにいる腸内細菌叢のメンバーとヒトのおなかの中にいるメンバーは、分類学的に見ると属レベルで15%しか被っていないのです。つまり、85%が全く違う属というわけです。
マウスの場合、腸内細菌の主力は乳酸菌です。乳酸菌(Lactobacillus)はその名のごとく代謝産物として乳酸を出すものです。ところがヒトの場合は、フィーカリバクテリウム(Faecalibacterium)と呼ばれるような、酪酸を出すものが多いのです。
このように、宿主の代謝能やその腸内細菌叢構成が違うため、同じ食品成分を入れたとしても、代謝のされ方がヒトとネズミでかなり違ってくるのです。
ここ4~5年の間に、ここまでご説明したようなネズミとヒトの齟齬を唱える科学論文が目立つようになってきました。果たして、「ネズミの実験結果は、そのままヒトには当てはまらない」ということがわかってきたのです。
私どももかなり以前からこの齟齬を問題視しており、ネズミがダメならどうするかと考えていました。ヒトを使うことが一番いいのですが、いきなり人体実験はできません。実験に使う食品成分の安全性については、ある程度それが保証されたものを使いますが、それでも動物実験に依らないヒト介入試験に先立つ食品成分の機能性プレ評価ツールが欲しかったのです。
そこで思いついたのが、ヒトの腸内環境を模したモデルをつくることでした。
腸管モデルを作る取り組みはなにも私どもが初めてではなく、10年以上前からオランダやベルギー、イギリスなどで行なわれていました。ある程度の結果は出ているようでしたが、私どもは彼らとはちょっと異なる切り口で腸管モデルの作製に取り組んだわけです。
Q:この研究室にある腸管モデルには、どんな独自性がありますか?
腸管モデル作製の際には私は勿論、先ほどお話ししたヨーロッパで開発された腸管モデルの情報を参考にしたり、実際に見学させてもらったりましたが、私どものモデルとは彼らのとはちょっと違います。
腸と一言でいっても小腸と大腸にはかなりの違いがあり、役割も違えば構造も違うのですが、ヨーロッパのモデルは、小腸と大腸を一緒に繋げてしまって、胆汁が出たり、粘液が出たり、胃酸が出たりといった感じで、とにかく機構的に模していて、いかにも腸管らしい構造です。
一方、私が自分たちのモデルは腸を小腸部と大腸部の2つに分割して扱っています。そして特に注目、注力したのは、大腸部での細菌叢の再現性です。
私の専門は細菌学です。ご縁あって日本の腸内細菌学の権威である東大の光岡 知足(ミツオカ・トモタリ)先生から腸内細菌の在り様を教えて頂いた経緯があるのですが、大腸はまさに「バクテリア王国」で、その内容物1gに1兆個ぐらいの菌がいるといわれています。私はまず、大腸の腸内細菌叢を模しているかどうかにこだわりました。
大腸では嫌気度(酸素が少ない状態)が非常に高くなり、偏性嫌気性菌(酸素がちょっとでもあると増殖できない菌)が完全に優勢となる特徴があります。
偏性嫌気性菌の代表として知られているのは例えばビフィズス菌ですが、乳酸菌は通性嫌気性菌で空気があっても育つものです。大腸の中では、ビフィズス菌のほうが千倍から1万倍の数で多く存在します。
このビフィズス菌の多さでもわかるように、大腸の腸内細菌叢は偏性嫌気性菌優勢でなければいけません。
しかし、これらの要件についてヨーロッパのモデルが満たしているのか、文献を調べても、実際に現地に行って担当者に直接インタビューしても確認することはできませんでした。
それともう一つ大事な要件があります。難培養の細菌の有無です。1兆個の中にはおよそ500~1500種程度の菌がいるといわれています。その中には通常いかなる培地にも生えてこないような難培養の細菌、つまり他の細菌の代謝産物がないと生きていけないような細菌がおり、それらが私たちの腸内の8割を占めています。こういった難培養の細菌が生えているかということも、ヨーロッパのモデルを用いた文献には言及されていませんでした。
一方、我々のモデルでは、次世代シークエンサーによる網羅的な菌構成の解析を通じて、難培養の菌の増殖も含めた大腸の腸内細菌叢の再現性が確認されています。これが本モデルの強みというわけです。
Q:現在の研究体制にいたるまで、どんな経緯がありましたか?
まずは、モデルに使用する基礎培地をどのようなものにするかが問題でした。
当初、私たちは大腸内の栄養環境を模すことに執着していました。消化されやすいものはだいたい小腸で消化されてしまうので、大腸内ではグルコースやデンプンなどはないだろうと考え、とりあえず消化・吸収しやすい糖分は総て抜いた液体培地使って実験をしていました。
しかし、そのような培地ではヨーロッパのモデルと同じように、菌数が1gに1兆個というレベルに全く達せず、菌種の多様性も限定的でした。ということで1年ほど、この状態でモデル開発の取り組みは空回りしていました。
もう止めてしまおうかとも思ったのですが、最後の手段で「嫌気性菌がたくさん生える」という市販の培地「GAM培地」を使うことにしました。
当時の学生がこれをみて、「先生、この市販の培地には大腸まで行き着かないデンプンもグルコースも入っています。それでも大丈夫ですか?」と質問してきました。
苦し紛れに「それなら、培養開始の時は、大腸ではなくて小腸の真ん中あたりだとして考えてみよう!」という答えになりました。培養開始9時間ほどで培地中のデンプンもグルコースも細菌達にすべて使い切られて、それ以降の培地の栄養環境は大腸のそれに近づくと想定したのです。
で、実際に使ってみたところ、本当にそのようになりました。総菌数も、多様性もほぼ実際の大腸の細菌叢と同等の状態を再現することに成功しました。
発見したときは、なんでこんな簡単なことに気づかなかったのだろうと思ったのですが、翻って「思い込み」を「思いつき」に転換することの難しさを知ることになりました。
*KUHIMは文部科学省先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム:バイオプロダクション次世代農工連携拠点(iBioK)において考案・開発されたものである。
実験台数を増設し、研究の効率と精度を上げる
Q:今後の研究課題としてどんな点が挙げられますか。
現在の私たちの腸管モデルは、ガラス容器の中で培養をしています。しかし、本物の腸管はガラスではありませんし、粘膜があって吸収や排出が行なわれる部分でもあります。そういった本物の大腸を模すことは、非常に難しいですね。どうにか工夫した膜層をつくり、様々な物質やりとりを実際の腸管壁のように行なえるようなものがあればいいなとは思っています。
現在の腸管モデルついてもう1つ至らぬ点は、一度に沢山の試験をこなせない点です。我々は1度に8つのヒト腸内細菌叢モデルを稼働できる連続嫌気培養装置2台を駆使していますが、それでも1度できる試験数は16です。現在、5社ほどの企業様と共同研究を行っておりますが、これらの研究で必要な試験をこなすのでいっぱいいっぱいです。もっと簡便にミニチュアライズしてもっとたくさん試験ができるシステムをつくっていかなければならないと考えています。
当然のことながら、「たくさん実験ができること」を重視しているのは、より精度の高い評価のためには沢山の実験データが必要だからです。
動物実験では、人が通常飲んでいる量より遥かに多い量を動物に投与して、そこから食品成分の機能性を評価している研究もありますが、私たちはあくまでもヒト介入試験がその先にあるということを念頭に、実際にヒトが食する量に近い量をモデルに投与して成績を出しています。
そのため、我々のモデルではときとして結果の解釈が非常に微妙な場合もあります。
そのぶん、たくさん試験をし、統計的な処理に耐えうるデータをつくる必要があります。数多くの試験をこなして、微妙な有意差を見極めていくことが必要ですね。
Q:この分野を志す学生には、どんなことが必要でしょうか。
当研究室では、これまで学部学生の半分以上が将来の研究者や研究職を目指して大学院に進みました。
本分野に興味ある学生だけではないかもしれませんが、私が彼らに伝えたいことは、「失敗を恐れないで!」ということです。
研究には失敗がつきものです。十やって一当たればいい。それでもめげない強いハートを持って、諦めないで続けることは大事だと思います。
関連して、思い込みにとらわれないことも大事です。例えば「こんなことやっても無駄だ」とか、頭の中で先回りしてしまう。しかし、研究は思いつきでやることも大事です。思い込みで先回りして、ダメだと決めつけるのは良くないですね。特に相手は生物で、私たちの頭の中の思い込みをはるかに超えたことをする存在です。人間が思い込みで実験を無駄だと思ってやらなければ、いつまでも真理にはたどり着くことができません。
私は大学院での研究モードを、よく山登りと航海に例えて話しています。まず、マスター(修士課程)のレベルは山登り。山登りは、大体登る前から頂上が見えていて、あそこに行けばいいんだなということがわかっているわけです。高い低いはあるかもしれませんが、低い山だとしても誰も登っていない山があるかもしれません。そこから見えるのは60億人の人間の中で、初めて見る景色であって、向こうに何があるかを伝えることができるようになるわけです。ですから、マスターレベルの人は、標高は色々だと思いますが誰も登っていない山を登っていると考えてください。
ここまではマスターレベルの話ですが、ドクター(博士課程)になるとまた話は違ってきます。
マスターの時は頂上が見えていても、ドクターの時には航海、つまり大海原にいて水平線が広がるだけで、どっちの方向に行けばいいのかわからない時も出てきます。自分が漕ぎ進んでいる先に、本当に目的の大陸があるのかわからない。誰も行ったことがないところに行くのですから、相当の不安、恐怖感もあるでしょう。
昨今ドクターに進む人はマスターの延長だと思われているような学生さんが多いようですが、そうではありません。ドクターに進まれる方はそれなりの洞察力と勇気とか覚悟が必要だと思います。
例えば、私たちがやっている腸管モデルを用いた研究も、動物実験では証明できないけれども、ヒトの実験ならば有効性があるものを探そうとしているわけですが、それは決して楽観的な感じではなく、その先に本当に何かがあるのか、幻を追っているのではないのか、という不安が常につきまっとっています。腸管モデルという船に乗っているけれど、進んでいるこの方向で日本が抱えている医療費や、高齢化の問題の解決に資するところに本当たどり着けるのか。こうした不安がすごくあるわけです。
しかし、もしその先に人の健康に資する知見があるのであれば、「是非それを得て万人の幸せに繋げたい!」。こんな滅私の志を持っていれば、その大海原も健気に突き進めるのではないかと思っています。
Q:企業活動とも密接に関わる研究分野ですが、企業に対して求めることはありますか?
昨今、多数の企業が機能性食品の開発に取り組まれていますが、中には当該食品成分の名前の「巷受けする」響きを重視されて、その成分のヒト腸内での動態がほとんど理解されないまま上市されている場合があるのが残念です。
食べたら確かに健康に何かいいことが起こる食品成分は確かに沢山あると思いますが、その作用プロセスやメカニズムを極めれば、もっと有用、簡便、安価なる機能性食品開発へ、延いては私たちの健康への近道も見つかるのではないでしょうか。
ですので、企業側も、営業利益も確かに大事なのですが、「全国民全体の健康への願望に応えよう!」とこれもまた「滅私」の志をもって機能性食品の開発に取り組まれることが必要ではないかと思っています。
一方、上市された「機能性食品」を選択するのは消費者で、その選択には正しい知識が必要だと思います。消費者の側も本当に健康になられたいのであれば、機能性成分のヒト腸内での動態や作用メカニズムについて勉強されることも必要かと思います。
医療費60兆円、近未来の我が国が孕むこの大きな社会問題に産学官民がこぞって向き合わなければならない時期にきていると思います。我々の腸管モデルが、この問題解消の一助となるよう、今後も関係各位の皆様とご一緒にさらに研究を進めていきたいです。(了)
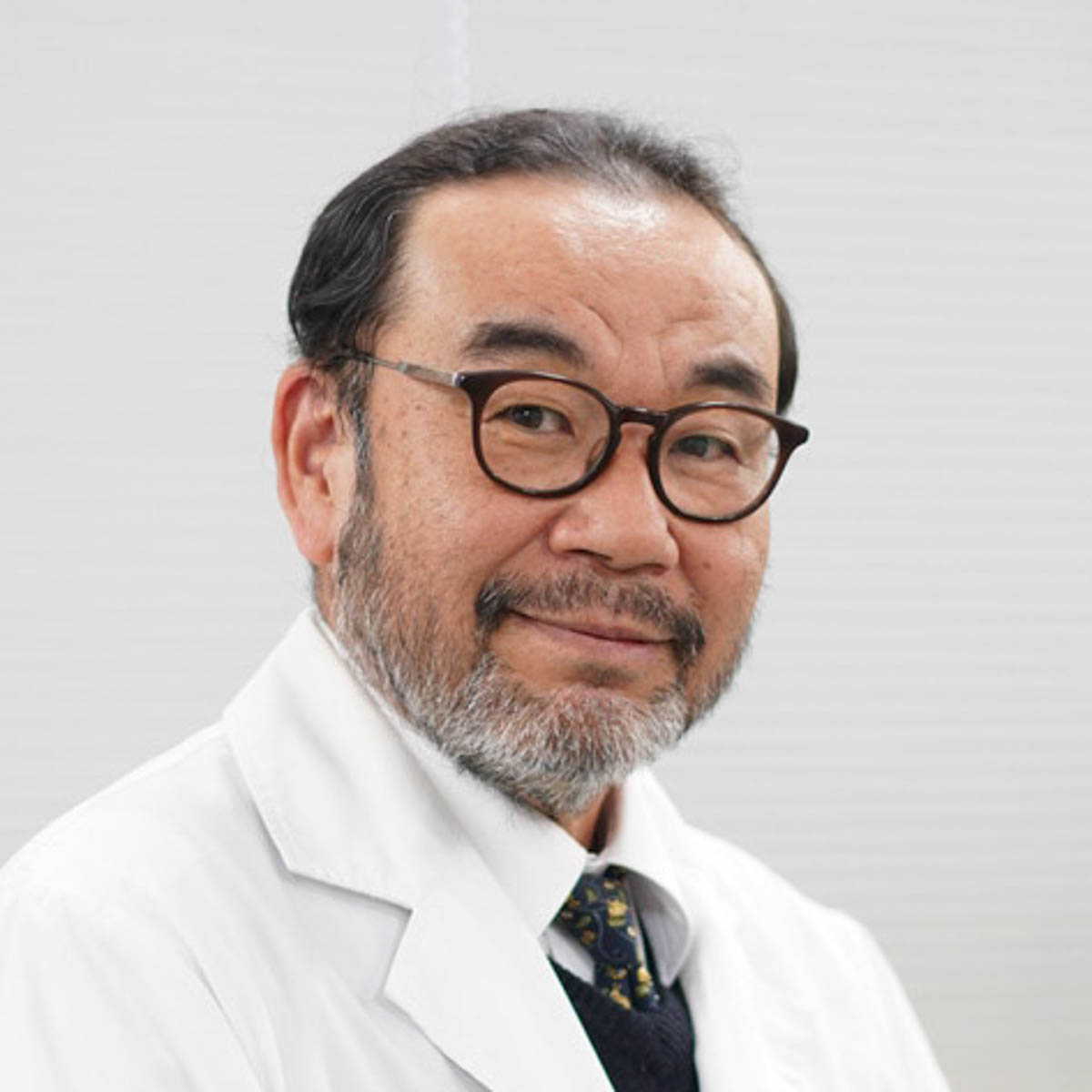
大澤 朗
おおさわ・ろう
神戸大学食の安全安心科学センター・センター長。
1979年、北海道大学獣医学部卒業後、豪留学。1986年にクイーズランド州立大学大学院博士課程修了後、1986年にクイーンズランド州立大学研究員に着任。1988年、ローンパインコアラ保護園主任研究員となり、動物研究に従事。
帰国後、1993年から徳島大学医学部助手。1995年、神奈川県衛生研究所主任研究員を経て、1999年に神戸大学 大学院 自然科学研究科生命科学専攻応用生物講座・助教授に着任。
2005年により、同農学研究科資源生命科学専攻・教授となる。
2007年からは神戸大学自然科学系先端融合研究環重点研究チーム・教授も兼務、2008年から7年間、神戸大学医学研究科医科学専攻・教授(兼務)も務めた。
2009年より現職。
