人間の体で起こるさまざまな変化の要因を探るには、体を構成する分子や原子がどのように組み上がっているのかを明らかにしなければならない。そのうち核酸・タンパク質といった生体高分子からひとつの構成単位だけを選択的に認識し可視化するには「有機化学的手法」が有効である。
こうした、原子単位で物質を扱う有機化学の考え方を生物学・遺伝学の分野へ積極的に導入しているのが、東京大学先端科学技術研究センター 岡本晃充教授だ。今回は岡本教授に、研究アプローチの有効性や、研究室が独自に開発したDNA のメチル化を発見できる「ICON法」などについて話を伺った。
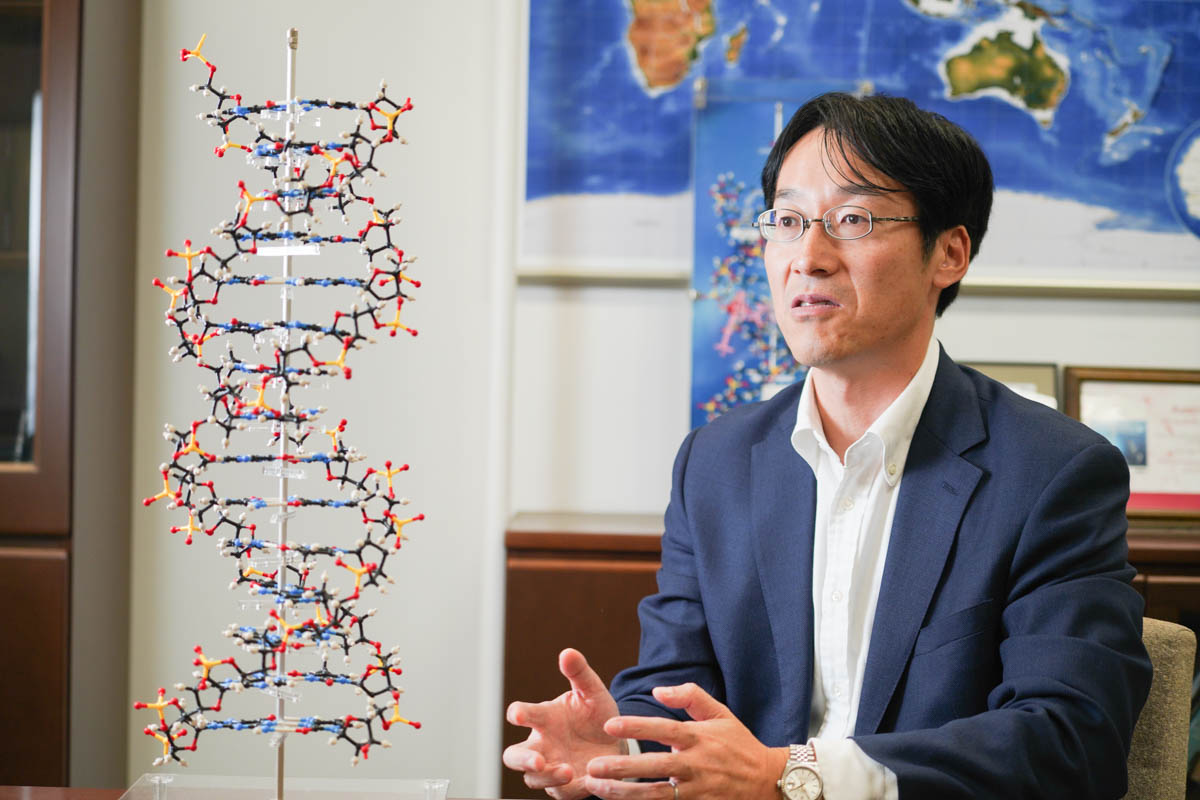
細胞を規定するメチル化に着目し、分子を観察
Q:まずは、研究のニーズについて教えてください。
まず研究の社会的ニーズからお話すると、病気の解明です。「私たちはなぜ病気になってしまうのか」、それを明らかにすることが社会的に求められています。健康で長生きしたいですよね。
現在は遺伝子を調べる際、遺伝子チップを使ってどこに病気の原因があるのかを調べることもできるようになってきました。その中で「多型」という部分に注目して、他の人とのDNAがどう違い、変異でどう変わったのかを調べることがあります。例えばDNA のひとつの「配列」が、グアニンからアデニンになる、などですね。
いっぽう、細胞の「働き」に変化が起きた場合、例えばタンパク質が作られなくなるということがあったりします。この、細胞の中のタンパク質が作られなくなるというところで、DNAの「メチル化」に注目する必要があります。
「メチル化」は、炭素原子1個と水素原子3個からできるCH3(メチル基)と呼ばれるもの(官能基)が分子に結合することです。
遺伝子情報が書き込まれた領域の直前の領域に、最初にタンパク質がくっついて遺伝子情報を読み出すためのさまざまな働きをおこなう部分があるのですが、そこでメチル化が起こると、その遺伝子が働かなくなってしまうのです。
例えば、現在ではIPS 細胞やES細胞などがあり、これらは多能性で様々な細胞になれる機能を持っていますが、そこにメチル化が付け足されていくことにより、細胞の機能が規定されていきます。様々なものになれる細胞が、これはできない、これはできないと繰り返していくことで、最終的に残った機能がその細胞の機能になるというわけです。
細胞の機能を規定することには、このメチル化が非常に重要になってくるのです。
ただし、細胞を守る遺伝子があるところでメチル化が起こってしまったりすると、細胞が本来の機能を失い、老化やがん化の原因になってしまいます。例えば、ピロリ菌は胃の表面の細胞に余分なメチル化を蓄積させることが知られていて、その結果胃の表面ががん化していくという仕組みがあります。
このように、メチル化を調べることが研究のひとつのターゲットになっています。
私たちはメチル基という、本当に小さい官能基が持つ、細胞の機能を変えてしまうという特徴に、すごく興味を持ちました。生物に取り込まれることによって遺伝子が機能しなくなったり、タンパク質が結合できなくなったりするのですから。
以上お話ししてきたように、メチル化を調べることは、すごく社会的ニーズ、病気の原因を調べる部分において重要です。
例えば、がん患者の血液の中には細胞から漏れ出した短いDNAが流れています。メチル化はガンのきっかけでもありますから、予め血液検査でDNAの状態を調べておくことで、がんになる可能性をある程度調べられるのではないかと考えています。
そしてもう一つ、人間そのものについても興味があります。メチル基以外にもアセチル基やリン酸基など様々な官能基が生体分子にくっついて細胞の働きに影響します。これらの官能基や原子、そして分子がどのように並ぶと私たち人間ができあがるのかにも興味があります。
遺伝情報を保持して次世代に伝える分子としてDNAがなぜ使われるのか。DNAがあんなに難しい構造をしているのはどうしてなのかということもそうですね。もっと簡単な構造でもいいはずなのに、難しい構造をしているのはなぜなのか。なるべくしてこの構造になったのか、こうしたことに興味がありますね。
Q:研究室の特長である、「有機化学手法アプローチ」とはどういったことでしょうか。
生体分子に付加したメチル基だとかリン酸基などは、バイオロジーの手法で、「酵素」や「抗体」を使って調べることもあります。しかし、解析の標的になるのが、水酸基、メチル基のような小さな官能基だった場合、バイオロジー的手法よりも、有機化学手法アプローチのほうがいい、といえます。
ターゲットに「特異的に、狙って」化学反応させることができれば、最終的には医学的な検査にも使えますし、一回の検査のコストも下げられるでしょう。
ひとつの生体分子の中にいくつも標的の官能基があったとしても、生体分子の立体構造の中の位置によって反応しやすい・反応しにくいの差が現れます。化学反応を使うことで、生体分子の構造と機能の様々な調べ方が出てくるのではないかと考えています。
私はもともと化学の出身なので、生体分子の検出に役立つ化学反応を創り出せたらいいかなと思っています。
さて、従来の有機反応化学は有機溶媒中、つまり油の中で反応させたり油に溶けるものをつくることが多い面がありました。しかし、DNA やタンパク質などの細胞をつくり出す物質は、大体水の中にいるものです。油と水は混ざりません。
そのため、水の中で使えるような化学反応を開発すれば、その反応を使って生体分子を調べたり人工的に新たな機能を持たせた「スーパー」生体分子を創ることも可能になってくると思います。そうすることで、本来の生命分子の機能を明らかにできるのではないか、と思っています。 
特定の核酸・タンパク質に結合して光る蛍光色素を開発
Q:実際の研究手法はどのようになっていますか。
調べることに着目する際には、「反応」を使った方法があり、付加反応や酸化反応など様々なものがあります。抗がん剤なども実際に生体分子と「反応」して働くわけですから、そういった部分も含めて反応です。
もうひとつ「見えるようにする」こともすごく大事です。視覚的に情報を入手する方法、つまり目で見て判断できるようにすることです。
ここで重要なのが、すべてを光らせるのではなく、目的の生体分子であるDNA配列やタンパク質構造などが、ある時にだけ光ってそうでない時は光らないという仕組みです。
そこで私たちが開発したのが、目的の核酸やタンパク質に結合した時にだけ光る蛍光色素です。その色素を核酸やタンパク質を認識する分子、つまり標的があることを認識してくっつくことができる分子に取りつけることによって、光るようにするわけです。
従来は、くっついていない状態でも常に光っていて、最初から背景が光っている蛍光を引き算して、どこが光っているのかを見るといった感じでした。
しかし、私たちが開発した蛍光色素の場合は、目的の生体分子がいないと光らないので、望むものだけを見ることができます。細胞中やひとつの個体の中など、圧倒的な量の他の生体分子が同時に存在していても、洗って綺麗にする必要もなく、見たいものだけを光らせることができるわけです。
私たちは、この手法のために開発した人工の核酸を「ECHOプローブ」と名付けました。細胞の中の核酸を簡単に見る方法がなく、私たちが考案したものです。この人工核酸は、細胞を活かしたままでその細胞の中の核酸の働きを観察することができます。
先ほどのメチル化の話に戻せば、私たちは、特定のDNA配列がメチル化しているときにだけ結合する人工核酸を用いた「ICON法」を開発しました。この方法は、水の中で使える化学反応を、蛍光でラベルした人工核酸と組み合わせています。この方法を使って、細胞の中のメチル化の状態を観察できるようになりました。
私たちは、光化学的なアプローチや最新の有機合成化学的なアプローチ、そして核酸やタンパク質をつくったり調べたりするアプローチなどをミックスして、これまで見ることができなかった標的のタンパク質や核酸配列が見えるようになればいいなと思っています。
ある遺伝子とある遺伝子がクロストークをしながら発現するため、細胞の中でのそれぞれのゲノムの位置関係がどうなっているかわかっていません。そしてそれらがどのようなタイミングでどう働くのかなど、まだまだわからないところばかりです。
そういった細胞の中のゲノムの構造や相互関係を解明するのに、ICON法やECHOプローブは非常に大事なツールになってくるのではないかなと思います。
さまざまな疾病関連遺伝子がありますが、それぞれに対して、幸いなことに、私たちの方法なら配列を変えたりするぐらいの程度のことを除けば、ICON法やECHOプローブの方法は共通して使うことができます。応用を可能にし、誰でも使える手法にしていきたいですね。
実際、すでに市販もされていますので、先生方と共同研究をしながら、様々な発見に行き着けばいいなと思います。ひとつひとつの病態で特徴がありますので、それに合わせたプローブをつくっていくことができたらいいですね。
Q:研究における課題として感じていらっしゃることはありますか?
標的になる生体分子は、様々な個性を持っているといえます。それぞれの個性に対して、産業的な課題で見た場合には、現在の方法は非常に共通性がありますし、たくさんの人に使ってもらうことでコストは下がっていくと思います。いわば、「量」の問題ですね。この量の問題をクリアしていきたいです。
私たちの領域でホットトピックになっている核酸医薬やタンパク質創薬などには様々な種類がありますが、薬にする時は量をたくさん製造する必要があるわけです。動物実験なども含めてかなりの量を消費しますので、その中で大量にDNAをつくったり、大量にタンパク質をつくる方法が大事になってきます。
同様に、私たちの分子も大量にコンスタントにつくることが大事になってくるため、ここに乗り越えなければいけない課題がありますね。
Q:企業との共同研究はどういった体制でおこなっているのでしょうか。
現在、当研究室は、数多くの企業と共同研究をしています。
あるお薬を処方するために、それぞれの人にあったお薬を処方する「個別化医療」があります。例えばある薬を与える前に「副作用が強く出るから、この人にはやめましょう」とか、逆に「この人にお薬を出しても効かないからやめましょう」といった情報にもとづいて医療方針を立てることです。
この個別化医療においては、前もってある程度遺伝子検査をしておいて、その結果によって薬を決めていくことも含まれます。そこで有効なのが、私たちの方法であるプローブによってあらかじめその人の血液を調べ、薬を決めるための判断材料にしておくことです。
これが今後発展していけば、普段の健康診断などでも今よりももっとたくさんのことがわかるようになるわけです。この方法もこれから発展していけばいいなと思っています。
Q:研究室にはどんな学生が多いのでしょうか。
先端科学技術センター(先端研)というのは、東京大学の研究所で、ここは大学院生が中心です。
この研究センターでは様々な研究分野の人たちが混ざり合って研究するような組織です。その意味で学生にとっては、非常にいい勉強になるのかなと思います。デバイスをやっている先生もいれば、ゲノムサイエンスやナノサイエンス、環境科学をやっている先生もいます。活発な共同研究をしています。
また、私は化学生命工学専攻というところにも所属していまして、この専攻の方は学部から学生が入っています。現在、先端研と化学生命工学専攻から学生は30人ほどいます。そのうち4年生は7人ほどです。みな大学院には進学しますが、最終的に博士までいってもらえればまとまった研究ができると思います。
進学してくる学生は、化学をやりたいと思ってくる人が多い気がします。あとは化学だけではなく、それらを使った生物学をやってみたいという子も多いですね。
生物学だけであれば、専門の学科がありますし、化学なら化学だけの学科があったりします。ここは化学生命工学専攻ということで、もちろん化学もやりますが、その中で化学の出口として生命の神秘にアプローチできる、そうしたケミストリーをやっていこうという人たちが集まるところです。
そのため学生にとって、フットワークが軽いことは大事かもしれませんね。確かに化学だけ、生物だけだったら研究室にこもって実験を完成させることができるかもしれませんが、一つの研究室でできることにはある程度限りがあります。
一つの研究室で閉じこもってしまうのではなくて、例えばゲノムサイエンスをやっている先生や医師、脳の研究をおこなう研究者など様々な人とコンタクトをとって、研究を大きく広げていくのは大事なことです。それも含めてフットワークの軽い人は向いているといえるかもしれませんね。
また、ひとつのことを深く掘り下げて研究を進めている専門家のひとたちから課題を聞き出す力も大事ですね。そのような先生方と仲良くして、彼らが持っている様々な課題を勉強して、それらに対して分子をつくっていこうというのはありますね。
フットワークを軽く色々な情報を手に入れて、そこから分子をデザインして、つくり出す。そして共同研究を通じて、前人未到の成果を上げていくことがすごく大事だと思います。
研究の面でいえば、学生には基本的な技術と研究背景をしっかり勉強してもらって、きちんと使えるようになってから社会に出てもらっています。昨今は企業とのオープンイノベーションがかなり活発になってきているため、企業には様々なニーズを言っていただけており、その中で私たちができることを選びながら、新しい分子づくりを学生と一緒にやっていければいいなと思います。(了)

岡本 晃充
おかもと・あきみつ
東京大学先端科学技術研究センター教授。
1993年、京都大学工学部合成化学科卒業後、1995年に京都大学大学院工学研究科合成・生物化学専攻修士課程修了。1998年に同博士後期課程を修了後、米国マサチューセッツ工科大学化学科博士研究員に従事。1999年より、京都大学大学院工学研究科合成・生物化学専攻助手を経たのち、2006年から理化学研究所 基幹研究所 岡本独立主幹研究ユニット 独立主幹研究員としてユニットリーダーに就任。2011年には同研究所 岡本核酸化学研究室 准主任研究員となる。
2012年1月より東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻 教授となったのち、同年4月からは現職。
