がん細胞は、遺伝子変異の蓄積によって生じるだけの存在ではない。周囲の栄養環境や細胞間の相互作用に応じて代謝を変化させ、その振る舞いを動的に変えていく細胞システムでもある。東京大学 先端科学技術研究センター ニュートリオミクス・腫瘍学分野の大澤 毅准教授は、がんの「代謝」と「栄養」に着目し、ゲノム変異や遺伝子発現、代謝物といった複数階層の生体情報を統合的に解析することで、がんの悪性化を支える基盤的な仕組みの解明に取り組んでいる。本記事では、がんを「栄養と代謝」という視点から捉え直す意義と、ニュートリオミクスという研究アプローチ、そしてその先に見据える最新の挑戦について話を伺った。
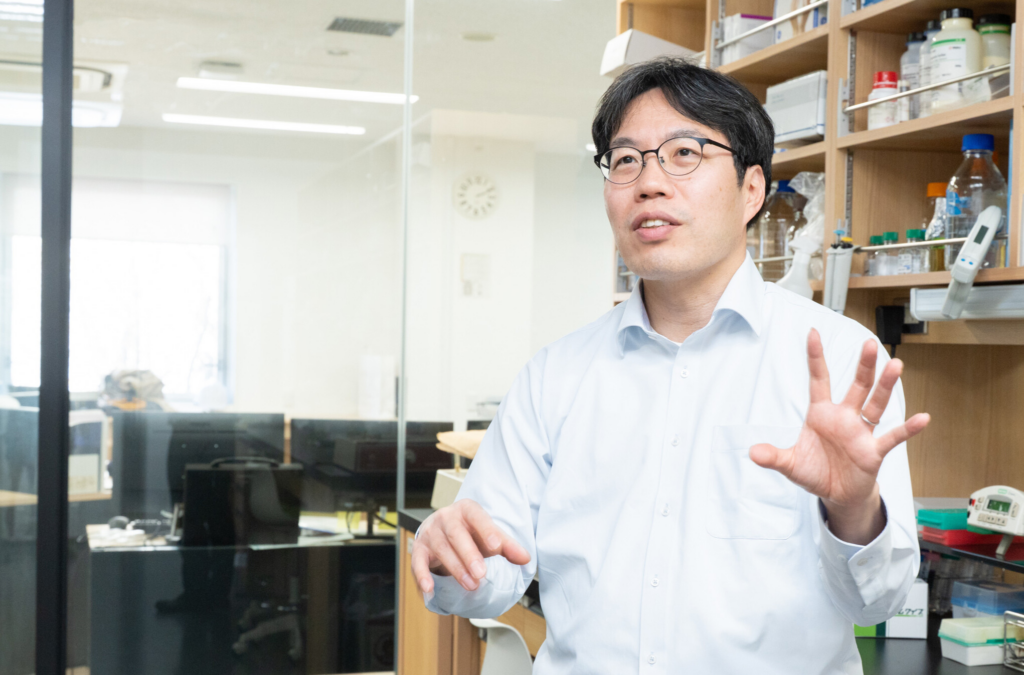
代謝を軸に、オミクスを統合してがん細胞を立体的に理解する
Q:研究概要について教えてください。
私たちの研究室では、がんの「代謝」と「栄養」に注目し、がんがどのように悪性化していくのか、分子レベルでの仕組みを明らかにしようとしています。代謝とは、食事などから取り込んだ栄養素をエネルギーや細胞の材料へと変換し、生命活動を維持するための一連の生化学反応の集まりです。細胞は環境の変化に応じて代謝の流れを調整しながら、生き延びています。
これまでのがん研究では、「がんは遺伝子変異が蓄積することで進行する疾患である」という見方が主流でした。確かに遺伝子の異常はがんの発生や進展に深く関わっていますが、それだけでは説明できない現象も数多く存在します。がん細胞は、利用できる栄養や周囲の環境に応じて、生き方そのものを柔軟に変える能力を持っているのです。こうした性質に着目すると、がんは単なる遺伝子の異常の集積だけでなく、「環境に適応し続ける細胞システム」として捉える必要があります。
その代表例が、がん細胞の代謝の特徴です。がん細胞は糖を大量に消費する性質を持ち、これは100年以上前にワールブルグ博士によって報告され、現在もPET検査などの診断技術に応用されています。しかし、がん細胞は糖だけに依存しているわけではありません。糖が枯渇すると脂質代謝へ、さらに栄養が乏しい環境ではアミノ酸代謝へと切り替えながら生存と増殖を続けます。このような多重的な代謝適応が、がんの悪性化や治療抵抗性の背景にあると考えられています。
かつては、代謝研究は「すでに解明された古い分野」と見なされることもありました。しかし近年、質量分析技術の進歩により、細胞や組織に存在する代謝物を網羅的に測定できるようになったことで再び注目を集めています。代謝物は食事や環境の影響を強く受けるため変動が大きい反面、「今、この細胞で何が起きているか」を直接反映する指標でもあります。さらに、遺伝子やタンパク質の働きの結果として生じます。遺伝子配列そのものが短時間で変化することはありませんが、代謝は刻々と変化します。だからこそ、代謝物を調べることで、細胞の状態や置かれている環境をより直接的に理解することができます。血糖値測定や尿検査が医療現場で広く用いられているのも、そのためです。
私たちは、この代謝の特性を研究の軸に据え、遺伝子、タンパク質、そして代謝物といった生体情報を統合的に解析する「ニュートリオミクス」というアプローチを取っています。ここでいう「オミクス」とは、体の中の情報を一部だけ切り取るのではなく、できるだけ網羅的に集めて全体像を捉えようとする考え方です。遺伝子やタンパク質だけを見るのではなく、その結果として現れる代謝の状態まで含めて捉えることで、がんという疾患をより立体的に理解しようとしています。
また、がん細胞単独ではなく、臓器間の代謝の連関や周囲の正常細胞、免疫細胞との栄養のやり取りにも注目しています。近年、一細胞レベルで遺伝子発現を解析できるようになり、細胞ごとの違いが詳しく分かるようになってきました。一方で、代謝を一細胞レベルで捉えることはまだ簡単ではありませんが、そこにも挑戦しています。
例えば膵臓がんでは、がん細胞そのものだけでなく、周囲に存在する正常細胞が病気の進行に深く関わっていることが分かってきました。一細胞解析の結果、膵臓がんの組織の中には、がん細胞のほかに線維芽細胞と呼ばれる正常細胞や免疫細胞が多く含まれており、これらの細胞ががん細胞にアミノ酸などの栄養を供給している可能性が示されています。膵臓がん細胞だけをマウスに移植した場合には腫瘍はあまり大きくなりませんが、がん細胞に加えて正常な線維芽細胞を一緒に移植すると、腫瘍が著しく大きくなることが確認されています。これは、がん細胞が自分だけで増殖しているのではなく、周囲の細胞から栄養や代謝の助けを受けながら成長していることを示しています。
このように、がんの進行は、がん細胞単独の性質だけで決まるものではありません。正常細胞や免疫細胞を含む「周囲の環境」との代謝的なつながり、つまり細胞同士の栄養のやり取りが、がんの悪性化を支える重要な要素になっています。私たちは、こうした細胞間の代謝の連関を一つ一つ明らかにすることで、新たな治療の糸口を見いだそうとしています。
Q:代謝を軸とした研究は、実際にはどのようなアプローチで進めているのでしょうか?
私たちは、「がん細胞の中や周囲で、実際に何が起きているのか」をできるだけ細かいレベルで捉えることを重視して研究を進めています。そのために、細胞全体を平均的に見るのではなく、代謝を一細胞レベルで捉える解析に取り組んでいます。技術的なハードルは高いものの、さらに細胞内の構造にまで踏み込んだ解析にも挑戦しています。
がん組織は、がん細胞だけでできているわけではなく、正常細胞や免疫細胞など、さまざまな細胞が混ざり合っています。そこで、それぞれの細胞がどのような状態にあり、どんな役割を担っているのかを、一つ一つの細胞ごとに詳しく調べています。
次に、細胞内の「オルガネラ」と呼ばれる小さな構造に注目しています。特に私たちは、非必須アミノ酸であるグルタミンに着目しています。通常の培養液には多くの栄養素が含まれているため、特定の栄養素の働きを切り分けて調べることは簡単ではありません。そこで、特定のアミノ酸や鉄、ビタミンを一つだけ抜いた「独自の培地」を作り、その条件下で細胞がどのように変化するかを解析しています。
こうした実験から、栄養が乏しくなると、がん細胞ではゴルジ体と呼ばれる細胞内構造が崩壊する現象が起きることを見出しました。ゴルジ体は、細胞内で合成されたタンパク質や脂質を加工し、それぞれの行き先に応じて振り分ける機能をもつ細胞小器官です。その働きから、細胞内の物流拠点にたとえられることもあります。通常は細胞核の近くにまとまって存在していますが、アミノ酸が不足した条件では、がん細胞に特異的にこの構造が分散していくことが分かりました。
そこで、どの栄養素がこの変化を引き起こしているのかを調べるため、アミノ酸を1種類ずつ加え直す実験を行ったのです。その結果、グルタミンを加えた場合にだけ、崩壊していたゴルジ体が再び元の形に戻ることが明らかになりました。興味深いのは、グルタミンが代謝されて生じるグルタミン酸や他の代謝物を加えても、この現象は回復しなかった点です。
この結果は、がん細胞がグルタミンを単なるエネルギー源として利用しているのではなく、グルタミンそのものを「シグナル」として感知している可能性を示唆しています。つまり、細胞内の配送システムであるゴルジ体の構造が、特定の栄養素の有無に応じて制御されている可能性があるということです。現時点では仮説の段階ではありますが、がん細胞特有の代謝適応を理解するうえで重要な手がかりになると考えています。
そこで現在は、この「グルタミンを感知する仕組み」を分子レベルで確かめるために、グルタミンの近くに集まるタンパク質を網羅的に調べる研究を進めています。その際に用いているのが「TurboID」と呼ばれる特殊な標識技術です。
この方法では、グルタミンやそのごく近くに存在したタンパク質に目印を付けることができます。例えるなら、グルタミンの周囲に「見えないインク」をばらまき、近くにいたタンパク質だけに印を残すような仕組みです。あとからその印を手がかりに解析することで、「グルタミンのそばに集まってくるタンパク質」を一つずつ洗い出すことができます。
実際にこの手法を使うと、グルタミンの近傍には多くのタンパク質が集まってくることが分かってきました。現在は、その中から「本当にグルタミン特異的に関わっているタンパク質はどれなのか」「他のアミノ酸では同じ現象が起きないのはなぜか」といった点を、比較実験を通じて丁寧に検証しています。
このように、単に栄養を与えて細胞の反応を見るだけでなく、「どの分子が、どこで、どの栄養を感知しているのか」を分子レベルで捉えようとしている点が、私たちの研究の特徴です。
近年は、ゴルジ体にとどまらず、ミトコンドリアにも栄養状態に応じた大きな変化が起きていることが明らかになりつつあります。ミトコンドリアは、細胞内でエネルギーを生み出す重要な細胞小器官で、通常は細長いひも状の構造を取り、細胞内にネットワークのように広がっています。
ところが、栄養が不足した状態、いわゆる栄養飢餓条件になると、がん細胞のミトコンドリアはこのひも状構造を保てなくなり、短く分断された状態へと変化することが分かりました。興味深いことに、この状態にグルタミンを添加すると、再びミトコンドリア同士がつながり、元の構造へと回復します。
ミトコンドリアが「切れる」「つながる」といった形態変化を起こすこと自体は知られていましたが、どの代謝物がその制御に関わっているのかについては、長らく解明されていませんでした。ミトコンドリアの分断に関する研究は近年報告され始めたばかりであり、特に「融合」を制御する仕組みについては、ほとんど手つかずの状態でした。
そこで私たちは、ミトコンドリアが融合した瞬間にだけ蛍光を発するように設計した実験系を用い、どの代謝物がミトコンドリアの構造変化を引き起こしているのかを詳細に解析しました。その結果、ある状態の代謝物が存在するとミトコンドリアは分断され、そこから別の状態へと変換されると、今度はミトコンドリアが再び融合することを見いだしました。現在、この代謝物については詳細な解析を進めており、海外の研究機関とも連携しながら成果の発表を準備しています。
重要なのは、この代謝物がミトコンドリアの膜上に直接存在するのではなく、ゴルジ体など他の細胞内構造から供給されている可能性が見えてきた点です。先に見つかったゴルジ体の崩壊現象と、ミトコンドリアの形態変化が連動しているとすれば、栄養状態の変化が細胞内の輸送系を介して、ミトコンドリアの構造や機能を制御している可能性が考えられます。
さらに私たちは、このミトコンドリアの形の変化が、がんの性質そのものにどのような意味を持つのかを検討しています。一般には、ミトコンドリアが分断されるとエネルギー産生が低下すると考えられがちですが、がん細胞では必ずしもそうではありません。実際には、分断されたミトコンドリアを持つ細胞ほど、細胞の極性が変化し、移動しやすくなる兆候が見られています。
細胞が周囲へ浸潤したり、転移したりする際には、細胞の前後方向、いわゆる極性が重要になります。その過程で、分断されたミトコンドリアが細胞の後方に集まり、細胞の運動性を高めている可能性が示唆されています。このことから、ミトコンドリアの形態変化そのものが、がんの浸潤や転移、さらには悪性化と相関している可能性があると考えています。
最近ではさらに、ミトコンドリアが細胞の外へ出て、別の細胞へと移動する現象にも注目しています。がん細胞のミトコンドリアには変異が多く含まれていることが知られていますが、それが正常細胞、特に免疫細胞へと取り込まれるケースが報告されています。実際に、がん細胞のミトコンドリアを赤色、正常細胞のミトコンドリアを緑色に染めて共培養すると、時間とともに正常細胞の中に赤いミトコンドリアが現れる様子が観察されます。ミトコンドリアはもともと細菌由来の細胞小器官であり、細胞の外へ出る性質を持っていると考えられています。こうしたミトコンドリアの移動や伝播が、免疫細胞の働きや腫瘍環境にどのような影響を与えているのかについても、近年注目が集まっており、実際にNature 誌でも報告されています。
Q: いま取り組んでいる研究における独自性を教えてください。
研究における独自性は、先ほども触れたように、がんを「代謝」を軸にして全体像として捉え直している点にあります。従来の研究では、遺伝子変異や遺伝子の働き方、タンパク質の量といった個々の情報を詳しく調べることが主流でしたが、私たちはそれらを切り分けて見るのではなく、代謝の変化と結びつけて理解しようとしています。
がん細胞は、環境に応じて糖、脂質、アミノ酸といった栄養源への依存を柔軟に切り替えながら生き延びています。このような段階的な代謝の切り替えは、単一の遺伝子や経路に注目するだけでは十分に説明できません。代謝を起点に全体の流れとして捉えることで、がんの適応戦略そのものが見えてくると考えています。
そこで代謝を研究の軸に据えながら、遺伝子やタンパク質に関する情報も統合的に解析する「ニュートリオミクス」というアプローチを採用しています。代謝を起点に生命現象を再構成することで、がんや生活習慣病といった複雑な疾患の本質に迫ることが、私たちの研究の大きな特徴です。
AIと創薬の連携により、代謝研究の成果を社会へ広げる
Q:研究の課題は、どのような点にあるとお考えですか?
研究上の大きな課題は、大きく2つあると考えています。
1つ目は、生体内代謝の複雑さそのものです。現在、代謝を標的とした薬がなかなか実用化されていない背景には、単一の経路を止めても、別の経路に迂回してしまう「バイパス現象」があります。いわば、一つの道を塞いでも、細胞は別の道を選んで生き延びてしまう。さらに、がんなどの疾患において、どの代謝経路がどの程度特異的に機能しているのか、そのメカニズムはまだ十分に解明されていません。こうした点を一つひとつ丁寧に明らかにしていくことが、研究としての大きな課題です。
一方で、私たちが取り組んでいる研究は、一つの物質が複数の代謝経路に関与する仕組みに着目しており、単一標的の限界を超えて、マルチプルに効果を発揮できる可能性があります。このアプローチは、これまでの課題を乗り越え得る方法だと考えています。
2つ目は、研究成果を創薬として社会に届けるまでのプロセスに関する課題です。特に、日本とアメリカでは創薬の事業化フェーズにおける環境に大きな違いがあります。アメリカでは、フェーズ1に進んだ段階で一定の評価水準が共有され、ベンチャーや投資が入りやすい仕組みがありますが、日本では評価の基準が明確ではなく、結果として事業化が進みにくいケースも少なくありません。
研究の成果をどのように実用化へとつなげていくのか。この点についても、研究と並行して考えていく必要があると感じています。
Q:この分野を目指そうとしている学生にメッセージはありますか?
研究の世界に興味をもっている学生の皆さんに、まず伝えたいのは、研究には「正解」が用意されていないということです。学校の勉強や受験では、答えが一つに決まった問題を解くことが求められますが、研究はそうではありません。そもそも、何が問いなのかすら、まだ分かっていないところから始まります。
私自身、高校を卒業してイギリスのロンドン大学に留学した当初は、英語も十分に話せず、勉強が特別できたわけでもありませんでした。それでも、大学在学中に出会った先生方はとても寛容で、授業が分からなければ時間を取って一対一で教えてくれました。その姿を見て、「こんな大学の先生になりたい」と思ったことが、研究者を志す原点になっています。
なかでも強く心に残っているのが、Sir Tim Hunt(サー・ティム・ハント)教授との出会いです。ハント教授は、細胞周期を制御する分子であるサイクリンを発見し、2001年にノーベル医学・生理学賞を受賞した研究者で、私がロンドン大学に在学していた際に指導を受けました。
博士課程の研究についてメールを書いたところ、「ぜひ会いに来なさい」と言ってくださり、初めて研究室を訪ねたときのことです。開口一番、「君はなぜここに来たんだ」と聞かれ、“NOBODY KNOWS THE ANSWER”と書かれた一枚の紙を渡されました。そこに書かれていたのは、「どれだけ偉くなっても、自分の問いに対する答えを知っている人はいない。だからこそ、自分で考えるしかない」という内容でした。
ハント教授は、「君の質問に対する答えは、僕にも分からない。でも、ここに来て一緒に議論することはいつでもできる」と言ってくれました。その後も、月に一度ほど食事をしながら、研究の話だけでなく、研究者としてどう考えるべきか、科学の将来はどうなるのか、といったことを語り合う時間を持ってくれました。
研究の世界では、技術は驚くほどの速さで進歩しています。私が学生の頃、何日もかけて行っていたDNA配列解析は、今では数百円で一晩あれば終わってしまいます。だからこそ、今ある技術に振り回されすぎないことが大切です。技術は手段であって、目的ではありません。
それよりも大事なのは、「なぜだろう」「面白いな」「もっと知りたい」という感覚です。どんなに突飛に見える仮説でも構いません。自分が本当に興味をもった問いを大切にし、早いうちから実験や研究に触れてみてほしいと思います。実際、私たちの研究室では中学生や高校生を受け入れ、一緒に実験を行う取り組みも行っています。研究とは、分からないことに向き合い続ける営みです。そして、その「分からなさ」そのものを楽しめる人にとって、これほど面白い世界はありません。ぜひ、自分の好奇心を信じて、一歩踏み出してみてください。
Q:今後の展望をお聞かせください。
今後の展望として、私たちは大きく2つの方向性を考えています。1つ目は、「AIを活用した次世代メタボロミクスの展開」です。これまでのメタボロミクス研究では、あらかじめ決めた代謝物だけを測定する「ターゲット解析」が主流でした。一方で私たちは、数千種類におよぶ代謝物を一括で捉えるノンターゲット・メタボロミクスにAI解析を組み合わせることで、疾患や個人ごとの代謝の違いを、より精密に読み解こうとしています。
従来、がんの遺伝子変異と代謝との間には明確な相関はないと考えられてきました。しかし近年の共同研究から、遺伝子変異が一つ、二つと段階的に蓄積していくにつれて、代謝プロファイルも徐々に変化していくことが明らかになりつつあります。代謝は検体の取り扱い条件に強く影響を受けるため、手術後速やかに低温保存するなど、代謝解析に適したプロトコルの整備が不可欠です。その上で得られたデータをAI解析にかけることで、がん種や遺伝子変異、さらには患者さん個々に固有の代謝プロファイルを捉えられるようになると考えています。
もう1つの柱は、「代謝を標的とした新しい制御法の開発」です。
PET検査に使われているように、がん細胞は特定の代謝物を選択的に取り込む性質をもっています。実際、フッ素化した糖が腫瘍に集積することからも分かるように、がん種ごとに特異的に必要とされる代謝物が存在します。私たちはこの性質に着目し、がん細胞が「必要として取り込んでしまう代謝物そのもの」を治療に利用できないかと考えています。
具体的には、アミノ酸などの代謝物に化学修飾を施し、がん細胞に取り込まれやすい「アナログ分子」を作製しています。例えばグルタミンに化学修飾を加えると、がん細胞はそれを通常のグルタミンと誤認して取り込みます。しかし、この修飾された分子は本来の代謝反応を正しく進めることができず、結果として天然のグルタミンと競合し、代謝を阻害します。つまり、代謝物そのものを“基質型の阻害剤”として用いるという考え方です。
このアプローチの大きな特徴は、創薬プロセスを大幅に短縮できる点にあります。従来の低分子創薬では、数万から数百万種類の化合物をスクリーニングし、ようやく候補分子を見つける必要がありました。一方で代謝研究の分野では、どの代謝物がどの酵素によって変換され、どこに異常が生じているのかが、すでに相当程度解明されています。基質となる代謝物そのものが、最初から「リード化合物」になっているため、そこに数種類の化学修飾を加えて比較するだけで、有望な候補を短期間で絞り込むことが可能です。
現在、私たちは必須アミノ酸のアナログや、化学修飾したグルタミンなど、複数の代謝物アナログを作製し、ヒトへの投与前段階の検証を進めています。放射線ラベルを用いた実験では、これらの分子が腫瘍に集積し、腫瘍の増殖を抑制することも確認されつつあります。また、がんセンターとの共同研究を通じて患者さんの検体を解析し、どのがん種で、どの代謝物アナログが有効になり得るのかを、AIメタボロミクス解析と組み合わせて検討しています。こうした手法により、実験自体は数か月単位で進めることが可能であり、そこから安全性試験などを経て、数年以内にファースト・イン・ヒューマン試験へと進める可能性も見えてきました。
こうした取り組みの背景には、低分子創薬を新しい視点から発展させたいという考えがあります。基質となる代謝物そのものを出発点にした創薬は、従来とは異なる意味での「低分子回帰」と言えます。日本はもともと低分子創薬に強みを持つ国であり、代謝を軸にした創薬は、その強みを現代的な形で再び活かすことのできるアプローチだと考えています。
また、がんに限らず、将来的には個別化医療や他の疾患領域にも応用できる可能性があります。代謝研究はAIや化学、創薬と結びつくことで、新規モダリティーを生み出せる分野です。そして、代謝という視点から生命現象を捉え直し、基礎研究から創薬、事業化までを一続きの取り組みとして進めることで、実際に患者さんの治療につながる選択肢を増やしていく。その成果を、がん患者さんやそのご家族の笑顔につながる形で社会に届けていきたいと考えています。(了)

大澤 毅
(おおさわ・つよし)
東京大学 先端科学技術研究センター ニュートリオミクス・腫瘍学分野 准教授
2001年に英国ロンドン大学キングスカレッジ 医療生化学部卒業。1999年6月~8月、米国ハーバード大学物理学留学。2005年 英国ロンドン大学 医学部大学院腫瘍学専攻、博士課程修了、腫瘍学博士(2010年取得)。2006年 東京大学 医科学研究所 腫瘍抑制分野 研究員。2007年 東京大学医科学研究所 システム生命科学リサーチフェロー、東京医科歯科大学分子腫瘍医学分野 特任助教。2011年 東京大学 先端科学技術研究センターシステム生物医学分野 特任助教を経て、2018年 東京大学 先端科学技術研究センター ニュートリオミクス・腫瘍学分野 特任准教授。2023年より現職。
