体を構成する細胞は、設計図は皆同じのゲノムDNA配列であるにもかかわらず、発生・分化の過程で異なった組織を形成する。これはヌクレオソームを基本単位としたDNA折り畳み構造が細胞の運命を決定しているからである。東京科学大学 生命理工学院 野澤 佳世准教授は、1 mmの百万分の一の世界を可視化するクライオ電子顕微鏡技術を用いて、2種類のヒストンのみから構成されるヌクレオソーム様構造(H3-H4オクタソーム)を世界で初めて明らかにした。また、野澤准教授は、クライオ電子顕微鏡を活用した人工細胞核の可視化などにも取り組んでいる。本記事では、野澤准教授に具体的な研究内容とそこに至った背景について、詳しく伺った。
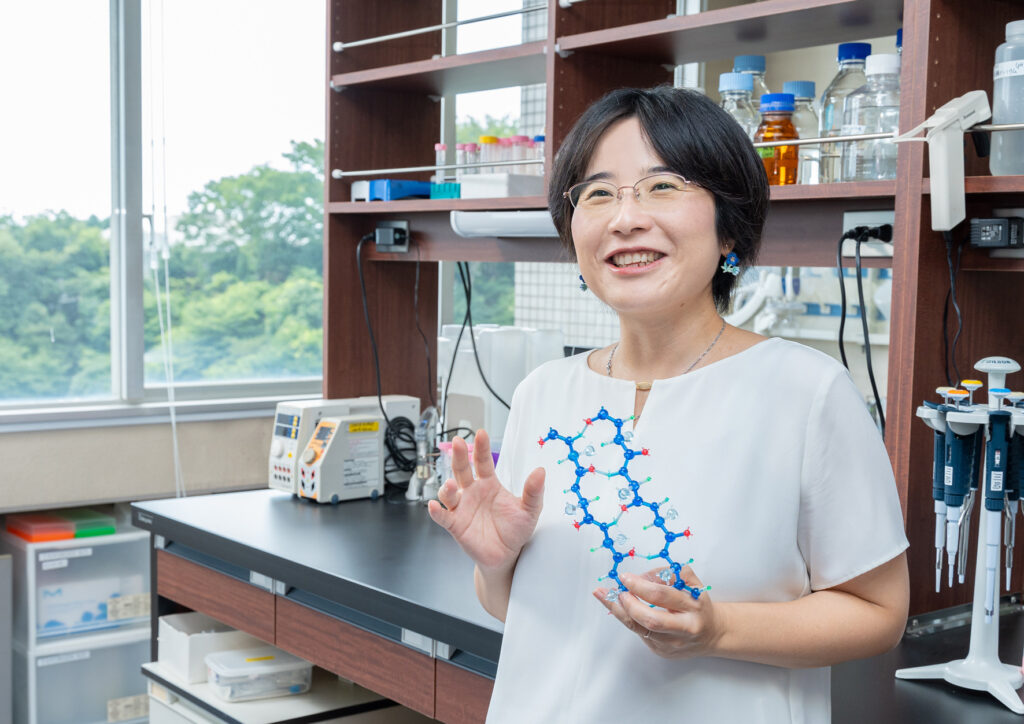
形からDNA折り畳み構造の機能を解明する
Q:研究概要を教えてください。
クライオ電子顕微鏡解析など原子の世界をのぞく技術を用いて、細胞の運命を決めるゲノムDNAの折り畳み構造を解明する研究を行っています。ヒトの身体は受精卵から発生・分化を経て、40兆個もの細胞からなる個体になります。水を除いた細胞の構成成分の約50〜70%はタンパク質であり、脳や腸、筋肉など異なる組織を構成するために、それぞれの細胞は異なるタンパク質群を取り揃えています。しかし、1つの受精卵の段階でも、40兆個の細胞からなる段階でも、生命の設計図であるゲノムDNAは同じものが使われています。
同じ設計図から異なるタンパク質群を作るために、細胞はDNAの作る立体構造を利用しています。2022年にヒトのゲノムDNA配列の全領域が完全解読されましたが、DNAの特定の部分をいつ、どのぐらいの量を読み取ってタンパク質を作るかを規定し、細胞の個性を生みだすDNAの立体構造については、まだまだ分からないことばかりです。
ヒトは、1 mmの1/100サイズの細胞核の中に2 mもの長さのゲノムDNAを収納するために、DNAをヒストンという樽状のタンパク質に高密度に巻きつけてゲノム折り畳み構造を作ります。この構造はクロマチンと呼ばれますが、実はこの状態のままだとタンパク質の設計図である遺伝子を読むことができません。巻きついた密な状態からゆるんだ状態になってはじめて、設計図を読むことができるのです。私たちの研究室では、2017年にノーベル化学賞を受賞したクライオ電子顕微鏡解析法などの「原子の世界をのぞく技術」を用いて、実際にゲノムの折り畳み構造を観察し、タンパク質の発現制御機構や疾患のメカニズムを解明しようとしています。
2022年には、クライオ電子顕微鏡解析を通じて新しいクロマチン構造基盤ユニットを発見しました。これまでクロマチンの基本単位であるヌクレオソームは均一な構造を持ち、その形成にはH2A、H2B、H3、H4の4種類のヒストンが必要でというのが常識でした。しかし私たちは、H3、H4の2種類のヒストンのみでも、ヌクレオソームに非常によく似た8量体の構造(H3-H4オクタソーム)が形成されることを、世界で初めて明らかにしました。
この研究に至った背景には、ヌクレオソームの「始まり」のメカニズムを知りたいというモチベーションがありました。先ほどお話したタンパク質の設計図が読み取られる「転写」や細胞分裂に伴ってゲノムのコピーが作られる「複製」のプロセスにおいて、ヌクレオソームの存在は障壁になります。そのため、細胞内ではヌクレオソームの破壊と再生が繰り返されており、このサイクルの異常は多くの組織のガン化に繋がります。
そこで私たちは、このヌクレオソームの「再生」過程を試験管内で再現する研究を行ってきました。従来のモデルでは、一度ヌクレオソームが破壊されて裸になったDNAは、まずH3、H4を2分子ずつ取り込んで4量体の足場を作り、その後にH2A、H2Bを2分子ずつ取り込むことで、ヌクレオソームに再生されると考えられていました。
しかし、実際にDNA とH3、H4を用いてこの足場構造を再現し、立体構造解析を行ってみると、H2A、H2Bが存在しなくても、安定な8量体構造が形成されていることが分かりました。ヌクレオソームの中間体を探す研究の過程で、偶然にも、教科書には記載されていない新しい構造体を見つけることができたのです。
H3-H4オクタソームの興味深いところは、ヌクレオソームと似た概形を持ちながら、クロマチンの構造変換を誘起する「アシディックパッチ構造」を持たない点です。クロマチンを凝集させて、ゲノム機能を抑制するメチル化酵素やクロマチンを緩ませて、転写や複製が起こりやすい環境を作るクロマチン・リモデリング因子の多くは、H2AとH2Bの分子表面に形成されるアシディックパッチを認識します。
こうしたDNA配列に依存しない、クロマチンの構造変換がもたらすゲノム機能の調節は「エピジェネティクス制御」と呼ばれています。しかし、私たちが発見したH2AとH2B を持たないH3-H4オクタソームについては、そのメカニズムが全く分かっていません。
従来のクロマチン研究では、ゲノムDNAをヌクレアーゼで消化した時に、150 bp程度のDNAが残る領域をヌクレオソームと定義していましたが、この方法ではH3-H4オクタソームを見分けることができません。私たちは、 H3-H4オクタソームには存在し、ヌクレオソームには見られない構造的特徴を出芽酵母内で検出することにも成功して、H3-H4オクタソームが生体内に存在することまで突き止めました。現在は、これまでヌクレオソームと思われていた画分のうち、何パーセントがH3-H4オクタソームなのか、ゲノムのどこに存在するのか、細胞周期のいつ機能するか、さらにヒトを含む高等真核生物の中にも存在するのか、といった疑問に答えるための研究を進めています。今後、H3-H4オクタソームを考慮に入れた解析が進めば、エピジェネティクス制御の異常がもたらす、ガン化や生活習慣病、精神疾患の理解についても新しいメカニズムが明らかになってくるかもしれません。
Q:研究における独自性はどんなところにあるでしょうか?
構造をベースに機能を理解したり、クライオ電子顕微鏡構造を活用して分子設計を行うところが独自性になると考えています。私たちは、 H3-H4オクタソーム以外にも、遺伝子のオン・オフを規定するDNAループの研究も行っています。これは、転写効率を著しく高めるエンハンサー配列と転写の開始点であるプロモーター配列がゲノム上で物理的に接触する現象です。特定のタンパク質を必要な時に発現させることで、細胞の個性を生み出す根幹を担っています。
ただ、DNAループは非常に難解であるため、研究があまり進んでいません。その理由は、DNAループを構成する因子が40種類以上もあるだけでなく、さらにそのループが多重化して、スーパーエンハンサーと呼ばれる巨大な複合体を形成するからです。最近では、がん組織の中でスーパーエンハンサーが形成され、遺伝子の異常な活性化を引き起こしていることも報告され、創薬ターゲットとしても注目を集めています。スーパーエンハンサーの内部では、DNAループ同士がクロストークを行うだけでなく、核酸やタンパク質の天然変性領域が会合して液-液相分離を起こし、非膜構造の中に転写反応を促進するリアクターが形成されることも知られています。近年発展してきているタンパク質の構造予測の技術を用いても、こうした超分子複合体が生み出す複雑で動的な生命現象を理解することは難しいのが現状です。
私たちは、これまでの研究でエンハンサーとプロモーターを橋渡しする転写メディエーターというタンパク質のうち、酵母の生存に必要最低限の15サブユニットを含む複合体を試験管内で再構成し、その構造解析に成功しています。このようにボトムアップ・アプローチでDNAループを組み立てて、創薬研究に必要な原子分解能の情報を獲得していく点も、私たちの研究の独自性の一つだと考えています。
Q:これら研究に至るまでの経緯や研究の醍醐味を教えてください。
私は学部生時代に、X線結晶構造解析で筋肉系タンパク質のトロポミオシンやアクチン、ミオシンなどの筋肉の滑り運動を研究していました。そこで分子構造の変化が、動的な身体の機能を生むきっかけになっていると知り、これは非常に面白いと感じました。
その後、東京大学の濡木先生の研究室に移ってからは核酸を対象に研究を行い、タンパク質の翻訳の理解に取り組みました。そこで、アミノ酸を運ぶtRNAによって、ペプチドからタンパク質が作られる瞬間を構造解析で観察するようになり、生物が作る不思議な構造に魅了されたのです。そこから細胞の起源をたどっていくと、設計図が書かれているDNAに行き着くと考えるようになり、生物が誕生する仕組みや構造を知りたいという思いから、DNAや遺伝子の研究に取り組むようになりました。
研究の一番の醍醐味は、生命機能の引き金となる「実際の構造を見られる瞬間」です。創薬や化合物の設計には構造情報が欠かせません。それに加えて自分で分子を設計し、編集や創出もできることが研究の魅力だと感じています。
特にクライオ電子顕微鏡解析は、氷包埋した分子の複数の溶液構造を一挙に解析できる手法です。得られたスナップショット構造群をつなぎ合わせることで、分子のダイナミクスや酵素反応を一連のムービーのように理解することができるパワフルなツールでもあります。凍結細胞のスライス切片に対して電子線トモグラフィー法を用いれば、細胞中の分子構造変化をとらえることも可能です。クライオ電子顕微鏡解析と構造予測ツール、MDシミュレーションを組み合わせることで、これまで以上に、よりリアルに近い状態で細胞環境の構造を見られるようになりました。
クライオ電子顕微鏡による人工細胞核解析に挑戦
Q:現在、取り組んでいるのには、どのような研究がありますか?
ユニークな研究テーマとしては、人工細胞核の開発があります。近年、ヘテロクロマチンやユークロマチンといったゲノムの立体構造に加え、ゲノムと核膜の相互作用も遺伝子発現を調節していることが分かってきました。実際、ゲノムの約30〜40%は核膜と結合することが知られており、この相互作用の破綻は、早老症や認知症、がガン、心筋症、脂肪代謝異常などの重篤な疾患を引き起こします。私たちは、核膜がどのようゲノムの形を変化させ、遺伝子を制御するのかを知りたいと考え、それを試験管の中で再現しようとしています。
人工細胞核の作成には、近年の合成生物学で注目されている人工細胞の技術を応用しています。例えば、この技術ではリポソームの中に無細胞合成系を封入することで、「光合成する細胞」や「自己分裂する細胞」のようなモデル細胞が作られ、大きな話題になっています。
私たちの研究でも、リポソームに核膜のような機能を持たせるために、ゲノムを核膜にアンカーさせる役割を持つタンパク質群を無細胞合成系で作り、そこに組み込んでいます。そしてクライオ電子顕微鏡を用いて、ゲノムがどのような形をとるのか、またその形の違いによって“タンパク質の設計図”である遺伝子がどれくらい読み出されやすくなるのか、という点を明らかにしようとしているところです。
これは非常にチャレンジングな研究で、ステップごとに試行錯誤を重ねながら進めていますが、ようやくリポソーム膜上にゲノムをアンカーするためのタンパク質を再構成するところまでこぎつけました。
実は、先ほどお話ししたDNAループは、核と細胞質をつなぐチャンネルである核膜孔複合体を介して、核膜ともつながっていることが分かってきています。活性化した遺伝子の周辺で形成されるDNAループが核膜孔複合体に結びつくことで、合成されたmRNAがスムーズに核膜孔を通り、細胞質のタンパク質合成装置へ届きやすくなる。そんな仕組みが働いている可能性があり、より効率よくタンパク質を作るための工夫なのではないかと考えられています。ただ、これはまだ“仮説”の段階で、実際の姿を直接見た人はいません。
細胞の中に近い状態でDNAループを理解するには、DNAループ単体ではなく、それが核膜とどのように連動しているのかまで見なければならない。そんな思いから、この研究をスタートしました。もちろん、細胞核をスライスして調べるという方法もありましたが、核の内部というのは細胞の中でも特に分子密度が高く、とても複雑です。遺伝子が活性化された領域をピンポイントで高分解能に可視化するのは、実は最も難しい部分でもあります。
そこで私たちは、ノイズのない環境で、遺伝子発現にDNAループと核膜がどう関わるのかを理解するには、人工細胞の中で“最小限のコンポーネントだけを組み立てて再現する”ことが、一番クリアに見えると考えました。時間も手間もかかるため取り組む研究者は多くありませんが、一からボトムアップ式で核を再現することにチャレンジしています。
実は、これまでクライオ電子顕微鏡で人工細胞内部のタンパク質を原子分解能で観察した例はありませんでした。現在、論文化しているところなのですが、私たちのラボでは、その観察法を新しく立ち上げることに成功しました。従来法で作られた人工細胞では、凍結の際に多くが破裂してしまったり、膜が多重化してノイズが入り込んだりして、クライオ電子顕微鏡での観察がほとんど不可能だったのです。
詳しい話はまだできませんが、観察を可能にするためには、クライオ電子顕微鏡観察に適したリポソーム膜の組成へ変更することや、タンパク質を効率よく包埋する方法の工夫、人工細胞のサイズ最適化など、いくつかポイントがあります。そうした改良を積み重ねた結果、人工細胞の中に存在するタンパク質の粒子を、非常にクリアに捉えられるようになりました。
Q:この研究における課題は何かありますか?
技術的な課題として、クライオ電子顕微鏡で人工細胞のような前例のないサンプルを安定して観察できる条件を整えるまでには、実際に数年を要しました。従来の精製タンパク質であれば観察方法が確立されており、共同利用施設を使えばスムーズに測定できます。しかし、誰も見たことのないサンプルでは、試料調製の条件を一から最適化しなければなりません。研究室にクライオ電子顕微鏡がない状況ではスクリーニングの機会も限られるため、試行錯誤の効率がどうしても低くなり、系の立ち上げに時間がかかってしまいます。また、クライオ電子顕微鏡の試料作製や運用に熟達した研究者が国内ではまだ多くないことも、研究推進の妨げになっています。
厚みのある細胞や組織の観察も、世界的に大きな技術的ハードルです。クライオ電子顕微鏡で観察するためには、電子線が透過できるおよそ300ナノメートル程度の薄さにまで試料を削る必要があります。細胞はそのままでは厚すぎるため、まず凍結した細胞を観察して適切な位置を確認しながら、集束イオンビームを用いて少しずつ削っていく作業が必要になります。この薄片化は非常に高度な技術を要し、習得にも長い時間がかかります。
日本でこの作業を一貫して行える施設や技術者は、現時点ではまだ限られています。一方、海外ではこうした手法を用いた細胞・組織の解析が、トップジャーナルでも多く発表されており、研究が急速に進んでいます。病理組織や特定の細胞を高分解能で観察したい場合には、この薄片化技術が欠かせませんが、日本ではまだ扱える研究者が十分ではないのが現状です。こうした理由から、クライオ電子顕微鏡とその関連技術は、いまだ新しく発展途上の分野であり、技術習得と普及が大きな課題になっています。
Q:この分野を目指したいと考えている学生にメッセージはありますか?
日本で求められる理系人材像は、海外とは少し違う部分があります。海外では博士課程までの教育で専門性を深め、独立して研究や論文執筆ができる力が重視されます。そのため、研究実績を持つ人材は、工学や創薬のような産業界でも高く評価され、高い待遇につながることも珍しくありません。
一方、日本では、学生自身が主体的に研究を進める経験を積めるのは、学部4年生や修士課程の限られた期間であることが多いのが実情です。この時期に手を抜かず、しっかり研究に向き合うことは、たとえ将来どのような職業に進んでも必ず役に立ちます。だからこそ、研究に直接触れられるこの貴重な時間を大切にし、思い切り取り組んでほしいと思っています。
最近では、製薬企業などで海外研修や留学といった先端技術を学ぶ機会に参加する社員を選ぶ際、博士号を持つ人材が優先される傾向もあるようです。企業としても、かつてのように長期雇用を前提とすることが難しくなっている中で、社員自身が専門性を高め、長く活躍できる技術や知識を身につけてくれることを重視しているのだと思います。
これからの時代は、目の前の作業をこなすだけでなく、長期的に価値を生む技術や知識を獲得する姿勢が、いっそう求められていくのではないでしょうか。
Q:将来の展望について教えてください。
一番の目標は、ゲノムDNAの構造が細胞に与えるインパクトを解明していくことです。そして構造解析によって可視化されたDNAループの機能を、ヒトの高次生命現象の理解につなげていきたいと考えています。さらに、DNAループの研究を、がん原遺伝子の上流で複雑なループ構造が形成され、遺伝子が異常に活性化されてしまう「スーパーエンハンサー」の構造解明へと発展させていきたいと考えています。
もしその仕組みを再現できるようになれば、腫瘍特異的なスーパーエンハンサーを人工的にモデル化することが可能になり、その領域を標的とした創薬にもつながるはずです。こうした取り組みを通じて、ゲノム構造と細胞機能の関係をより深く理解し、新しい治療法の開発にも貢献していければと願っています。(了)

野澤 佳世
(のざわ・かよ)
東京科学大学 生命理工学院 准教授
2007年 帝京大学 理工学部バイオサイエンス学科 卒業。2009年 東京工業大学大学院 生命理工学研究科 修士課程修了。2012年東京大学大学院 理学系研究科 博士課程修了。2009~2012年 2012年 ドイツ・ミュンヘン大学 Human Frontier Science Program Postdoctoral Fellow
(Patrick Cramer Lab)、2014年 ドイツ・マックス・プランク生物物理化学研究所 Postdoctoral Fellow (Patrick Cramer Lab)などを経て、2018年 早稲田大学 理工学術院 次席研究員。2018年 東京大学 定量生命科学研究所 助教 を経て2022年より現職。
