フッ素化合物は医薬品や半導体、次世代通信に欠かせない存在であり、その合成方法の革新は喫緊の課題となっている。従来の金属触媒を用いた方法ではコストや廃棄物、残渣の問題が避けられず、産業応用には大きな制約があった。お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学科系 矢島 知子教授は有害金属を使わず可視光のみで進行する有機合成法の開発に取り組み、環境負荷を低減しながら多様なフッ素化合物を創出した。さらに、実験の再現性を高める光反応装置「Infallibright(インフォリブライト)」の開発や、次世代通信の鍵となる低誘電ポリイミド材料の合成にも挑戦を続けている。今回は、矢島教授が挑戦している研究内容、そこで直面する研究課題、装置開発の舞台裏、そして基礎研究から社会実装へと広がるビジョンについて話を伺った。
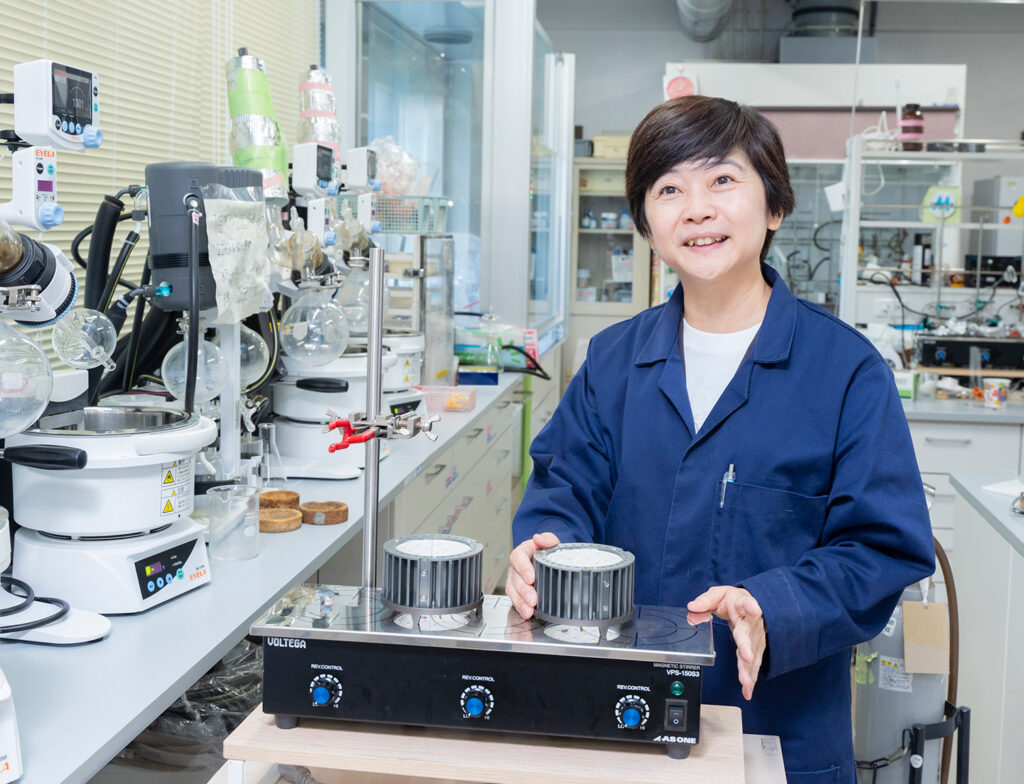
社会に不可欠なフッ素化合物を、安全かつ持続可能な方法で生み出す
Q: 研究概要について教えていただけますか?
銅などの有害な金属を用いずに、可視光で反応が進む有機合成法の開発を行っています。従来の合成法では金属触媒を大量に必要とし、そのためコストが高騰するのみならず、反応後には廃棄物や残渣の処理という大きな課題を抱えていました。しかも、多大なエネルギーを投入しなければ反応が進まないケースも多く、環境負荷の増大は避けられませんでした。そこで私たちは、よりシンプルで、低負荷エネルギーでも反応が進行する新しい合成プロセスの確立を目指しています。
フッ素化合物はスマートフォンの部品や航空宇宙や自動車向け材料、医薬品など、現代社会を支える重要な分野で幅広く利用されています。一方で、一部の有機フッ素化合物は環境に有害であるとされ規制が始まっています。しかし、それはごく一部の化合物であり、全てのフッ素化合物を同様と考えて規制してしまうと、私たちの便利な日常は成り立たなくなります。だからこそ、重要なのは「使用を停止すること」ではなく、安全かつ環境に配慮した方法で合成し、適切に利用することだと考えています。私たちはその一環として、食品添加物としても利用される無害な有機色素を触媒に用い、可視光照射のみで反応が進行する合成手法を開発しました。自然光でも反応が進むほどシンプルで、環境負荷の小さい条件で利用できる点が特徴です。
さらに私たちの研究室では、ヨウ素が結合したフッ素化合物をフッ素源として積極的に活用しています。入手が容易で構造のバリエーションも豊富なため、幅広い分子設計に応用することが可能です。さらに、この化合物を用いることで多様な反応形式を展開でき、医薬品や機能性材料、半導体素材など、幅広い分野に資するフッ素化合物の創出が可能となります。
実際、市販医薬品のおよそ3割には、フッ素官能基が含まれています。薬効性や安定性を高めるためにフッ素を導入することは極めて重要ですが、従来の方法では金属触媒を用いるため、反応後に金属が残ってしまいます。医薬品では微量の金属でも体内影響を及ぼす可能性があるため厳格な除去が求められ、それが製造コストや工程の負担増につながってきました。
同様の課題は半導体材料にも及びます。微量の金属残渣が混入するだけで性能が低下してしまうため、材料の品質維持の大きな障壁となっています。だからこそ「金属を使わない合成法」の確立は、医薬品・半導体双方にとって極めて高い意義を持ちます。不要な残渣処理を回避しつつ、製品の性能や安全性を確実に担保できるからです。私たちの研究室では「金属を使わない、だから残らない」という一貫したコンセプトを掲げ、研究を展開しています。このアプローチは、次世代のものづくりに不可欠な基盤技術になると考えています。
Q: 装置の開発にも取り組んでいるとお聞きしています。具体的には、どのような研究なのでしょうか?
実験の安定性と再現性を確保することを目的に、独自の光反応装置を開発しています。従来の装置は、懐中電灯のように横からの光照射が主流で、光の当たり方や距離が一定せず、実験の再現性に課題がありました。この課題を解決するため、フラスコ全体を360度から均一に照射できる光源を設計し、実験経験の浅い学生でも安定した結果を得られるよう工夫しました。
また、容器が熱を帯びると反応条件に影響を及ぼし、熱に脆弱な化合物だと分解してしまう恐れがあります。そこで私たちは、光源の周囲にフィンを設置し、卓上送風機によって効率的に冷却できる仕組みを導入しました。これにより、余計な熱の影響を排除し、光そのものによる反応だけを正確に評価できるようになりました。
さらに、この装置ではブルー・グリーン・白色・UVといった異なる波長を選択できるように設計しています。光反応は照射する波長によって進行の仕方や触媒の働きが大きく変わるため、研究目的に応じて最適な波長を選べることは極めて重要です。必要に応じて対応する光源を追加すれば、幅広い反応条件に柔軟に対応できる点も大きな特徴です。
装置の名称は LED光源装置「Infallibright(インフォリブライト)」。「絶対失敗しない」を意味する Infallible と、「明るい」を意味するbright を組み合わせた造語です。その名の通り、光化学反応をより確実に再現できる装置として位置づけています。この開発は、LEDメーカーとの共同研究として約3年前に開始し、既に意匠および特許の出願も完了しています。従来の光源装置は1台あたり約10万円と高価で研究現場での普及を妨げる大きな要因となっていました。私たちは価格を抑えることで、より多くの研究者が利用できる環境を整えることを目指しています。実際に議論を重ねる中で、その実現性が具体的に感じられるようになりました。商品化までには一定の時間を要しますが、学会での発表を通じて全国の大学や研究機関から問い合わせや関心の声が寄せられており、社会実装への期待と手応えが高まっています。
Q: この装置の開発で一番苦労したのはどこでしょうか?
一番苦労したのは、光学メーカーとの認識をすり合わせることでした。相手方は光学の専門家として高い知見を有していましたが、私たち化学者との視点が異なり、前提に違いがありました。さらに、当初は研究用途ではなく、ベッドサイド用の照明器具の開発をイメージされていたのです。しかし、私たちが目指したのは、化学実験における光反応に特化した研究用の装置でした。
その方向転換を可能にしてくれたのが、URA(University Research Administrator)と呼ばれる研究マネジメントの専門職の方でした。「これは光反応装置に応用できるのでは」というアドバイスをいただき、その助言をもとに相手方にも研究的な価値や市場性を丁寧に説明したのです。
その結果、当初は想定外であった用途にも「それなら面白い」と共感いただき、収率向上や実験の安定性に資する意義を共有できました。それ以降は「どの程度の市場規模を見込めるのか」「価格設定はどうすべきか」といった実務的な議論にも発展し、最終的には世界展開も視野に入るほどに議論が深まりました。異分野間の認識のギャップを乗り越えた経験こそが、意匠や特許出願につながる成果へと結実したと考えています。
Q:研究における独自性はどのような点にありますか?
私たちの研究における独自性は、長年にわたり積み重ねてきた知見の厚みにあります。博士課程の頃から約30年にわたり、フッ素を含む化合物の光反応を一貫して研究してきました。その結果、フッ素化合物特有の反応性や性質について、他では得られない深い知見を積み上げることができました。この蓄積があるからこそ、企業の方々からは「この課題を解決するにはどうすればよいか」「どのような分子設計をすれば狙った性質を得られるのか」といった具体的な相談をいただくようになってきました。学会で発表すると、すぐに実務に直結する質問や共同研究の打診があるのも、長く一歩一歩積み上げてきた証だと思います。
一時的なブームに左右されずに、同じ領域の基礎研究を継続してきたからこそ、いま社会実装の場面で成果を活かせるようになってきました。化学は産業に近い学問です。基礎から応用、そして社会還元へとつなげていく一貫した研究姿勢こそが、私たちの研究室の強みであり、独自性だと考えています。
Q: これまでの経緯について教えてください。
博士課程に在籍していた当時は、有機金属を用いた反応研究が大きな主流となっていました。国内外の研究者が次々と新しい反応を発表し、私の所属していた研究室もその分野に取り組んでいました。しかし私は、多くの研究者が支持する領域よりも、むしろ取り組む人が少ない領域にこそ未解明の課題が潜んでいるのではないかと考えるようになりました。そこから「金属を使わなくても反応が進む方法を開発できるのではないか」という発想に至ったのです。
お茶の水女子大学に着任してからは、この着想を具体化するべく「できるだけ金属を用いない合成法」の研究を進めてきました。当時、光を照射するだけで反応が進行する手法は、あまりにも単純すぎて地味だと受け止められることもありました。しかし私は、複雑な条件や高価な金属触媒に依存するより、簡便で再現性の高い方法論にこそ学術的・実用的な価値があると信じて研究を続けてきたのです。
実際に金属触媒反応では酸素や水と容易に反応するため、グローブボックスでの操作や完全な溶媒脱水といった厳格な管理が求められます。対照的に、私たちの方法は「フタを開けたまま空気中で光を当てるだけ」で進むほど扱いやすいものでした。当初は私自身も半信半疑でしたが、企業の研究者から「蓋を閉めなくてもできるなら、それだけで十分に価値がある」と評価いただいたことで、自らの研究方針に大きな自信を持つことができました。
こうして、「複雑さよりも簡便さを重視する」という研究姿勢を一貫して追究した結果、従来は困難と考えられていた反応が意外なほど容易に進む事例を次々と見出すことができました。金属を使わない合成法を探り続けた歩みこそが、私の研究の出発点であり、現在へとつながる重要な経緯だと考えています。
Q: 最近はどんな研究に力を入れているのですか?
最近は、フッ素を含むポリイミド材料の研究に力を入れています。これは「低誘電材料」と呼ばれ、電気信号を伝える際のエネルギー損失が極めて小さいという特性を持っています。5Gや6Gといった次世代通信では、信号の減衰をできるだけ抑えることは、高速・大容量通信を実現するための必須条件となります。その点、フッ素系ポリイミド材料を基板や半導体に応用することで、通信性能を飛躍的に向上させることができるのです。
現在広く用いられているポリイミドはフッ素含有量が限られており、誘電率もやや高い傾向があります。そこで私たちは、新規のフッ素系ポリイミドの合成に挑戦しており、実現すれば通信分野における基盤技術の革新につながると考えています。さらに、このポリイミドは過去に輸出規制の対象となった戦略的物資でもあります。日本が国際競争力を維持するためには、特許の有効期限が切れて他国でも生産できるようになる前に、独自の新材料を開発していく必要があります。
この研究テーマは、産業界からの関心も非常に高く、技術説明会では10社以上の企業からお問合せをいただきました。化学メーカーだけでなく、材料メーカーからも新たな応用の可能性をご指摘いただくなど、多様な視点が研究を進めるうえで大きな刺激となっています。
こうした背景から、低誘電材料の研究は学術的にも産業的にも意義が大きく、社会実装へ直結するポテンシャルを持つテーマとして、今後一層力を注いでいきたいと考えています。
基礎研究から社会実装へ――広がる光反応の可能性
Q:研究での課題があれば教えてください。
現在、私たちの研究室ではフロー合成や光反応装置の大型化に取り組み、スケールアップに対応できる方法を模索しています。一方で、一部のフッ素化合物が環境面での リスクとして指摘されたことで、『フッ素材料は扱わない』と判断する企業も少なくありません。しかし重要なのは“使用を避けること”ではなく、“適切に管理し、安全に利用すること”だと考えています。
歴史的に見ても、公害は物質そのものが原因ではなく、不適切な管理や無責任な廃棄によって引き起こされてきました。そのため私たちは、研究段階から外部への漏出防止や廃棄・リサイクルの仕組みまで視野に入れた取り組みを行っています。具体的には、ドラフト設備を用いた実験体制を整え、学生の曝露リスクを低減するとともに、生成物の回収やリサイクルまでを含めたサステナブルな研究環境を構築しています。
今後これを産業化へと展開するには、大学と企業が協働し、知見を共有・蓄積しながら大規模生産に適用できる仕組みを構築することが不可欠です。幸い、私たちの光反応はシンプルかつ拡張性が高いため、工場スケールでの応用にも適しており、将来的には太陽光を活用した屋外反応といった新しいアプローチへと発展する可能性もあります。このように、持続可能な産業化を見据えた挑戦を続けていきたいと考えています。
Q: この分野を目指している学生に伝えたいことはありますか?
東京工業大学からお茶の水女子大学へ移ってきた当初は、あまりの環境の違いに、教育者としての役割が務まるのか、学生をしっかり指導できるのかという不安がありました。しかし実際に学生と接してみると、その不安はすぐに消えました。学生たちは真面目で主体的に研究へ取り組み、先輩が後輩の実験を自然にサポートするなど、助け合いの文化が根づいていたのです。そこから「この先輩のようになりたい」という新たなロールモデルも生まれていました。こうした“学習共同体”としての好循環が育まれていることは、教育者としても大きな喜びです。
私はこの環境をさらに発展させるため、学生が自主的に挑戦できる指導を心がけています。私の指示がなくても「やってみました」と報告してくれることがあり、そこから思いがけない発見につながることも少なくありません。たとえば、ある学生は「紫外光でしか進まない」と考えられていた反応を、可視光で試してみたところ成功し、研究が大きく前進しました。私自身の発想では至らなかった挑戦が成果を生む瞬間は、研究者としても感動的です。だからこそ、挑戦する学生の姿勢を尊重し、積極的に後押ししたいと考えています。私自身、かつて否定されて辛い経験をしたからこそ、安心して挑戦できる環境をつくることに強い思いがあります。
学生へのアドバイスとして最も強調しているのは「研究を楽しむこと」です。研究は試行錯誤の連続ですが、その過程を前向きに受けとめ、「明日はうまくいくかもしれない」と思える姿勢こそが成長につながります。近年は「タイパ(タイムパフォーマンス)」が重視される風潮もありますが、効率だけを追うのではなく、大学時代にこそ思い切り挑戦し、自分の限界を知ることが将来の大きな力になります。
特に女性の学生はライフイベントによる制約を受けやすいため、今のうちに挑戦と失敗を積み重ねる経験は、将来の貴重な資産となります。大学生の間は失敗しても責任を問われることはありません。だからこそ、挑戦しないことが最大の損失だと強調したいのです。
Q: 企業との連携については、どのようにお考えですか?
企業の方々とお話しする機会は増えていますが、実際に共同研究に進めるかどうかは「人」によるところが大きいと感じています。企業担当者が社内を説得し、「ぜひ実現したい」という強い意思をもって推進してくださる場合には、困難があっても共に解決策を模索できます。一方で、上層部の判断だけで立ち消えてしまうケースでは、私たち研究者の努力だけでは前に進めません。
社会実装を見据えた研究は、研究者と企業担当者がまさに二人三脚で取り組む営みだと思います。こちらも真剣に汗をかきますので、企業の皆さまにも同じ熱意を持って挑んでいただければ、学術と産業の双方にとって大きな成果につながるはずです。
Q: 今後の展望をお聞かせいただけますか?
まず光反応によるフッ素化合物の合成について、これまでにない新しい反応を開発していきたいと考えています。研究の現場では、副反応の中から学生が思いがけない成果を見いだすことがあり、その中には学術的にも新規性の高い、これまで存在しなかった反応が含まれることもあります。偶然の発見を大切にし、体系化された新しい合成法へとつなげていくことは、反応開発の学術的醍醐味であり、今後も力を注ぎたいテーマです。
同時に、研究を学術的に深めるだけでなく、社会実装へと展開することも重要です。フッ素化合物や光反応は、医薬品や半導体材料といった社会基盤を支える分野に直結しており、大学における基礎研究の成果をいかに応用に橋渡しできるかが問われています。
たとえば、研究室から生まれたLED光源装置「Infallbright(インフォリブライト)」の商品化はその一例であり、自らの研究が技術や製品として社会に還元されることは、研究者として大きな自信と励みになっています。
社会とつながる研究を進める一方で、私の原点にあるのは「ものづくりの楽しさ」です。分子を自分の手で組み立て、新しい化合物を生み出す過程は、自分の好きな手芸や編み物で作品を仕上げていく感覚にも似ています。実験を通じて成果が目に見える形で現れることは、有機化学ならではの魅力であり、研究を続ける大きなモチベーションとなっています。
有機化学は、ものづくりが好きな人にとって大きな可能性を秘めた分野です。しかし現在でも、女性研究者はまだ少数派です。近年は学生の女性比率が高まり、学会でも多くの女性を見かけるようになり、「ここまで変わったのか」と感じることもありますが、博士課程へと進む人材は依然限られています。だからこそ、潜在的な適性を持つ人材が一歩を踏み出し、研究の場に加わってほしいと願っています。多様な人材が集まり、それぞれが挑戦と発見を重ねていくことで、学術的な知のフロンティアはさらに広がります。私自身は、基礎研究から社会実装までを一貫して支える研究室を築き、「実験は楽しい」という原点を学生と共有しながら、新しい可能性を切り拓いていきたいと考えています。(了)

矢島 知子
(やじま・ともこ)
お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学科系 教授
1993年東京工業大学 工学部化学工学科 卒業。1995年東京工業大学 大学院 博士前期課程 理工学研究科 化学工学専攻修了、1997年12月東京工業大学 大学院 博士後期課程 理工学研究科 化学工学専攻修了。 1998年1月よりお茶の水女子大学 理学部 化学科 助手。2007年4月にお茶の水女子大学 大学院人間文化創成科学研究科 助教になった後、2015年4月お茶の水女子大学 基幹研究院自然科学系 准教授を経て2020年4月より現職。
