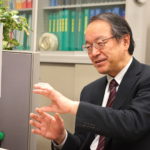シミュレーションと実際のデータを擦り合わせ、シミュレーションの精度を磨く「データ同化」研究。その進歩によって突発的なゲリラ豪雨を先読みできる日が近づいている。にわかに脚光を浴びるデータサイエンスの分野でデータ同化研究を先導しているのは理化学研究所の三好建正先生だ。革新的な気象レーダーとスーパーコンピュータ「京」の両輪が支えるゲリラ豪雨予測の仕組みとは。社会の変化を捉えうるデータ同化研究について、お話を伺った。 Q:現在のご研究内容について教えてください。 私たちのチームはデータ同化の研究に取り組んでいます。ふだん、「データ同化」という言葉を耳にすることは少ないですよね。ではどういうものかというと、コンピュータを使ったシミュレーションと現実のデータを合わせることを意味しています。これが近年は様々な分野で進んでいるのです。例えば天気予報ではコンピュ … [もっと読む...] about スパコン「京」で、ゲリラ豪雨を予測する〜三好建正・理化学研究所チームリーダー
新素材で、半導体業界に革命を起こす~竹谷 純一・東京大学教授
シリコンでできた高価な半導体、そのイメージを覆す新素材が登場した。驚くことに塗って乾かすことによって作る有機半導体だ。物理や化学の基盤の上で、革新的な新素材を用いたデバイスの開発に取り組んでいるのは東京大学の竹谷純一教授。大量に安く作れる半導体は、我々の暮らしにどのようなインパクトをもたらすのだろうか。新素材の実装の先にある次の社会について、竹谷教授にお話を伺った。 IoT の真価を引き出す新素材を使った有機半導体の可能性とは Q: … [もっと読む...] about 新素材で、半導体業界に革命を起こす~竹谷 純一・東京大学教授
iPS細胞を未来のステージへと進める〜山中伸弥・京都大学教授・iPS細胞研究所所長
2012年のノーベル生理学・医学賞の受賞から5年。iPS細胞を用いた研究の発展は年々勢いを増している。日本でも産学が連携して応用研究が進む一方、創薬分野においては早くから研究環境が整っていたアメリカを追う形で研究競争が展開されてきた。そして現在、iPS細胞の無限の可能性は、生命科学分野において生命の神秘を解き明かす鍵を握っている。iPS細胞を用いた再生医療や創薬の世界で日本が生き抜くために、そしてiPS細胞に続き世界を驚かせる研究成果が生まれるために必要なこととは何か。iPS細胞研究の最前線と、医療の進歩への飽くなき献身について、京都大学iPS細胞研究所所長・山中伸弥教授にお話を伺った。 次なるステージへと進むiPS細胞研究、安全性と時間・費用がカギ Q:現在研究所が取り組んでいらっしゃるご研究の内容について教えてください。 この研究所には現在 … [もっと読む...] about iPS細胞を未来のステージへと進める〜山中伸弥・京都大学教授・iPS細胞研究所所長
高速の画像処理技術で、多方面の技術課題を突破する〜石川正俊・東京大学大学院教授
人体の仕組みはいまだ解き明かせぬ謎に溢れているが、その人体の限界を越え、一足飛びに進歩する「高速化」の技術が、我々の世界を席巻しつつある。その領域で、日本のみならず世界の研究においても先頭を独走しているのが東京大学の石川正俊教授だ。我々の目にも止まらぬ高速技術は、社会や生活に何をもたらすのか。高速の視点から得られるビジョンについて、石川教授にお話を伺った。 「高速」があらゆる分野に変革をもたらす Q:現在は画期的なロボットの研究開発に取り組んでいらっしゃるのでしょうか。 現在の研究では、より幅広い応用分野を視野に入れています。ロボットに関する内容は全体の4分の1くらいで、高速のセンサーに基づいてロボットをできる限り高速で動かす研究です。もちろん知能ロボットですが、センサーの性能を上げたことによってロボット全体の性能が上がるのです。特に、ロボット … [もっと読む...] about 高速の画像処理技術で、多方面の技術課題を突破する〜石川正俊・東京大学大学院教授
トップレベルの環境で、国家の10年計画を実現する〜杉山将・革新知能統合研究センター長
産学協同で日本の人工知能研究を振興するための国家プロジェクトが産声を挙げた。2016年4月にはその一端として理化学研究所が「革新知能統合研究センター」、通称AIPセンターを設置。指揮をとるのは東京大学教授でありAIPセンター長を務める杉山教授だ。基礎研究の進展とともに多彩な応用研究へと裾野を広げつつあるAI研究においては、産官学の垣根だけではなく、ときには国境すら越える柔軟な展開が期待される。AI技術と共に生きる社会の実現に向けて、日本はどのように舵をきっていくべきか。杉山教授にお話を伺った。 国を挙げての人工知能研究・開発が始動、国際的な研究機関を目指した枠組み作りへ Q:現在の活動内容について教えてください。 現在はクロスアポイントメントという制度を利用して、AIPセンター長と東京大学の教員の二つを兼務しています。まず、大学の教員としては、 … [もっと読む...] about トップレベルの環境で、国家の10年計画を実現する〜杉山将・革新知能統合研究センター長
モデルマウスの作成で、高尿酸血症研究の前進を目指す~細山田 真・帝京大学教授
成人男性の5 人に1 人が抱える高尿酸血症。多くの現代人が恐れる痛風につながる生活習慣病だが、その環境要因の解明にはまだ至っていない。その研究に不可欠な実験用マウスの作成に取り組むのは帝京大学薬学部の細山田教授だ。尿酸代謝が人間と大きく異なるマウスをどのようにしてヒトと同じ条件に近づけるのか。長年の研究を結実させて新たな遺伝子疾患をもつマウスを作成し続ける細山田教授にお話を伺った。 マウスで高尿酸血症研究の前進 Q: … [もっと読む...] about モデルマウスの作成で、高尿酸血症研究の前進を目指す~細山田 真・帝京大学教授
科学・技術と社会の相互作用から、問いを作り出す〜江間有沙・東京大学特任講師
人工知能が実際に社会の中に取り入れられる現場を訪れ、AIと社会の関わり方を議論するAIRの活動に関心が集まっている。そうした科学・技術と社会の相互作用を議論する取り組みは、AIに限らず様々な研究領域に広がりを見せる。その中心で議論の場作りに貢献しているのが、STSの研究を行う江間さんだ。文と理、研究と研究の垣根を越えたユニークな取り組みについて、お話を伺った。 世界の「切り取り方」を再定義するSTS Q:研究内容について教えてください。 研究領域は「STS」と呼ばれる分野です。STSは「Science & Technology Studies」と「Science, Technology & … [もっと読む...] about 科学・技術と社会の相互作用から、問いを作り出す〜江間有沙・東京大学特任講師
インタフェースの発達が、複合現実感をもたらす〜檜山 敦・東京大学先端科学技術研究センター講師
情報世界と現実世界を掛け合わせた複合現実感が、より身近なものとなってきた。特に高齢者の活躍を支援するジェロンテクノロジーを含め、誰もが先端技術を使えるようなヒューマンインタフェースの設計が活発化しつつある。その中心で画期的な研究開発を行なうのが、東京大学先端技術研究センターの講師を務める檜山先生だ。情報世界へと拡張する社会はどんな方向へ進んでゆくのか。高齢者支援やスポーツの分野でも存在感を大きくする情報研究の「今」を伺った。 高齢者が活躍できる世界を、情報・VR技術を使って実現する Q:「複合現実感」とは、どのようなものなのでしょうか。 複合現実感とは、実世界とバーチャルリアリティの作り出す情報世界の二つを融合させた概念のことです。その中には実世界の割合が大きいものからバーチャル世界の領域が大きいものまであり、二つの領域の比率によって名称が異な … [もっと読む...] about インタフェースの発達が、複合現実感をもたらす〜檜山 敦・東京大学先端科学技術研究センター講師
創薬は、ビッグデータ活用で激変する〜奥野恭史・京都大学教授/理化学研究所副グループディレクター
ビッグデータを活用した新しい医療への取り組みが始まっている。その要点の一つが、京都大学の奥野教授が主導する医療シミュレーション、ビッグデータ創薬などの開発だ。より課題解決において能力を発揮する次期スーパーコンピューターのポスト「京」開発元年となった2015年。大きく舵をきったIT領域と共に、医療はどのように進んでいくのか。奥野教授にお話を伺った。 現代における医療・創薬はスーパーコンピューターとビッグデータなしには語れない Q:現在の研究内容について教えてください。 我々の研究の特徴は医療・創薬の領域においてIT、コンピューターの技術を用いる点です。どのような技術なのかというと、一つはスーパーコンピューター(スパコン)を用いたシミュレーションの技術です。もう一つはAIを利用した、ビッグデータ情報の活用への試みです。つまりスパコン、そしてビッグデ … [もっと読む...] about 創薬は、ビッグデータ活用で激変する〜奥野恭史・京都大学教授/理化学研究所副グループディレクター
「群知能」の研究から、社会を考える〜栗原聡・電気通信大学教授
一匹では小さな小魚でも、仲間と集まれば天敵をも恐れない大魚となる。童話「スイミー」の逸話だが、同じような現象が自然界に見られるのである。我々人間も例外ではない。バラバラの個人である私たちは、寄り集まって国家を成している。このように自然界にも人間社会にも共通して見られる「群知能」の原理を究明し、新時代の情報ネットワークの構築に活用しようと研究しているのが、栗原教授である。我々の生活のあらゆる面に応用できる群知能の奥深さ、そして世界中で加速するAI競争の中で日本がとるべき戦略について、栗原教授にお話を伺った。 「群知能」とは何か? Q:現在の研究についてお教え下さい。 人工知能の研究をしています。その中でも「群知能」や「知能創発」といった分野で研究を行なっています。群知能とは何かというと、群れのことです。人を含め、全ての知能は群知能であると言い切っ … [もっと読む...] about 「群知能」の研究から、社会を考える〜栗原聡・電気通信大学教授