現在、触媒として使われている主流は金属錯体であり、パラジウムやロジウムなどの金属に有機物がついたものが用いられるのが一般的だ。しかし、こうした金属の使用を前提としていると、資源を持たない日本では他国との貿易関係に産業が依存してしまうことになり、また微量でも毒性が残るという課題もある。こうした問題を乗り越え、安全度を高めるべく、有機分子だけで触媒作用を示す研究を行なっているのが、学習院大学の秋山教授だ。今回は、金属を使わない有機化合物だけの触媒作用の研究の概要について伺った。

金属錯体の課題を乗り越える
Q:研究の概要からお聞かせください。そもそも有機触媒とはどのようなものなのでしょうか?
触媒とは、何かと何かを混ぜる時にその化学反応を促進させるもののことをいいます。
触媒は、ノーベル化学賞授与の対象として注目されることが頻繁にあります。例えば、2001年にノーベル化学賞を受賞された名古屋大学・野依良治先生の研究は、金属錯体を用いて不斉還元といって炭素―炭素二重結合に水素を付加させることを実現したことが高く評価されました。また、2005年のグラブス先生や2010年の根岸先生の研究でも、基本的に金属錯体を用いて炭素と炭素を結合させる様々な反応を促進させて、新しい素材を作ったりするわけです。
このように触媒として使われるのは多くの場合金属錯体であり、パラジウムやロジウム、ロテニウムなどの金属に有機物がついているものを用いるのが、1990年代2000年代から続く主流の研究になります。
一方、我々の研究はそれと少し異なり、金属錯体を触媒として使用した時と同じような作用は示すのですが、それを金属が入っていない、要するに有機化合物だけで作用を起こすことを目指した研究を行っているわけですね。
もちろん金属を使うことは非常に素晴らしい面もたくさんあるのですが、同時に問題点もいくつかあります。たとえば、金属錯体には、例えばランタノイドなど、なかなか日本では採取できない希土類が使われている場合があり、それらは主に中国で生産されていますが、中国がそれを日本に輸出しないということも一時あったわけですね。
特殊な金属は南アフリカなど特定の国でしか採取できないことはよくあることですが、万が一政治的な問題が発生した場合、途端にそのような金属類が日本に入ってこなくなる可能性も十分あり得るわけです。そうなると、資源を持たない日本の企業は大きく困る事態になります。
また、金属には毒性があるものも多く存在します。金属の触媒は薬の合成などにも多く使われていますが、ppmという非常に少ない量でも薬に毒性成分が残ってしまいますし、そしてそれを取り除くのがけっこう厄介だという問題もあります。
我々は当初からそれを目指していたわけではありませんが、結果として、金属を使わずに有機分子だけで触媒作用を示す研究を2000年頃から活発に行なうようになりました。
また、同時期から金属がなくても様々な反応を起こせるということがわかってきています。金属を使わないことで生成物に毒性成分が残ってしまう可能性は低くなりますし、そもそも金属採掘をしないので、環境を破壊しない=「グリーン」であるという点でも有機触媒は非常に期待をされています。
Q:研究に至るまでの経緯をお聞かせください。
まず化学の話になりますが、金属錯体はある分子を活性化することに寄与します。そもそも、私たちの研究は、有機合成、つまり有機化合物の主骨格である炭素同士を結びつけていくことを目的としていました。
例えば塩酸や硫酸に含まれているH+(プロトン)は、主に炭素と酸素を結合させる反応を促進しますが、有機化学の主流となる炭素同士の結合における触媒としてはあまり使われてきていませんでした。そこで、H+を有機化学の実験にも使えないかと考えたことが今の有機触媒研究の原点となっています。というわけで、20年前、研究を始めた当初は有機触媒を作りたいという思いはありませんでした。
それで、最初は綺麗なものを作るための触媒を作っていたのですが、最初はそこまで上手くいきませんでした。
そこで、どうせならリン酸触媒という、新たな触媒が作れないかということで研究が始まりました。
時間はかかりましたけれども、2004年には論文を発表することができました。偶然にも東北大の寺田先生のグループも同時期に同じような触媒研究をしていたのですが、論文発表後、我々の作った触媒に世界中の研究者から注目が集まり、今や世界中の研究で使われるようになりました。
有機触媒というのはもう少し広い分野で、これ以外にも多くの有機化合物が酸触媒や塩基触媒として作用するものがあり、2000年ごろからとても注目されています。我々はあくまでもH+に注目していており、有機触媒の開発を目指して研究を始めたわけではなかったのですが、有機触媒の分野が広がってきて、結果として我々の研究がその中の一つに数えられるようになったというわけです。そのため、もう少し視野を広げて研究をしてみることにしました。今後このような触媒を使って何ができるかを考えていくことも課題の一つですし、今よりももっと質の高い触媒を作るということも取り組んでいることの一つです。
Q:いい触媒とはどういうものなのでしょうか?
作りやすいことももちろん条件の一つですが、触媒はあくまでも反応を促進させるだけで、それ自身が生成物と反応するわけではありません。そのため、なるべく少ない量で反応を促進できる触媒ができるといいですね。また回収して使うこともできるので、再利用できたほうがよりいいわけですね。
ただ、現時点で理想にどれくらい近づけているかというと、実際のところはまだまだですね。あくまでもまだ実験室レベルの段階ですから、将来企業に使ってもらうためには不十分なところはたくさんありますので、今よりももっと少ない量で触媒として機能するところまで活性を上げていかなければならないと感じています。
Q:他の研究と比べて、体制や完成物で違うところはありますか?
繰り返しになってしまいますが、2000年くらいまで触媒といえば金属錯体、または酵素などの生体触媒が主でした。
そこに有機触媒が加わり、今はそれら三つが代表的な触媒になると思いますが、それぞれお互いの得意分野を活かして棲み分けられるといいと思いますね。
これまで酵素で実現できなかったことも、有機触媒を使えば実現できるようになる、といった具合にです。将来的にはどこかの企業で薬の合成にそれらの触媒が使われることなどになれば面白いと思います。
Q:有機触媒に取り組む研究室としては、世界で唯一なのでしょうか?
いいえ、日本にもいくつか研究室はあります。また、日本は有機化学に強いのですが、なにぶん国からの予算が減り続けています。一方、中国は政府が多額の投資をしており、研究者をアメリカに派遣させてから中国での研究をさせていたりして、人的資源もお金もある中国は熾烈な競争相手となっています。個人的には、化学分野では日本は負けていると思います。
ちょっとしたアイデアを、地道に追求する
Q:大学学部卒業から今までの経緯をお聞かせください。
1985年に博士課程を卒業してからは、当時薬の合成に興味があったので、製薬会社(塩野義製薬)に勤め、大阪で三年間薬の合成の研究を行なっていました。
その後1988年にポストを見つけて愛媛大学に移りましたが、6年在籍したうち1年はアメリカのスタンフォード大学で研究をさせてもらっていました。愛媛大学を離れてからは、ずっと変わらず学習院大学におります。ここは場所もいいですし、他の大学と比べて停年も70歳と長く、とても居心地がいいんですよ。
実は、最初は南極観測隊に興味があったんです。元々化学に関する分析が面白そうとは思っていたのですが、次第に有機化学に興味を持ってそちらの道に進むことにしました。有機化学は実験科学なので、新しいものを作ったりするのはとても面白いと感じています。
Q:化学が発展するにはどういう要素があるといいのでしょうか?
我々がいる化学分野は、そこまで大型の機器が必要というわけではありません。
例えば物理学では、カミオカンデなどいった何十億円もかかる機器を作って初めて実験が始められるということが多々ありますが、我々はそういったものは必要としません。
ただし、人的資源の重要性は大きいと思いますね。ある程度の人手はいると思います。
Q:手法としては仮説を立てて実験を行うといった、スタンダードな手法でしょうか?
基本的にそうなりますが、やはり試行錯誤なのでうまくいかないことも多々あります。もちろん仮説も立てますが、理論が先に立つまずは反応を見ることが先なので、化学はとにかく実験を繰り返すしかないですね。
Q:研究の面で、技術的な課題や、産業的な課題などはありますでしょうか。
我々の技術は、学部の4年生でも作れて実験もできる段階にあります。ただし先ほども申し上げた通り、産業的に使ってもらうとなると、なるべく少ない量で使えるように、また再利用をしやすくするようにするといった課題があります。まだまだ質を向上させていかなければなりませんし、改良の余地はたくさんあります。
Q:実際にはどのような企業からオファーがありそうですか?
直接やり取りをしているわけではありませんが、企業の人と話をすることはしばしばあります。
企業側としては既存の反応に適するものがあれば使いたいというスタンスですし、まだ有機触媒を工業的に使っているという話は聞きませんので、そこをもう少し実用化できるようにしていきたいと思いますね。
現在は医薬品の中間体の合成の一段階に使われたりすることに期待していますね。つまり、薬というのは何段階かに分けて混ぜることを繰り返すことで作られていくのですが、その工程の途中で使ってもらえればいいと考えています。
Q:学生の方はどういった方がいらっしゃいますか?
学部4年は6人、院生は10人程度いますね。今は,スペイン人のポスドクが1人、スペインからの短期滞在の大学院生が1人いますね。皆地道にコツコツと実験をしています。基本的に研究は一人ずつ個別に行なっていますが、研究内容が近い者同士でチームを組んでいる学生もいますね。
基本的には大学院修士課程を修了した後は、広義の化学に関する企業に勤めることが多いですね。
Q:海外留学生がわざわざ日本にいらっしゃる魅力というのは、どこにあるのでしょうか。
中国から1人、日本で研究したいと、つい最近はスペインからも来て研究したりしていますが。来てくれるからには多少は魅力があったのでしょうね。日本人学生はあまり留学をしませんが、学生をつながりのあるスペインの大学に2ヶ月ほど送って共同研究したりはしています。今来ているのはバレンシア大学の学生ですね。中世からある古い大学です。
Q:この分野では、学会なども開かれているのでしょうか?
学会にも色々行きますが、一番の中心は日本化学会ですね。他には有機合成化学協会というのもあります。私も関わる日本プロセス化学会は、企業の薬品会社のプロセス化学のものつくりの研究をしている人たちが多く参加するので、実業寄りの学会と言えますね。
Q:今後、ますます触媒研究の可能性が広がると思いますが、どういった学生に来てほしいと思われますか。
実験化学の分野なので、手を動かして実験をすることが好きな人が必要ですね。本やパソコンで勉強するだけではなく、ある意味でものつくりの原点でもある実験でいろんなものを作っていくことに喜びを見出せる、新しいことに興味がある学生に来てほしいです。
特に化学というのは、圧倒的な頭脳はなくともちょっとしたアイディアが活きる分野です。アイディアを元に好奇心から手を動かして実験をしてみて面白いものができるということもあるので、アイディアマンの方がいいかもしれません。とにかくアイディアを出して実践してみることが大事ですね。
ある先生が「実験は1000回やっていいものが3つ生まれればいい」とおっしゃっていましたが、試行錯誤の中で少しでも面白いものが見つかっていけばいいんです。実験が好きな人は楽しいでしょうし、そこから考えていろんなアイディアを出していくのもより楽しいでしょうね。
Q:将来的に企業と手を組んでいくこともあると思いますが、企業に期待されることはありますか?
企業も昔に比べると余裕がなくなっており、基礎研究がなかなかできなくなってきています。アメリカは今でもどんどん学会に発表をしている企業がありますし、日本も基礎研究にも目を向けて、新しいものをどんどん作っていってほしいと思います。新しいものを生み出すには、企業自身がある程度研究に投資していく必要はあると思います。
Q:どういう体制だと組みやすいなど、要望はありますか?
私が所属していた会社も昔は基礎研究に力を入れていて、今から3, 40年ほど前は「塩野義大学」と呼ばれるほどアカデミックなことをやっていました。将来的に企業と共同研究ができればいいと考えていますが、企業の中の具体的な問題点について直接情報交換ができるのは我々にとって非常に貴重ですね。共同研究ができれば、直接問題点を出し合ってその解決方法を一緒に考えていくことができます。学会でもあるんですけれどもね。企業と共同研究することで、まず直面する課題を解決しつつ、長期的な展望も描くこともできると思います。
Q:今後の目標についてお聞かせください。
やはり我々としては企業で実用できる触媒、触媒反応を生み出し、それを企業で実際に使っていただければ嬉しく思います。直近で達成できるかはわかりませんが、将来実用化できるように研究を進めていきます。(了)
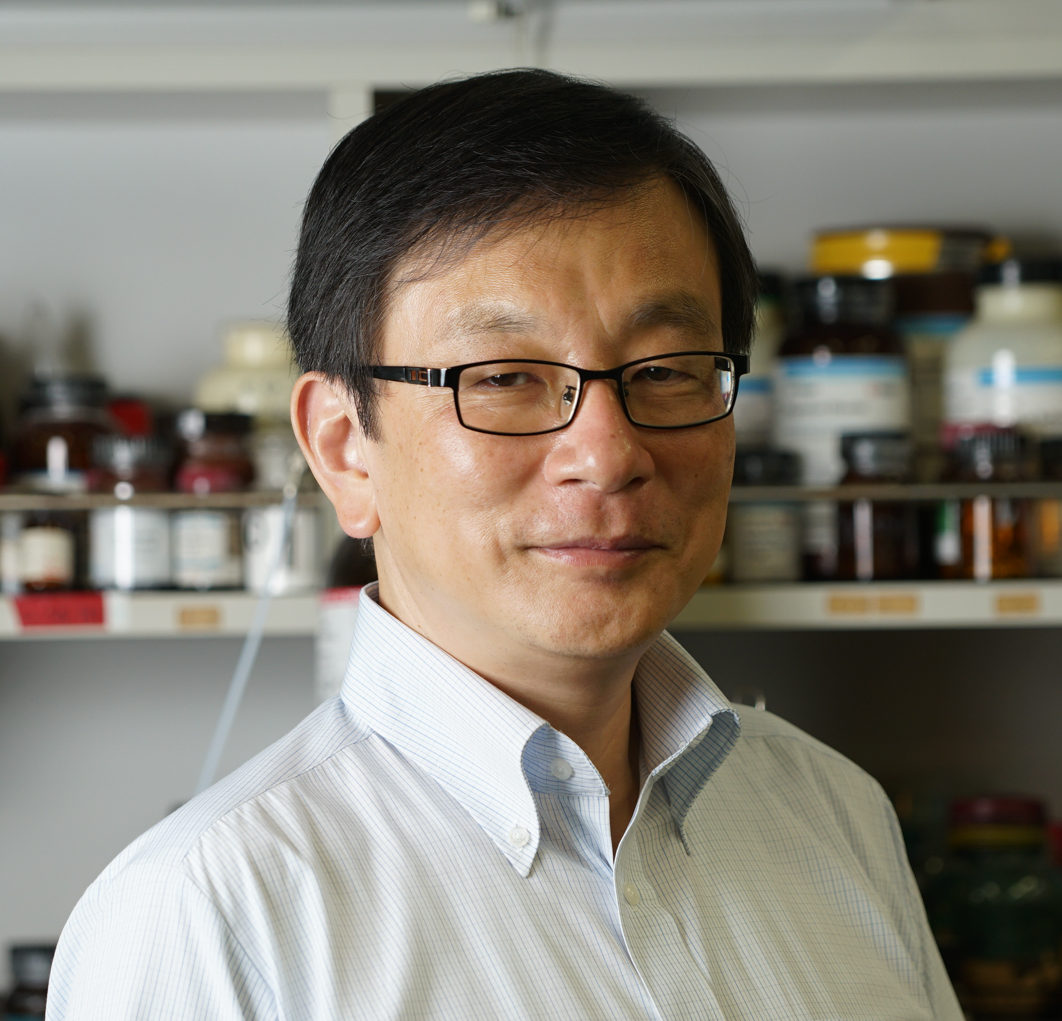
秋山 隆彦
あきやま・たかひこ
学習院大学理学部化学科教授。
1980年、東京大学理学部化学科卒業後、東京大学大学院理学系研究科化学専門課程博士課程修了(理学博士)。1985年、塩野義製薬株式会社の研究所に入所し、民間での研究を進める。1988年に愛媛大学工学部助手となり、1992年にスタンフォード大学 (Professor B. M. Trost)博士研究員として渡米。帰国後、1994年に学習院大学理学部化学科助教授となり、1997年より現職。
