刺激や熱に応答する、機能的な材料「スマートポリマー」の可能性が注目されている。「これまで治らなかった病気を、素材の力で治す」ことを目指し、医療分野での実用化研究を進めているのが、物質・材料研究機構 准主任研究者の荏原充宏(えばら・みつひろ)氏だ。今回は、荏原氏が実際に開発したがん治療用メッシュや腕時計型尿毒素除去フィルターの紹介を中心に、「紙きれであるポリマー1枚で、病気を治す」展望を伺った。

医療分野を視野に入れた、特殊ポリマーの研究
Q:研究対象とされているスマートポリマーとは、どのようなものですか?
ポリマーを一般的な言葉でいうと、プラスチックになります。この世の中の物は金属、セラミックス、ポリマーの3つに大きく分類できます。僕はその中のポリマーについて研究しています。プラスチック以外ではゴムや樹脂などもポリマーになります。触ってもらうとわかると思いますが、ほとんどがポリマーです。ですから服や紙などもポリマーと言えますし、もっと言えば我々の身体を作るたんぱく質もポリマーのような構造をしています。
続いて、「スマートポリマー」について、直訳すると「賢いポリマー」になります。例えば刺激に応答するポリマーや熱に応答するポリマーなど、少しユニークなポリマーを総称して、スマートポリマーとしています。ですから何か一つの物質をスマートポリマーと呼んでいるのではなく、色々なものがあるわけです。
私は「つくば科学教育マイスター」というものに認定されておりまして、小学校に行ってスマートポリマーを生徒たちに見せたりしています。その中では、小学生にもわかりやすい説明ができるように、スマポレンジャーという戦隊ものをモチーフにしたショーもしています。
スマートポリマーには様々な種類がありますが、いくつか例をあげると「刺激応答性ポリマー」、「形状記憶ポリマー」、あとは何度切ってもくっつく「自己修復性ポリマー」や、身体の中で溶けてしまう「生分解性ポリマー」など、普通ではないちょっと特殊なポリマーをスマートポリマーと呼んでいます。
Q:現在、世の中にある物質だけではどうしても不十分なのでしょうか?
例えばプラスチックはそれだけでは何もしませんよね。世の中でたくさん使われていますが、それ自体では何もしません。そこに熱をかけたら反応してくれる、光を当てたら反応してくれるというように、少しユニークな物質をつけることで今までできなかったことができるようになるのではないか。これが私たちのやろうとしていることです。
プラスチックと聞くとプラモデルのようなものをイメージする人も多いかもしれませんが、実際私たちの周りにあるものは全てプラスチックのような構造でできています。ですから、身体に悪い影響のないものも開発されています。
Q:具体的には、どのような場面で活躍するポリマーを目指されていますか?
何かスイッチを入れることで性質のONとOFFが変わりますので、本当にたくさんの使い方ができると思います。
ただ私たちはあくまで、医療の分野で使えることを目指しています。例えば現在使われている医療材料には、100円ショップで売っている商品とほとんど同じプラスチックが使われています。こんなに身近なもので病気を治しているわけですから、もっとスマートなものができればこれまで治らなかった病気も治せるようになるのではないかと考えています。例えば身体の中に埋め込んだスマートポリマーが、お医者さんが外から刺激を加えることで、病気を治してくれるようなイメージをすると分かりやすいかもしれません。
Q:実際に医療現場で使うことについて、課題はありますか?
従来の医療だとこういったガンが治らない、こんな心臓病が治らないというのを、スマートポリマーで治していきたいです。
ちょっと飛躍しますが、この病気を治すためにはこんな性質が必要で、そのようなポリマーを作るにはどんな分子構造にしたら良いかという感じですね。分野で言うと化学、ケミストリーになりますね。日本語で言うと「高分子」、英語で言うと「ポリマー」です。高校でも習うような学問です。ポリマーは物質が数珠のように繋がっているものです。その繋ぎ方を少し変えると、こんな性質に変わるというようなノウハウはすでにあるわけです。
Q:貼るタイプのがん治療用メッシュを開発されましたが、これはどのような開発背景があるのでしょうか。
これはがんに直接貼るタイプのもので、皮膚がんの場合は皮膚に貼ることになりますが、身体の中にあるがんの場合は内視鏡などを使って貼る感じです。
例えば胃がんの手術をしてがんを取ったとします。この段階が原因で亡くなることはさほど多くなく、取った後数年後にがんが再発してしまうことが死因のほとんどを占めています。ですから、がんの治療=手術の後にいかにがんを再発させないかが非常に重要になってくるわけです。がんを取って終わりではなく、その後に貼って再発を防ぐというものです。
またこのメッシュは貼る部分に応じてサイズを変えることもできます。そもそもなぜスマートポリマーを使うのかをお話しするならば、がんと戦う際にまず必要になるのが抗がん剤です。それに加えてがんには熱に弱いという性質があります。普通の細胞は比較的熱に強いものですが、がん細胞は反対に熱に弱いです。つまり、熱をかけながら抗がん剤を使うことで、さらに強い効果が期待できるわけです。
また、抗がん剤というと副作用が気になりますが、熱と抗がん剤を合わせて使うことで効果が強くなる分、副作用が出ると言われている量の10分の1まで薬を薄めても十分な効果が期待できます。
つまりスマートポリマーを使えば、熱と抗がん剤の両方を使う非常に良い治療ができるわけです。
簡単にイメージするなら、IHヒーターをがんの患部に近づけるとメッシュから抗がん剤と熱が出るような仕組みです。ここで注意したいのは、熱と抗がん剤の治療を絶えず続けてしまうとがん細胞がすぐに耐性を持ってしまうため、治療の効果が得られなくなってしまうことです。そのため、本当に必要なタイミングで治療をして、しばらくしたら止める。このようにスマートポリマーを使って、治療のONとOFFを上手く切り替える事が非常に重要になってくるのです。
Q:メッシュはすでに、実用レベルまで開発されているのでしょうか?
がんを撃退するという面では、動物で効果を試しているのが現段階です。実用段階に近いものでいうと、手の痺れや神経痛などがある場合に症状に関わる神経に直接巻いて薬を出すタイプのものなどは、すでに製薬会社さんと一緒に開発を進めています。しかし、先ほどのがんのメッシュに関しては熱と抗がん剤という少しトリッキーな部類になりますから、まだ動物の段階です。
Q:続いて、腕時計型尿毒素除去フィルターも開発されましたが、こちらは何をするのでしょうか。
尿毒素除去フィルターと聞くと、ちょっと難しそうに聞こえるかもしれません。まず、透析治療という治療法がありますよね。週に3回は治療に通わなければならないなど、患者にとってはかなりつらい治療だと言えます。一方で言い方は悪いかもしれませんが、透析治療は日本の医療機器の中で唯一輸入黒字産業となっている部門でもあります。また透析治療には1回に100リットルほどのきれいな水も必要ですから、先進国でしかできない治療でもあると言えます。言い換えれば、被災地や発展途上国ではなかなか難しい。
こうした背景から、僕たちはスマートポリマーを使って、身体の中の悪い物質だけを吸着してくれるようなメッシュを作っています。これができると、患者さんは腕時計のように小さなものを身につけるだけで尿毒素を取り除けるようになります。病院に行かずに治療、というわけにはいかないかもしれませんが、発展途上国などで使えるようにしていけたらと思っています。中でもインドや中国からの問い合わせが多いですね。
医療分野の最先端の研究は、iPS細胞やゲノム編集など、高度なレベルに向かっています。私自身もここに来るまではずっと再生医療の研究をしていましたが、費用もすごくかかるし、人員もたくさん必要です。留学中にはビル=ゲイツ氏の財団で、途上国医療の研究もしてきました。その時によく言われていたのが「世界70億人のうち、50億人は1日を2ドル以下で生活している」ということ。つまりほとんどの人は、医療の恩恵を受けられないことになります。しかし、ティッシュペーパー1枚であれば、おそらく世界中のどこでも使えるはずですよね。つまり「紙きれであるポリマー1枚で、病気を治したい」、これが僕の目標です。
いまは途上段階としてがんのメッシュの方法などをとっていますが、もっと言うと抗がん剤も使用せず本当に紙きれ1枚でがんを倒せるようになれたらいいなと思っています。
材料を極めるべく、最良の環境に身を置いた
Q:現在の研究にいたるまでのご経歴をお聞かせください。
元々は早稲田大学の応用化学科にいましたが、早稲田大には医学部がありませんので、医療を研究したい場合は近くの東京女子医大に行き、そこでポリマーを使った再生医療を研究していました。早稲田大学を卒業後、アメリカのシアトルにあるワシントン大学に3年ほど留学しました。その後また日本に戻り、大阪大学の医学部附属病院にある未来医療センターという最先端の研究を患者に応用するような所に2年ほどいたあとで、現在の物質・材料研究機構にやってきました。
オファーがあったのもそうですが、やはり自分の中で材料の分野をしっかり研究したい、極めたいという思いがあったからですね。病院では様々な研究をしますが、そこには良い材料が必要になってくるというのもありますね。
あとはスマートポリマーを作ろうとしても、ここのように良い施設でなければそれを具現化することが難しいという理由もあります。普通の病院の中だけではなかなか難しいですね。本当に自分たちが絵に描いた材料を形にするには、材料の研究にフォーカスを当てる必要があるのではないかと考えています。
Q:簡易的な医療材料を開発したいと思った直接のきっかけはあったのでしょうか。
ワシントン大学に留学した時に、ビル=ゲイツ氏と奥さんのメリンダ=ゲイツさんがやっている財団で途上国医療についてのプロジェクトをやることになりました。途上国についてですから、例えば私たちが考えたテーマを提案しても「それは冷蔵庫がなくてもできますか?」とか「それは泥水でもできますか?」などと先生に言われてしまい、何も言えなくなったのですね。先生の言うとおり、私たちの考えたテーマは途上国では全く役に立たないとそこで実感させられたわけです。
この経験から少しマインドを変えて、スマートポリマーなら途上国でも役に立つのではないかと考え始め、現在の研究に移ってきました。その意味では、財団での経験はすごく大きなものだったと感じています。
インドや中国など後進国とまでは言わないものの、人口が多い割には医療のインフラが整っていないような所からの反響は大きいと思います。今のがん治療の中心はやはり高度な病院だと思いますが、先ほどの貼るがん治療のようにティッシュペーパー1枚で治療ができるようになれば、途上国でも治療できるようになるのかなと思います。
Q:日本の物質化学の分野は、世界的な視野で見るとどのくらい進んでいるのでしょうか?
一般論になってしまいますが、ものづくりの分野では日本はものすごく強いと言えます。例えばバイオの分野となるとみんなアメリカに留学しますが、それと同じように物質科学の分野ではみんながここに留学してきます。ですからここには外国人が6割くらいいて、公用語も英語です。材料科学という意味では、ここは世界でもトップクラスの研究所であると言えますね。また、スマートポリマーだけを見ても研究自体は様々なところで行なわれていますが、ネットで検索すればここがでてきますから間違いなく代表的な拠点の一つであると思っています。
Q:現在、どのような環境下で研究されているのでしょうか。
物質・材料研究機構は、大学ではなく国立の研究所にあたります。最近の情報でいうと、理研と産総研と物質・材料研究機構が特定国立研究開発法人として国から指定されています。
また私自身、色々な大学の教員もやっておりまして、主に筑波大学と東京理科大ですがそこから何人か学生が来てここで研究をしています。大学だと施設がなくてあまり良い研究はできませんし、一方で国研にはものすごい施設がある分学生はいないわけです。その意味ではWin-Winになるというか、お互いにとって良い環境が作れているのではないかと思っています。
現在私たちはがん、透析、途上国での感染症の診断と、大きく3つのチームに分かれそこをさらに細分化したチームで研究をしています。このテーマをやってと学生に指示する事はなく、大体はネットなどでうちの研究室のことを調べて来る学生が多いですから、あらかじめやりたいことが決まってることが多いです。そのあたりは大学とは違う部分だなと思っています。大学であれば黙っていても勝手にどこかしら研究室に配属されますが、ここは自分から手を挙げなければ来ることはできません。ですから、やる気の多い学生さんが多いと感じています。
Q:技術的、産業的、法律的な課題はありますか?
まず技術的な面ですが、すごくポジティブに言うと、私たちは課題があればそれを解決するまでとことん材料を設計することができますから、常にそこをクリアしていけるようなものを作っているつもりです。
産業的な面では我々の手に負えない部分もいくつかあって、大きな所で言うとコストの問題があります。ポリマーはいくらでも安く作ることができます。しかし安くしすぎてしまうと患者さん側は嬉しいかもしれませんが、企業さんにとっては儲からないので何のメリットもなくなってしまいます。
最後に法的な面で言うと、医療材料をやっている以上厚労省などの認可を取らなければなりません。ここで製薬企業側からすると、薬価が重要になってきます。しかし厚労省が定めた薬価に従わなければなりませんから、勝手に値段を決めることはできません。安いポリマーを作っても、あまり高い薬価は取れないため、なかなか儲からなくなってしまいます。コストと聞くと高すぎて問題になるイメージがあるかもしれませんが、反対に安すぎて問題になることもあるわけです。
一昔前なら日本の企業さんも底力があったと思います。しかし今はできあがったものならやってくれますが、一緒に何かを作ろうという感じがないのでそのあたりが課題なのかなという気はしますね。もちろん目を輝かせながら来てくれる企業の方もいますが、ほとんどの場合話し始めの段階でこれは無理だなとわかってしまうくらいの企業さんが多いです。
Q:どんな学生が多いですか?
私たちのところは大学院生からの受け入れですが、先ほどもお話ししたとおり国内だけでなく国外からもたくさんの学生が来ています。ケミストリーの分野ですので、すごく数学ができるとか物理の計算ができるとかというよりも、ものづくりに興味があればどんな人でもできる分野かなと思っています。
「人が想像できることは、必ず実現できる。」これは僕の好きな言葉で、フランスの作家のジュール=ベルヌという人の言葉です。彼はSFの父とも呼ばれていて、アポロ計画の100年くらい前にはすでに月世界旅行という本を出していました。また20世紀のパリという本を19世紀に書いていて、そこには街に電車が走っていたり、FAXでやりとりをする様子が書かれていました。一つ言いたいのは、例えばお医者さんにこんなものを作って欲しいと言われて、それを言われるままに作るのももちろん大事なことだと思います。ニーズがあるからです。しかし先ほどの貼るがん治療などは誰に頼まれたものでもなく、私たちが想像して勝手に作ったものです。その意味では、自分たちで想像して作り出すこともこの分野の面白さだと思っています。
月に一度アイデアコンテストをやっているのですが、普通の研究室ではまずやらないでしょう。アイデアと言っても口で言うだけではなく絵に描いて表現することにしています。
例えば「タイムマシン」と聞いた時に何かしら頭の中にイメージが浮かぶと思いますが、多くの人はドラえもんに出てくるタイムマシンのイメージに引っ張られていたりします。あのタイムマシンを作者が書いていなければ、誰も想像することができないですよね。アイデアコンテストではみんなに好きなように画用紙に描いてもらって、壁に貼りだしたりもしています。こういうことは若いほど面白い考えが生まれやすいようです。たまに小学校に行った時に生徒さんに描いてもらったりもするのですが、びっくりするようなアイデアが出てきたりします。
Q:企業に期待することはありますか?
企業の人も色々考えているのはよくわかります。ここで僕が言うことではないかもしれませんが、すごく優秀でも口下手な学生はほとんど就活で落ちてしまっている気がします。反対にあまり能力がなくても口だけ達者な人は受かっていることが多い感じもしますね。企業の人にはもっと一人一人の本質を見抜いて欲しいと思いますね。営業ではなく研究者を雇うわけですから、多少口下手だったとしても研究者として能力がある人を採用した方が良いと思います。
あとは、例えば難治性の疾患や世界的に見ても数%しかいない子供の病気となると、全く採算が取れません。困っている人はたくさんいるのに、研究が進んでいないのです。先ほどの透析の話もそうですが、現段階である程度良い産業になっているものだとなかなかイノベーションを起こしづらいですよね。でもそんなことを言っているうちに、こんな状況が続くなら海外でやろうかとなってしまいますから、得をするのは海外の会社になってきます。長期的展望を持ってほしいと感じます。
Q:今後の目標をお聞かせください。
がん自体、先進国に特化した病気とも言えます。おそらく途上国の場合ですと、がんに至る前に別の病気で亡くなる患者さんが多いという面があると思います。ですからがんで亡くなる人が多いのは、言い換えれば他の病気で亡くなる人が少ないとも取れますから、それなりに良い治療があるとも言えます。
先ほどの透析なども良い例で、日本では透析さえしていればほとんどの場合助かります。がんで死ぬのは良いことではありませんが、ご家族もご本人も準備ができますし、言い方を変えれば寿命とも言えるかもしれません。また早期に見つけて治療すれば、治る可能性も十分にあります。
厄介ながんと言うと、やはり膵臓がんですね。なかなか見つけにくいと言われています。そこも筑波大学の先生とともに、新しい治療方法を見つけるべく、研究を進めてまいりたいと思います。(了)
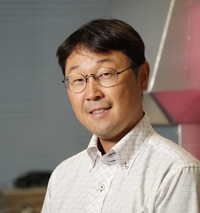
荏原 充宏
えばら・みつひろ
物質・材料研究機構 准主任研究者
1975年東京都生まれ。早稲田大学理工学部応用化学科卒業後、2004年に同大学院博士後期課程修了。
2004年、米国ワシントン大学バイオエンジニアリング学部 博士研究員となり、3年間の研究ののち、2007年に大阪大学医学部附属病院未来医療センター 特任助教。
2009年から物質・材料研究機構に赴任し、2016年にはMANA准主任研究者となる。近年では2015年から2017年まで、東京大学大学院工学研究科 非常勤講師を務める。また、2015年より東京理科大学連携大学院 准教授、2016年より筑波大学連係大学院 准教授、2017年より米国ワシントン大学バイオエンジニアリング学部 客員研究員も兼任する。
