これまで生命の神秘に覆い隠されてきた細胞内のメカニズムが、次々と開発される画期的な観察技術によって、急速に解明されつつある。世界中の研究者の注目を集める超解像顕微鏡「SCLIM(スクリム)」を開発した中野明彦教授は、この分野を牽引する研究者だ。中野教授の活躍の場は、細胞生物学研究や顕微鏡開発だけに留まらない。研究機関の垣根を越えて日本の学術基盤を強化するための試みが中野教授を中心に始まっている。生物学について、そして今後の基礎研究のあり方について、語って頂いた。
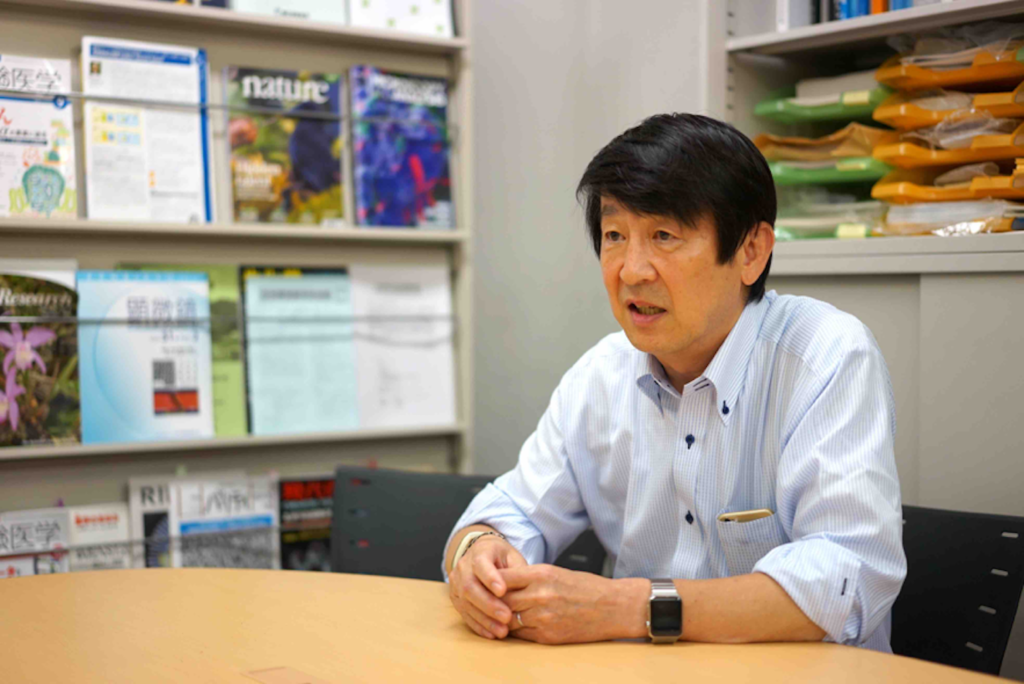
Q:現在の研究内容とは?
専門は細胞生物学です。その中でもタンパク質の細胞内輸送、つまり細胞内でタンパク質が運ばれる際に、はたらくべき場所まで到達するまでのさまざまな過程を研究しています。細胞内では、細胞小器官、つまり膜で仕切られた区画が、それぞれ独立した機能をもち、相互作用しています。その間をつなぐ輸送の過程で、膜と膜、区画と区画の間で、小胞とよばれる小さな膜の袋が走り回っています。それを膜交通とよびます。行き先を間違えたり、ぶつかったりしないように交通整理が必要です。細胞内の膜交通、英語でメンブレントラフィックといいますが、その研究に携わって、もう40年近くになります。
高校の教科書にも書いてあるように、細胞には核があって、小胞体があって、ミトコンドリアやゴルジ体があります。電子顕微鏡で見ると、細胞の中にはびっしりこれらの細胞小器官が詰まっています。その混み合った中で、細胞の遺伝情報(DNA)に従って作られた多種多様のタンパク質が、小胞体やミトコンドリア、ゴルジ体など、それぞれはたらくべき場所に正しくたどり着かなくてはなりません。そのメカニズムを知ることが細胞生物学の大きなテーマの1つです。
私が目指しているのは、この過程を目で見ることです。細胞は小さいので、目で直接見ることはできません。顕微鏡が必要です。19世紀に光学顕微鏡が普及しましたが、光学顕微鏡では細胞の中のさらに小さい構造はなかなか見ることはできませんでした。20世紀に電子顕微鏡ができて、ようやく微細構造が見られるようになったのです。しかし、電子顕微鏡による観察には、試料を固定して真空中で電子線を当てる必要があり、生きたままの状態の細胞は見られません。そのため、細胞に何が起こっているのかは固定細胞の静止画像から想像するしかなかったのです。それでも、生化学、遺伝学、分子生物学などの発達で、いろいろなことがわかるようになりました。この分野の先達が2013年にノーベル医学生理学賞を受賞しており、この分野の研究の重要性が認められたことをうれしく思っています。
「生きたまま見る」を追求
実際に生きたまま目で見ることの意義は、非常に大きいものです。1つ1つのことを証明するのに、大変手間のかかる検証作業を経る必要がなくなり、見たままに事実を伝えてくれるのですから。もちろん、得られた観察結果の解釈のためにも実証実験は必要です。しかし、「今起こっていること」をありのままに目で見られたら、それまでの考え方がまるで間違っていたということが一目でわかってしまうこともあります。私は、1990年代後半に「生命活動を生きたまま目で見る」ライブイメージングという方法論に手を染め、そのおもしろさに魅せられたまま今日まで研究を続けてきました。
仮説ベースだった生物科学
生物科学という分野はもともと、生化学や遺伝学の実験結果、それから電子顕微鏡の像などから、想像して仮説を立てて検証するという学問です。根本的なことが理論的に解明できていないので、たとえて言うなら、「1 + 1 = 2である」ことを示すために「1 + 1 = 0ではない」、「1 + 1 = 1でもない」「3でもない」と延々否定していって、10くらいまで否定したところで、ようやく「だから多分1 + 1 = 2だろう」と結論するのです。これが今までの生物学、生物科学でした。 そのため、「これ以外の解はないだろう」という相当強い確信をもったとしても、実はそれ以外の解がある可能性を否定することができていません。
こういった生物学の曖昧さに決着をつける有力な方法に、生きたまま細胞を精密に観察するライブイメージングがあるのです。生細胞内で何が起こっているのかを目で見て確認できれば、さまざまな問題を一気に解決する可能性が広がってくるでしょう。それは生物科学者の長年の夢でした。そしてそれを可能にしたのが、2007年にノーベル化学賞を受賞された下村脩先生の、クラゲの光るタンパク質の発見でした。緑色蛍光タンパク質GFPの発見が、生物科学における非常に大きな革命となったのです。
GFPは、構成アミノ酸の自発的化学変化によって光る(蛍光を発する)構造を作ります。単一の遺伝子から作られているので、そのDNAをさまざまな細胞に取り込ませるとその中で光ってくれます。よい顕微鏡があれば、自分が光らせたい部分を光らせて見ることができます。ミトコンドリアやゴルジ体の挙動を生きたままで見ることができるのです。
この技術が1990年代の後半に成功したことで、細胞を生きたまま見るライブイメージングの世界が一気に進歩してきました。だからこの分野はたかだか20年ほどの歴史しかないのですが、今や生物科学の世界では、GFPを使ったことのない研究者はほとんどいないのではないかと思うほど、必須のツールになりました。
Q:GFPの発見によって、生物学の研究が一気に進んだのですか?
はい。しかし、顕微鏡がよくないと、せっかくGFPを使ってもぼんやりと光っているような像しか見えず、あまり大したことはわかりません。そのため、理化学研究所(理研)に着任したとき(1997年)、「なんとか光学顕微鏡で細かい像まで見られるようにしたい。そのためには非常に性能のよい顕微鏡が必要だろう」と考えていました。そうした顕微鏡に求められる能力がいくつかあります。まず「空間分解能」と「時間分解能」、つまり小さいものや速く動いているものを見る能力です。また、少数の分子を観察するためには撮影するカメラの感度がよくないといけません。それから、細胞内では空間的広がりの中でさまざまな方向の動きがあるので、それを3次元的にちゃんと追える必要があります。また、GFP本来の緑の光1色でできることは非常に限られており、輸送を見るためには少なくとも2色は欲しい。それから、2つの区画の間をものが行ったり来たりする様子を見たいなら、3色が必要、ということになっていくのです。だから、できるだけたくさんの色を同時に見たい。これらのいくつもの要求が同時に達成できなければ、ライブイメージングによって膜交通のメカニズムを解明することはできないのです。
はじめにこう考えたのはまだ東京大学の助教授の時代でしたが、誰に話しても「無謀だね」と言われたのですよ。しかし理研に移ってきてみると様子が違いました。ここ理研・和光本所は大学とは違って、物理・化学・生物・工学といったさまざまの分野の研究者が同じキャンパスで入り交じって研究しており、分野の垣根が低い環境だったのです。普通、大学ならば理学部、工学部、薬学部などいくつもの学部があり、それぞれの学部の中でまた物理学科、化学科、生物学科のように細かく分かれています。その区分を越えての交流は、なかなか難しい。 しかし理研ではその垣根がなく、私の研究の内容に物理屋さんや工学屋さんが、興味をもって耳を傾けてくれるのです。そして「おもしろそうなことやっているじゃない。どういう装置を使うの?」と聞くので、「これこれこういう性能をもつ顕微鏡を探しているんだけど、これがなかなかないんだよ」と言うと、「じゃあ作ればいいじゃない」という反応がすぐに返ってきたのです。私は「どこかでよい顕微鏡を作っていないだろうか」と探していただけでした。「なければ作ればいい」。目からうろこが落ちました。
それでは!と自ら顕微鏡の開発を思い立ち、いろいろな出会いがありました。民間企業やNHKとも協力しました。そして非常にラッキーなことに、経済産業省傘下のNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)からの委託を受けて、2002年から2007年までの5年間、顕微鏡開発のための大きな予算をいただきました。各社と協力しながら開発を進めた結果、今までの顕微鏡ではぼんやりとしか見えなかったものが、くっきりと、しかもとても速いスピードで動いている様子が見えるようになったのです。
ゴルジ体は普通、扁平な膜の袋(槽)が数枚積み重なった層板状の構造をしています。この構造には方向性があり、新たに合成されたタンパク質(積み荷とよびます)が入ってくる側をシス、分泌に向けて出て行く側をトランスとよびます。シス槽に入った積み荷タンパク質に対して糖鎖修飾などのさまざまな生化学反応が始まり、シスからトランスに向けてさらに次第に反応が進んで、最終的に完成したものがトランス側から出てきます。このシスからトランスへ「積み荷がどうやって運ばれているのか」というのが大きな問題でした。これを説明する有力な仮説が2つありました。
第1の説は、積み荷タンパク質の入った小胞が、槽から出芽して次の槽に融合するということをシスからトランスへ順繰りに繰り返すと考えます。つまり、安定な区画である槽の間を積み荷を積んだ小胞が順番に進んで行くと説明するモデルです。しばらく皆が信じていた説ですが、それでは説明できないことがいくつか出てきて、別の説が唱えられるようになりました。
第2の説は、新しい槽が次々に作られると考えます。まずシス側に新しい槽が作られ、また次に新しいシス槽ができて、そのたびにすでに作られた槽はトランス側に向かって前進していき、トランス側の一番端にきた槽がバラバラになって次の目的地へ進むと考えるのです。槽がシスからトランスに向けて前進する過程で槽の性質が変わっていくので、この第2の説は「槽前進/槽成熟モデル」とよばれています。第1の説は、動かない槽の間を小胞が進んでいくので、「小胞輸送モデル」といいます。このどちらが正しいかを巡って長い間論争が続きました。
槽成熟モデルで重要なことは、槽が移動するにつれてその性質が変わっていくということです。多くの生物種でシスからトランスにかけて5〜6枚の槽が並んでおり、それぞれに酵素が大量につまっています。小胞輸送モデルは酵素がずっと同じ場所に「いる」という考え方ですが、槽成熟モデルでは、最初にシスの性質をもっているものが、トランス方向に進みながら次第に性質を変えていく必要があります。そのためには、酵素の方がトランスからシスに向かって小胞で逆行すると考えます。ちょっと虫のいい説明ですが、この酵素の逆行輸送で槽が成熟できることになるのです。電子顕微鏡で観察するとゴルジ体の回りには多数の小胞が見えますが、それがシスからトランス方向に積み荷を運んでいるのか、トランスからシス方向に酵素を運んでいるのかは、動きがわからないので判断できません。
一方、ライブイメージングならこの論争を解決できるはずです。まずゴルジ体に色をつけます。たとえば、シス側をクラゲのGFP、緑色の蛍光タンパク質、トランス側をサンゴから取れる赤い色の蛍光タンパク質、RFPで標識します。それらが混じり合う中間の部分は、光としては黄色になります。小胞輸送モデルが正しければ、区画(槽)は永久に安定なはずなので、色は変化しないはずです。一方、槽成熟モデルが正しければ、シス側の何もないところに緑色の槽ができて、緑から黄色、赤へと変化していき、最後はバラバラになってなくなることになります。両者の違いは一目瞭然のはずです。しかし、ここで1つ大きな問題がありました。そもそもゴルジ体は、直径が500-1000ナノメーターくらいの大きさしかありません。槽の厚さは数十ナノメーター、槽と槽の間隔は10ナノメーター以下と、普通の顕微鏡では到底1つ1つの槽を見分けられません。私たちは、モデル生物の1つ、酵母の利点を活かしました。酵母は不思議な生物で、ゴルジ体の槽が層板状に重なりません。そのため、緑、黄色、赤に塗り分けられた槽を、非常に容易に判別できるのです。「これなら色が変わるかどうかわかるかもしれない」と思って実際に観察してみたところ、槽の色が緑から黄色、そして赤へと次第に変化していく様子が明瞭に見てとれました。これは小胞輸送モデルでは決して起こらないはずのことです。決着!です。
たった1つの動画で、決着がついた
極端な言い方をすれば、たった1つの動画で10年以上続いた論争に決着がついたのです。ライブイメージングの威力です。この実験で、その素晴らしさを心底から感じました。本当に文字通り、百聞は一見に如かず、です。よく、「ただ見ているだけじゃないか」と言われるのですが、ただ見るだけでこれだけ明確な答えをくれるのですから、それがライブイメージングのすごさを物語っているでしょう。もちろん、その後「どうやって色が変わっていくのか、なぜシスからトランスへの一方向だけなのか」など調べなければならないことがたくさん出てきます。1つの謎の解決は新たに10の謎をよぶ、といわれますが、それまた楽しからずや、でしょう。まずは、最初のとっかかりとして、従来信じられていた説が間違っていたことを、この動画1つで証明できたのです。
生物学では、「細胞は、もっているもの(DNAでも細胞小器官でも)の量を2倍に増やして、細胞分裂してできる2つの娘細胞に渡す。つまり細胞小器官は永遠に引き継がれる安定なものだ」という考え方が定着していました。ところが槽成熟の考え方はそうではなく、次々に新しいものができては消えていく。つまり、細胞小器官の存在はダイナミックに変化しうるものであることを示したのです。これは、細胞生物学における大きなパラダイムシフトになりました。 私たちがこの仕事を2006年に論文発表した結果、細胞生物学の多くの教科書に長年載っていた小胞輸送モデルが、槽成熟を示すモデルに書き変わりました。教科書に載るような発見というのはうれしいものですが、教科書を書き換える発見というのもそれに劣らず、いやそれ以上に気持ちのよいものです。この仕事の後も、膜交通のメカニズムに関する問題に次々に取り組んでおり、新しいことを見つけては今までの説をくつがえしているところです。細胞生物学の教科書はこれからもっと早いスピードで変わっていくと思いますよ。私もこれまで教科書や解説書などいろいろ書いてきましたが、その内容も自分で直さないといけないことばかりです。
細胞内輸送の魅力にとりつかれる
Q:約40年の研究生活の経緯を教えてください。
子どものころは病気がちで医者によくかかっていて、自分も医者になりたいという気持ちが強くありました。医者という職業で、患者さんの病気を治すことも素晴らしいことだろうけれど、病気の原因究明など、医学の進歩に貢献するような研究もしたいと考えていました。つまり基礎医学の道に進みたかったのでしょうね。しかし、同時に物質の成り立ちを知ることなど、物理学にも非常に興味をもっていました。いろいろ悩んだあげく、物理を専攻するつもりで東京大学の理科I類に入りました。
ところが、大学に入っていろいろ勉強してみて、生物科学の分野に膨大な数の未解決の問題があることを知りました。「これからは生物科学、生命科学の分野の方がおもしろい発見がたくさんあるのではないか」と、いとも簡単に気が変わり、理学の中での新しい生物学分野に進んでみようかなと思ったのです。理Iから理学部の生物化学科に進学しました。
いろいろなことに興味をもち続けながら大学院も生物化学専攻に進み、翌年には博士の学位を取って就職するというタイミングで、国家公務員試験を化学で受けました。研究室に残る道もあったのかもしれなかったのですが、実は学生結婚をしていて妻が働いて稼いでくれていたので、早く自分の職を得たいと思ったのです。
そこそこの成績で合格して、採用が決まったのが厚生省の国立予防衛生研究所(今の国立感染症研究所)の研究員でした。そこでウイルスや免疫の生化学的研究を始めたのです。研究を進めるうちに細胞内輸送の問題のおもしろさに気がつきました。たとえば、ウイルスが細胞に感染して増殖するときに、ウイルスは細胞を騙して自分のタンパク質を作らせて、細胞外に出てくるのですが、このときのウイルスタンパク質の挙動はまさに細胞内輸送そのものです。その当時、1980年ころの話ですが、細胞内輸送の分野はまだほとんど未踏の世界で、小胞体で作られて細胞の外に出るまで、何が起こっているか、まるでわかっていませんでした。「これはおもしろい、このテーマを攻めてみよう」と実験に没頭し、これが結局私のライフワークになりました。
1984年に、カリフォルニア大学に留学しました。酵母の遺伝生化学を学びたくて、ランディ・シェクマンの研究室に行ったのです。彼は若くしてバークレー校の教授になった大変優れた生化学者で、のち2013年にノーベル医学生理学賞を受賞します。バークレーでの研究生活は非常に楽しかったですね。ここで酵母の膜交通の分子機構に関わるいくつかの手がかりを得たことが、現在の研究に続いています。
Q:研究環境の違いなどは感じましたか。
そうですね。アメリカから帰ってきて、国立予防衛生研究所の主任研究官に昇進して、少し自由に研究ができるかなと思ったのですが、勝手な研究テーマは許されなかったし、やはり国民の予防衛生に役に立つ研究をしなくてはいけないというプレッシャーがありました。もう少しのびのびと研究をしたいと考えていたときに、東大の理学部生物学科にいた安楽泰宏教授に声をかけていただき、講師として着任することになりました(2016年のノーベル賞医学生理学賞を受賞した大隅さんの後任でした)。理学部というところは、すぐに役に立つことを目指すのではなく、基礎研究にじっくり取り組むことを尊ぶ学部です。学生時代からなじんだその環境で、いろいろと新しいことを見つけることができました。教科書に載る発見もしました。東大理学部には講師および助教授として9年間いたのですが、教室のルールで教授の定年退職のときには研究室を閉じ、助教授も辞めなくてはなりません。幸運なことに、そのタイミングで理化学研究所の主任研究員に採用してもらうことができ、1997年から、和光市にある理研本所で「生体膜」研究室を主宰することとなりました。
理研は、基礎研究を行なう上での自由度は大学と全く変わらない環境でした。1つ大きく違ったのは、先にも言いましたが分野の垣根の低さです。そのおかげで、顕微鏡開発のような思い切った舵取りが可能になったのだと思います。理研はプロフェッショナルな研究を行なう機関で、教育機関ではありません。学生もいるにはいますが、大学から預かっている形です。基本的には皆がプロの研究者なので、こちらが手取り足取り教えなくても、「こういうテーマでどう?」とアドバイスするだけで、どんどん研究を進めていってくれます。研究効率が非常によく、次々に成果が出てくるのが楽しくて仕方がありませんでした。
しかし、ずっとプロのメンバーと研究をしていると、無垢な学生が入ってくる楽しみがないことに気がつきました。大学にいると、毎年新しく入ってくる学生の中には、物を知らない、でもやたら元気だけあるような輩が結構いて、そういう連中に研究のおもしろさを教え、「こういうことをやってみない?」と引き込んでいく。そういう楽しみが、私には忘れがたかったのです。そんなときにまた東大から、教授として戻ってこないかと声がかかりました。理研で、顕微鏡開発を含め、いろいろおもしろい仕事が動き出していたときだったので、非常に悩みましたが、「理研をどうしても辞めたくないので、兼任させてくれるなら」とわがままを言い、結局それが通って東大理学部教授と理研の招聘主任研究員を兼任することを許してもらいました。それから13年経ち、主任研究員の職は定年退職しましたが、光量子工学研究領域のチームリーダーという形でラボをもち、いまだに東大と理研の二足のわらじを履き続けています。
Q:理研の風土を、大学に持ち込むようなことはされているのでしょうか?
ええ、そういった努力をずいぶんしてきましたし、ずいぶんよくなってきたと思います。少なくとも学科を越えてさまざまな取り組みを行なう動きが盛んに出てきました。現在東大の総長をされている五神さんも、もともと、理学部の物理学科から工学部に移られて、また理学部に戻ってきた方なので、その活躍もあって理学部と工学部の交流もよくなりました。またその交流の間には理研が入ったりもしており、よい関係で分野の交流ができ始めていると思います。一方、現在は理研の方が巨大になり、和光、筑波、播磨、横浜、仙台、神戸、大阪と多くのキャンパスに多くの研究センターがありますから、その中で交流するのが少し難しくなってきたと感じることもあります。その間を横断的につなぐことがとても大事で、戦略的研究展開事業などとよばれる理研の横断的なプロジェクトがいくつか進められています。私が代表を務めているのが「4D細胞計測」というプロジェクトです。3次元の空間的な広がりに時間軸を加えて、生きた細胞の計測を、細胞内の極微細な構造から大きな組織の深部まで、そして超高速の速い動きから何日にも及ぶ長期間まで可能にし、「4次元をきわめる」ことを目指しています。単に3D動画で観察することだけでなく、それを定量的に測定して、さまざまな操作を加え、さらに数理モデルを立てたりデータ主導によるコンピュータ解析を行い、シミュレーションした結果をまた実験にフィードバックする、そういうプロジェクトを始めて4年になります。理研のいろいろなキャンパスの30以上の研究室チームを加えて、新しい顕微鏡を使った最先端のイメージングや、さらに新しい技術開発をしようと取り組んでいます。生物屋だけではなく、物理、化学、工学、数学、情報の人たちにも加わってもらっている、とても理研らしいプロジェクトだと思います。
Q:今後、学生や政府、企業に期待していることはありますか?
現在、大学では、基礎研究どころか、そもそもアカデミアに残ろうと考える学生が減ってきています。大学院の進学率は下がってきており、また大学院に入っても修士で就職してしまい、博士課程に進まない学生が多いという現状です。理学部は元来アカデミアを志向する学生が多く、博士の学位を得て大学に残り、大学の先生になりたいと志すのが普通でした。しかし現在では、東大理学系でも修士修了者の半分くらいしか博士課程に進まなくなっており、非常に深刻です。 その原因の一つは、学位取得後の安定した職がない、いわゆるポスドク(ポストドクター)問題にあります。ポスドク1万人計画などの政府の施策により、ポスドクのポストはずいぶん増えました。科研費などの資金で採用することも簡単にできるようになりました。しかし、ポスドクの職までは見つけられるのですが、任期制なので2〜3年、長くてもせいぜい5年で辞めなくてはなりません。次の定職が見つからないので、また別のテーマでポスドクをする。そういうサイクルを繰り返して、最近では40代でもポスドクという人が増えています。学生は、先輩たちが40歳を過ぎても定職がなく苦労しているのを見たら「あのようにはなりたくない」と思うでしょう。だから、頭のよい優秀な学生ほど早く研究に見切りをつけて、「大学に残っていたっていいことはないから、官庁や企業に行こう」と思うのですね。官庁や企業に優秀な人材が行くことは、それはもちろんよいことではあるのですが、アカデミアに優秀な学生が残らないと日本の学問、知のレベルが落ちていく一方ではないですか。
ポスドク問題を何とか解決するのは我々の責任でもあり、日本学術会議はじめさまざまな科学コミュニティで努力しているのですが、残念なことになかなか簡単には変わりません。それでも「学問、研究はこんなにおもしろいのだよ」ということを1人でも多くの学生に伝えたいですね。学生にももう少し頑張ってもらいたいと思います。諦めないでほしい。近年、企業でも博士採用、あるいはポスドク採用をするところがずいぶん増えています。現在2万人近いポスドクがいるのです。非常に高学歴で優秀な人材が大勢、職がなくて困っているので、ぜひ彼らを有効活用して下さいというお願いをしています。アカデミア、研究の道に進みたいと考える学生たちに少しでも勇気を与えたいという気持ちがあります。
政府は、資源の乏しいわが国では科学技術立国が必須であると言っています。また「イノベーション」という言葉が声高に言われるようになって、さまざまな技術革新が社会の経済活動の新しい原動力になるのだという考え方が広がってきています。研究も、自己満足にしかならない基礎研究ではなく、社会の役に立つ研究をしろと言う声が聞こえてきます。もちろん、税金を使って行なうことですから、役に立つのかと問われることは当然のことだと私も思います。しかし、明日すぐに役に立つ研究ばかりが大事ではないでしょう。10年後、20年後、あるいはもっと先の将来に役に立つかもしれない基礎研究に投資しないと、実りは必ず細ってきてしまいます。役に立つという考えが行き過ぎると、研究者たちが自由な発想で取り組む基礎研究ができなくなり、日本の科学が滅んでしまうのではないかととても心配しています。
21世紀に入ってからの日本のノーベル賞受賞者数は世界第2位です。毎年のようにノーベル賞受賞者が出て、国際的にも高く評価されていますが、ノーベル賞に値するような研究には20-30年という時間がかかります。最近の受賞者の研究の多くは、1980年代、1990年代の、国が基礎研究に積極的に資金を投入していた時代に始まっています。のびのびとよい研究をすることができた時代の成果がいま実を結んでいるのです。現在は、といえば、大学や研究機関の運営費は大幅に削られ、外部資金を申請する際にはしばしば「波及効果」や「何の役に立つか」を書かないといけません。すぐ役に立つことばかりに自分の研究をゆがめていって、目先の成果を出すような研究だけを行なっていたら、日本の基礎研究はガタガタになってしまうと憂えます。イノベーションも応用研究も大事ですが、それと同じくらい基礎研究も大事なのだと声を大にして言いたい。実際そう言い続けています。つい先日ノーベル賞医学生理学賞を受賞した大隅さんも、基礎研究の重要性、すぐに役に立つのではない研究の重要性を強く訴えていました。全く同感です。あのような純粋基礎科学から大きな研究を成し遂げたことの素晴らしさを、もっともっと多くの人が認識してくれるといいなと心から思っています。
Q:自身の研究において中長期目標などは設定されていますか?
せっかくこれだけさまざまなものを生きたまま見られる顕微鏡を開発したので、とことん見てやりたい。そして、今まで自分が知らなかったことを、1つでも多く知りたいと思っています。というのも、もうわかったことだと思われていた生物科学の定説の多くが、実は空想でしかなかったのではないかと強く思うのです。1つでも多く正しいことを発見して、間違ったモデルを書き換えていくことが大きな目標です。あと何年現役の研究者を続けられるかわかりませんし、自分自身でできることには限界があるでしょう。でも、若い研究者たちがその後を継いで、ありのままの現象をしっかり見ていってくれればと思います。
また、私たちが理研で製作したSCLIM顕微鏡がいま3台あるのですが、ここで使っているだけではもったいないと思っています。もっと広く普及させて、いろいろなところで使ってもらいたい。できれば、世界中の研究者がこの顕微鏡を使って研究できるようになったらいいですね。実際、国際学会で発表するとよく言われるのですよ。「お前1人で独占するなんてずるい。俺たちも使いたい」とね。一つの方向としては、私たちが開発した顕微鏡を商品化して世に出すということもあるだろうと考えています。研究者がビジネスを始めるのはなかなか難しいことだと実感しているところですが、将来、国内はもちろん世界中の人たちが使ってくれるようになったらすばらしいでしょうね。それでさらに1つでも多くの謎が解ければ、すごくうれしいことだと思います。< 了>

中野 明彦
なかの・あきひこ
東京大学大学院理学系研究科教授、理化学研究所光量子工学研究領域チームリーダー。ライブイメージングなどの多角的な手法を用いて細胞の膜交通のメカニズムを探究する。その研究を評価され、2000年の井上学術賞、2012年の文部科学大臣表彰・科学技術賞など数々の賞を受賞している。国立予防衛生研究所(現国立感染症研究所)、カリフォルニア大学バークレー校留学などを経て現職。
