「医工連携」領域の研究においては、倫理的に検証の難しい医療分野の問題を予測・解決する手法として、計算によるシミュレーションが有効である。こうした視点から、電磁界や熱などの物理的負荷によってヒトの体内で生じる物理量と、それによって誘発される生理応答を統合し、計算機上でモデル化する手法で注目されているのが、名古屋工業大学大学院工学研究科/電気・機械工学専攻の平田晃正教授だ。 携帯電話が出す電波の人体に与える影響を調べる技術から始まり、現在は分野横断的な研究に取り組んでいる平田教授に話を伺った。

医工連携・異分野融合するための技術開発
Q:研究の概要を教えてください。
「生体」におけるシミュレーションを、複数のテーマで研究しています。
シミュレーションによる予測技術が本当の意味で進化すると、AIではなくシミュレーションですべてが可能になると予想されています。新しいことに取り組むとき、まずはシミュレーションというのが当たり前になっていきます。
そのなかでなぜ、生体におけるシミュレーションかというと、AIだけではどうしても足りない部分があるためです。医療では症例数が少なかったり、個人差が大きかったりするため、AIに学習させる十分な蓄積データがないという課題があります。ここが着眼点になります。
私たちは当初、ヒトの物理現象のシミュレーションしかしていませんでした。すると何が起こったかというと、医師と会話ができないことが判明したのです。医師は体の中の物理現象がどうであっても、「そうなんだ」で終わってしまいます。理解してもらえないのです。物理現象によって、何が起こるのか・人がどう反応をするのか、そこまで説明できないと、会話が通じません。
医工連携の成功例が多くない原因もここにあります。分野が多すぎて用語も異なり、会話がマッチしないため、何が必要なのかお互いに分からないし、伝えきれない。
ここで有効なのが、シミュレーションなのです。AIはインプットしたものに対してのデータは出てくるのですが、良質なデータを学習していないと出力結果に十分な信頼性が得られません。その良質なデータを、高度なシミュレーション結果が補ってくれると考えています。医師と医工連携・異分野融合するための技術開発が研究概要だといえます。
計算結果を医師にどう理解してもらうかをテーマに研究を取り組んでいると、必要な着眼点がわかってきました。ヒトというのは、体内で生じた物理に対してどう反応・応答するのか。ここまで一貫してシミュレーションできなければ、意義のあるものにはなりえません。
さて、ここで生体における物理といっていますが、実際にはそのほとんど電気か力学です。世の中の研究者のなかで、電気と熱を同時に扱い、その生体の応答をさらに複合的に見る私のような研究者は数えるほどしかいません。その意味では、独自性を出しやすい分野だと感じています。
Q:研究の実際の題材として、電気自動車・脳・熱中症など多様なテーマに取り組まれています。これらの題材は、どういった選び方をしているのでしょうか。
まず、電磁界の安全性についてですが、電波法なども含めて我が国の法に関わる部分です。携帯電話も一定出力以上を出してはいけませんよね。こうした規則を作るために、私が最初に取り組んだのが物理シミュレーション、中でも電気と熱の複合シミュレーションでした。
次に、電気自動車に取り組んだのは、自動車産業が強い土地柄もあるかと思います。当時、総務省の検討会を介して自動車メーカーの担当者をご紹介頂いたのですが、そのときの課題が無線充電する電気自動車の安全性でした。昨今、プラグインハイブリッドが叫ばれていますが、ワイヤレスで充電しようとしたときに周囲に漏れる電磁界がどうなっているのか、人に本当に影響がないのかという課題を明らかにしたいというご要望でした。
安全性を検討することは、効率的に電波を出す、あるいは充電の効率を上げる、ロスを少なくするということと同じです。そのため、安心・安全性に加えて皆さんに安心して頂くデザインをすることで、高効率な機器デザインにも繋がってくるんですよね。こういった意味で行政に貢献しているというのが、電気自動車とスマートフォンなどの安全性に関するテーマだといえます。また、この研究は、全体像としての複合的なシミュレーションのスキルがあったとしたら、その一部として電気の部分を切り出したものになります。
Q:続いて、脳への電気刺激研究について教えてください。
例えば脳疾患の治療や診断のために、脳に電気刺激を与えるシーンがあります。これが本当に安全なのか、副作用のリスクを減らすにはどうしたらいいか、また余計なところを刺激しないためにはどうすればいいか、などが課題となります。
脳外科の手術では、手術前に患部の位置をある程度特定するのですが、同時に脳機能の推定も必要になります。それらをより明確にすることができたら有用ですよね。開頭手術を行ったときに検査をする手間を省くことができるため、手術の時間の短縮にも貢献できるだろうと着目しました。これは、執刀数が日本で最も多い東京女子医科大学との共同研究になります。手術では、デバイスを使って脳を刺激し、神経の反応を見極めるということが行われますが、これまでは、医師の経験に頼っている部分がほとんどでした。その部分に少し物理的知見を加えることによって、今後改善できる可能性を見出していきます。
Q:続いて、 熱中症研究について教えてください。
熱中症について研究に取り組み始めたときに最初に気づいたことですが、医師の視点からすると、事後のことしかわからないんですよね。彼らは、搬送されてきた人のことしか正確にはわからない。ということは、熱中症になる過程を再現することによって、少し視点を変えた啓発活動ができるんじゃないかと考えています。
私たちの生活で極限の環境はサウナで、その中に人がいた場合、体温はどうなっていて、汗をどうかいているか。そこがシミュレーションできたら、私たちが健康で生活をしていく上でのすべてのシミュレーションはできるはず、それを応用しています。
熱中症になりやすい日を考える際、一日中暑い日というのは容易に想像できますが、もっと言えば、高齢者の場合は「三日間」暑い日が続くとさらにそのリスクが高まります。これは恐らく水分の損失だと予想しているのですが、こうした仮説をシミュレーションで解析、検証していきます。一方、若い人はどうかというと、過度な労働とかスポーツをやったときの熱中症は、当日の暑さのみに影響されることを立証できました。
気象データなども含めて複合的で詳細なシミュレーションをすれば分かります。AIでは、気象データを入れてこういう数字が出た、というところまではできますが、そこに「なぜ」という道筋、解答はありません。一方、シミュレーションはそこの「なぜ」を詳細に再現することができます。結果的に、どこまでだったらリスクが十分小さいのかということが言えるわけです。熱中症予防では、この「どこまでであれば、大丈夫か」がとても重要です。
この技術の実用化されている例として、日本気象協会が出している「熱中症セルフチェック」があります。これはGPSの位置情報を使って位置を割り出し、気象データと連携、そこに活動と年齢を記入すれば、どれくらいまで活動をしていいか、そしてどのくらい水分が失われるのかということがわかります。
新型コロナウィルスの問題も同じなんですけれど、どこまで我慢すればよいのか、大丈夫なのか、絶対ではないにしても、そういう情報、目安が欲しいじゃないですか。暑い日に「動くな」というのは簡単ですし、活動しなければ熱中症にはなりません。でも現実問題、暑い日でも動かないといけない場合もあるわけです。そこを科学することで、私たちの生活を豊かにできる。ここに、大学が取り組まなければならない課題が見えてくると感じています。
基礎から得られた知見をデバイス開発へ
Q:研究における課題としてどんなことを感じていますか。
今まで基礎研究が多かったので、この基礎から得られたことをデバイス開発に繋げていきたいなと感じています。
実際、医療機器を開発するときに絶対にシミュレーションが必要だと思います。日本はそれが弱いと感じています。アメリカでは、大学と企業が連携してシミュレーションで予測するという研究がさかんに行なわれています。医療機器の開発において、安心・安全・設計を考えた際、確実に私たちの技術が必要になるだろうと思っています。相談を頂くと、どうそれを繋げていくか、もう少し新たな要素を加えないといけないというのは当然出てきます。
例えば、物を触った時にピリっとくる電気現象。これって電気的なモデル側は多く研究されているのですが、実際には物を触った瞬間に力学的な触覚も働いているんですよ。しかし、両者を組み合わせた研究はない。複合的な人の感覚っていうものはどれだけ触っているかでも当然変わってきますので、ここまでモデル化できないかと考えています。
私は、こうした一連の流れをこれまで何度も経験してきました。そういった意味で課題というよりも、シミュレーションを組み合わせて実問題をいかに解いていくか。もうこれしか残っていないと思います。
Q:この分野を志す学生にとって必要なことは何でしょうか。
この分野を志す学生さんがいたら、心の底から自分で新しい分野を作りましょうよと伝えたいですね。うちにあるベースというのは他にはないので、そこに何か加えただけで新しくなるんですよ。その新しいところを目指して行こうよと伝えています。
昨今、日本人学生が就職をしたときに困ることとして、自分で考えることができないという声をよく聞きます。その点、うちの学生は確実に強いです。学問的ベースがあって、課題発見力と課題解決力の両方がある。分野外の人と共同研究をするので、説明能力もつく。ということで、就職の際に尋ねられることはもちろん、就職した後に求められる力も自然と身についていきます。
Q:世の中の企業と、どんな関わり方をしてみたいですか。
人と関わる、電気か熱のことをやっているところとはお話してみたいですね。おそらく、何かしらで役に立つことはできると思います。実際に、現在もやらせて頂いたりはしているんですが、ベースになるのは、面白い研究がしたいという思いです。この「面白い研究」に関する課題というのは、どこかの企業が持っているテーマというよりは、ある特定の企業さんの、常にユニークな考えをお持ちの研究者さんと共同でやるというのが面白いと思うのです。
ごく稀に、そこまで考えてものづくりをやっていたのかという人に出会うことがあります。それだったらうちの技術使えるよ、お手伝いできるよ、と言います。企業にメッセージというよりも、企業の研究者さんにもう少しオタクになって欲しいかな。企業の人で同じ部署ですごい商品開発をするんだって調べてくる方がいらっしゃるんですけど、そこにもう少し最先端の基礎技術をスパイスとして与えてあげられると良いものができると思いますね。
Q:今後の近い目標を聞かせてください。
現在、この分野で研究をやっていて、前に誰もいない状態が続いていますし、新しいことしか目指していないので、目標は具体性がないです。ただ、先に述べたように、シミュレーションでできるだけ再現してやりたい、それを予測技術に生かしたい。その意味で、今の状況には、非常に満足しています。この状況を楽しみつつ、1つでも2つでも新しいことにはチャレンジしていき、それが実際に社会に反映されたらと考えています。(了)
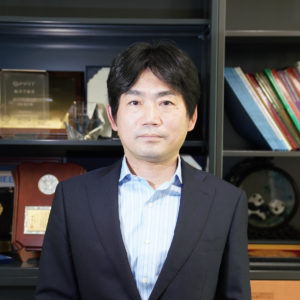
平田 晃正
ひらた・あきまさ
名古屋工業大学工学研究科 教授、先端医用物理・情報工学研究センター長。
1996年3月 大阪大学工学部 通信工学科 卒業。2000年大阪大学通信工学博士課程 修了。工学博士。
大阪大学大学院 工学研究科の助手を経て、2005年より名古屋工業大学工学研究科助教授となる。
2007年より同 准教授、2016年より現職。
