細胞をプログラミングし、従来では不可能だった治療を可能にする「合成生物学」が、近年めざましい発達をとげている。こうしたなか、制御原理があまり開発されてこなかった「細胞間コミュニケーション」に注目し、次世代医療に応用可能な形でエンジニアリングすることを目指した研究を行なっているのが、東京大学大学院 医学系研究科生体物理医学専攻 医用生体工学講座 生体情報学分野の小嶋 良輔助教だ。改変した細胞自身や、そこから分泌される微粒子などを新しいドラッグデリバリーシステムとして利用可能とする研究に取り組む小嶋助教に、研究の展望について伺った。

より高機能なモダリティーを薬にする
Q:まずは、研究のニーズについて教えてください。
近年、「プログラミングした細胞を用いて、従来不可能だった疾患治療を可能にしよう」という流れが世界的に出てきています。分野的には「合成生物学(Synthetic biology)」の一部ですが、「生体分子をパーツとして、新しい細胞機能を構築し、これを細胞内にインストールすることで疾患治療細胞を構築する」というようなコンセプトです。 通常薬として用いられる小分子ではなく、生体が利用している高分子であるRNA、DNA、たんぱく質などをパーツにして、うまく機能を構築し、これを細胞に組み込むことで、より高次な機能発揮できる細胞自身を薬として用いることができるようになります。
例えば、がん治療について考えてみましょう。よく用いられる小分子医薬(分子標的薬)は、がん細胞で活性が異常に亢進してしまっているタンパク質に「鍵と鍵穴」のような形でくっついて、その機能を阻害する形で機能を発揮します。
一方、近年盛んに利用されるようになってきた抗体医薬は、特定のたんぱく質に結合する、抗体という機能性タンパク質に薬をくっつけて、がん部位に選択的に薬を運ぶことでこれを殺すというような形で使われます。これらの薬を用いるときには、基本的にがんを特徴づける明らかなマーカータンパク質ががん細胞に発現していることが必要ですが、常にこのようなマーカーが発現しているとはかぎらず、また複雑な免疫系なども関与してくるので、シンプルに一対一の対応で治療できるものばかりではありません。
このような時に、よりハイスペックなセンシング機能を持つ細胞を望むがん細胞を認識して殺すようにプログラミングすることで、従来不可能だった治療が可能になるというわけです。
例えば、患者から免疫細胞をとってきて、そこに特定のがんに発現するたんぱく質を認識し、免疫細胞内にシグナルを流すレセプターを発現させると、そのたんぱく質が発現しているがん細胞を選択的に殺すように免疫細胞をリプログラミングできます。
最近、承認がおりて臨床で使われだしているものがありますが、これは単一のマーカータンパク質を認識するものです。研究レベルでは、この細胞に、例えばマーカーAとマーカーBが同時に発現しているときだけ、これを殺す、というような、さらに複雑なロジックを組み込むことで、さらに高次元な治療が行える、というようなことが示されてきています。
このようなロジックは、ターゲットにする分子やアウトプットとして用いる分子をを変えることで、様々な疾患の治療に応用することができる可能性があります。例えばある病気にかかった時に血中に分泌される疾患マーカーを感知して、その疾患を治療するたんぱく質を分泌するような機能を細胞に組み込んで、この細胞を身体の中に入れておくと、病気になっているということを細胞が勝手に診断して、治してくれる。こういったことも可能になってくると考えられます。
Q:実際にどのような形で研究に取り組んでいますか。
通常のライフサイエンスでは、基本的に、ある仕組みがわかっていない生命現象があったときに、この現象を細分化してトップダウン的なアプローチでクエスチョンを解くということを行います。ある疾患を治療したい、と考えた時には、まずその時に起きている生命現象を理解しなければ治療法を開発することはできませんから、非常に大切なアプローチです。
一方、合成生物学では、少し別の視点から、「これとこれを組み合わせれば、こんなものがつくれるのでは?」というようなボトムアップ的な思考を行います。これまでにわかってきた生物学的知見を組み合わせて「どんな細胞機能を構築できるだろう」という別の視点からみることで、新たなものづくりができないか、ということを日々考えるわけです。(このものづくりの過程で、生命現象の理解自体が進む、という別の素晴らしい面もあるのですが、こちらも話し出すと長くなりそうなので、今回はあまり触れないでおきます)
留学先のスイスで行ってきた研究についてもう少し詳しくお話しすると、私は「細胞間のコミュニケーションを自在に制御する」手法の開発を試みてきました。従来の哺乳類細胞の合成生物学の分野で行なわれてきたことは、主に一つの細胞に注目して、その細胞に何をさせるかという、一つの細胞内である程度完結する機能のプログラミングでした。ただ、がんなどの疾患を、プログラミングした細胞で治療しよう、ということを考えた時には、相手の細胞を感知して、それに対してアクションを起こす、という「細胞間のコミュニケーションを制御する」必要があります。
しかしながら、相手に対して自分がどのようにインタラクションするかを制御するのは、一つの細胞内のイベントを制御するのに比べて難易度が上がるので、従来はあまり行なわれてきませんでした。そのため、ここを開拓してみようかなと考えたのです。
私はもともと化学者(ケミスト)で、ものづくりの基本的な考え方は身についていましたが、バイオロジーを深くやっていたわけではないので、まずこれまでに仕組みの解明が進んでいる細胞の機能を、自身で理解をするところから始めました。研究プロジェクトを発案する段階では、3ヶ月くらいずっと論文を読むことに集中して過ごしましたね。作りたい機能を念頭に置きながら、どういった生体分子を組み合わせればその機能がつくれるのか、宝探しと頭の中での工作を同時に行う感じですね。
アイデアが出てきたら、新しいたんぱく質や遺伝子スイッチを自分でデザインして、それを細胞に発現させて、望む機能が出るかをテストします。もし系がうまく働かなくても、実験結果から失敗原因を推測し、使用するたんぱく質の構造を最適化する等して、フィードバックを何回も繰り返すことで、望みどおりの機能を細胞に発揮させることを試みます。
やっていることは、コンピューターのプログラミングに似ているかもしれません。コーディングして、実際にコンピューターに投げて動かして、ダメなところがあればエラーを修正して、再度プログラムを走らせて、という感じです。
例えば、このようなアプローチによって、特定の細胞の中に生きたまま侵食して行って、自爆しながらターゲットの細胞を殺す機能性細胞を開発することに成功しました。
少し具体的にお話します。自然界では、ある細胞が別の細胞の中に生きたまま侵入する現象が知られているのですが、この際にRhoAという細胞骨格の制御に重要な役割を担っているタンパク質が、侵入する細胞の後ろ側に集まる、ということが知られていました。
ここで我々は、特定の細胞接触が起きた時にだけ、RhoAが細胞接触面の後ろ側に強制的に追いやられるように細胞内のタンパク質の動きを制御してあげれば、その細胞が相手の細胞を侵食できるのではないかと仮説を立てました。
一方、別のCD43というタンパク質は、細胞外に大きなドメインを持つため、細胞が強い相互作用を介してタイトに接触した際に、物理的に狭いところにはいられなくなり、細胞と細胞の接触面から追い出されるという現象が起こるということが報告されていました。大きなものが狭い場所から追い出されるという非常に単純な物理現象です。
以上2つの仮説・実験事実を鑑みて、CD43の細胞外ドメインに、活性化したRhoAを結合しておき、相手の細胞を認識するレセプターと共に発現したところ、相手の細胞の接触に応じてRhoAの局在が望む形で変化し、仮説通りに細胞の侵食を起こすことができました。生きた細胞が特定の生きた細胞の中にインベージョンするように、細胞を“プログラミング”できたわけです。
この他にも、細胞から分泌されるエクソソームと呼ばれる微粒子に自在にカーゴとなるRNAを封入して、疾患細胞に効率的にカーゴを送達して疾患治療タンパク質を発現させ、遠隔から治療を行う機能性細胞なども開発してきました。
今後の研究の方向性としては、「こういうファンクションを出したいけれど、このピースが欠けている」というときに、自分で新しいものを発見・開発することで、今までは不可能だったエンジニアリングを可能にするようなアプローチをしていきたいと考えています。
というのも、これまでは、基本的に報告論文から集めてきた情報をもとにシステムを組み上げていましたが、そうすると研究者たちが同じようなものを参考にして同じようなものをつくるということが起こりがちになってしまう上に、どうしても”proof of concept”を超える本当に有用なシステムができにくくなってしまうと感じたからです。
例えば、先に述べたエクソソームを用いたカーゴ送達のシステムを実際の医療に有用なものにしようと考えた時には、望む疾患部位に選択的に改変したエクソソームを送達するシステムの存在が必須ですが、これを可能とする優れたシステムはまだほとんどないのが現状です。何かしら論文を出すには、報告されているターゲティングのシステムを使えばある程度のことはできますが、本当の医療のニーズにはこれでは答えられません。
新しいシステムを構築するのに必要なピースを自分で探索・発見し、それをさらにエンジニアリングに活かすアプローチを大事にしていきたいですね。
新しい知見を「発見」する
Q:今後の課題として、どんなものがありますか。
個人的には、細胞やそこから分泌される微粒子を用いた新しい疾患治療システムを作るのに有用な、新しい生物学的知見の開拓、およびそれに基づくエンジニアリングの革新と、有機化学とのシナジーの開拓を課題にしていきたいと考えています。
前者に関しては、お話ししたように、いかに新しい知見を「発見」するかというところが課題ですね。これにあたっては、通常のバイオロジーで用いられるトップダウン的なアプローチに加えて、先に少し述べましたが、細胞を改造してそのアウトプットを観察することで、逆に機能を理解する、というアプローチが有効であると考えています。例えば、細胞自身や、そこから分泌される微粒子を様々なタンパク質を用いてランダムに改変して、それがどのようなふるまいをするのかを観察(スクリーニング)することで、新しい設計指針を得る、というようなやり方です。現在こういった研究に鋭意取り組んでいます。
後者に関しては、こちらも先に述べましたが、私はもともと化学の分野の出身で、有機合成の力を駆使して機能性の小分子もつくることもできます。細胞の改造と小分子の改造の両方をできる人は稀有です。機能性小分子と機能性細胞は得意とすることが違いますし、相補的に補いあえる部分があると考えられるので、これらを協奏的に利用して、新しい機能性物質を開発できたらと考えています。
自分がいまできることにこだわりすぎず、あらゆるものを総動員して医療に役立つ新しいものをつくっていきたいですね。
Q:研究室には、どんな学生がいますか。
私はもともと薬学部の出身で、今は医学部にいます(https://cbmi.m.u-tokyo.ac.jp/)。私は助教なのでまだ研究室の主催者ではないのですが、方向性を自由に決めながら数人の大学院生・大学学部生といろいろなプロジェクトをやらせて頂いています。研究室の上長である浦野泰照教授が薬学部のラボ(https://www.f.u-tokyo.ac.jp/~taisha/)を兼務されていることもあり、薬学部の学生さんとも一緒に仕事ができる機会もあり、個性あふれる学生さん達と日々楽しく研究をさせてもらっています。
基本的には、ケミストリーを武器に医療や生命科学の研究に役立つツールを作ることに主眼を置くラボなので、これまで述べてきたようなバイオエンジニアリングをやっているとは知らずに入ってくる学生さんが多いですが、境界領域を研究している研究室を希望してくる学生さんなだけあって、広く興味を持って、なんでもやってみようというスタンスの人が多いので、助かっています。(もちろん、これまで述べてきたようなバイオエンジニアリング的なことを一緒にやってみたいという人は大歓迎ですので、是非一緒に研究しましょう。宣伝です(笑))
学生さんには、本当にいろいろなことに興味をもって、好奇心旺盛に研究に取り組んでほしいですね。学生の皆さんには、この先、数十年というたくさんの時間があるわけですから、その間に時代はどんどん移り変わって、様々な研究手法・分野が登場し、その時に応じて求められるスキルや興味のあることも変わっていくはずです。
ですから、学生の間に一番身につけるべきことは、特定の分野における特殊な技術というよりも、新しい知見や技術を積極的に取り入れて自分をアップデートする適応力と、今ある知見・材料から次にやるべきことを考えられる論理的思考力だと思います。
学生時代の研究を通じて、一度基本的なスタンス・考え方を身につけられれば、きっとどんなことにも対応できるはずです(これは最終的に研究の分野に進まなくても同じことです)。好奇心を持って研究に取り組み、どんな分野に進んでも自らの血肉となる基礎力を養ってほしいですね。
Q:企業とかかわる機会などは増えていますか。
最近、企業の方から私が開発した技術に関してヒアリングを行いたいといったお話も多く、興味を持っていただいて大変ありがたいです。
ただ正直なところ、企業の方が求めるニーズについてまだ把握しきれていない部分があると感じています。もう少し課題を企業側と共有できるようになれば良いですね。すぐにお金にならないからと会社では取り組めないような研究対象でも、大学ならある程度時間をかけて違ったアプローチができる、といったこともあるかもしれません。
企業の場合、最終的にお金につながらないと投資しづらいと思いますが、そこにこだわらずにできるという大学の強みを何かしらの形で発揮できればと思います。また、何か事業になりそうなことがあれば積極的に自分から立ち上げてみたい、という気持ちもあります。こちらはまだ明確なビジョンが立てられておりませんが、研究を進めていくにあたってアンテナを張っておきたいですね。
Q:最後に、今後の目標を教えてください。
まず、短期的には、自分の仕事として、名刺がわりになる成果を挙げたいですね。 これまで、留学してポスドクとしてやってきた研究は、どうしても世間からはボスの研究の一部として見られることが多いと思います。大学教員として、ある程度独立した形でステップアップして、「小嶋良輔といえば、この仕事」というものをつくりあげたいですね。
長期的には、おもしろいscienceから始まって、最終的には医療に役立つものが作れるような一気通貫した研究をしたいと思っています。日々の研究生活自体は細かい地味な作業の積み重ねですが、学生さんと大きなビジョンを共有して、大きなことを成し遂げたいですね。
最後にもう一点、改変細胞などによって新しい医療が可能になっていくのはよいのですが、それにあたって医療に係るコストが益々増加して行ってしまうという面があるので、社会で持続可能な技術になるように、これを大幅にコストダウンできるような革新的技術も作っていかなければならないと感じています。
究極的には、外から薬を投与するだけで、体内の細胞を副作用なくプログラミングできるようになればよいのかもしれません。なかなか難しいと思いますが、鋭意研究を進めていつかこういった観点からもブレイクスルーを起こせたらと思います。(了)
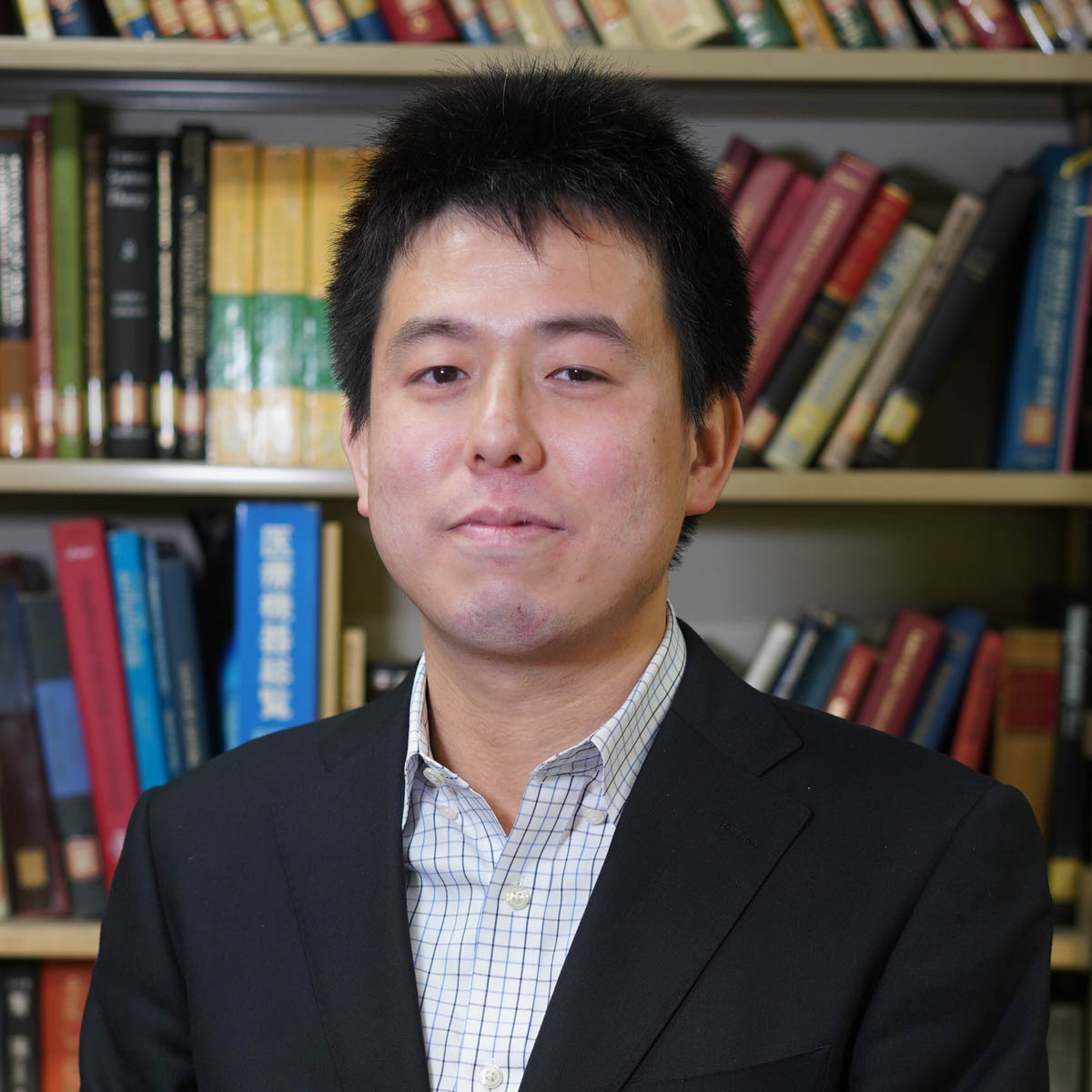
小嶋 良輔
こじま・りょうすけ
東京大学 大学院医学系研究科 生体物理医学専攻 医用生体工学講座 生体情報学分野 助教。
2009年、東京大学薬学部卒業。2014年、東京大学大学院薬学系研究科博士課程 修了。2014年、スイス連邦工科大学チューリッヒ校博士研究員を経て、2017年より現職。
2017年10月より、JSTさきがけ研究者兼任。
