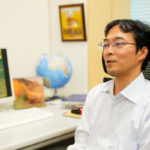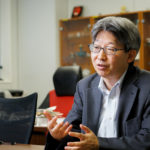我々の暮らしを支えるネットワーク通信技術は、年々増加するデータ量によって圧迫されつつある。デバイスや光回線の進歩が鈍化し、データ量の増大をカバーしきれなくなることが予測されており、対策が急がれている。こうしたなか、従来の通信の仕組みにとらわれないまったく新しい情報通信技術のアーキテクチャを構想し、長い年月をかけて実用化を進めているのが、産業技術総合研究所の並木周氏。副研究部門長を務める並木周氏に、今後の実現を目指す光ネットワーク仮想化の基本構想について伺った。 処理限界を迎えるネットワークの課題を、仮想化で解決する Q:まずは、研究の社会的背景とニーズについて教えてください。 情報は世界中でネットワーク上、あるいはクラウド上で処理され、伝達されています。情報量が多い時では年率200%、最近ではちょっと落ち着いて30%程度のところもあれば、クラウドデー … [もっと読む...] about 光スイッチで、次世代のネットワーク技術を創出する〜並木周・産業技術総合研究所 電子光技術研究部門 副研究部門長
コンピュータ外科学で、外科手術をサポートする〜中村亮一・千葉大学フロンティア医工学センター准教授
外科医が行なう手術には高度な技術が必要であるが、その習得・実践をサポートするのに有効なのが「コンピュータ外科学」と呼ばれる、コンピューターやロボットを活用した外科手術である。「医療用のナビゲーションシステム」の実現をめざし、患者に負担の少ない超音波を使ったナビゲーションなどの開発をおこなうのが、千葉大学フロンティア医工学センターの中村亮一准教授。研究の中心は、手術のなかでもナビゲーションが難しい柔らかい臓器に対して、超音波をつかったナビゲーションをおこなうことと,ナビゲーションを利用して医師の技術を分析することだ。今回は中村准教授に、コンピュータ外科学の現在と未来について伺った。 超音波で柔らかい臓器のナビゲーション手術を実現する Q:まずは研究の概要について教えてください。 私が行なっているのは、「コンピュータ外科学」というものです。といっても実は … [もっと読む...] about コンピュータ外科学で、外科手術をサポートする〜中村亮一・千葉大学フロンティア医工学センター准教授
微生物の糖質分解酵素に着目し、酵素の産業応用につなげる〜伏信進矢・東京大学大学院教授
ヒトのおなかにいる腸内細菌は、実に多くの種類の糖質分解酵素を持っている。近年、このタイプの酵素は次々と新しい種類が発見されており、産業応用をにらんだ研究が盛んになっている分野である。こうしたなか、ビフィズス菌が糖鎖を分解する際に作り出す酵素に着目し研究を進めているのが、東京大学大学院農学生命科学研究科の伏信進矢教授だ。今回は伏信教授に、腸内細菌の酵素研究が盛んになった要因と、産業応用に向けて乗り越えるべき課題についてお話を伺った。 ビフィズス菌を中心に、酵素の糖質分解酵素に着目 Q:まずは、研究の概要について教えてください。 私たちが研究しているのは非常に基礎的な、「酵素のかたち」です。酵素が立体的にみてどんなかたちをしていて、どのように働くのかを研究しています。これは、「構造生物学」や「酵素学」と呼ばれている分野です。 構造生物学でいうと、医療応用 … [もっと読む...] about 微生物の糖質分解酵素に着目し、酵素の産業応用につなげる〜伏信進矢・東京大学大学院教授
試作コインランドリの運営を通じて、企業のイノベーションを推進する〜戸津 健太郎・東北大学マイクロシステム融合研究開発センター准教授
半導体、MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)、光関連等のデバイスに関連する一連のものづくりにおいては、一企業が自前で生産設備を持つことが難しい。クリーンルーム、加工装置を中心とする専門的な設備を取り揃えるだけではなく、技術支援・開発・人材育成の体制も整え、広く利用者に門戸を開放しているのが、東北大学 西澤潤一記念研究センターにあるマイクロシステム融合研究開発センターに設立された、「試作コインランドリ」だ。企業のニーズに応えることで、年々利用者も増えている同施設で運営責任者を務めるのが、東北大学マイクロシステム融合研究開発センター准教授の戸津 … [もっと読む...] about 試作コインランドリの運営を通じて、企業のイノベーションを推進する〜戸津 健太郎・東北大学マイクロシステム融合研究開発センター准教授
最新の気象モデルで、都市気候を解き明かす〜日下 博幸・筑波大学計算科学研究センター教授
異常気象や温暖化が社会問題として叫ばれるなか、東京や名古屋など都市近辺の気候研究の必要性が高まっている。世界最大のユーザ数を誇る「WRF」モデルや筑波大学が中心となって開発した世界最新の「City-LES」を用いて、都市気候を中心とした気候や気象の研究に取り組んでいるのが、筑波大学計算科学研究センターの日下 … [もっと読む...] about 最新の気象モデルで、都市気候を解き明かす〜日下 博幸・筑波大学計算科学研究センター教授
遺伝子群や神経回路の研究から、記憶の仕組みを解明する〜奥野浩行・鹿児島大学大学院教授
ヒトはどのように物事を記憶しているのか?という問いは、古来から研究されてきた永遠のテーマの一つであり、そのメカニズムは現在でも完全には解明されていない。記憶の仕組みを解明することは、脳を解明することにほかならず、認知症やPTSDといった症状を改善する治療法の開発につながることが期待されている。こうしたなか、幅広い記憶研究のなかでも「陳述的記憶」を中心に研究をおこなうのが、鹿児島大学大学院の奥野浩行教授。経験・学習に関連する遺伝子群や、それらが発現する神経回路の性質と機能を解明することで、記憶のメカズニムを明らかにする研究をおこなう奥野教授に、研究の基本的アプローチについて伺った。 「陳述的記憶」を中心に研究 Q:まず、脳研究の社会的ニーズとはどういったところにあるのでしょうか。 そもそも記憶というものは、「我々が人間として、人間らしく行動するために必 … [もっと読む...] about 遺伝子群や神経回路の研究から、記憶の仕組みを解明する〜奥野浩行・鹿児島大学大学院教授
葉緑体の観察で、選択的オートファジーの全容を解明する~泉 正範・東北大学学際科学フロンティア研究所 助教
植物の葉緑体にはまだまだ解明されていない謎が多く残っており、特に葉緑体の分解がどのように行なわれているかについては解明する余地が多い。葉緑体は植物の活動のなかで意図的に壊されることがわかっているが、そのメカニズムを解明することで、植物のエネルギー生産や成長の仕組みが明らかになることが期待されている。こうしたなか、植物細胞のライブセルイメージングや分子遺伝学解析を駆使した研究を進めているのが、東北大学学際科学フロンティア研究所の泉正範助教だ。今回は泉正範助教に葉緑体の分解研究についての基本的なアプローチをお話いただいた。 葉緑体が「壊される」要因を研究 Q:まずは、研究の概要についてお話しください。 植物は光合成という働きで二酸化炭素を吸って、酸素を出します。吸った二酸化炭素は糖やでんぷんに変わり、植物はそれを使って生きています。光合成は植物の中に多く … [もっと読む...] about 葉緑体の観察で、選択的オートファジーの全容を解明する~泉 正範・東北大学学際科学フロンティア研究所 助教
組織工学の研究で、生体移植を実用化する〜清水達也・先端生命医科学研究所 所長
日本国内でも年々認知が高まりつつある再生医療であるが、細胞は個別単位にばらばらの状態で移植しても治療効果が不十分であり、組織工学と呼ばれる、細胞から組織単位のものを培養作製し移植する技術が求められている。日本国内における組織工学の黎明期から20年以上研究を続けているのが、東京女子医科大学先端生命医科学研究所の清水所長。臨床医でありながら、この分野のエンジニアとして基礎研究も行なう清水所長は、細胞シートの研究開発、および臨床応用を推進し、現在ではiPS細胞から人の心筋細胞シートをつくることができるまでになるなど、めざましい成果をあげている。基礎研究と臨床応用の両面で期待を集めている清水所長に、現時点での組織工学の成果について伺った。 ティッシュエンジニアリングで組織を丸ごと移植する Q:組織工学研究の概要についてお聞かせください。 再生医療の研究自体は … [もっと読む...] about 組織工学の研究で、生体移植を実用化する〜清水達也・先端生命医科学研究所 所長
磁性体の研究で、磁石の可能性を最大限に引き出す〜千葉大地・東京大学准教授
日常生活で使われる磁石には鉄やニッケル、コバルトといった材質があるが、じつは我々の目に見えないところでは大小様々な磁石が活躍している。たとえば微小な磁石は、パソコンのハードディスクなど記録媒体に使われている。そんななか、磁性体を中心とした材料の新しい使い方を見つけるべく、磁石の知られざる潜在能力を見つけ、活用する研究をおこなっているのが、東京大学工学系研究科物理工学専攻の千葉准教授。磁石の研究で注目される成果を挙げる千葉准教授に、磁石がもつ応用の可能性について伺った。 電流も磁界も使わずに書き込める方法に挑戦する Q:まずは、研究の概要についてお聞かせください。 私たちは磁石を研究対象としていますが、磁石といっても、皆さんがおそらく触れたことのある棒磁石のような赤と青に分かれている大きな磁石を扱うわけではありません。私たちが着目しているのはナノサイズ … [もっと読む...] about 磁性体の研究で、磁石の可能性を最大限に引き出す〜千葉大地・東京大学准教授
バイオメカニクスの観点から、ヒトの歩行の仕組みを解明する〜荻原直道・慶應義塾大学理工学部教授
人が歩くメカニズムは、単純そうにみえて非常に奥が深い。歩くメカニズムを解明することで、臨床医学やロボット工学への応用が可能になるとされ、新たなアプローチでの歩行研究に期待が寄せられている。こうしたなか、「歩く」の起源にせまるべく、ヒトおよび霊長類の運動機能と身体構造の進化メカニズムを機械工学的視点から研究しているのが、慶應義塾大学理工学部機械工学科の荻原直道教授だ。人間の歩行の仕組みを理解することで、からだの動きに関わる様々な分野のベースになると考える荻原教授に、ニホンザルの二足歩行研究を中心とした現在の研究手法について伺った。 機械工学をベースに、二足歩行のメカニズムと進化を探る Q:まずは、歩行研究の社会的なニーズについて教えてください。 もともと機械工学科の出身で、航空宇宙工学の勉強をしたいと思って大学に入りました。しかし大学で学ぶうち … [もっと読む...] about バイオメカニクスの観点から、ヒトの歩行の仕組みを解明する〜荻原直道・慶應義塾大学理工学部教授